過去と現在の生産量と投入量を比較することで、生産性の上昇率が測定できる。全く同様に、自国と外国の生産量と投入量を比べれば、全要素生産性(TFP)や労働生産性の水準の内外格差が測定できる。
図は労働生産性(就業者数×就業時間一単位あたりの実質粗付加価値)の日米比較である。輸送機械や一次金属など輸出型産業(業種)の生産性は日本の方が高い半面、運輸、商業、電気ガス水道など大半の非製造業では米国の約半分であり、このため経済全体の生産性も米国の約6割にとどまっている。
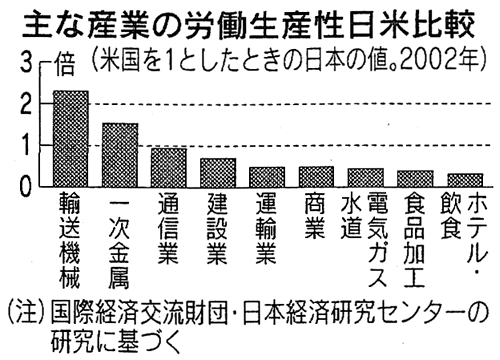
このような生産性格差を生み出している一因は、第2回でもふれたようにIT(情報技術)活用の差であろう。初回みた欧州連合主導の国際連携研究(EU―KLEMS)のデータベースによれば、2004年におけるIT資本ストックの国内総生産(GDP)に対する比率(1995年価格)は、米国の32%、ドイツの18%に対して、日本は16%にとどまる。特に流通や対個人サービスで、日本のIT投資の出遅れが目立つ。
これは見方を変えれば、それだけ日本では生産性向上の余地が大きいということである。米国ではITやソフトウエアがすでに広く社会に普及して飽和点に達し、最近では生産性上昇の停滞が指摘されることも多いが、日本はこれからIT革命の恩恵を享受できる可能性がある。
なお、生産性の国際比較は特に非製造業で誤差が大きいことを指摘したい。たとえば日本では、顧客がキメ細かなサービスを要求することが多く、このため、サービスの質が海外より高い産業が多いと考えられる。一方、生産性の国際比較では、単純化していえば、運輸業であれば1時間の労働で何キログラムの貨物を何キロメートル運んだか、小売業であれば1時間で消費者にどれだけの量の商品を販売したかを比べている。時間指定の配達やスーパーの24時間営業など、サービスの質の違いが十分には考慮されていない点を割り引いてみる必要がある。生産性の国際比較は、今後改善すべき余地が大きい研究分野といえる。
2007年12月19日 日本経済新聞「やさしい経済学―潜在成長力と生産性」に掲載


