少子高齢化の進行などに伴い日本の潜在成長率(インフレを起こさずに達成可能な実質経済成長率)に対する関心が高まってきた。
供給側からみると、実質経済成長率は(1)労働投入増加(2)資本投入増加(3)生産技術・効率の改善度合いなどを示す全要素生産性(Total Factor Productivity =TFP)上昇――の3つの寄与に分解できる。これを成長会計と呼ぶ。図は労働をさらにマンアワー(就業者数×就業時間)と質(学歴・熟練度など)に分解した日本に関する成長会計の結果である。経済成長率は1990年以降急落したが、これについて図からは労働、資本、TFPの3つの寄与がすべて減少したことが分かる。それらは不況に伴う需要不足にも起因し、好況が維持されれば部分的に回復する可能性はある。
しかし、構造的な成長抑制要因も見逃せない。労働に関連しては、先行き生産年齢(15-64歳)人口の減少が本格化する。資本についても、日本は欧米より資本係数(資本ストック/国内総生産=GDP)が高く資本の粗収益率(営業余暇/資本ストック)が低い状況にあり、今後の投入急増は期待しにくい。
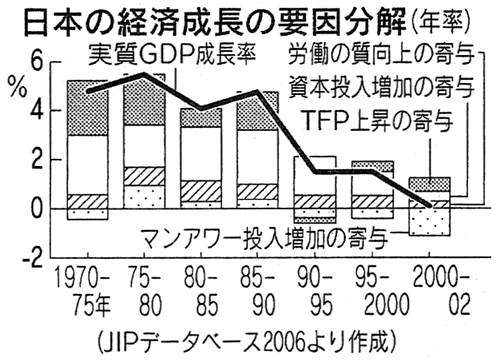
詳細は省略するが、一定の仮定の下で新古典派成長論に従えば、人口減少の悪影響を就業率上昇や労働の質改善、IT(情報技術)投資の促進で相殺するにせよ、日本経済の活性化に必要と思われる2.5%程度の潜在成長率を達成するには、TFP上昇を近年の年率0.5%程度から80年代までの同1%超に引き上げることが求められる。
本稿では、近年のTFP研究の成果(筆者も参加して経済産業研究所と一橋大が合同で作成する日本産業生産性=JIP=データベースや、そのデータを提供している欧州連合主体の国際連携プロジェクト=EU-KLEMS)を基に、成長力向上のための日本の課題を考えていきたい。
2007年12月12日 日本経済新聞「やさしい経済学―潜在成長力と生産性」に掲載


