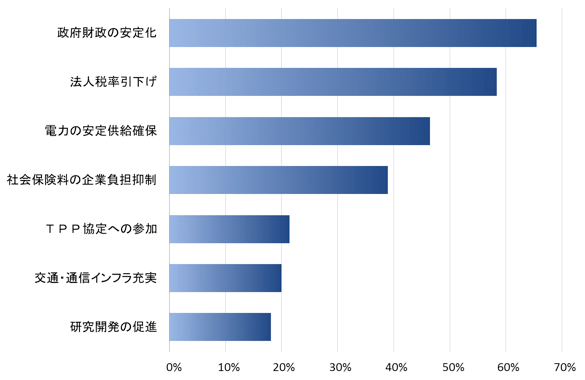日本経済は、2008年秋のリーマン・ショック、2011年春の東日本大震災という2つの大きなショックに直面した。世界経済危機は「百年に一度」、東日本大震災も「想定外」と言われ、事前に予測することが困難なショックだった。これらの結果、2007年から2011年の間の実質経済成長率は平均年率マイナス0.8%となった。税収の減少や財政支出の増加により、政府債務残高のGDP比率は200%を超えている。これはギリシアを上回りOECD諸国中で最悪の水準である。こうした状況の下、高齢化に伴う社会保障支出の増加ともあいまって、若年世代・将来世代の負担が一段と高まることとなり、世代間格差が深刻な問題になっている。
戦後最悪の経済成長率となったリーマン・ショック
バブル崩壊以降の長期経済低迷に伴い日本の財政状態は悪化の一途をたどってきたが、2002年から08年初にかけては、世界経済の高成長に牽引された73カ月にわたる戦後最長の景気拡大により経済成長率は2%前後で推移し、この間「踊り場」と言われる景気停滞局面もあったが、財政支出を伴う景気対策は採られなかった。また、財政赤字削減に向けて、歳出・歳入一体改革など財政健全化に向けた取り組みも始まっていた。世界的にも米欧主要国で「大いなる安定」と言われる景気変動幅の縮小が観察され、(1)金融政策の改善、(2)企業の在庫管理技術の進歩、(3)石油危機などの大きなショックに見舞われなかったことがその理由として論じられていた。今から振り返れば、3つ目の「幸運」という要素が大きかったと言える。
しかし、2008年9月15日に米国で発生したリーマン・ショックに端を発する世界経済危機は状況を一変させた。正確に言えば米国の金融危機は2007年のサブプライム・ローン問題から始まっており、日本の景気拡大も事後的に見ると2008年2月がピークで、外需減少から景気は下降局面に入っていた。実際、2008年4~6月期、7~9月期と2四半期続けて年率換算で4%を超えるマイナス成長となっていた。このため、2008年8月末には「安心実現のための緊急総合対策」という小規模な財政支出を伴う景気対策が7年ぶりに策定された。
リーマン・ショックは、直ちに金融市場、外国為替市場を激動させた。日経平均株価はショック前の9月12日の1万2214円から10月28日には一時7000円割れの安値を付けるまで急落した。外国為替市場では円が急騰し、12月までの3カ月間に円の実効為替レートは24%増価した。日本は小泉内閣下で進められた金融機関の不良債権処理や自己資本比率引き上げの結果、金融システムの健全性が比較的高かったため、当初、リーマン・ショックの実体経済への影響は限定的との見方もあった。しかし、その後の展開はそうした予想とは大きく異なり、輸出と生産は異常な速さで低下し、企業の業況や資金繰りは大幅に悪化した。
当時の生産の動きを少し詳しく見ると、鉱工業生産指数は、2008年9月から翌年2月のボトムにかけてマイナス31%と歴史的に例のない大幅な低下を記録した(図1)。業種によって状況は異なり、海外発のショックだったため直接・間接の輸出依存度が高い産業ほど大きな影響を受けた。自動車の生産はマイナス55%と半分以下に落ち込み、鉄鋼、一般機械、電子部品の生産も40%を超える減少となった。他方、第三次産業も経済危機の影響から無縁ではなかったが、ボトムまで半年間の活動指数はマイナス7%と製造業に比べればずっと小さかった。
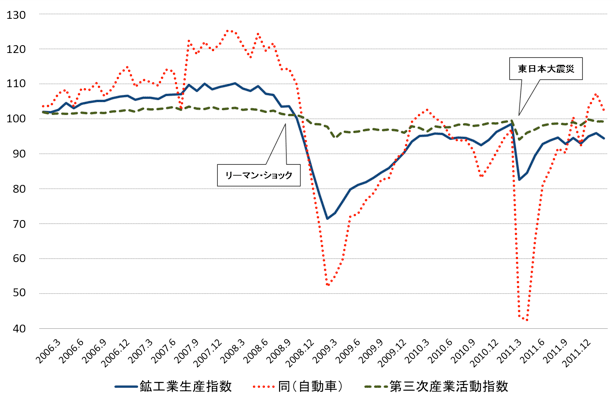
2009年1~3月の輸出総額は前年比45%以上の減少、うち自動車は約70%減であり、生産の大幅減少は輸出の縮小に符合している。リーマン・ショックが貿易と工業生産を大幅に低下させた理由についてはその後多くの研究が行われ、耐久財製造業の急速な在庫調整、金融不安に伴う貿易金融の収縮が大きく影響したことが指摘されている。
リーマン・ショック後の生産減少は極めて急速で、当時は底なしという印象だった。政府の月例経済報告における景気の基調判断では、2月から4月にかけて「急速な悪化が続いており、厳しい状況にある」という過去に例のない強い表現が採られた。結果的に、2008年度の経済成長率は前年比マイナス3.7%と戦後最悪の数字を記録した。翌2009年度もマイナス成長となり、企業収益の悪化に伴って法人税収が2007年度の14.7兆円から2009年度には6.4兆円へと大幅に減少するなど、税収減が財政赤字拡大の要因となった。
生産の急減は企業の資金繰りを急速に悪化させた。社債の安全性を示す指標である社債利回りの国債に対する上乗せ幅は拡大し、資金調達環境の悪化は中小企業にとどまらず大企業・中堅企業にも拡がった。金融システム不安に対処するため、日銀は主要国中央銀行と協調しつつ政策金利引き下げやドル資金供給オペを開始した。政府は中小企業に対する緊急保証制度の20兆円、セーフティネット貸付制度の10兆円への拡充、大企業・中堅企業への危機対応融資制度の発動等を行った。
財政による景気刺激策も積極的に講じられた。麻生内閣は3回の経済対策を策定し、拡張型の補正予算が編成された。約5兆円の補正予算を伴う「生活対策」(10月)、「生活防衛のための緊急対策」(12月)、そして「経済危機対策」(2009年4月)である。「経済危機対策」は、国際協調を踏まえてGDP比2%を上回る真水規模の景気対策とされ、約15兆円の補正予算が編成された。これらの経済対策では、金融市場・資金繰り対策のほか、一人1万2000円の定額給付金、エコカー減税・補助金、エコポイント制度の導入といった施策が盛り込まれた。
世界経済危機に際しては諸外国でも財政出動が行われ、その規模はGDP比で米国5.7%、ドイツ3.3%、4兆元(約57兆円)の追加支出が行われた中国では16%にのぼった。グローバル化した経済では一国のみの財政刺激策の効果には限界があり、また、企業や家計の先行きに対する不安感を低減する上でも、国際協調に基づく果断な対応は有効だった。それまで、主要国では裁量的な財政政策を景気刺激策として用いることに否定的な議論が主流となっていたが、世界経済危機以降の理論・実証研究は、深刻な不況時には従来考えられていたよりも財政政策の有効性が高いこと、財政政策が世界経済危機からの回復に一定の効果を持ったことを示している。反面、景気対策が重い財政負担となったことは言うまでもない。
一般に雇用情勢は景気変動に遅行するが、製造業を中心に派遣労働者の削減が急速に進み、2008年末には日比谷公園に年越し派遣村が開設されるなど「派遣切り」が社会問題となった。リーマン・ショックから1年間で失業者は100万人近く増加し、失業率は4%から5.4%へと上昇した。政権交代後、鳩山内閣の下で、「緊急雇用対策」(2009年10月)、「明日の安心と成長のための緊急経済対策」(12月)という雇用に力点を置いた政策が採られ、後者は7.2兆というかなり大きな予算措置を伴うものだった。
東日本大震災で自動車の生産は56%減
政策の効果もあってその後の景気は比較的順調に回復し、東日本大震災前、2010暦年の経済成長率は4.4%と高い数字となった。鉱工業生産は、円高の影響があったものの、2011年2月にはリーマン・ショック直前を5%下回る水準にまで回復してきた。しかし、3月11日の東日本大震災は、再び日本の産業活動に甚大な影響を及ぼす。3月の鉱工業生産は、直接的な被災だけでなく、サプライチェーン問題や電力不足の影響もあって前月比16%低下し、特に自動車は56%減と、リーマン・ショックを上回る急激な減少となった。情報通信機械も25%減と比較的大きな影響を受け、第三次産業活動も前月比5%強低下した。海外発のリーマン・ショックと違って震災直後の為替レートは一時円安に振れたが、夏以降は欧州危機の影響から円高が進み、電力不足とともに生産活動を制約することになる。
サプライチェーン問題、電力不足を中心に、日本企業への影響を少し詳しく見てみる。我々が行った日本企業約3400社の調査結果によると、約2割の企業がサプライチェーン途絶の直接的影響、約4割の企業が間接的影響を受けた。東北・関東以外でも過半数の企業が影響を受けており、サプライチェーン問題は日本全体に広がりを持っていた。この経験から、特に製造業では海外からの調達を拡大し始めた企業も多く、国内の生産ネットワーク空洞化の一因となっている。
東日本大震災の直後、東京電力管内では3月末にかけての約2週間、計画停電が実施された。夏には東京電力と東北電力の管内でマイナス15%という電力需要抑制目標が設定され、大口需要家には電気事業法に基づく電力使用制限が発動された。大震災の直接の被災地ではなかった中部電力や関西電力の管内でも自主的な節電要請が行われた。こうした電力供給制約について、全国で約4分の1、東北・関東地方に限ると半数近い企業が直接の影響を受けたとしており、間接的な影響があった企業も約2割にのぼる。
東日本大震災後、経済対策という形で実施されたのは「円高への総合的対応策」(2011年10月)だけだが、震災復興対策として累次の補正予算が策定され、政府支出が上積みされた。2011年度第一次補正4兆円(5月)、第二次補正2兆円(7月)、第三次補正12兆円(11月)である。こうした復興需要もあって、欧州経済危機の深刻化や夏の電力供給制約などのリスク要因が存在するものの、今年度は比較的高めの成長が予想されており、「政府経済見通し」は実質経済成長率2.2%、鉱工業生産指数6.1%の伸びを見込んでいる。しかし、これら復興対策も結果として政府債務の増大をもたらす一因となっており、財政破綻のリスクを高めるという副作用を伴っている。
財政の悪化と広がる世代間格差
リーマン・ショック前の2007年に安倍内閣が作成した「日本経済の進路と戦略」の参考試算では、世界経済の減速等がなければ2011年度に基礎的財政収支は黒字化し、政府債務残高対GDP比は136%へといくぶん低下しているはずだった。この想定と比較すると、2つのショックの結果、足下の実質GDPは60兆円以上低い水準であり、一般会計税収は2008~2011年度の4年間累計で65兆円の減収、政府債務残高対GDP比は200%を超えている。
構造的に言えば、日本の財政赤字や政府債務残高拡大の主因は、高齢化に伴う社会保障給付の増加とそれに見合った負担の不足だが、この数年間に限ると、世界経済危機、東日本大震災とそれらに伴う税収減・財政支出拡大も大きく影響した。最近の分析は、日本の政府債務を安定化させるには毎年の予算でGDP比10%程度の財政収支改善が必要なことを指摘している。
前述の調査では、震災からの復興を進め日本経済の成長力を高めるための政策として重要なものは何かを尋ねている。それによると約3分の2の企業が政府財政の安定化を挙げており、これは法人税率引き下げやTPP協定への参加よりも多い(図2)。特に金利が企業経営に大きく影響すると見ている企業では、8割近くが政府財政の安定化を重要課題として挙げている。欧州危機を背景に日本企業が財政破綻リスクを意識し始め、政府債務の増嵩が金利高騰を招くことへの懸念が高まっていることを示唆している。また、社会保険料の企業負担抑制も多くの企業が重視しており、特に人件費の割合が高い中小企業でこれを挙げる企業が多い。
政府債務の増大、社会保障の給付と負担のアンバランスは、いずれも将来世代への負担の先送りであり、世代間の公平性の問題と密接な関係がある。ただし、世代間格差は個人の生涯を通じた負担と給付の比率で議論されることが多いが、そうした単純な損得勘定だけから世代間の対立を煽ることは望ましくない。そもそも同一の世代内でも所得や寿命の違いによる負担と受益の個人差は大きいし、経済成長で賃金が増加すれば将来世代の負担を差し引いた上での生涯純所得は高くなるからである。逆に、世界経済危機と東日本大震災の深刻な影響を被ったここ数年間の日本経済のように、産業活動が縮小し、マイナス成長が続けば世代間の不均衡は一層拡大する。経済成長率の比較的小さな違いでも、長期的には生涯所得の世代間格差に大きく影響する。
世界経済危機と東日本大震災の1つの教訓は、幸運は長期にわたって続かないという現実である。今後も海外発の大きなショックや大規模災害が起きる可能性は低くない。政府財政に余裕がない場合、これらのショックへの対策でも後の世代ほど十分な支援を受けられないという世代間格差が生じかねない。多くの企業が経済成長のための重要課題として挙げた政府財政の安定化と社会保障負担の抑制は、直接的な財政効果とともに安定的な成長の実現を通じて、二重の意味で将来世代の不利益を緩和する効果を持つ。
2度のショックの影響もあって日本企業の国際競争力に陰りが見られる中、世代間格差のこれ以上の拡大を避けるためにも、税制・社会保障制度改革の実行は急務である。
『中央公論』2012年7月号に掲載