2008年の金融危機の後、多くの先進国は若年層失業率の高さに悩まされることになりました。景気が後退すると、労働市場の入り口にいる若年者は、すぐにそのしわ寄せを受けることになるのです。
特にその影響が大きかったのがスペインで、20~24歳の男性労働者の失業率は12年に50.5%に達しています。ポルトガルやイタリア、ギリシャといった他の南欧の国々でも同様に若年男性の失業率は高い水準に達しています。一方で、北欧諸国での若年者の失業率はそこまで高くはありません。
国ごとの若年失業率の違いを考えるにあたって重要になるのが、解雇規制の厳しさに代表される労働市場の制度的硬直性です。解雇規制が厳しくなると労働市場における転職や離職が少なくなるため、労働市場の流動性が下がることが知られています。そのため、本来、流動性が高い若年者は大きな影響を受けるのです。
さらに金融危機のようなマクロ経済ショックに対する対応の違いも重要です。解雇規制が厳しい国々では、マイナスのショックに対し、企業は中高年を解雇するわけにはいかないので、若年者の採用を抑えます。そのため、若年の失業率は景気動向に敏感に反応することになります。一方で、米国のように解雇規制が緩い国では若年層から中高年層まで幅広い年齢層の失業率が同じように変動します。
九州大学の村尾徹士助教と筆者は、経済協力開発機構(OECD)諸国のデータを用いた実証研究を通じて、解雇規制が厳しい国では、若者層が負のマクロ経済ショックの吸収役を担っていることを明らかにしました。
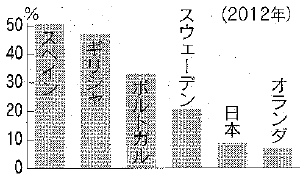
2013年10月24日 日本経済新聞「やさしい経済学―雇用を考える 若者と高齢者」に掲載


