安倍政権の主導のもとで「女性の職業生活における活躍の推進に関する法案(仮称)」が国会に提出される運びとなった。実効性は不確定だが趣旨は良く、また数値目標についても経団連の反対を押し切って定めることとしたのは評価できる。数値は実情に応じて企業が定めるというのも、これまでの日本企業の女性人材の育成不足もあり、無理やり員数合わせをするのは経済的に不合理なため、やむをえない措置である。むしろ数値目標と実現値を「見える化」し、各企業がどの程度の目標を定め、かつ実現できたのかを透明化することか必要である。
しかし問題は、わが国で経済活動における女性の活躍が進まない主な理由が日本的雇用システムにあることだ。従来の雇用慣行や制度の大規模な改革なしには、女性活躍の推進も、時代に見合った有効な人材活用もできないと筆者は考えている。その理由を述べたい。
日本的雇用システムの成り立ちとその戦略的合理性
日本的雇用システムは高度成長期には合理的な制度であったが現在はそうでない(例えば八代、1997)と主張されることか多いが、筆者は高度成長期にも一般的な合理性を持っていたか否かについて、後述の理由で留保がある。しかしゲーム理論でいう戦略的合理性を持っていた(川口、2008)という論点には全く同意である。
戦略的合理性というのは、いったん1つの制度を持つと、他の制度の合理的選択に影響を及ぼすことをいい、伝統の異なる国が合理的制度を持つ近代になっても、異なる制度を持つことの説明として使われることか多い。
単純な例で言うと、はじめに土台となるA1とA2という制度のうち、A1という制度が、その国での文化的伝統や選択時の状況により選択されたとする。戦略的合理性とは、つぎにB1とB2という別の制度の選択をする場合の選択理由に関するものである。組み合わせとしては、合理性の高い順に[A2、B2]>[A1、B1]>{[A1、B2]、[A2、B1]}であると仮定する。つまり、B1はA1と補完的で、B2はA2と補完的な制度である。ここで、既にA1を選んだ企業は、B1を選ぶ可能性が高くなる。それは仮に[A2、B2]の組み合わせの合理性が[A1、B1]の合理性を上回っても、[A2、B2]の選択のためには既存のA1という制度をA2に変えなければならず、そのコストが通常大きいためである。このようなB1の選択を戦略的合理性を持つという。しかし、無の状態から選択するなら、[A2、B2]の選択が合理的であるため、戦略的合理性の原理で作られた一連の制度が最終的に最も合理的とは言えない。
戦略的合理性を持つ一連の選択の結果は、最初の選択に依存し、それを制度の経路依存と呼ぶ。また、このように選択されて出来上がった制度は相互補完的で、部分的変換が非常に難しく、制度の集まりのセットとしては、他に優れたセットがあっても、それに変換できないという劣等均衡を生む。つまり制度的に最も合理的ではないのだが安定性を持ってしまい、外的条件の変化に適応力を失ってしまうのである。この劣等均衡を打ち破る有効な手段は、セットとしてより合理的な組み合わせの制度の要素のうち、既存のセットと最も根本的に両立しがたい要素を、外から強制することである。
では、具体的に日本企業のA1の選択にあたるものは何か? それは雇用者への強い雇用保障制度(終身雇用制度)と、年功序列的賃金制度と退職金制度を核とする賃金制度の2つである。終身雇用制度の基について、村上・公文・佐藤は『文明としてのイエ社会』(1979)で、日本の正規雇用が欧米企業のように時期を定めた雇用主と雇用者の契約でなく、半永久的雇用関係である点についてそれを「縁約」と呼び、その起源を武家社会の「家制度」にもとめた。近年では濱口(2011)が西洋の雇用の「ジョブ型」に対し日本の雇用を「メンバーシップ型」と名付けたが、その特徴付けは村上・公文・佐藤と共通する。
しかし、仮に終身雇用制度が江戸時代の家制度を模倣したものであったとしても、その制度が戦後の経済成長とともに普及したのは、その時期になって新たな経済機能を持ったからである。高度成長期に日本企業は将来の事業の拡大を見込み、長期的に労働需要が供給を上回ることを見越し、雇用者、特に企業内人材投資を行った雇用者の流出を低く抑えることに利益があり、このために強い雇用保障を与えて定着性を増そうとしたのである。労働需要が長期的に増加する見込みのもとでは、人減らしの必要性が少なく、強い雇用保障による雇用調整の硬直性のコストは低かったからである。また、年功序列的賃金制度と退職金制度は、雇用者に長期就業のインセンティブを与える賃金後払い制度と理解できる。
このような理由で高度成長期には日本的雇用システムは合理性を持っていたとされるが、このA1にあたる選択自体、日本の文化的土壌の中での限定的合理性であった。そのことを指摘した者は見当たらないので、ここで指摘しておきたい。雇用者の定着性を確保するという目的ならば、欧米における「家族に優しい」企業、つまりワークライフバランスを達成しやすい企業に変えることも、優秀な女性雇用者が育児期に離職してしまうのを防ぐという意味で有効な手段であったはずである。しかしわが国企業の選択は村上・公文・佐藤が指摘したように、武家社会の家制度をモデルにした結果、伝統的性別役割分業を暗黙の前提とし、男性中心の職場を念頭に置いたため、女性雇用者の貢献を重視しなかったのである。
重要なのは日本的雇用システムの特徴は強い雇用保障を核としたことで、いくつかの相互補完的制度を持つに至ったことである。
まず、重要な補完的制度として労働時間による雇用調整制度がある。正規雇用者への強い雇用保障は、欧米のように雇用を雇用者数で調整する(労働需要が減れば解雇・レイオフし、増えれば雇用者を増やす)ことを困難にした。従って正規雇用の雇用調整は主として労働時間でする必要があり、時間調整のためのバッファーとして恒常的な一定の残業と、その結果として長時間労働が定着したのである。
また、各種労働需要の増加を市場からの雇用でそのつど満たす西洋型の雇用調整は採用できないため、広い範囲の職務に就くことが可能な「ジェネラリスト」養成に力を注ぎ、企業内雇用者で多様な人材を供給できるように努めることになった。いわゆる内部労働市場の発達であるが、これは一方で高度な専門家が育ちにくいため、西洋型の「専門職務の分担の明確な分業」ではなく、「職務が無限定な協業」を発達させた。
しかし、このような働き方は雇用者自身による労働時間管理の自律性を低くする結果となった。具体例を挙げると、筆者が知る某企業ではIT部門雇用者に導入したフレックスタイム勤務を生産性が下がったので廃止したという。理由はその企業の雇用者が、同僚と顔をつき合わせて相談しながらでないと効率的に仕事が進められないためだそうである。仕事に共同責任があり、個人間の分業より、協業になじんでいる日本の雇用ならではの結果であり、個人間の効率的分業がなされ、週1回程度顔をつき合わせて調整を図るだけで仕事を効率的に進められる米国のIT関係専門職の働き方と極めて対比的である。
日本の雇用者の共同責任や連帯性には、独自のインセンティブ・システムとして発達した日本型ボーナス制度の影響もある。欧米型のボーナス制度は、企業業績に特別な貢献をした個々人に対して与える特別賞与である。全員が貰えるわけではなく、基本給と比べた割合も個人により異なる。これに対して日本型ボーナス制度は企業業績に応じ、正社員全員にほぼ(基本給との比で)一律に与えられる。
終身雇用制が長期的に正社員の利益と会社の利益が連動する仕組みであるのに対し、ボーナス制度は短期的に雇用者の利益と会社の利益を連動させる仕組みである。日本型の特性は、企業で一律の報酬であるために、個人の行動に外部性(個人の行動が意図せず他者の利害に影響を与える性質)を生み出す点である。つまり、企業の業績への貢献が平均以上の雇用者は、企業だけでなく同僚にも利益を与え、反対に平均以下の雇用者は企業だけでなく同僚にも損失を与えることになる。日本型ボーナス制度は、欧米型制度と異なり、単に企業と雇用者の間だけでなく雇用者間にも利害の連動をもたらすのである。これは雇用者間の結束と協力のインセンティブを引き出すとともに、奥野(Okuno, 1984)が示したように、「ただ乗り者」の同僚に対する強い規範的拘束の必要を生み出す。
この結束と規範的拘束を同時に生み出す日本型ボーナス制度は、不確実性が少ない状況で集中力が重要なときには機能を果たすが、不確実性が増し、多様で自由な個人の貢献による環境適応力が重要な時期には、個人がリスクを取る行動を抑制するのでむしろ逆機能となる。また、外部性の存在は雇用者間の共同責任を強化することになった。
このように終身雇用制度、年功序列的賃金制度、長時間労働、日本型ボーナス制度、共同責任のもとで、会社の成長と正社員の所得と地位の成長が一致しやすい「運命共同体」的状況が高度成長期に生まれたことも、「保障と拘束の交換」を雇用者が受け入れる下地を作ったといえる。
日本的雇用システムの機能不全と女性の不活用
このような相互補完的制度の確立は、既存の制度を前提として積み上げる際の戦略的合理性を有していた。しかし、相互補完的に出来上がった制度の有効性は、その機能の前提が外的条件の変化のもとで崩れた際には、制度変換の部分的手直しが出来難く、劣等均衡でありながら、そこから抜け出せない大きな足枷ともなる。
これをまとめたのが表1である。R1とC1の組み合わせが高度成長期の状況である。一方、R2とC2の組み合わせが現在の状況であり、そこでは終身雇用も内部労働市場ももはや機能しない。終身雇用は雇用調整にとって硬直的であり、内部労働市場は同質的な情報を持つ集団が決定権を持つので環境適応力が小さいからである。
| C1:市場で評価される技術革新などで成功モデルの不確実性は小:集中力が重要 | C2:市場で評価される技術革新などで成功モデルの不確実性が大:環境適応力が重要 | |
| R1:労働需要の安定的増加が期待できる。雇用調整の柔軟性の必要なし | 終身雇用、内部労働市場は機能する | 内部労働市場は逆機能、多様性は機能 |
| R2:労働需要は不確実、雇用調整の柔軟性が必要 | 終身雇用は逆機能 | 終身雇用、内部労働市場は逆機能、多様性は機能 |
日本的雇用システムの機能不全のもう1つの結果が、著しい女性人材の不活用である。一方で家庭内の伝統的男女の分業のもとで家事育児責任を担わされた女性には、長時間労働も拘束性の強い働き方も、男性並みに出来ようがない。このため7割以上(現在は6割程度)の女性が結婚や育児を契機に退職するようになり、それが他方で、企業が女性は結婚・育児離職するものという前提のもとに、女性に対し人材投資や人材登用をしない慣行を制度的に作り上げる結果となったのである。
問題は、企業が自分たちの雇用システムそのものが不合理な女性の不活用を生みだしているという認識に乏しいことだ。厚生労働省が行った企業に対するアンケート調査によると、女性の管理職がいない・少ない「3大理由」の第1が、「現時点では、必要な知識や経験、判断力を有する女性がいない」というもので、過半数の企業がこの理由を挙げている。第2、第3の理由は「将来管理職に就く可能性のある女性はいるが、現在管理職に就くための在職年数などを満たしている者はいない」「勤続年数が短く、管理職になるまでに退職する」というもので、共に女性の勤続年数の短さを理由に挙げている。企業から見れば女性は経験不足だからというのが主な理由である。しかしこれは事実と矛盾する。
図1は最近筆者が『日本労働研究雑誌』に発表したものだが(山口、2014)、ホワイトカラーの正規雇用者に限った2009年調査の結果である。縦軸は管理職割合で、横軸は入社年である。図は勤続年数が同じでも、男女の管理職への昇進率は著しく異なることを示している。女性正社員が一生(入社年が1979年以前で31年以上)その企業に勤めて達成できる課長以上割合(20%)を、男性正社員は11~15年目に達成し、女性正社員が一生その企業に勤めて達成できる係長以上割合(50%)を、男性正社員は6~10年目に達成してしまうのである。
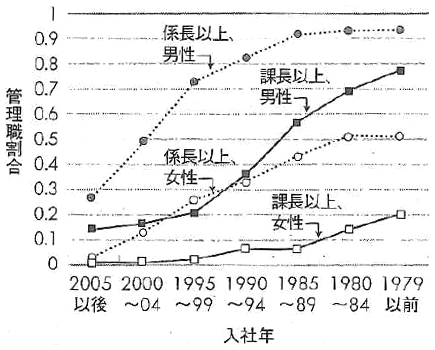
つまり、女性の勤続年数が短いという企業側理由は、勤続年数が同じでも男女で昇進率が著しく異なる事実を無視する点で、極めて一面的である。しかし図1は男女の教育差を考慮していないという批判があるだろう。かつて女性は短大卒が多く、大卒割合は男性よりはるかに少なかった。その疑問に答えるのが図2である。
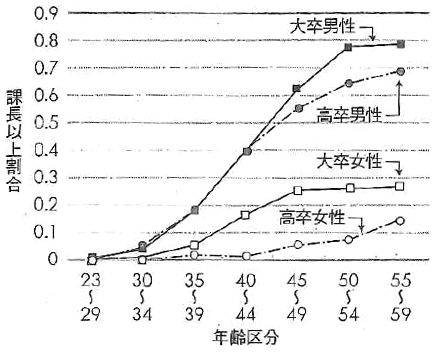
図2は男女別・学歴別に、課長以上割合を縦軸に、年齢を横軸に示している。結果は高卒男性の方が、大卒女性よりはるかに課長以上割合が高いことを示している。
社会学では生まれによる属性で社会的機会が定まるのを前近代社会、教育など達成の属性で定まるのを近代社会と言うが、わが国はこの点でいまだ近代社会と言えない特徴を有している。
ちなみに米国では、管理職になるには大卒であることや経営修士(MBA)の資格を持つことなど、学歴が性別によらず最も強く影響する。筆者の上記論文での分析では、男女の教育・年齢・勤続年数の差で説明できる男女格差は係長以上割合で30%、課長以上割合ではわずか21%であった。
男女格差を説明する他の要因に労働時間、特に通常週49時間以上従業しているか否かがある。男女の労働時間差をさらに説明要因に加えると、男女格差を説明できる度合いは係長以上割合で43%、課長以上割合で39%と大幅に増大する。また長時間労働と管理職であることの関係は女性の方が男性より強い。
この事実と関連し、男女の管理職格差の原因について、加藤・川口・大湾(Kato et al., 2013)の経済産業研究所での最近の企業内人事についてのパネル調査データ分析は以下の2つの重要な事実を明らかにした。
1つは長時間労働は男性の昇進率を高めることはないが、女性では昇進率に大きく影響するという事実である。これは長時間労働が女性にのみ管理職資格要件となっていることを示唆する。
2つ目の発見は、高い人事考課結果が男性では昇進率を高めるのに、女性では高めないという事実である。これは、女性は人事考課結果によらず昇進率の低い職に配置する「間接差別」の存在を示唆する。実際女性のホワイトカラー職の約4分の3が事務職に配置され(男性は約4分の1)、「女性事務職」は「男性事務職」と異なり残業時間が少なく、管理職昇進率が著しく低いという特徴を持っている。つまり、長時間労働が女性にとって男性以上に管理職要件なのは、残業をしない者は、その大多数が女性の「一般事務職」であり、能力にかかわらず最初から管理職登用候補から外され、潜在的にはより多様な能力があっても事務能力以外発揮できない職に就かされているからである。
経済産業研究所の2009年の調査では、わが国の従業者100人以上の企業で課長以上の女性が1人もいない企業は45%にものぼる。また、管理職者中の女性割合でいうと日本は約10%、米国では40%を超える。日米女性に潜在的管理職能力に差はないと考えられるから、これはわが国企業の著しい女性不活用といえる。
女性の活躍推進のための雇用制度改革の重点は何か
結論として、女性の活躍の推進には、雇用者が性別によらず能力発揮できるよう、企業が人材活用のあり方について従来の時間的拘束性の強い働き方から、労働者の時間管理の自律性のある、柔軟な働き方に変える必要があるが、それには以下の点が重要である。
(1)企業トップが合理的な女性活躍推進にコミットし、必要な制度改革を主導する。
(2)女性に対する間接的差別制度となりうる制度を廃止する。一般職・総合職の区別といったコース制を通じた職務経験機会と昇進機会の男女格差、女性割合が多い非正規雇用者に対する賃金差別、長時間労働を管理職要件とすることなど、すべて女性に対する間接差別を内包している。
(3)長時間労働に依存し、1日当たりの生産性を重視する働き方から、時間当たりの生産性を重視する働き方に転換する。実際わが国の時間当たり生産性は、他の多くのOECD諸国より低い。また、わが国より時間当たり生産性の高いOECD諸国のすべてがわが国より女性人材活用度が高い。
(4)職務内容を明確化することで個人の生産性を計りやすくするとともに、労働者(特にホワイトカラー)の時間管理の自律性を高め、長時間労働でなく職務達成の評価により昇進・昇給機会が与えられるルールを確立する。
(5)雇用者福祉でなく、人材活用の手段としてのワークライフバランス施策を導入する。
だが初めに述べたように、相互補完的に出来上がった日本の雇用制度を企業の自主努力で改変するのはなかなか難しい。この点で筆者は以下の3点の法制化が必要と考えている。特に初めの2つは、長時間労働に依存するわが国の慣行の根本的見直しを企業に要求する。
(A)最大労働時間の制限。例えば労働基準法の限定時間の趣旨に沿い、原則週55時間を最大就業時間とする。
(B)オランダ、ドイツ、デンマークなどで法制化されている、労働者がペナルティを受けずに就業時間を一定程度選択できる権利をわが国も保障する。
(C)わが国の雇用機会均等法改正における極めて限定的な女性への間接差別の定義を改め、例えば英米流のより包括的定義に変える。
最後にあえて付け加えると、女性の活躍の推進は、単なる経済成長戦略の手段であってはならない。多様な個々人が、より自由に生きられることでその潜在能力をより開花でき、その結果個々人がより良く生きられるとともに社会により良く貢献でき、また、その結果、経済組織も社会も活性化する。そのような社会に日本がなるための試金石として、女性の活躍の推進があり、仕事と生活の調和の達成も存在する、と筆者は考えている。
「中央公論」2014年12月号(中央公論新社)に掲載


