資本は先進国から発展途上国に輸出されるという「定型」に反して、東アジアなど貯蓄過剰な途上国から先進国への資本輸出が拡大している。先進国での家計貯蓄率の低下もこの傾向に拍車をかけており、日本も5年後には資本輸入国に転じる可能性がある。
2つの「定型」現在は不成立
通商とともにグローバル化の原動力となるのが、金融市場の国際的な発展である。そもそも発展した金融市場が経済にどのように貢献するかといえば、収益率が低い国から高い国への資本移動を可能にすることと、余剰資金を持つ主体から資金不足の主体への資本移動を可能にすることの2つを通してである。
第1の国際資本移動については、資本蓄積の遅れた発展途上国における資本収益率は先進国より高いため、資本自由化により、先進国から途上国への資本輸出が発生するという「定型性」が予想される。実際、19世紀における英国や第一次大戦以降の米国は、リーダー国であると同時に資本輸出国であった。また、第2の余剰資金の移動については、20世紀以降、先進国において「所有と経営」の分離が進み、家計の貯蓄が企業の投資を可能にするという「定型性」が確立した。
驚くべきことに現在の世界経済では、この2つの「定型性」がともに成り立たなくなっている。第1の「定型性」については、1997年のアジア通貨危機の後に逆転現象が起き、現在は先進国が途上国から資本を輸入している(表)。この表は、かつては資本を輸入していた東アジアが、通貨危機後には資本輸出をするようになったことが逆転の大きな原因であることを示すが、これも通貨危機の産物である。
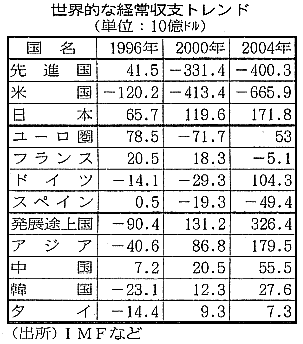
つまり東アジアは、活発な投資が誘発したドル建て短期債務の膨張に対して、ドル準備が不十分であったために、取り付け騒ぎの性格を持つ通貨危機を経験したのだが、それに懲りて政府が外貨準備を増やす一方、企業も投資に慎重になったので、貯蓄が投資を超過し、経常収支が黒字に転じたのである。
世界的には貯蓄が過剰
今年4月にバーナンキ米連邦準備理事会(FRB)理事(当時)は、現在の世界的な国際収支不均衡問題の主因は、東アジアの異変が引き金となった「世界的な貯蓄過剰傾向」にあると指摘した。そう考えられるのは、もし最大の資本輸入国である米国の資金需要がこの問題の主因ならば、過剰な資金需要を反映して実質金利が上昇するはずなのに、逆にそれが低下しているからである。
では先進国の中で、なぜ米国の経常収支赤字だけが突出したのか。それは、景気後退の兆候に対して積極的な財政金融政策で応じたからだ。「貯蓄」とは所得のうちの支出に向かわない部分であり、それを「投資」による支出で補えなければ、所得に対する支出の欠乏が不況を生む。それゆえ「世界的な貯蓄過剰傾向」は、実質金利の低下とともに不況の危険をもたらすので、米国の政策は世界不況を未然に防いだ意義がある。
だが、米国に限らず、最近の先進国が採った金融緩和策には、バブル誘発という副作用もある。つまり、金利引き下げが住宅投資を刺激し、それがバブルの疑いの強い住宅価格の高騰につながって、それに気を良くした家計の消費拡大という景気刺激効果を生むのである。住宅価格が上昇した先進国では経常収支の悪化傾向が見られ、住宅価格が現在も下落する日本やドイツで経常収支が好転するのと好対照をなす。
次に、家計の貯蓄が企業の投資を可能にするという第2の「定型性」にも、先進国では変化があった。つまり、家計貯蓄率が大幅に低下する一方で、企業の貯蓄超過(貯蓄と投資の差額)が増大した。とくに米国の家計貯蓄率はほぼゼロに落ちたが、これは景気刺激策による消費拡大と表裏一体である。他方、企業の貯蓄超過が最も顕著なのは日本である。ただし企業全体としては、デフレが定着した1998年以降の傾向で、「一般企業(非金融法人)」と「金融機関」に分けると、「一般企業」の数字は景気との連動性が強い。
これはおそらく、不況では債務の返済を優先して投資を控えるためで、バブルのピークの1990年には53兆円、1997年にも11兆円の投資超過であったのが、1998年に20兆円の貯蓄超過に転じ、2003年でも10兆円の貯蓄超過だ。他方で「金融機関」は、不良債権に対する引き当てのため、バブル崩壊後の1992年以来、一貫して貯蓄超過である。そのピークは2000年の18兆円で、2003年には15兆円まで下がっている。
アジア通貨危機が起きた1997年は、金融破綻により日本でも経済が暗転した年だ。したがって、東アジアが資本輸出に転じ、日本企業が貯蓄超過に転じた現象は、ともに不況における「減量経営」の反映である。つまり、現在の国際収支パターンの「異常性」の一部は短期要因による。しかし、それに加えて2つの長期要因があることも見逃せない。第1は、中国ファクターである。中国は近年、投資を大幅に増加させているが、それでも貯蓄が上回り、世界的な「貯蓄過剰傾向」を助長する。第2は、先進国において高齢化により家計貯蓄率が低下していることだ。
日本収支動向 企業の貯蓄カギ
とくに注目されるのは、1947年から1949年に生まれた団塊の世代が、2007年から09年にかけて引退する日本である。退職者は貯蓄を引き下ろして生活するので、今後、家計貯蓄率は急低下する。今年の『経済財政白書』は2010年の家計貯蓄率を国内総生産(GDP)比で2.5%(可処分所得比で3%)程度と予測する。しかるに、現在の日本の公債残高はGDP比170%だから、金利を2%とすると、国は毎年GDP比3.4%の利払いが必要で、これだけで将来の家計貯蓄を上回る。果たして5年後の日本は、国債の消化に外資の助けを必要とするのか。
その鍵となるのは企業の貯蓄である。「一般企業」は好況では投資超過になるが、5年後にそうでなければ日本経済はジリ貧である。「金融機関」も多分それまでに不良債権問題を解決し、貯蓄超過を減らす。今は世界最大の資本輸出国である日本が資本輸入に転じれば、世界的に実質金利が急騰して投資が減少し、日本の企業はやはり貯蓄超過を増やすかもしれないが、わずか5年後に、赤字国債の消化に外資の助けが必要になる心配は消えない。その場合、世界全体としても、主要国経済が東アジアと産油国からの資本輸入に立脚するという異常な状態になる。
巨額の財政赤字を抱えて資本輸入国になるのなら、それに備えて国内金融市場のテコ入れが必要だというのが小泉政権の考えだろう。衆院選挙で焦点になった郵政民営化もその一環である。完全民営化が12年先という法律の成立によって日本経済がすぐ改善するわけではないが、世界最大の金融機関である郵貯の資金運用の透明性は、日本の金融市場の透明性に直結し、郵政事業の売却益は、将来の国の借金返済を助けるから、郵政改革はマーケットへの宣伝効果が大きい。
宣伝ということでは、衆院選で亀井静香氏への「刺客」として堀江貴文氏を広島の選挙区に立てたのも、明らかに敵対的買収の「公認」というメッセージをマーケットに送るためだ。この選挙によって小泉氏が「マーケット・フレンドリー」という称賛を英エコノミスト誌から受け、日本の株価が上昇したのはまさに政権の思惑通りであろう。しかし、巨額の国債残高を抱えながら、今後貯蓄率が急低下する日本の先行きを考えるなら、これはもちろん「小さな一歩」にすぎない。
2005年10月18日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


