未曽有の大地震と大津波によって引き起こされた福島第1原子力発電所事故は、原子力災害の脅威を改めて世界中に再認識させた。原子刀発電の安全性に対する信頼が大きく傷つけられた状況で、わが国においても原子力政策の方向性を含むエネルギー政策の見直しが始まった。
くしくも東日本大震災当日に、現在のエネルギー政策の見直しに密接に関係する法案が閣議決定された。再生可能エネルギー特別措置法案(いわゆる再生エネ法案)である。この法案は、太陽光や風力、地熱などの自然エネルギーをもとに発電された電気について、国が定める一定の期間・価格で電力会社に買い取りを義務付けるものである。
買い取りに要する費用は使用する電力量に比例した賦課金(サーチャージ)という形で電力料金に上乗せされ、電力需要家である一般家庭や企業が負担する。本法案については菅直人首相が今国会での成立に強い意欲を示すが、コスト増を警戒する経済界などから根強い反対がある。
自然エネルギーの導入拡大は、地球温暖化対策の一環として福田康夫内閣のころから重要な政策課題であった。既に導入されている住宅用太陽光発電に対する余剰電力買い取り制度はまさにその流れをくむものだ。再生エネ法案は、住宅用太陽光発電に限定していた余剰電力買い取り制度を事業用にまで拡大・拡充することで、地球温暖化対策のみならず、エネルギーセキュリティーを向上させ環境関連産業を育成しようとする政策的な狙いがある。
再生エネ法案を議論した昨年時点の試算では、2020年までの自然エネルギーの追加導入量の過半は住宅用太陽光発電によるとされていた。しかし、大震災をきっかけとする原子力政策の見直しで状況が変わった。5月の主要8カ国(G8)首脳会議で菅首相は、発電電力量に占める再生可能エネルギーの割合を20年代に20%超の水準に到達させると述べたが、事業用を中心に大幅な自然エネルギーの導入拡大を目指さなければ達成できないだろう。
今後のエネルギー政策の見直しで議論すべき論点は多岐にわたるが、本橋では再生エネ法に焦点を絞り、自然エネルギー電源を普及させる際の課題を3つ取り上げたい。
◆◆◆
まず買い取り価格の設定についてである。グラフにあるように、自然エネルギーは既存電源と比較して発電コスト(設備の耐用年数内で稼働・投資コストを回収できる発電単価)が高いうえ、エネルギー種別によって格差が極めて大きい。自然エネルギーの大量導入には、国民負担の最小化の観点からも、コストが低く効率性が高いものから競争的に普及させられるような枠組みを考える必要がある。
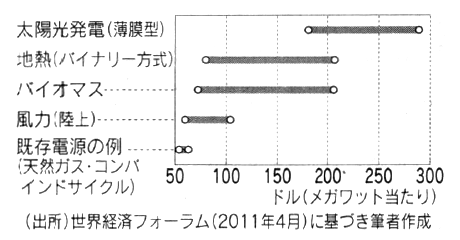
わが国では、1970年代の石油ショックを機に太陽光発電に関する研究開発を積極的に進めてきたことから、自然エネルギー電源でも太陽光発電に注目が集まりがちである。しかしそのコストは今なお高く、海外においては風力発電を自然エネルギーの主軸に据えるのが一般的である。
太陽光や風力といった自然エネルギーの種別ごとに、そのコストに基づいて買い取り価格を決めてしまうと、異なる自然エネルギー間での競争原理が働かなくなり、社会全体の効率性の観点からいびつな形で自然エネルギーが導入されかねない。自然エネルギーを導入するためのコストが将来どこまで低減するのかを科学的知見に基づいて精査しつつ、経済効率の観点から自然エネルギーの最適な構成(ベストミックス)を達成できるように買い取り価格を設定すべきだろう。
次に、自然エネルギーの導入を促進することによる経済効果についてである。再生エネ法の素案を議論していた昨年4月公表の試算では、再生エネ法により住宅用太陽光発電が普及すると、想定されるシナリオに応じて20年までに総額2兆~40兆円程度の経済波及効果を見込んでいた。
数字だけをみるとかなりの経済効果があるようだが、試算の前提条件として海外製品との競合がないほか、再生エネ法に伴う国民負担増により企業が生産拠点を海外に移転することはないなどの現実性に欠ける仮定を置いている点に注意が必要である。
特に風力発電や事業用太陽光発電については国際的にみても日本の高コストは明らかである。実際、わが国が強みを持つとされる住宅用太陽光パネルでさえ輸出に苦戦しているうえ、国内市場でも中国を中心とする海外からの安価なパネルの輸入増が目立つ。
他方で、わが国の製造業は近年の円高や雇用規制の見直しを背景に海外への拠点シフトを加速させている。今回の再生エネ法の導入により、電力を多く消費する産業(例えば化学産業や電炉業)を中心に、国内での雇用継続がさらに困難になる状況も想定される。自然エネルギーの普及による経済効果について、震災後の産業界の実態を踏まえて改めて検討し直す必要があるだろう。
自然エネルギーの導入コストを電気使用量に応じて回収する枠組みは、電気の需要家に節電への努力や省エネに対する投資を促すと期待できる。しかし、自然エネルギーの普及による低炭素化のメリットはエネルギーに関わる経済全体に及ぶことを考えると、コスト負担を電力料金だけに課すことが公平性の観点から合理的かどうか、説明を尽くす必要がある。
再生エネ法の精神を制度として持続可能なものとするには、自然エネルギー普及の負担増を電力料金以外に税金などでも支える仕組みとする視点も重要ではないだろうか。
◆◆◆
最後の論点として、自然エネルギーの普及促進の観点からあるべき電力の供給体制について考えたい。
当面は、供給力確保のために発電・送電双方における一体的な投資や運営を迅速に進めなければならないので、発送電一貫の電力会社に任せることに経済合理性がある。発送電部門を分離すると、両部門を同期的に調整することが難しくなり、電力の需給逼迫がさらに深刻になりかねないからである。
しかし、中長期的には自然エネルギー普及に伴う国民の負担増を少しでも減らすためにも、事業のより一層の効率化が求められる。東京電力の置かれた状況と合わせ、日本全体の電力事業のあるべき姿を真正面から議論すべきだ。
中長期的な電力事業のあり方には少なくとも2つの方向性が考えられそうだ。ひとつは発電部門あるいは小売・卸部門における競争の活性化である。新規参入者が送電線を使って様々なサービスを提供すれば、電力需要家の新たなニーズが開拓されイノベーション(技術革新)も活性化することが見込まれる。
わが国でも電力市場の活性化を目的として、これまで4回にわたる制度改革を通じ、発電部門の自由化、小売部門の部分自由化、そして発電部門と送電部門の会計分離などを進めてきた。特に送電部門については電力会社から独立した中立機関を設置し、送配電の接続・利用に関して新規参入者が不当な取り扱いを受けることのないよう監視する仕組みをつくった。
電力会社の発電・送電部門を別会社にする構造的な発送電分離を求める声は、これまでの制度改革での会計分離がうまく機能していないとの認識も背景にあると思われる。まずは会計分離の問題の所在を明確にすべきだ。問題の性質によっては構造分離が必ずしも適切な解ではないからだ。例えば、新規参入者が系統を自由に使えないことが問題であれば、系統接続の規制強化が適切な対応である。
◆◆◆
効率的な電力事業を目指すうえでのもうひとつの方向性は、規模の拡大である。海外に目を転じると、欧米では、資源ナショナリズムの台頭とそれに対する交渉力を確保するために、電力やガス業界などの分野を越えた合併が相次いでおり、巨大なエネルギー総合企業が誕生している。
わが国でも電力事業の経営リスクが格段に高まる中で、低廉な電力を安定的に供給するには、リスクに耐えられるだけの規模拡大を目指すことが重要な経営課題となってよい。最終的な供給責任主体を明確にしつつ、発送電分離の議論をきっかけとして地域や業界の垣根を越えた再編の機運が高まるのであれば、わが国のエネルギー産業の将来にとっても望ましいことだ。
2011年7月8日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


