消費税の引き上げが迫り、景気への影響が心配されている。消費増税は財政をいくぶん改善するが、巨大な公的債務残高に比べ、その効果は小さい。今回は消費税と、それによって支えることができる公的債務の大きさの関係について考える。
一般に、税率を上げすぎると税収が減るという関係が、あらゆる税について成り立つと考えられてきた。ラッフアー・アソシエーションのアーサー・ラッファー会長は1974年、税率と税収の関係は図(上)のラッファー曲線のようになると主張した。
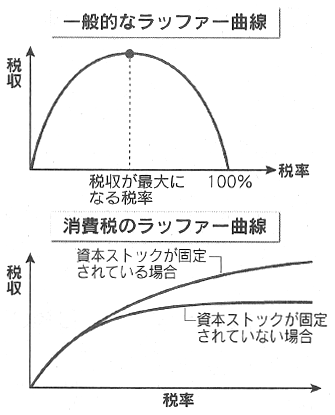
例えば労働所得税で考えると、税率が低いうちは税率を上げるにつれ税収は増える。しかし、税率を上げすぎると、賃金の大半を税として取られてしまうので、労働者はバカバカしくなって働かなくなり、賃金所得が減る。課税ベースが減るので税率を上げても税収は減る。つまりラッファー曲線は逆U字型になるのである。税率の上昇が労働者の意欲を低下させるなどして実体経済を悪化させることを「税のゆがみ」という。
これが正しければ、どのような課税政策をしても政府が得られる税収には上限がある。したがって税収で支えられる公的債務の規模にもにも上限があるはずだ。また、税収は経済の規模以下になるのが当然で、税収に上限があるのも当たり前のように思える。
しかし近年、実はこの想定が消費税については当てはまらないかもしれないことを示唆する研究が出てきた。
◆◆◆
欧州中央銀行のマシアス・トラバント氏と米シカゴ大学のハラルド・ウーリッグ教授は2011年の論文で、労働所得税、資本所得税、消費税について、米国と欧州連合(EU)諸国のラッファー曲線を推計した。専修大学の奴田原健悟准教授は13年、この論文をもとにキヤノングローバル戦略研究所で日本のラッファー曲線を推計した。
奴田原准教授は、大東文化大学の郡司大志准教授と法政大学の宮崎憲治教授が11年の研究で推計したデータからラッファー曲線を計算し、税収を最大化するには労働所得税を増税し、資本所得税(法人税に相当)を減税すべきだと論じている。
トラバント氏らと奴田原准教授は、消費税のラッファー曲線は右上がりである、ということを発見した。つまり消費税の税率を上げると、消費税による税収は増え続けるのである(図参照)。彼らのモデルでは、消費税率を上げ続けると、消費税収はある一定の数値に向かって増え続ける。つまり、消費税収は増え続けるが、上限がある。
◆◆◆
しかし、仮定を少し変えるだけでこの結果は大きく変わる。トラバント氏らは、生産設備などの資本ストックの供給量は変動し、減ることがあると仮定している。筆者の計算では、「経済活動には、土地のように供給量が一定の生産要素も必要である」と仮定すると、消費税率を上げれば税収をいくらでも大きくできるのである。
なぜ資本ストックの量が変化する場合は消費税収に上限があり、資本ストック(土地)の量が一定のモデルでは税収をいくらでも増やせるのだろうか。新古典派成長モデルでは、消費税率が上がると「税のゆがみ」で労働投入が減り、機械などの生産要素も減ると仮定している。このため増税により消費が減る度合いが大きく、税収はあまり増えない。だが土地は労働投入が縮小したからといって減らない。このため土地の存在を組み込んだモデルでは消費の減り方が小さく、結果的に税収は際限なく増え続けるのである。
生産量や労働力が有限なのに、消費税収が際限なく増える、という結果は直感的には信じがたい。矛盾を解く鍵は、「集めた税金が、すぐにまた課税対象になる」という点にある。消費税収は国債の償還や社会保障給付などとして国民に支払われ、ふたたび消費に回され課税される。このため消費税収と国民の収入がともに国内総生産(GDP)の大きさを超えて、両建てで増えることが可能なのである。
消費税率を上げればいくらでも税収を増やせるということは、理論的には「消費税率を上げれば、いかなる額の公的債務でも持続可能にできる」という驚くべき事実を示している。公的債務は将来の税収の現在価値を超えられないが、消費税率を上げれば、将来税収は将来のGDPを超えて際限なく大きくできるからである。
◆◆◆
ただこの結果は、あくまでも理論的な目安だ。どんな額の公的債務でも消費税を上げれば持続可能にできるとしても、社会全体にとって最適な債務と消費税率の組み合わせは存在するはずである。
例えば、消費税率を上げると国民の消費量は減少し、最終的にはゼロに近づいてしまう。これも「税のゆがみ」である。税率が上昇すると消費財が割高になるため、国民は消費財購入を減らし、それらを使わない余暇を増やす。その結果、労働供給もGDPも減少し、税率を無限大にするとゼロになる。消費額も税率の上昇とともに減少していく。税収を増やせたとしても、これは社会にとって望ましい状態ではない。
一方、公的債務(国債発行)が増えることにはメリットもある。国債は家計や企業に貯蓄手段を提供する。家計や企業はいざというときのために資源を保蔵する必要があるが、金属などのような生産手段としても使えるもので保蔵されると、生産活動が減り、経済全体では無駄が生じる。国債が貯蓄手段になれば、こうした資源が生産に使われるため経済の効率が上がる。
この効果は、国債には世代間の消費を平準化させる効果があると論じた米マサチューセッツエ科大学(MIT)のピーター・ダイヤモンド教授の1965年の論文の指摘とほぼ同じである。MITのベングト・ホルムストロム教授とトゥールーズ第一大学のジャン・ティロール教授の98年の論文も、企業に手元資金の急な枯渇が生じた場合に国債は経済効率を高めるとした。
最近は、金融危機との関連で、資産バブルが崩壊したときに国債発行を増やすとバブル崩壊が実体経済に及ぼす悪影響を緩和できる、と指摘されている。例えばMITのリカルド・カバレロ教授と米ノースウェスタン大学のアーヴィンド・クリシュナムルティ教授の2006年の論文や、ミネアポリス連銀のナラヤナ・コチャラコタ総裁の09年の論文がある。
このような国債発行のメリットと、税のゆがみによるデメリットのバランスを考えると、最適な国債発行額と消費税率が存在することが分かる。国債発行額と消費税率が小さいときはメリットが勝るので、社会にとっては税率(と国債発行額)を上げることが望ましい。しかし税率が上がるにつれてメリットが減少し、デメリットが増加する。社会厚生は税率がある値になると最大になり、さらに上げると減少する。この値が最適な債務と消費税率になる。
最適な債務量とそれを支える消費税率は、経済モデルの構造によって大きく異なる。現実的な値を得るには精緻なモデル作りが必要だ。いずれにしてもGDPの230%近い日本の公的債務を消費税でまかなうには大幅な増税が必要で、最適規模を超えていることは間違いないであろう。
2014年2月14日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


