日本における雇用関係は、1980年代から現在に至るまで20年以上の長期にわたって徐々に変化してきた。変化の方向は、企業と労働者の間の暗黙の信頼関係に基づいた日本型雇用慣行の重要性の低下である。本稿では長期の変化を概観し、その変化をもたらしている原因を指摘するとともに対応策を提案したい。
戦前から高度成長期にかけて発展した日本型雇用慣行は長期雇用、年功賃金、企業別労働組合で特徴づけられる。これらの特性は近年どのように変化しているのだろうか。
◆◆◆
まず長期雇用の慣行についてみると、日本の雇用労働者の勤続年数は短期化しつつある。上野有子氏と筆者は82~2007年の総務省「就業構造基本調査」を用いて、同一企業への勤続年数がどのように変化したかを分析し、内閣府より発表した。この期間に労働者の年齢構成が変化していることに注意しながら、同じ年齢時の平均勤続年数が世代によりどのように変化したかを調べたところ、男性労働者(非正社員含む)に関しては44~49年生まれの世代よりも若い世代では一貫して平均勤続年数が短くなったことが明らかになった(グラフ参照)。
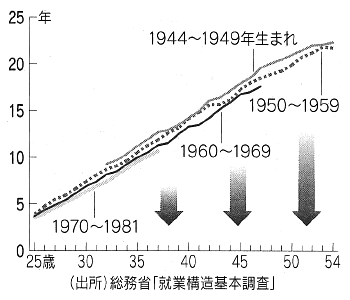
例えば45年生まれと比べると、70年生まれの男性はどの年齢でみても、およそ2割勤続年数が短い。こうした勤続年数の短期化の傾向は、正社員か非正社員かを問わず、勤め先の企業規模や産業を問わず、同じように起きている。
また雇用労働者の平均勤続年数の短期化は、雇用労働者に占める非正社員の増加によっても説明できる。総務省「労働力調査」によると、84年時点では雇用労働者の15%を占めるにすぎなかった非正社員は、10年時点では34%にまで増加している。
年功賃金については、濱秋純哉氏、堀雅博氏、前田佐恵子氏、村田啓子氏らが厚生労働省「賃金構造基本統計調査」に基づいて内閣府から発表した論文は、加齢に伴う賃金増加を示す賃金カーブが89~08年の20年間に、特に40歳以上の中高年層で平たん化したと報告している。加えて厚労省「労働組合基礎調査」によると、労働組合の推定組織率はほぼ一貫して低下している。
これらの統計の動きは長期雇用、年功賃金、企業別労働組合といった日本型雇用の特徴が、およそ20年間の長期にわたって徐々にその特徴を弱めてきたことを示している。
それではなぜ長期雇用や年功賃金といった日本型雇用慣行の根幹を成す特徴は弱まってきたのだろうか。原因を探るためには、そもそも日本型雇用慣行がどのような経済環境の中で成立してきたかを考える必要がある。
企業が早い段階から労働者を囲い込み、企業の内部で育成していくという日本型雇用慣行は戦前に起源を持つことが知られており、その重要性がピークを迎えたのが高度成長期であった。欧米諸国から導入した新しい技術を使いこなすため高い技能を持った労働者が必要になったが、そうした労働者を市場から調達することが難しかったため、各企業が独自に労働者を育成してきたといわれる。
各社で労働者の自社養成が重視されるようになると、転職をすることが前の仕事に向いていなかったとの烙印(らくいん)を押されることにつながり、転職が一般的ではなくなる。そうなると、今の企業で技能を磨いて転職を通じてキャリアアップを図ろうという意欲を労働者は持たなくなる。一方、企業は労働者の技能蓄積への意欲を引き出す社内制度を工夫する必要に迫られ、多くの企業は将来の雇用を暗黙に約束したり技能蓄積に対して昇給で報いる職能給制度を導入したりした。
その結果として、長期雇用と年功賃金が日本型雇用慣行の特徴となったのである。また将来の雇用保障や賃金上昇を前提として労働者が技能蓄積に励むためには、労働者の企業に対する信頼が不可欠であり、企業別労働組合は企業と労働者の情報伝達の仲立ちをして信頼関係を保つことに貢献してきた。
◆◆◆
このように長期雇用・年功賃金・企業別組合で特徴づけられる日本型雇用慣行は、労働者と企業が共同して技能に対して投資をし、その人的資産を保全し、投資からの収益を企業と労働者で分け合うという投資共同体を成立させてきた。景気の荒波にもまれた時には、正社員の労働時間やボーナス支払いを柔軟に調整して労使協調で解雇を避け、人的資産を保全しようとしてきた。
非正社員に対する職業訓練機会の提供が正社員に比べ低調という多くの実証研究の結果も、非正社員が日本型雇用慣行の枠外に位置すると考えれば説明がつく。
人的資産と技術水準は補完的な関係を持つため、技術進歩を反映する全要素生産性(広義の技術革新に基づく生産性)の成長率が高い時には、共同投資の結果である人的資産が高い収益を生み、日本型雇用慣行は魅力を持っていた。しかし、日本の全要素生産性成長率はバブル崩壊後に低下した。アジア生産性機構の推定によると、日本の全要素生産性は70~90年には年率平均1.0%で成長していたが、90~08年にかけては同0.4%の成長にとどまる。
バブル崩壊以降のマクロ経済の低成長は、人的資産に対する共同投資体としての日本型雇用慣行の存在基盤を揺るがすことになった。ただし、すでに長期雇用関係の中で形成された人的資産や労働者と企業の間の信頼関係を壊すことは、労働者にとっても企業にとっても望ましいこととはいえない。結果的に、新たに長期的な雇用関係に入る人々が少なくなる形で、日本型雇用慣行の中で働く人々が徐々に減少してきたのである。
浅野博勝氏、伊藤高弘氏と筆者が経済産業研究所のプロジェクトとして雇用の非正社員化を分析したところ、非正社員の増加は、若い世代の男性労働者や女性労働者といった労働市場への新規参人者に集中することがわかった。
ただ、日本型雇用慣行が特徴を弱めているとはいっても、性急にその役割を否定する必要はない。現在うまくいっている人材育成の機能をも否定しかねないからだ。むしろ目指すべきなのは、新卒時点に集中している正社員になるチャンスを少しでも分散させること、正社員にならなくても展望を持って働ける社会を構築することだろう。
◆◆◆
日本企業は共同投資体のメンバーとなる正社員の採用には極めて慎重である。そもそも企業が採用面接で自社に合った人材を見分けるのは難しい。様々な人材が入り交じる労働市場から適切な人材を探し当てるのは確率の要素も加わるため、適切な人材がいる確率が高い新卒から採用してリスクを減らそうとする。既卒者の中に適切な人材がいたとしても、よほど前の職場で実績を上げた人でなければ、あえてリスクを取ろうとしないのは仕方がないことだ。
面接だけでなく実際に働いてもらってから採用することができれば、中途採用に積極的になる企業が出てくるだろう。しかしこうした採用方法を妨げているのが試用期間の法的取り扱いである。試用期間終了後に正式採用しないことは、日本では解雇と同列に取り扱われている。そのため、「とりあえず働いてもらって相性がよければ採用する」という採用活動は現在の裁判所の判断の下では難しい。「試用期間の満了に伴う雇用契約の終了は解雇ではない」ことを法律で明文化すれば、正社員への入り口を多様化することにつながるだろう。
中途採用の機会が広がれば非正社員の中にも将来を見据えて技能蓄積に強い意欲を持つ人が増えるだろう。非正社員のスキルアップに取り組む企業に一段と人が集まるという好循環も生まれるだろう。非正社員の技能形成を促進するには、身につけた技能を生かせる中途採用の入り口を拡大することがまず大切だ。
一方で、正社員の入り口が多様化したとしても、全体としては非正社員として職業人生を歩む人々は増えていくだろう。その現実を受け入れたうえで、社会保障や労働市場制度などを設計することが必要だ。「非正社員の増加を異常な事態とみなして、正常な状況に戻そうとする」発想自体を転換することが、求められているのではなかろうか。
2011年8月30日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


