道路財源問題が大詰めを迎えている。道路利用を適切な水準にするには、利用者が社会的費用を負担するとの観点が重要である。この点で、暫定税率を撤廃して燃料税負担を下げる方向は正当化できない。費用便益分析で便益を甘く見積もっている点も修正すべきである。
2つの問題重なり合う
道路財源制度の見直しが政治的な争点になっている。こういったときこそ、冷静な分析に基づいて、代替案を周到に評価しなければならない。
そもそも、道路財源制度には、2つの問題が重なり合っている。
第1は、道路利用者にどれだけの負担を求めるべきかという問題である。暫定税率を廃止すべきかという現時点での争点がこれである。道路利用者は、燃料税に加えて、高速道路料金なども負担しているので、これらとの関係も重要である。
第2は、集めた税収をどう使うという点である。一般財源にするのか、特定財源にするのかという問題に加えて、地域間の配分をどうするかという問題もある。
燃料税や高速道路料金は、道路の利用や自動車の車種選択に影響する。たとえば、燃料税を低くしすぎれば、自動車利用が過剰になり、公共交通機関の利用が過小になる。また、燃費の悪い車が多くなってしまう。
道路利用は様々な社会的費用をもたらしている。これらはおおまかに、(1)道路サービス供給費用(道路損傷費用など)(2)他の道路利用者への外部費用(混雑費用、事故費用など)(3)道路利用者以外への外部費用(温暖化費用など)の3つに分けられる。道路利用を適切な水準にするためには、道路利用者がこれらの社会的費用を負担するようにしなければならない。
走行距離課税 燃料税で代替
筆者は昨年まとめた『道路特定財源制度の経済分析』で、道路利用の社会的費用に関する内外の研究を展望した。これによると、ガソリン乗用車のもたらす社会的費用は表のようにまとめることができる。
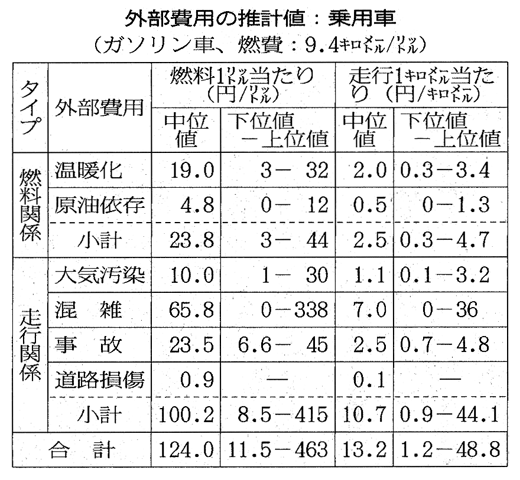
社会的費用の推計値には大きなバラツキがある。この表では、現時点でベストと思われる推計値を中位値とし、一定程度の信頼性があると思われる推計結果のうちで最低水準と最高水準をそれぞれ低位値及び高位値として設定した。
社会的費用の中で最大のものは混雑外部費用である。走行1キロメートルあたり7円、ガソリン1リットルあたりにすると65.8円と推計されている。これは、現在の燃料税より高い。ただし、混雑費用は混雑の程度に依存するので、時間帯や路線によって大きく変動する。
温暖化費用は、わが国での対策費用の推計値である炭素トンあたり3万円を前提としており、1リットルあたり19円とかなり大きい値となった。世界的には、これより低い水準とされていることが多いが、これから地球温暖化問題が深刻になっていくと、上昇していくことが予想される。
技術的、制度的制約がなく、自由に最善の政策を選択できるとし、さらに、中位推計値が正しいとすると、最適な税・料金体系は以下のような構造になる。
(1)温暖化及び原油依存費用に対応して、ガソリン税を1リットル当たり約24円にする。(2)走行によってもたらされる混雑費用、事故費用などに対しては、平均で1キロメートル当たり約10円の走行料金を負担させる。
現状では、高速道路などの有料道路以外で走行距離課税を導入するのは困難であり、これが燃料税で代替されていると考えることができる。走行距離課税部分について燃料税相当額を計算すると、中位値では、同約100円となる。
車体を保有すると、車両の生産プロセスで温暖化ガスが発生するといった問題がある。しかし、これは定量的には小さいので、ほとんど無視できる。また、生産段階での外部費用は、他の製造業と共通のベースで課税する方が望ましい。したがって、車体保有についての外部費用はほぼゼロであると考えてよい。
現行税制では、燃料課税は揮発油税に石油税などを含めてもガソリン1リットルあたり59円程度で、表の中位値合計の半分以下である。逆に、車体課税の方は重課されており、通常、車体課税の負担の方が燃料課税の負担よりはるかに大きい。また、高速道路料金は非常に高く、走行1キロメートルあたり25円程度と、ガソリン1リットルあたりに換算すると200円を超える。
残念ながら、本推計から揮発油税の水準を1リットルあたり90円にすべきか、120円が妥当かといった問題に正確な答えを出せる段階ではない。しかし、暫定税率を撤廃して、燃料税負担を1リットルあたり30円程度にまで下げることを正当化するのはほぼ不可能であろう。
税収すべてを道路に使うな
一方、利用者が社会的費用に見合う燃料税負担をしたとしても、税収をすべて道路整備に使うべきであるとはいえない。
第1に、温暖化費用などの道路利用者以外への外部費用分は、道路整備にあてる理由はない。環境税として一般財源にするのが望ましい。
第2に、道路損傷費用や混雑費用部分については、一定の仮定の下で、「収支均衡特性」が成立することが知られている。これが成り立つ場合には、最適な税率を設定して得られる税収で、最適な道路整備水準をちょうどまかなうことができる。しかしながら、収支均衡特性が成立するための条件は厳密には満たされていないことが多い。
おおざっぱには、以下のような問題である。道路として利用できるためには、一定程度の幅員や地盤整備、舗装などが必要であり、かなり大きな固定費がかかる。交通需要が少ない地域では、利用者の燃料税負担ではこの固定費をカバーできない。こういった場合でも、税負担以上の便益を受ける利用者がいるので、道路をつくった方がよいケースがある。例えば急病で病院に駆け込む人にとっては、道路利用の価値は税負担をはるかに上回るはずだ。このように超過分(経済学で消費者余剰と呼ばれる)が十分大きければ、赤字でも道路整備をした方がよい。
交通量が多く、ネットワークが密な大都市圏では、逆の状況になる。道路整備による追加的費用が逓増的になり、コスト増に見合った便益が得られなくなるからである。
第3に、生活道路については、歩行者へのサービスや防災機能などの自動車交通以外の便益が大きいので、固定資産税などの市町村民税から補てんするのが望ましい。
以上を踏まえると、個別プロジェクトの費用便益分析を積み上げて適切な道路整備水準を求め、それに必要な財源を道路整備予算とするアプローチが望ましい。政府が「道路の中期計画(素案)」で必要財源を積み上げ、それをベースに道路財源を決めているのは、このアプローチを採用していると解釈できる。
だが、この素案の中身は様々な問題がある。
例えば、道路関係税に関して、徴収費用や価格体系を歪めることで生じる付加的な社会的費用を考えれば、費用便益比を厳しく設定しなければならない。また、時間価値の設定も再検討が必要である。日本の場合には、欧米諸国と比較して、通勤やレジャーの時間価値が高めに設定されており、便益を過大推計する傾向がある。
さらに、現在の事業評価では日平均交通量が用いられており、ピーク時の渋滞がうまく取り込まれていない。通勤渋滞の顕著な地方都市近郊路線などでは便益が過小推計されていると思われる。
素案の中身に立ち入った議論はこれまでほとんど行われていない。中身を精査し、どれだけの財源確保が必要か、早急に判断すべきであろう。
2008年3月24日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


