1 研究の背景:社会資本整備事業への信頼を回復するために
公共事業バッシングがいまだに続いている。社会資本整備の必要性を国民に理解してもらうためには、無駄な公共事業を排除し、真に有益なものに絞り込まなければならない。一般の人たちにはあまり知られていないが、道路事業が先陣を切って導入した費用便益分析(あるいは費用対効果分析)は、無駄な公共事業を排除するための最も有効なツールである。
公共事業の評価においては、1件1件の事業について、その便益と費用を評価し、便益費用比が低いものは採択しないということを行っている。この仕組みについて国民の信頼を得ることが、公共事業に対する不信を取り除く最善の方策であろう。そのためには、用いられている評価手法、各種原単位(時間価値等)、需要予測等の妥当性をざまざまな立場の人たちが検証し、オープンな議論を行って評価の妥当性を評価する必要がある。また、評価手法について、その信頼性を高めるための不断の努力が必要である。日本交通政策研究会及び道路経済研究所におけるわれわれの研究プロジェクトでは、これらの要請に応えるための研究を行ってきた。
2 道路投資の便益推計手法に関する実務上の課題
便益評価実務における課題としてわれわれが取り上げたのは、2つの相互に関連する問題である。
第1に、現在の費用便益分析マニュアルでは、道路投資による便益を総交通費用の減少で計測するという「総交通費用方式」が採用されている。経路間の完全代替性が満たされている場合には、この方式を用いて差し支えないが、そうでない場合には、バイアスを生むことが指摘されている1)。完全代替性のもとでは、(一般化)費用が低い経路と高い経路が存在すると、利用者がすべて低い方の経路に流れなければならないが、これは現実的でない。一般化費用以外の要因が経路選択に影響するからである。
第2の問題は、需要予測と費用便益分析が同じ理論モデルに基づいておらず、これらの間の整合性に疑問があることである。
3 便益計測手法の選択についての基本的考え方
われわれの一連の研究では、これらの2つの課題にどう対処できるかを検討し、実務においてどのタイプの評価手法を選択すればよいかを考えた。
まず最初に、費用便益分析の基本に立ち返って、具体的な便益計測手法を選択する際の判断基準を検討した2)。費用便益分析においては、投資の便益について良好な近似を得ることが必要である。そのためには、(1)投資を行うケースと行わないケースの双方における交通量に加えて、(2)各利用者の一般化費用(金銭的費用、時間費用等を合計した利用者の実質負担)、(3)需要曲線の形状の3つを精度高く予測しなければならない。これら3つを精度高く推定するために、どういう手法が望ましいかを考えるのが、推計手法の選択における課題となる。具体的な推計手法については、いくつかの異なったアプローチが可能であり、対象プロジェクトの特性に合わせて適切な選択を行わなければならない。
4 便益推計手法のタイプ分け
便益推計手法はいくつかの視点からタイプ分けすることができる。
第1は、経路間の代替性である。完全代替を仮定するモデルは確定的均衡モデルと呼ばれている。完全代替を仮定しない便益推計手法にはロジットモデル等がある。
第2は、需要予測モデルと便益計測を分離するか、一体として整合的なモデルを用いるかの選択である。分離するアプローチでは、需要予測には4段階法等の必ずしも経済理論的には整合的でないモデルを用いる。便益推計においては、こうして得られた需要予測結果に需要曲線の形状に関する情報を組み合わせて便益推定値を得る。イギリスのTUBAでは、需要予測と便益推計を分離するアプローチを採用している。需要予測と便益評価を同時に行うことができるモデルには、上述の確定的均衡モデルやロジットモデルがある。
第3は、経路レベルで便益計測を行うか、あるいはODレベルの価格インデックスと交通量を用いて計測するかの選択である。
5 ODレベルと経路レベルの便益計測3)
ロジットモデルにおいては、ログサム変数と呼ばれている関数を用いて便益評価をODレベルで行うことができる。また、経路レベルの需要を用いて便益を計測することもできる。ロジットモデルであろうとなかろうと、通常の需要曲線を一般均衡的波及効果を含むように拡張した一般均衡需要曲線を用いれば、経路需要曲線の左側の面積(下図の網掛け部分の面積)で消費者余剰の変化が計測できる。
ロジットモデルでは、需要曲線のパラメータの設定によって便益推計値が大きく変化する。最も重要なパラメータは、所得の限界効用(一般化費用の係数)と経路ダミーの2つであり、これらのパラメータをなるべく正確に推定する必要がある。
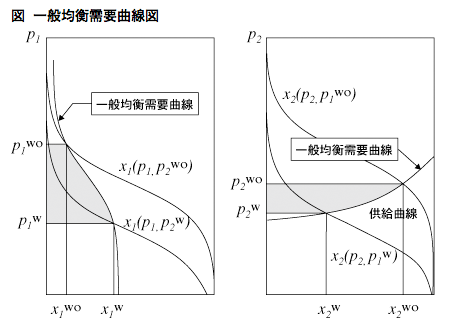
6 まとめ
われわれの研究プロジェクトでは、費用便益分析の実務を改善するという目標をもって、便益推計手法についての研究を行ってきた。便益推計には複数のアプローチがあり、それらから適切に選択しなければならない。いずれの方法を用いるにしても、めざすのは精度の高い便益推計であり、この視点からの評価が必要である。われわれの研究の最も重要なメッセージは、便益推計値を決定的に左右するのは、交通量予測値、一般化費用推計値、経路レベル需要曲線の形状の3つであり、これらの検証をしっかり行っていかなければならないということである。ODレベルで推計する場合でも、経路レベルの需要曲線を導出して、それが妥当なものになっているかどうかを検証することが必要である。
社団法人日本自動車工業会『JAMAGAZINE』2007年2月号に掲載


