わが国の男女共同参画、ダイバーシティ(多様性)の推進について、社会的公正と経済的合理性の整合性の観点から考察したい。社会的公正の自由主義的原理は経済的合理性と重なる部分も多い。しかしわが国の制度は公正と合理性の実現に矛盾を生み、経済・社会の活力を失わせている。
自由主義的公正原理の1つは社会的機会の平等で、個人的状況による障害を除去することが重要だ。貧困、育児、身体的障害の場合を考える。
シカゴ大学のJ・ヘックマン教授は、6歳未満児童の家庭教育環境の不平等の縮小が貧困階層児童の能力発達や地位達成の遅れを減少させることを、未就学児童の実験的教育介入と追跡調査で示した。わが国でも小学生の学習達成や学習意欲に大きな階層格差がみられることは、苅谷剛彦オックスフォード大学教授が指摘した。貧困家庭の未就学児童への教育介入は、家庭環境による機会の不平等を減少させ、生産的な国民を効率的に生み出す投資となる。
育児については例えば、柔軟に働ける職場環境の実現や保育施設の充実と政府による利用費援助は、女性の結婚・育児に伴う離職率を下げ、仕事と家庭の役割を両立できるようにし、男女の雇用と能力発揮の機会の平等を推進する。
また、米国における非重度身体障害者の雇用率はわが国を大きく上回る。平均所得も健常者の89%と大差はなく、能力が生かされている。
バリアフリーの社会の実現は、障害の有無によらない雇用と能力発揮の機会の平等をもたらし、障害者の経済的自立と生産性向上につながる。言い換えれば、初期条件(貧困)、ライフサイクル条件(育児)、偶発条件(身体的障害)による社会的機会の差を減少させる仕組みが重要だ。
わが国では貧困、育児、身体的障害などは福祉問題と考えられている。しかし、これらは機会の平等の問題であり、個人的状況の障害を取り除き、多様な人々が持てる力を発揮できる社会を実現することに経済合理性があるとの観点を欠いている。これらの制度改革・社会改革は一時的な費用を伴うが、将来への投資として必要なのである。
◆◆◆
もう1つの重要な原理は「分配」および「再分配」における公正原理だ。何が公正な分配なのかは価値観により異なるし、時代の要請でも変化する。現在は付加価値を生み出す多様な人材を輩出できるような公正原理が望ましい。G・ホマンズ元ハーバード大学教授は著書「社会行動-その基本形態」(1961年)で、「個人の貢献に応じた報酬」を自由な交換に基づく分配公正の原理とした。これは経済学者が合理的と考える「限界労働生産性に応じた賃金」の原理に近いが、報酬は金銭に限らず概念的にはより広い。この分配原理は報酬を通じて生産性向上や貢献をしようとするインセンティブ(誘因)を個人にもたらす。
わが国の報酬基準は、個人の多様な才能を生かせず、前述の公正基準とも矛盾するものが多い。例えば同じ職務で同程度の質の仕事をしていても、正規雇用か非正規かで賃金も機会も大きく異なる。非正規雇用の多い女性と若者に不公平であり、生産性向上への意欲を低下させている。
わが国では企業への忠誠と従属を表す基準(年功、長時間労働、不特定業務など)を満たす正社員には高い報酬が支払われる。また、業績評価はあっても社内の業績に限定されており、評価基準はいずれも企業特殊的かつ一律である。雇用者に企業に対する長期関与のインセンティブは与えても、多様な才能を労働市場でより良く生かすインセンティブをそぎ、育児、教育再投資、非営利組織(NPO)活動など企業外での生産的活動との両立を困難にしている。
では欧米ではどうか。筆者の知る米国大学教官の評価を例に挙げる。業績は論文数と発表した学術雑誌の質、論文・著書の引用件数、論文・著書の賞の獲得、外部研究資金獲得額、クラスの平均学生数、指導大学院生数、大学内外の各種委員会貢献度など多様な尺度で計られる。著書で賞を取っても、一流学術雑誌に続けて論文を出しても、大規模研究資金を獲得しても、優れた院生を数多く育成しても、すべて高く評価される。
教育・研究で多様な資質を持つ人材が能力を生かし、他人より優れた実績を上げることが評価されるのだ。そしてその評価は「メリット昇給」の配分に反映され、昇進審査には外部審査員の評価を反映して普遍的なものにする。一方、わが国の大学では業績評価は形式的で、昇給・昇進に結び付く仕組みも明確でない。
雇用者にも多様な才能がある。生産性向上やイノベーション(技術革新)のあり方も多様だ。企業の人事管理は筆者の専門ではないが、それでも米国企業で評価の基準は多様と聞いている。わが国では、公正な評価とは受験内容をはじめ一律の基準によるものと考えられているが、人材評価には多様な人々が能力を発揮できるようなインセンティブを与える基準が望ましい。
◆◆◆
わが国特有の人材活用上、不合理な分配問題もある。高度成長期に発達した手厚い企業福祉制度は、夫婦の伝統的分業(「夫は主に仕事、妻は主に家事育児」)を前提として、男性が大多数の世帯主正社員に家族賃金や家族福祉を提供する制度だ。もともと女性や独身者、企業福祉のない企業の雇用者に不公平な制度であり、非正規雇用者や未婚・非婚者の増大で一層不公平な制度になっている。
加えて、企業福祉は正社員1人当たりの固定費用を高くするため、企業に正社員を少なくして1人当たりの労働時間を長くしようとするインセンティブをもたらす。短時間正社員はコスト高になるため普及せず、育児期の女性の働き方の選択肢も狭めている。企業が人件費削減のため、固定費用の少ない非正規雇用を増やす一因にもなっている。
例えば欧米のように非正規雇用も含め企業福祉は、年金と健康保険の一部企業負担など社会保障に限定し、負担を雇用者の所得に比例させれば雇用者1人当たりの固定費用とはならず、多様な働き方を可能にする。より包括的福祉については国の政策として雇用先や雇用形態に依存せず、婚姻の有無に中立的な公平な制度にすることが望ましい。
同様の問題は税制や社会保険制度による所得再分配にもある。女性が働いて得る年収により、配偶者の被扶養者にとどまるかどうかの境目となる「103万円の壁」「130万円の壁」の問題だ。
この問題を巡っては、女性雇用の推進者が配偶者控除の廃止を主張し、専業主婦の擁護者が存続を主張するという対立構図があるが、経済合理性の観点からは配偶者控除の廃止・存続は中心課題ではない。妻がより多く所得を得ると、夫婦の所得の合計が減る場合があるという不合理が問題だ。解消には配偶者控除を段階的に縮小し、妻の所得が増えれば常に夫婦の所得が増えるようにすればよい。
この問題は、所得税に関する限り、配偶者特別控除の適用で部分的に解決されているが、配偶者控除は住民税や民間企業の配偶者手当にも影響するので、それらを含めた包括的改革が必要である。社会保険の「130万円の壁」についても同様の対応が必要だ。
◆◆◆
表は、従来のわが国の原理とそれに変わる原理を対比したものだ。新しい原理の下では、社会が多様な個人の能力発揮の機会を広げ、企業が多様な個人に能力発揮や自己投資のインセンティブを与え、個人が強くなることで企業も社会も強くなる。それが低迷を続ける日本経済・社会の活性化の鍵だと筆者は考える。
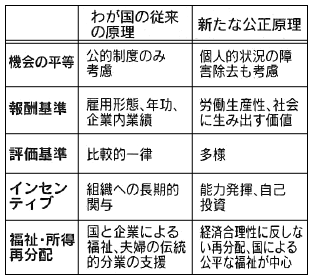
2011年11月30日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


