景気の急減速を受け、雇用情勢が悪化している。正社員にも賃下げなどの影響が懸念されるが、非正規雇用者の解雇が強まる中で、その労働負荷が一部の正規社員にしわ寄せされる結果、労働時間の二極化がさらに拡大する恐れが高まっている。パート就業者を除く雇用者の所定外労働時間は6年連続で増加し、過労死等による労災支給決定件数は年々増えている。働き盛りの正規雇用男性の中で週60時間以上も就業する人は2割以上に達し、この割合は増えてきた。以下でこの問題を計量分析の視点で考えたい。
欧州連合(EU)諸国では1993年、所定外労働時間を含めて就業時間が週48時間を超えないことを定めた労働時間指令が適用され、この指令の適用除外を選択した英国を除き、働き過ぎの問題はほぼ存在しない。経済先進国の中で働き過ぎは、規制のない英米など英語圏諸国とわが国特有の問題であった。
◆◆◆
ただ、ここに意外な事実がある。非自発的に就業する時間が長いことを意味するオーバーエンプロイメント(過剰就業)を日米比較すると、日本の労働力調査に相当する米国の人口現況調査(Current Population Survey)によれば、就業者中「現在の就業時間と同じ」でよいと考える者が66%、「働く時間を短くしたい」とする過剰就業者が7%、「時間を長くしたい」と考える不完全就業者が27%であり、過剰就業者の割合は極めて少ない。
一方労働政策研究・研修機構の原ひろみ研究員と佐藤博樹東大教授の研究では、日本の雇用者では就業時間が「今のままでよい」とする者が49%、「短くしたい」者が45%、「長くしたい」者が6%と、過剰就業者の割合が非常に高い。日米で就業時間には大差がないのに、なぜこうした大きな違いが出るのか。
この疑問への回答と日本の過剰就業の実態を知るため、筆者は2000年に慶應大学が20-49歳の男女を対象に行った『家族・人口の全国調査』データのうち学生を除く4238人の分析をおこなった。この調査では週当たりの就業時間(「実際」)と希望就業時間(「希望」)について、それぞれゼロ、1-15時間、16-34時間、35-41時間、42-48時間、49-59時間、60時間以上の7区分で調べた。
図1は男女別、有配偶・無配偶別の就業時間についての「実際」と「希望」の一致・不一致の割合を示したものだ。非就業者を含めたのは就業時間のミスマッチについて総合的に見るためである。
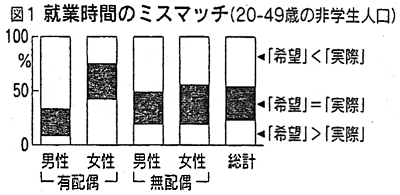
平均的には「希望」が「実際」を下回る過剰就業者が46%、希望と実際が一致するものが31%、「希望」が「実際」を上回る不完全就業者と失業・潜在失業者の合計が23%と、やはり過剰就業者の割合が高かった。
属性別にみると、有配偶女性を除く他の3区分で過剰就業の割合が高く、特に有配偶男性では約3人に2人が過剰就業者だった。一方有配偶女性では「希望」が「実際」を上回る者の割合が高いが、これは有配偶女性の約3人に1人が無職だが就業を希望している失業・潜在失業者であるためだ。また有配偶女性はより長時間働きたいとする就業者も多い。つまり労働市場で就業時間のミスマッチがあり、一方で有配偶男性中心に過剰就業が生まれ、他方で有配偶女性の潜在失業や不完全就業を生み出しているのだ。
◆◆◆
過剰就業者が多いかどうかは就業者の割合にも依存する。図2は対象を雇用者に限り、過剰就業者を、フルタイムでの就業を希望するが残業時間は減らしたいという「非自発的超過勤務者」、短時間就業や無職を希望する「非自発的フルタイム就業者」、短時間就業でさらに就業時間減を望む者の割合を示したものだ。男性には非自発的超過勤務者が多く、女性には非自発的フルタイム就業者が多いが、この差は女性に短時間の就業希望が多いことでかなり説明できる。
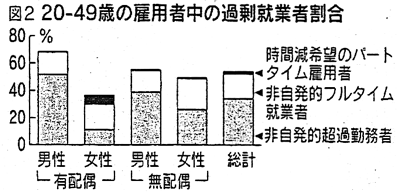
常勤者とパート・臨時の比較では前者の過剰就業者割合がはるかに大きいが、さらに常勤者の中で比較すると「家庭の用事のために仕事の日時を変えることができる」かどうかが過剰就業に大きく影響する。しかしいまだ時間的に柔軟な職場で働く者は多くはない。平均的には女性に比べ男性の方がフルタイム就業希望者中の非自発的超過勤務者の割合が高いのだが、この男女差は子どもがいるかどうかでも変わり、最も年下の子が6歳未満の場合で最大となる。フルタイム就業希望でも幼児がいれば、女性は幼児がいない女性より就業時間が減るが、男性は他の男性よりむしろ増える傾向があるからだ。
ここには、企業が子育てに対し伝統的男女の分業を前提にしている様子が垣間見える。こうした男女の分業の固定化が、現在少子化を生み出している原因の1つなのである。また職業別には他の職に比べ管理職者も非自発的超過勤務者傾向が強いため過剰就業度が高い。
非自発的超過勤務の割合は、他の条件が同じなら、残業時間が長いほど、希望残業時間が少ないほど、実際と希望の時間の関連度が低いほど、それぞれ大きくなる。残業時間が長くても、それが希望に即しているなら過剰就業は起こりにくい。女性はフルタイム就業希望でも男性より希望残業時間が少なく、もし残業時間が同じならむしろ女性の方に非自発的超過勤務者割合が多くなるのだが、実際には男女の残業時間差は希望時間差より大きく、男性のほうが過剰就業になる。
一方常勤とパート・臨時については、フルタイム就業希望者なら残業時間の希望には差がない。だが実際の残業時間は常勤者の方が長い。同様に管理職と他の職の間も希望残業時間に差はないが、実際の残業時間は前者が長い。
◆◆◆
希望に反して残業時間の長い常勤者、男性、管理職者は、それぞれ臨時・パート、女性、その他の職の者に比べ、より一般に賃金が高い。従来日本の雇用制度では正規雇用者と企業との間には「保障と拘束の交換」がある、すなわち企業は正社員の雇用を保障する一方で、その代償として長時間残業や頻繁な転勤を求めるといわれてきた。しかし今回の分析結果は「高賃金と意に反した残業」の間にも交換があることを示唆する。
これが日米の違いを生み出している根本原因と思われる。米国で過剰就業者の割合が低いのは、残業が雇用者の希望に即しているからだが、その理由は時給者にはわが国より手厚い超過勤務手当の制度があり、この制度が適用されない管理職者や専門技術職者には業績に対する昇給・昇進の配分という成果のインセンティブ(動機づけ)が制度として発達しているからである。日米ともに高賃金と長時間労働が関連している点は、類似しているが、一方では雇用者の働くインセンティブを高めて希望と実際の就業時間の一致を促進し、他方は男性正社員、とりわけ管理職者には本人の意向を無視して残業を強いる構図が見られる。
日本企業の高賃金への「見返りの滅私奉公」ともいえるこの残業のあり方は、終身雇用制度で正社員を解雇しにくいため、労働需要が増した戦後の高度成長期に雇用者増員ではなく就業時間を長くして調整する慣行が発達し、必要なときは文句を言わずに残業するという規範ができたことが原因だと考えられる。
だがこの慣行が現在多くの弊害をもたらしている。雇用環境悪化の中で、潜在失業や不完全就業が増える中で過剰就業が一部の雇用者に集中。就業時間のミスマッチ拡大という外部不経済を生み、女性や非正規男性雇用者の人材活用を妨げている。ワークライフバランス(仕事と生活の調和)の達成が困難になり、少子化の原因ともなっている。
今こそ、より多くの雇用者が時間的に柔軟に働ける職場を実現すべきである。それには、労働市場でのワークシェアリングを促進できる雇用制度改革とともに、滅私奉公的働き方に対して報酬を与える賃金制度を見直し、個人の時間当たりの生産性と付加価値の創出に報酬を払うようにすることが欠かせない。
2008年12月26日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


