政府は昨年11月、「日本経済は緩やかなデフレ状況にある」との判断を示した。前回(2001年3月~06年6月)以来3年半ぶり、今世紀に入り既に2回目である。しかし大局的にみると、日本経済のデフレ状況は1990年代半ばから続いているといってもよい。消費者物価(生鮮食品を除く総合)の前年比上昇率を見ると、消費税が引き上げられた97年と原油価格が高騰した08年を除き、マイナスかゼロ近辺で推移している。筆者の推計では、製品の質の向上に伴う実質的な価格下落が完全に反映されていないため、消費者物価上昇率には年平均で1%弱の上方バイアスがある。それを考慮すると、物価下落は15年程度も続いていることになる。
◆◆◆
今回のデフレは前回と同じくマイルド(緩やか)で、1930年代の大恐慌のように数十%の物価下落は見られない。一方、不良債権問題が深刻化して金融機関の破綻が相次いでいるわけではない点は前回とやや様相を異にする。そのため今回は、I・フィッシャーのいう「デフレがデフレを呼ぶ」デット(負債)デフレーションやデフレスパイラルの可能性を指摘する論者は少ない。ただデフレ解消に向け、インフレ目標導入や非伝統的な金融政策が有効かどうかの議論は盛んである。
前回のデフレ局面では、原因や政策対応を巡って、時に激しい議論が繰り返された。デフレに対する正しい処方せんを得るには、その前提として、物価期待の形成メカニズムと実体経済への影響を、実証的にも十分理解しておくことが必要である。人々の物価の先行きの予想を表す期待物価上昇率(予想インフレ率)は、経済主体や対象とする期間によって多様だが、たとえ名目金利が変わらなくても期待物価上昇率が変動すれば実質金利も変わり、家計消費や設備投資などの実体経済に大きな影響を与える。
デフレ期待があれば、実質金利上昇や実質債務負担の増加をもたらし耐久財購入を延期させるなど経済に悪影響を与えるほか、負債過多の主体から資産過多の主体へ実質的な所得転移が進む。また期待物価上昇率は賃金や価格の設定行動を通じ、実際の物価上昇率自体にも影響を及ぼす。
さらに期待物価上昇率は、中央銀行の物価安定機能にも影響を与える。期待物価上昇率が中長期的に大きく変化しない場合を「十分安定している(well anchored)」と呼ぶ。中央銀行への信認が安定した環境をつくり出し、逆に安定していない場合には物価安定機能が働きにくくなる。
◆◆◆
物価期待形成メカニズムに関しては伝統的な合理的期待形成理論をはじめ多くの理論が生み出され、そうしたメカニズムが実際に働くのか、働くための条件が現実に満たされているのかについては、海外では数多くの実証研究が提示されている。しかし、経済政策全般にいえることだが、日本ではそもそもデータの構築や実証による政策の裏付けが十分でないことが多く、物価期待もその例外ではない。前回の局面でも、期待物価上昇率は足元の物価上昇率に等しいと仮定して議論を進めているケースが多かった。
いうまでもなく「期待」物価上昇率は直接目に見えないので、何らかの方法でとらえなければならない。これまでいくつかの方法が開発されているが(詳細は拙著『期待と不確実性の経済学』参照)、海外では、家計や企業へのサーベイによる期待物価上昇率の把握が盛んに行われている。米国では60年代からミシガン大学を中心に家計へのサーベイを通じた期待物価上昇率の計測が行われており、期待形成のメカニズムの解明や政策運営のレファレンスとして応用されている。日本でも2000年代に入ってから、定量的な把握が徐々に進んでいる。
前回のデフレ局面で短期的な期待物価上昇率を直接計測したものとしては、内閣府の「国民生活モニター調査」がある。図は01年6月から04年3月までの四半期ごとの期待物価上昇率の推移を示したものだ。この調査では、日ごろよく購入する品物に関し、1年前と比較した物価の変化と今後1年間の変化について、具体的な数値を尋ねている。
図によると、まず足元の物価上昇率(実感インフレ率)は消費者物価上昇率の動きをよく追っており、家計は実際の物価の動きを正しく把握している。次に期待物価上昇率は、マイルドなデフレを裏付けるように01、02年は若干のマイナスで推移したが、03年1~3月期に突然1%に跳ね上がった。その後はいったん下落したものの、04年1~3月期に1%弱まで上昇している。この調査の対象者は無作為抽出で選ばれたものではないという点で偏りがあるが、家計の期待物価上昇率を直接定量的に質問する方法は、その後内閣府「消費動向調査」や日銀「生活意識に関するアンケート調査」などで取り入れられている。
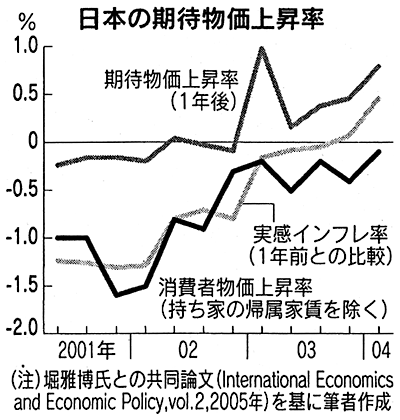
◆◆◆
ではこうした物価期待の動きは何によって決定されるのか。期待物価上昇率の決定要因としては、足元の物価上昇率(適合的期待)、過去の期待物価上昇率(期待の慣性)、所得要因、さらには金融政策や世界的な事件のぼっ発などの外生的要因などがある。筆者と内閣府の堀雅博氏の研究によると、期待物価上昇率の変化の一部は、適合的期待や期待の慣性で説明できる。
金融政策については、政策変更を知っていても実際に期待物価上昇率を上昇させた家計の割合は少ない。しかし日銀による01年3月の量的緩和政策導入や03年の資産担保証券買い入れ検討については、物価期待を変化させたと答えた家計では期待物価上昇率は1位%弱上昇した。また01年9月の米国同時テロでは1.2%、03年3月のイラク戦争のぼっ発では1.4%程度、期待物価上昇率が上昇した。過去の石油ショックの記憶からか、こうした事件は家計の物価期待に大きなショックを与えるからだろう。03年初めの期待物価上昇率の「ジャンプ」はイラク戦争のぼっ発によってほぼ説明できる。
外生的ショックが家計の期待物価上昇率に影響する事例として為替レートの変化もあげられる。琉球銀行の与儀達博氏との共同研究によれば、本土返還以前ドルを通貨として使用していた沖縄で、71年にニクソン・ショックが起こり、ドルの価値が17%下落した。その結果、期待物価上昇率は4~5%上昇したと推定されている。
このように期待物価上昇率にインパクトを与える経路は多様だが、外生的なショックで大きな影響を受けることが示唆される。金融政策も、政策変更を知っているだけでは有意な変化をもたらさないが、実際に変更した家計にとっては、テロ事件やイラク戦争と変わらない効果をもたらした。金融政策で直接的にデフレ期待を反転させようとするなら、少しでも多くの家計に働きかけ、家計が理解し物価期待を修正するよう、大胆かつ分かりやすい形で実施していくことが重要だろう。
さらに堀氏との研究では、デフレ期待が消費行動の及ぼす影響も検証し、住宅ローンを抱える世帯に限って、デフレ期待自体が消費を萎縮させること、耐久財の購入時期も遅らせること、デフレ期待が失業不安と結びついて消費に悪影響を与えること、が確認されている。米国でも大恐慌時に金融資産保有高や負債残高により、耐久財や住宅購入への影響が異なったことが米コロンビア大学のミシュキン教授によって示されている。
本稿で示した実証研究は、家計の短期的な物価期待の形成メカニズムの解明の一端にすぎない。企業の期待物価上昇も内閣府「企業行動に関するアンケート調査」などでデータを集めているが、定量的な計測自体には家計よりもさらに大きな困難が伴う。しかし幸いなことに、前回のデフレ局面以後、日本でも期待物価上昇率のデータの整備や蓄積が進んできた。こうしたデータを積極的に利用して、物価期待形成のメカニズムの理解を蓄積した上で、政策論議を進めていくことが必要だろう。実りあるマクロ政策論議と「出口戦略」の策定のためにも、さらに今回のデフレ状況の教訓を引き出すためにも、今こそその努力が求められているのである。
2010年3月24日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


