米国に比べて2倍以上の電力価格負担を強いられている日本の消費者が、さらに価格上昇を受け入れる余地はあるのだろうか。福島原発事故を受け、稼働を止めた原発を補うため化石燃料依存度は88%に達し、電力価格は現在までに35%上昇している。
経済産業省は長期エネルギー需給見通し小委員会を設置し、2030年における電源構成について検討している。需給見通しには電力価格上昇の抑制は当然に織り込まれると思われるかもしれない。しかし、過去の政府試算では電力価格上昇はきわめて大きいものだった。12年、民主党政権下のエネルギー・環境会議では、国民に提示されたすべての選択肢で、30年における電力価格は60%から2倍以上の上昇となっていた。なぜこれほどの上昇となるのか。
◆◆◆
一般には再生可能エネルギーの増加の影響とみられがちだが、実際には省エネ拡大の影響の方が大きい。省エネ(省電力)と電力価格上昇はコインの両面である。省エネは、その多くが省エネ技術を体化した資本財の導入によって実現される。そして資本の更新時期を迎えたとき、追加的に大きな費用負担のないままに、新しい省エネ技術は緩やかに経済体系に組み込まれていく。市場経済において、省エネを加速するためには、企業や家計において合理的な投資機会となるよう、その背景に電力価格の上昇が必要となる。言い換えれば、将来の電力価格水準をターゲットとすれば、それに対応して実現可能な省エネ量の水準はおのずと定まる。
政府は電力消費者の負担とせずに、補助金や直接規制により省エネを推進してきた。しかし、そうした安易な政策手段による隠れた費用も結局は国民の負担となる。省エネヘの負担を余儀なくされた企業では、生産コストはトータルで上昇し、国際競争力を喪失していく。家計では教育や健康への投資が阻害される。
一般的に資本財価格は相対的に低下する傾向にあり、将来の電力価格が安定的でも、市場経済においても省エネ技術は時間をかけて導入されていく性質のものである。政策によって得られるのは、少しばかりの「前倒し」効果にすぎない。非合理的な選択は、最終的にだれの負担になろうとも、一国経済の成長力をそぐことになる。
政府はこの20年以上、コスト負担を顧みることなく、省エネ努力を数量的に積み上げることに腐心してきた。省エネの過大推計は、電力需要の過小推計を導く。そして二酸化炭素(CO₂)排出量を小さく、電力構成における再エネ比率を大きく見せる。ゆえに理想的な政策目標に近づけるには、禁断の果実となる。
図は日米両国における需要見通しについて、1990年代後半からの予測値と実績値の推移を示している。日本では少しの需要減少を契機に、その減少トレントを引き継ぐように省エネが過大に推計されている。前政権の見通しを上回らないよう、過去の過大推計は将来の更なる過大推計の布石ともなる。そうした推計値は、リーマン・ショックや震災で生産が大打撃を受けた実績と皮肉にも近似した。
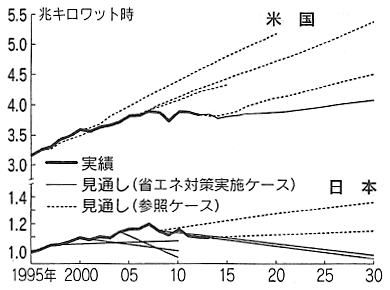
◆◆◆
その近似を根拠として、30年に向けて年率1.7%という高い経済成長率の想定のもとでも、省エネ努力の積算はきわめて大きなものとなっている。しかし震災後の生産縮小によらない電力需要の減少は、その多くが省エネの「前倒し」によるものであり、30年時点で残る省エネ効果はわずかであると考えられる。
対照的に米国での見通しは合理的である。参照ケースは将来の予測値としての機能を果たしている。09年には大きく縮小しその後も停滞しているが、将来の需要は再び過去の成長率へと戻る見通しである。最良技術導入ケースでも増加が見込まれている。
求められる需要見通しは、企業が中長期の事業計画を構築しやすいよう現実性の高いシナリオであり、経済合理性を度外視した積算ではノイズでしかない。
電力需要の過小推計のもとに電力供給が計画され、もし将来に想定を上回る需要が現実化したとき、コインの表面(数量側)から見れば電気使用制限か停電、あるいは老朽火力の発電増加などでCO₂排出量が膨らんで海外から排出枠を購入するという負担を余儀なくされる。コインの裏面(価格側)から見れば、需要を大幅に減少させるため、筆者の試算では電力価格の倍増が必要となる。その結果、日米の需給見通しに基づけば、日本の電力および炭素排出の価格は30年にはともに米国の5倍もの水準になってしまう。とても経済成長と両立するシナリオではない。
電力価格の倍増への懸念は絵空事ではない。エネルギー政策で先行している欧州諸国では、21世紀に入り軒並み倍増した。イタリアは欧州連合(EU)の電力自由化指令が国内法化された99年を転機として急速な電力価格上昇に見舞われ、13年には3倍、消費者物価指数で除した実質価格でも2.3倍へと高騰した。
産業ごとの成長率と生産コストに占める電力依存度はほぼ無相関だったが、高騰後は強い負の相関が見られる。窯業土石、ゴム製品、パルプ紙製造業など、一国平均よりも年率で3~4%ほど成長率が低い。電力価格倍増は、輸入財への代替や海外への生産移転などを通じて、国内の産業構造を大きく変えてしまう力をもっている。その結果、80%近く石炭火力に依存する中国や、過剰な再エネ負担なしに安定した電力価格を保つ米国へのシフトをもたらした。
21世紀に入ってイタリアの経済成長率はほぼゼロで、先進諸国で最低となった。電力価格高騰による生産縮小は、一定の仮定に基づく積算でみれば年率0.15%ほどの成長率の低下要因と解される。これを日本経済の将来見通しに適用すれば、30年の断面では国内総生産(GDP)の約2.2%の下落となり、それまでに失う所得の総額は100兆円近い。日本が同じ轍(てつ)を踏んではならない。
◆◆◆
再エネは系統対策コストを含まずとも、経済性のある事業は限られ、ほとんどは政策支援なしに成り立たない。再エネの固定価格買い取り制度(FIT)による賦課金総額は15年度に1兆円を超えると言われるほど膨大となった。一部が期待した経済効果も無残なものである。導入前には30%程であった太陽電池の輸入シェアは、一気に80%近くまで上昇した。年率20%ほどで下落していた太陽電池の輸入価格は、導入後の13年初めには(外貨建てでも)プラスに転じ、過度な価格競争に陥っていた中国企業が大きく一息ついただけである。
FITは買い取り価格を固定してしまうことで企業の競争を阻害し、価格低下を阻む引力にすらなる。価格上昇を抑制するためFITからの出口戦略の構築を急ぎ、再エネの目標値は20%ほどまでとして中長期的に整備していくことが現実的であろう。
電源構成の見通し策定は、エネルギー政策における停滞を前進させる指針の役割も担う。エネルギー安全保障と低炭素、そして経済成長と両立する電力需要に対応できるベースロード電源として、原発の役割は依然として大きい。安全性と効率性の向上のため、原発のリプレースも将来の選択肢である。原子力は20%以上を目標とすべきである。残りは石炭と天然ガスの間の民間企業による選択である。原子力と再エネの適切なシェアの維持は、自由化による価格上昇リスクの抑制のためにも有益であろう。
2015年3月19日 日本経済新聞「経済教室」に掲載

