米国企業で中国など海外での生産活動を米国内に回帰させる動きが進んでいる。ゼネラル・エレクトリック(GE)は、ケンタッキー工場で国内向けの新たな家電製品の生産を開始した。フォード・モーターはやはり国外の生産を縮小し、テキサス州の生産拠点の拡充を計画している。米国内で生産活動が活況を呈しているのは、ドル安によって製造コストが低下していることの影響が大きい。中国においては人件費が高騰しており、米中の相対的な賃金格差が縮小傾向にある。
海外生産に伴う人件費以外のコストも大きくなっている。米ハーバード大学のマイケル・ポーター教授らは、生産プロセスの高度化によってコストに占める人件費割合が縮小し、海外生産に伴う品質管理の問題や離職率の高さ、知的財産問題などの「隠れたコスト」の影響が大きくなっていると分析している。シェールガス革命の影響も大きい。天然ガス価格の低下に伴い、ダウ・ケミカルはテキサス州に世界最大のエチレン工場を新設すると発表した。
◆◆◆
このように米国において製造業の復権が見られることは事実であるが、中国など海外での活動の手を緩めているわけではない。製造業の国内回帰というより、グローバルレベルで生産活動の最適配置を進め、需要のある国で生産する「地産地消」を進める動きと見るべきである。
キャタピラーは建設機械の生産をアジア拠点から米国に戻しているが、同時に中国の研究開発拠点を強化し、現地のニーズに合わせた製品の開発に力を入れている。経済成長率が高い新興国では所得水準の向上とともに人件費が上昇する。長期的にみると先進国と新興国の生産コストは収斂する方向に向かう一方で、言語や生活習慣、政治体制、経済システムといった国や地域による違いは厳然として残る。従って、グローバル経済における製造業の復権は、マーケットニーズに合わせた「モノづくりの現地化」がポイントとなる。
ビジネスリスクが高い新興国において、生産拠点の一極集中を避ける必要もある。さらに、分散的な生産システムを可能とする技術革新も進んでいる。3次元CAD(コンピューターによる設計)の普及で製品の開発、設計プロセスの短縮が進んだが、3次元プリンターによって、さらに試作や小ロット生産まで短期間で進めることが可能となる。市場ニーズに合わせて製品開発から生産まで現地で行うモノづくりの現地化の有効性が高まっている。
人口が増加している米国経済と比較して、人口減少時代に入った日本において国内市場の伸びしろは小さい。日本の製造業の復権の鍵を握るのは、成長が著しい新興国を含むグローバル市場への展開である。
日本では、海外からの売り上げが半分以上で、従業員も海外子会社における人数が圧倒的に多いという企業は少なくない。しかし、海外も含めた企業グループの組織、ガバナンス(統治)は日本の本社が中心で、海外の多様性を生かした真のグローバル経営ができている企業は少ない。グローバルレベルでのモノづくりにおいて、市場ニーズに対応した分散型システムの優位性が高まっている中で、日本企業は、現地化で欧米企業に後れをとっている。
◆◆◆
現地の市場ニーズを反映した新たな製品を開発するためには、現地ならではの発想が必要である。しかし、日本企業における商品開発は、日本の本社主導で行われることが多い。図は、中国における特許データから中国発の発明割合を企業の国籍別に見たものである。欧米企業においても、中国特許のうち中国で発明されたものは数%のオーダーと現地法人の関与は小さい。しかし、2000年代後半からその割合は上昇傾向にあり、低水準で推移する日本企業との格差が広がっている。
また、中国において発明された特許の引用情報をみると、日本企業の特許は、日本の本社(自社)特許を引用しているケースが圧倒的で、現地開発も本社主導であることが分かった。一方、欧米企業においては、中国国内の大学や企業など現地機関の特許を引用しているケースが多く、現地のイノベーション(革新)システムとの連携が進んでいる。多様な市場に対応したイノベーションを起こしていくためには現地ならではの発想が必要であり、日本人中心の組織からは生まれない。
モノづくりの現地化を進めるために必要なのは、現地法人への権限の委譲と現地人材の登用である。欧米の企業と比較して、日本企業は現地社員の裁量や昇進可能性が小さいということで評判が悪い。「本社のコントロール」→「現地幹部職員が育たない」→「現地に裁量権を与えられない」という悪循環を断ち切る必要がある。長期的には、本社で新卒の外国人人材を積極的に採用することも重要だ。
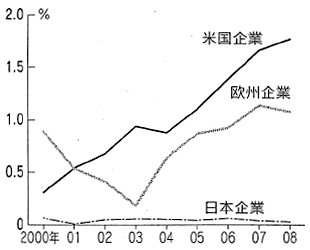
◆◆◆
日本企業は、研究開発の国際化や、現地企業との協業によるオープンイノベーションの障害として「技術流出の懸念」をあげる場合が多い。これは、日本のメーカーが国際競争力のある製品をベースに現地化する「モノ中心モデル」から抜け切れない状況にあるからだ。
日本企業は戦後、安価で良質の製品を生み出す生産技術で世界市場を席捲してきた。しかし、韓国や台湾、中国といった国・地域が急速にキャッチアップしてきており、工業経済時代のモノ中心モデルでは限界がある。今後、日本の製造業が国際競争を勝ち抜くためには「サイエンス経済」に対応したモノづくりを志向する必要がある。サイエンス経済とは、IT(情報技術)や生命科学といった科学的知見をベースにビジネスモデルを組み立てる新たな経済メカニズムである。
ここでは、自前で特定の技術や製品を開発するのではなく、技術的なプラットフォーム(基盤)を提供するプレーヤーと、その上でユーザーとともに新たなビジネスモデルを組み立てるビジネスイノベーターの水平分業が進む。医薬品において画期的な有効物質を開発するバイオベンチャーと、それを実際に商品化する大手製薬企業の分業などが典型的事例である。
サイエンス経済時代のモノづくりは、製品や技術の売り切りモデルではなく、顧客サービスからの価値創造が主眼となる。顧客との相互作用によって常にサービスを向上させる継続的なイノベーションが肝要だ。新興国企業の台頭によって多くの製品がコモディティー(日用品)化する中、日本企業としては、より現場に近いビジネスイノベーションに力を入れていくべきだと考える。
例えば、医療機器メーカーにとっては、個々の病院のニーズに対応した最適なシステム構築が目標となる。消費者向けのビジネスにおいては、多様なユーザーに対応した柔軟性の高い製品設計が必要となる。そのためには顧客企業や一般消費者との協業が重要だ。特に、グローバルビジネスにおいては、進出先の市場やビジネス環境に精通した現地企業と戦略的連携を視野にいれる必要がある。
政策的には、国境を越えたM&A(合併・買収)を円滑にするため会社法や税制面の整備に力を入れるべきである。また、企業においては、グローバルレベルでのオープンイノベーション戦略を立案し実行に移すことが必要だ。日本では「モノ中心モデル」で競争力を保持している企業が多い。しかし、手遅れにならないうちにサイエンス経済時代に対応した戦略に舵を切ることが必要である。
2013年12月30日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


