成長戦略の一環として企業統治(コーポレートガバナンス)を巡る議論が熱を帯びている。社外取締役の選任を促す改正会社法が成立し、機関投資家に投資先の企業との積極的対話を求める日本版スチュワードシップコードも運用段階に入った。小論では、1997年の金融危機以降の日本の企業統治の変化を整理した上で、今後の改革の方向について検討したい。
まず日本企業の上場の動向を確認しておこう。実は国際的に見て日本の大企業は上場する傾向が強い。98年の売上高上位500社のうち上場企業は70%を占めた。英国ですら28%で、独仏は14%、イタリアは10%以下だった(上位1000社、96年)。その後、上場企業は米国では97年から2011年までに38%減少し、英主要市場でも48%減った。一方、日本は同期間に約2300社から3600社に増えた。日本企業の「稼ぐ力」を考える上で、上場企業の統治に注目するのは自然だ。
◆◆◆
97年の金融危機以降、日本の上場企業の株式所有構造は大きく変化した。東証上場企業の機関投資家の保有比率は96年から13年までに23%から48%に伸びた。2000年代の英80%、米60%に比べれば低いが、米国の90年代の水準に匹敵する。13年にはこのうち海外機関投資家の保有比率が30%を超えた。ただ、それらが持つ日本企業の情報は限定的で、投資先も時価総額の大きい企業に限られる。
一方、96年に56%だった事業法人・銀行・保険会社の保有比率は06年に34%まで急低下したが、それ以降は微減にとどまり、13年は31%だった。この安定株主は、実は英米で増えているプライベートエクイティ(PE)ファンドと共通の機能を果たしている。
英国のPEはTOB(株式公開買い付け)で株式を非公開化し、経営陣を短期的な株主の圧力から解放して企業の掲げる使命の実現を助ける。投資先の経営や監視(モニター)にも積極的に関与する。同様に日本の事業法人なども長期保有を約束して経営安定に寄与し、財務危機が起きると介入し救済にあたる。
もっとも、どちらも資金調達が借り入れ中心でエクイティ(自己資本)という緩衝材を欠いており、外部ショックに弱い。この難点はバブル崩壊後の日本企業や、リーマン・ショック後の英企業の回復の遅れに表れている。
しかし日本は、こうした弱点を克服しつつある。企業は過去20年、上場のメリットを享受しつつ安定的な株式所有を維持し、機関投資家の増加も受け入れた。この進化は、機関投資家が支配的な一方、上場企業が減少した英米とも、上場企業が少なく創業家への集中度が高い大陸欧州とも異なる。
日本企業の統治が抱える問題も英米や大陸欧州と大きく異なる。大陸欧州の問題は創業家と会社との利益相反が中心だ。他方、リーマン危機後の英米では、短期志向の株主がM&A(企業の合併・買収)やリスクデータを過度に求めたことが問題とされる。
逆に日本企業の問題は外部株主の支配力が弱く、リスクをとらない保守的な経営がまん延している点にある。現在議論されている改革は、株式の長期保有、従業員の経営への関与といった日本企業の利点を維持しつつ外部株主の利益をより強く反映させ、株主と他の利害関係者の利益のリバランスを図る必要がある。
◆◆◆
2月に公表された日本版スチュワードシップコードは、機関投資家が投資先への監視を強めることで、このリバランスを図る契機となる。資産の運用者(投資顧問会社、生保など)と保有者(年金基金など)に投資方針の明確化と対話を求め、投資家の重視する項目について企業との共通認識を深める一方、受益者への説明責任を強化する。
同コードが十分な情報収集と、議決権行使方針の明確化を求めたことは、これまで判断基準が形式的だった議決権行使を実質化する。各機関に利益相反の特定と対処方針の公表を求めたことも、銘柄選択に当たり関係企業への配慮が危惧されることの多かった投資運用者の透明性・信頼性を高める機会となろう。
ただし同コードには、対話を通じた機関投資家による監視の強化という点で本質的な限界がある。本来、株主が持続的成長に関与するには長期保有のコミットメント(約束)が不可欠だ。しかし投資顧問の基本的なビジネスモデルは分散投資によるリスク回避にあり、長期保有にはコミットしない。
平均保有期間が1年程度と短いアクティブ運用中心の機関に、企業の中長期の成長を考慮した対話を求めるのは難しい。一方、株価指数の構成銘柄を機械的に組み入れるインデックスファンドの運用機関も対話に要するコストの支払いに限界があろう。
対話を通じた監視強化には、長期投資を約束する保険会社などの株主の参加が不可欠だ。この点、「物言わぬ株主」と呼ばれていた保険会社がコードの受け入れを表明したことは歓迎される。今後は銀行の対応も焦点となろう。
長期保有を促すには種類株式など新たな仕組みも検討課題となる。英オックスフォード大学のコリン・メイヤー教授らが提案する、保有期間を登録し、長期保有される株式に普通株より大きな議決権を与える方法は検討に値する。長期的利益に関心を持つ株主の監視への動機を強め、安定株主の確保も容易になる。
◆◆◆
従業員などと投資家の利害のリバランスを図るもう1つのポイントが、経営陣を監視する独立性の高い機関である。独立社外取締役について、選任しない場合に理由の説明を求めた改正会社法の主眼はこれを促す点にある。
日本企業の取締役会は、マネジメントボードと呼ばれるように、経営上の意思決定を担う点に特徴があり、監督と執行の分離をうたった執行役員制が普及した後も実は大きく変化していない。この構造を維持したまま少数の独立取締役を選任しても根本的な変化は期待できない。必要なのは従来の取締役会を経営の監督に特化したモニタリングボードと呼ぶべき仕組みに改革することだ。社外取締役の導入が外形的な整備にとどまるのか、実質的な変化を伴うのかは今後の注目点である。
もっとも、日本企業が全てモニタリングボードに移行する必要はない。社外取締役に期待される機能は経営執行陣への助言と監視にある。独立した第三者による監視は、少数株主だけでなく従業員などの利益も保護する。この役割は、従業員の企業へのコミットを競争力の源泉に置く日本企業では特に重要である。
一般に独立取締役導入の合理性は、助言を必要とする事業の複雑性(図の横軸)と投資家と経営者の利害対立(エージェンシー問題)の深刻度(図の縦軸)に依存する。事業多角化が進んだ企業は外部からの助言の有用性が高い。他方、内部成長を中心とする新興企業などは監視の必要性は低く、現行のマネジメントボードで十分かもしれない。
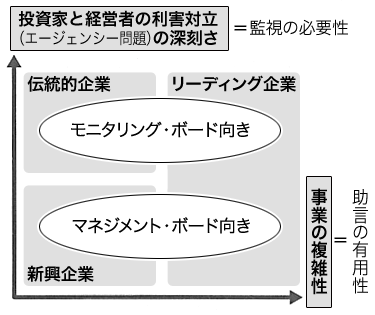
しかし事業が成熟し、現預金保有が多いか、買収防衛策を導入した伝統的企業では監視の必要性は高い。また、リーディング企業の中でも、潜在的に従業員と投資家の利害対立が深刻な企業、例えば人的資本(人材)の重要性が高く、外部資金への依存度が高い企業、事業の組み替えが不可欠であるか、M&Aによる成長を志向する企業ではモニタリングボードヘの移行の合理性が高い。
今回の会社法改正を契機として、日本企業が事業特性やステークホルダーとの関係に応じた適切な取締役会の形を選択することが期待される。
2014年8月6日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


