第2次安倍晋三政権の経済政策、アベノミクスが本格的に展開されてから1年が過ぎた。この間様々な政策が打ち出されてきたが、その中で異彩を放っているのは、政府からの何度にもわたる賃上げ要請であろう。本来、労働者の賃金決定は経営者と労働組合の交渉に任されていることから、政府の積極的な関与や、他の政策との整合性について、きちんと整理しておく必要があるだろう。
今回の政府要請を意義づける最もわかりやすい根拠は、吉川洋・東京大学教授が提起した、近年の賃金の低下がデフレの要因であるとする議論だ。しかしこの論拠をとるとしても、安倍政権がデフレ対策として最重要視してきた金融政策との役割分担をどう整理するかという課題が残る。
政策間の整合性の問題に目をつぶって短期的に見れば、来年度賃上げをする環境は整っていると言える。安倍政権になってから国内総生産(GDP)成長率は堅調に推移し、昨年前半の急激な円安の影響もあって企業収益は著しく改善している。有効求人倍率は1を超え、失業率も4%を下回る状況から考えると、賃上げの雇用への悪影響は考えにくい。4月から消費税率が上昇するため、多少の賃上げをして実質所得を確保する必要性は理解できる。
しかし、今後持続的な賃上げ状況が続くのか、賃上げの方法としてボーナスなどの一時金がよいのか、賃金水準そのものの底上げであるベースアップ(ベア)を実施すべきなのかどうかについては、個々の企業の個別の業績期待だけでなく、他の経済政策との連関性の考察を避けて通ることはできない。
◆◆◆
もし経済全体の回復が今後も続くようであれば、個々の企業のパフォーマンスの差を超えて、継続的に広い業種で賃金を上げていくことが可能だろう。しかし、この1年間のGDPの増加要因を見ると公共投資依存が鮮明になりつつあり、成長戦略で強調された民間設備投資はほとんど景気回復に寄与していない。市場はアベノミクスが財政拡大とそのファイナンスの政策で終わってしまうのではないかと懸念を持ち始めている。一進一退を繰り返している株価はその表れといえよう。
政府としては、賃金の上昇が消費を喚起していくことにより、こうした景気の天井感を打ち破る役割を果たしてくれるものと期待しているのだろうが、それは実現可能なのだろうか。1980年代後半の日本経済であれば、このプロセスにも現実味があったかもしれない。当時は円高もあって実質所得が増加し、それが消費の増加、国内生産の拡大につながっていった。自己資本比率規制の制約を受けなかった金融機関も積極的に企業の生産能力拡大を支えた。
しかし、当時と現在では経済の構造は大きく変化している。それを端的に表しているのは、円安下で続く貿易赤字である。背景には原子力発電所の稼働停止に伴うエネルギー輸入増もあるが、円安にもかかわらず輸出が思ったほど回復せず、一方で消費の回復から輸入が増加している点も影響している。生産拠点の海外移転などで日本の生産構造は大きく変化しており、消費の増加は必ずしも国内生産の回復につながらず、輸入の増加を伴うのである。
また、政府は企業の内部留保を賃金上昇にあてればよいと考えているようだが、企業は90年代後半の金融危機を経て、自らを守るため金融機関への依存を減らし、キャッシュフローを蓄積して存続を図る方向へと変わっている。貿易構造だけでなく、雇用慣行や、金融機関と企業との関係も80年代後半とは大きく変質しているのである。こうした構造変化を踏まえると、賃金の上昇から始まる好循環経済の考え方は、期待外れに終わる可能性がある。
したがって、来年度の賃上げをボーナスなどの一時金で実施するか、ベアで実施するかは、結局、今後の各企業の生産性上昇率や業績見通しに応じて判断すべきだという至極当然の結論に至る。
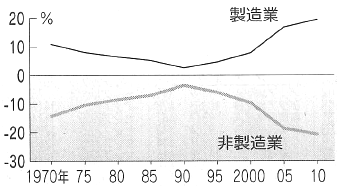
ただバブル崩壊後、企業間、産業間での生産性格差と賃金格差は広がる傾向にある。図は日本産業別生産性データベースを使って、製造業と非製造業の賃金が民間の平均的賃金からどれだけ乖離しているかを示したものだが、ここ20年間にわたって製造業と非製造業の格差は広がっている。この背景には両産業の生産性格差がある。
より産業を細かく分類しても同様の結果が得られ、同一産業内の企業レベル、また企業内の部門別でも同様の生産性格差が生じていると考えられる。これまで企業内の部門別生産性格差は、高生産性部門から低生産性部門への内部補助を通して賃金格差への顕在化を避けてきた。しかし、昨今の電機企業の「選択と集中」に見られるように、こうした内部補助を続けることには限界があり、生産性格差は賃金格差として顕在化する可能性が高い。
◆◆◆
日本全体の生産性格差が広がる中で、賃金格差拡大を避けつつ多くの人が賃金の上昇を享受する方法は2つある。1つは個人所得税の累進度を高め、高所得者から低所得者への分配度を強めることである。しかしこの方法は、高所得者の意欲を損ね、賃金上昇の源泉である生産性上昇そのものを抑制する危険性がある。
したがって望ましいのは2つ目の方法である。すなわち、ある程度の累進税率を維持しつつ、流動的な労働市場を活用し、より生産性が高い、賃金の高い職種・業種へ労働者が移動しやすい環境を作っていくことである。もし政府が持続的な賃金上昇を望むならば、労働市場改革は避けて通れない課題であることを再度認識し、その実現に向けて早急に取り組むべきである。
それにしても、今回の賃上げプロセスは、政府が主導権をとって進めたという点で異例である。政府は法人税減税や規制改革を通して賃上げの環境を整えていく手法よりも、直接的な賃上げ要請という方法をとった。
労働者への配分決定は、労働組合との協議を踏まえた経営者の重要な決定事項である。国際的に高い法人税を払い、規制によって経営戦略の制約を受けながら、さらに賃金の決定まで政府からの要請に追随する姿を見ると、経営者の役割が改めて聞かれているように思う。今回の賃上げ決定が政府からの指示待ち企業を多く生み出すとすれば、それは成長戦略が目指す方向とも矛盾する。
◆◆◆
むしろ政府は、賃金決定に関して間接的な介入しかできない民間部門よりも、規制などを通じてより経営に影響を及ぼすことのできる医療や介護、保育所など非営利部門の賃金上昇を促す方策を考えるべきであろう。日本産業別生産性データベースによれば、非営利部門全体の付加価値シェアは4%(政府部門を含めると20%)になる。これは金融業とほぼ同じ規模である。
医療などの非営利分野は年率6%で労働投入が増加し、成長産業と認識されている。しかしここでの賃金は年率マイナス1.5%で下落を続けている。これは規制によって経営の自由度が制約されている中で、付加価値が労働投入量ほどは増えないため、労働供給増から賃金が低下するというゆがんだ形の市場メカニズムが働いているのである。もし政府が本気で国民全体の賃金上昇を考えているのであれば、規制改革を通じて非営利部門の賃金上昇を政策的課題とすべきであろう。
人々の所得を持続的に上昇させていくためには、短期的な民間企業への呼びかけだけでは不十分である。法人税減税や規制改革、労働市場改革を通じて生産性を向上させ、賃金上昇につなげていきやすい経済環境を作り出すことこそが政府本来の役割である。
2014年2月18日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


