政府が成長戦略の大きな柱として生産性に着目し、その向上に力を入れている。2006年の「新経済成長戦略」を皮切りに、07、08両年度の「骨太の方針」ではサービス産業を中心とした労働生産性の向上がうたわれ、生産性を5割向上させる目標やIT(情報技術)化の促進、職業訓練を通じた人的資本の育成政策などが打ち出された。
05年から日本が人口減少社会に転じ、労働投入、資本投入、生産性という経済成長を支える三本柱の一角が崩れ、成長力減速が不可避になった。戦後の経済成長で半ば当然だった三本柱の増加という前提が崩れ、経済成長を今後も維持するにはより生産性の向上を重視した政策をとらなくてはならなくなった。
また、02年以降の景気回復で長期停滞から脱却したが、他の先進国と比べ日本経済の成長力は勢いがなく、国際通貨基金(IMF)や経済協力開発機構(OECD)などの国際機関や海外のエコノミストらから、「生産性向上こそが成長力を回復させる切り札」との指摘も相次いだ。
生産性向上を通じ成長力を高めるとの考え方は必ずしも間違いではない。だがマクロ的な財政・金融政策とは異なり、生産性向上策での政府の役割は、民間部門の生産性向上のための環境整備が中心である。政府はこの生産性向上という分野に関し、データ蓄積は必ずしも十分ではなく、まとまった政策を実施してきた経験も乏しい。こうした状況で、果たして今の政策は妥当といえるだろうか。以下では、最近の動向や経済学の分野での新しい知見を踏まえ、生産性向上をめぐる「通説」を批判的に再検討する。
◆◆◆
まず、最近の日本の生産性の動向をもとに、単純な生産性向上が成長力強化につながるのかという観点で、政府の姿勢に疑問を呈したい。
深尾京司一橋大学教授が今年5月9日付の本欄で示したように、日本産業生産性(JIP)データベースの08年最新版によると、2000年代前半の生産性は、労働生産性上昇率、全要素生産性(TFP)上昇率ともに回復の傾向を示している(図)。
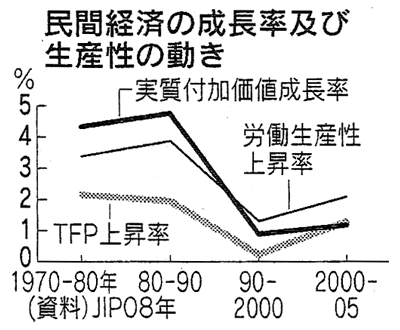
これを製造業と非製造業とに分けると、製造業では、1990年代から2000年代前半にかけTFP上昇率は1.4%から1.3%とほぼ横ばいだった一方、労働生産性上昇率は2.3%から2.7%へと少し改善した。非製造業は、労働生産性上昇率が0.9%から1.8%へ、TFP上昇率がマイナス0.2%から1.3%へと上昇した。
生産性上昇率自身は依然製造業が非製造業を上回っているが、改善幅は非製造業の方がはるかに大きい。数値目標達成だけに目を向ければ、すでに政府の生産性向上策はほぼ達成されたことになる。
重要な点は、各業種における生産性向上の背景だ。製造業は02年からの輸出主導型の景気回復を受け、国際競争力の強い分野を中心に国内でも設備の増強へと転じた。実際上場企業の中で大型投資を実施する企業の比率は、02年の景気回復以降徐々に増加している。このため付加価値が増えるとともに、労働生産性も改善しているのである。TFP上昇率に変化はないが、新規設備の増加で資本の質は非製造業以上に改善されている。こうしたプロセスの下での生産性の回復は、「前向きの生産性向上」と呼ぶことができよう。
一方、非製造業では、付加価値の伸びが90年代から2000年代にかけてほとんど改善していないのに、生産性指標だけが改善している。これは明らかに生産が増えない中で、労働投入の節約や新規投資の抑制で生産性向上を図った結果である。
米連邦準備理事会(FRB)のオーライナー研究員らの研究では、米国でも2000年代に入りサービス産業を中心としてこうしたリストラを通した生産性の向上がみられるという。彼らの考えによれば、最初に労働分配率が上昇し、逆に資本分配率が低下した産業では、翌期にリストラを行うため労働投入量を減少させ、生産性を上昇させる現象が見られる。我々もJIP08年版を利用し、90年代から2000年代にかけての日本のサービス業の生産性向上の背景を調べたが、結果はオーライナー氏らの研究と同じく、サービス業ではリストラ型の生産性向上が進んだ、というものだった。
近年サービス業では、リストラを進める一方パートや派遣など非正規雇用者を大幅に増やしている。こうした労働者への職業訓練は少なくてすむ。つまり企業は人的資本の蓄積がない中で生産性だけを無理に上げているのである。こうした非製造業での「後ろ向きの生産性向上」パターンは、必ずしも生産性の向上が経済全体の成長率向上には結びつかない。政府も職業訓練を通じた人的資本の向上策を打ち出してはいるが、専門化が進むサービス業では、社会人になってからの教育には限度がある。学校教育も含めたグローバル経済に対応した、より抜本的な人材の育成策を考えるべきだろう。
◆◆◆
業種ごとの生産性向上パターンの違いに対する認識だけでなく、政府が個々の企業の特性の違いに関し十分理解しているかどうかも疑問の余地がある。
最近米ハーバード大学のアギヨン教授を中心とするグループは、技術レベルの異なる企業が競争環境の中でどんな生産性向上に努めるか、考察している。それによると、技術水準の高い企業は、競争的な環境になるほど、競争から一歩抜け出すために一層の生産性向上のために努力する。だが先端的な技術水準から遅れた企業は、多少生産性向上に向けて努力したところで、現在の競争状態を脱して優位に立てる確率は低いため、生産性向上への意欲を失ってしまうという。
このことは、小売業を考えてみるとわかりやすい。イトーヨーカ堂やイオングループなどの大規模なスーパーは、絶えず流通の効率化を図り、店舗の見直しなどを通じて生産性の向上努力を怠らない。一方、高度な技術を有しない小売業者にとっては、IT設備を導入しても、自分を取り巻く競争環境がさほど変わるわけではないので、現状維持を選択する可能性がある。したがって、一律にIT化を促進したり、規制緩和を進めたりしても必ずしもすべての企業が生産性を向上させるとは限らない。
◆◆◆
競争政策が生産性向上をもたらすとする議論では、生産性の低い企業の市場からの退出を念頭に置いているが、残念ながらこれまでの日本の企業の低い退出率を見ると、日本では市場からの退出がスムーズに行われているとはいいがたい。細野薫学習院大学教授の最近の研究では、金融危機に伴う資金調達の制約によって、企業の参入・退出に歪みが生じ、実に生産性上昇率の3分の1が失われたとしている。
むしろ政府としては、単純な規制緩和よりも、技術ギャップを大幅に埋める政策か、さもなくば企業の市場からの退出をスムーズにする政策を考えるべきであろう。
2年前に「フラガール」という映画がヒットした。これは石炭不況にあえぐ福島県の常磐炭鉱の街で、フラダンスを中心とした新しい娯楽施設を開設するまでの物語である。かつての日本も、石炭産業だけでなく、繊維産業などで構造改善を進めつつ、新たなビジネスを作り上げていく基盤を作り上げてきた。
生産性向上を通して経済成長を維持する政策は始まったばかりである。政府は、単にマクロ的な数値目標を掲げるだけでなく、産業や、企業の違いに配慮しながら長期的な視点で、きめ細かな政策を粘り強く続けていく姿勢が求められている。
映画で描かれたような、新たなビジネスに挑戦する人たちは、若い世代を中心に現在の日本でも多く存在しているはずである。こうした人々が、今の日本の停滞状況を打破できるような環境の整備こそが政府の役割であろう。
2008年8月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


