日本経済は、1990年代の長期停滞、俗に言う「失われた10年」から脱却したが、残された課題は多い。特に人口減少下で安定的な経済成長を確保するためには、労働市場、金融市場の調整力を高め、生産性向上を図ることが肝要となる。
今月(3月)9日、日銀が決定した量的緩和の解除は、長きにわたった日本経済の停滞に最後の別れを告げる儀式となった。すでに景気回復期も50カ月を超えており、日本経済は新たなステージに入ったとみて差し支えない。しかし、これで日本経済の課題が全て解決したわけではない。むしろこれから長期停滞期に積み残されたより構造的な課題との対峙が始まるのである。
こうした問題意識から、中堅・若手の経済学者が集まり、「失われた10年」を超えて、今後日本経済が生産性を向上させ、持続的な発展を達成するための条件を、企業の雇用戦略、資本蓄積、金融市場の整備の3点に絞って考察をおこなった。
労働市場に配分の歪み
今回の景気回復の主役は、政府ではなく民間部門だった。特に注目されるのは、2003年から始まる民間企業の収益回復である。この収益回復の背景には、1990年代を通して断続的に行われてきた雇用や資産のダウンサイジングがある。上場製造業についてみると、ダウンサイジングを実施した企業は、80年代は10%だったのに対し、90年代には20%超にのぼっている。
雇用のダウンサイジングからみると、企業がより柔軟な希望退職のノウハウを蓄積し始め、横並びではなく前向きなダウンサイジングを実施してきたことが、短期的な収益・生産性の向上につながっている。しかし、長期にわたる雇用削減は決して望ましいとはいえない。この間企業は正規労働者の比率を低め、積極的に非正規労働を活用してきた。こうした非正規労働の活用は、収益の向上には寄与するものの、必ずしも生産性の向上にはつながっていない。
また削減の対象となった労働者が、必ずしも成長産業へ移動できたわけでもない。労働者が競争力の高い産業に就業できないという労働市場での配分の歪みは、2001年以降、労働生産性を年平均0.3%も引き下げている(図)。その意味で、労働市場では長期停滞からのひずみを残しており、このために長期にわたる景気回復期間の中で産業間、世代間の労働移動を進めることができるかが課題となる。
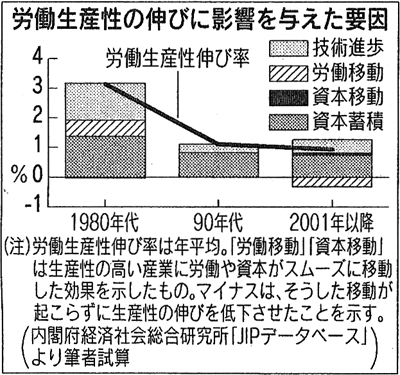
既存設備の質の向上急務
次に資本蓄積面に目を移そう。よく知られているように生産性向上を実現するためには、技術進歩を達成するか、資本蓄積を進めるかのいずれかである。しかしこれまで企業が進めてきた資産のダウンサイジングは、既存設備の老朽化をもたらし、生産性の上昇にはマイナスとなっている。現代の技術革新は、それが設備に体化され実際に生産にかかわることによって初めて経済効果を持つ。したがって設備の更新は、単に生産能力を維持するにとどまらず、新規技術を実用化するためにも不可欠なのである。
設備の老朽化は、単一の企業や産業だけの問題ではない。90年代後半から進展したIT(情報技術)化とも不可分の関係にある。90年代に出遅れた日本のIT化は、その後の政策的支援もあって、量的には世界のトップ水準に達し、IT部門の生産額も経済全体の10%以上を占めるに至った。
しかしながら日本の場合は、こうした量的なIT化が生産性の向上や経済全体への成長へとうまく結びついていない。恐らくこれは米国と日本の産業構造の違いに起因していると考えられる。米国では通信業や情報サービス産業のような少数の産業が経済全体をけん引していったが、日本では多くの産業の連携を通じて、はじめて新製品を生み出し経済全体を底上げする構図だ。たとえば、2000年代に入ってから市場が急拡大したDVD、デジタルカメラ、薄型テレビなどは、ITやその周辺技術だけでなくいろいろな分野の先端技術の組み合わせが奏功したものだ。
こうした日本独特の産業構造を踏まえると、IT技術を活用して経済全体を伸ばしていくためには、IT資本だけでなく、既存設備の質も向上させる必要があるといえよう。IT資本は、2003年度からの投資促進税制もあって増加したが、今後は既存設備の質の向上のために、減価償却制度自体の見直しを含めた抜本的な投資支援策が必要である。
もっとも十分な資本蓄積がなされるためには、金融市場が整備され、設備投資資金が円滑に供給される必要がある。その点で、急速に低下する家計貯蓄率は懸念材料となる。
直接金融通じた統治機能強化を
とはいえ貯蓄不足は、設備投資にとって絶対的な制約要因ではない。現実に米国は80年代から貯蓄率の低下が続いているが、それでも4%台の経済成長を達成している。それは米国が、市場に信頼される金融政策を実施したことに加え直接金融市場を整備して、国外から安定的な資金を呼び込んだからである。
最近の金融政策のポイントは、短期金融市場を通じて、人々の将来経済に関する期待に、いかに上手に働きかけることができるかにかかっている。つまり、金融政策は将来の望ましい経済状況への道筋を明確にするために使われるのである。将来の物価上昇率の変化と連動させて量的緩和政策を実行してきた日銀の政策は、その1つの試みともいえる。
それでは果たして、市場はこうした政策情報を織り込んで価格形成を行ってきたのであろうか。株価、長期国債利回り、円相場を見ると、生産指数や消費者物価指数といった公的な経済情報に対しては反応するものの、残念ながら日銀や政府が発信する経済や政策に関する情報に対してはあいまいな反応しか示していない。90年代の米国の繁栄が、米連邦準備理事会(FRB)を率いたグリーンスパン議長の金融政策に負うところが大きかっただけに、量的緩和解除後の日銀がどのように市場と対話していくかが重要な課題となる。
金融市場は単に資金を供給するだけでなく、ガバナンス機能を通じて企業の成長性を促進する役目も持つ。従来はメーンバンクを中心とした間接金融機関がこの役目を担っていたが、今後は直接金融市場からのガバナンス機能が期待される。
実際、日本でも株主の保有構造の違いは収益率の差に影響を与えている。特に90年代後半以降、企業における収益率は、金融機関の株式保有率が高いほど低く、大株主に株式保有が集中するほど高くなる傾向にある。このように企業や投資家は市場価値を重視する方向に向かっている。海外からの資金調達の必要性を考えれば、今後はより市場で開示された情報を意識した企業経営の重みが増していくであろう。
将来の日本経済を考える上で、最大の課題は人口減少を前提にしてどのように生活水準を維持していくかということであり、そのためには生産性の向上と市場機能の活用が不可欠である。
最近では生産性の向上は単に技術の進歩だけによって達成されるのではなく、市場機能を有効に利用しつつ日常の経済活動の中から内発的に実現するものだという理解が深まっている。ここで述べた雇用、資本蓄積、金融市場の変遷も、つきつめれば生産性向上とそれに伴う生活の安定という目的に行き着く。
昨今「市場原理主義批判」が盛んだが、本来の市場主義とは、こうした生産性向上に裏打ちされた企業価値を正当に評価し、投資家や労働者に生産性向上分を還元することを意味する。これからの日本経済には、まさにこの生産性を持続的に向上させる経済制度を構築できるかが問われているのである。
2006年3月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


