異次元緩和はデフレ「期待」を打ち破り、インフレ「期待」を作り出すことでインフレを実現するのが狙いとされる。ただ、ゼロ金利で利子を動かせないのにどうやって「期待」を操作できるのかは理論的に明らかではない。マクロ経済学で、期待形成はどこまで分かっているのだろう。
支配的枠組みである合理的期待仮説は、ミクロの家計や企業の合理的な情報処理と意思決定を仮定し、マクロ経済への影響を理論化している。ただ、合理的期待の本質は経済における期待が「自己言及性」を持つという点にあり、企業や家計の合理的な意思決定は必ずしも本質的ではない。自己言及性とは、期待が巡り巡って自分自身(期待)を決める性質のことである。
◆◆◆
米シカゴ大学のロバート・ルーカス教授の1976年の論文、いわゆる「ルーカス批判」は、期待(または経済法則)が自己言及性を持つことを指摘した。例えば「インフレは家計に『賃金が増えて豊かになった』と錯覚を起こさせ、消費を増やす」という期待(法則)があったとする。政府が景気をよくしようとインフレを起こすと、国民はこの法則を理解しているうえ、「国民に錯覚を起こさせたい」という政府の意図を読んで、物価高に備え消費を減らす。すると「インフレになっても消費は増えない」という別の法則が生まれる。
このルーカス批判が示す期待の自己言及性とは、「経済システムの中にいる国民と政府が、経済システムの法則(期待)を知っており、それに基づいて行動すると、結果的に法則が変わり得る」という事実である。経済法則は、図のような期待形成のループによって生成される。このためマクロ経済政策は効果を失う、とルーカスは述べた。このループは永久に続くので、一般的には経済法則はいつまでたっても定まらない。
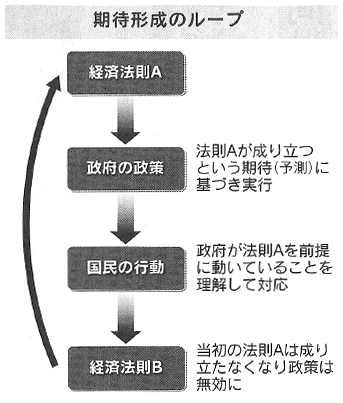
だが、ある条件のもとでは、期待形成ループを通り抜けても期待が変わらない場合がある。このように期待が不動点になるための十分条件の1つが「家計や企業が合理的に情報処理する」というミクロの合理性なのである。
「期待形成の不動点」は安定しており、経済学者が分析することは容易である。逆にそれ以外の期待は不安定で、意味のある分析ができない。そこで現代のマクロ経済学者は、この不動点を「合理的期待」と名付け、実際の経済で形成される期待だと仮定して理論を作ってきたわけである。家計や企業が完全に合理的であるという強すぎる仮定を置いたのも、これを正当化するためだった。
◆◆◆
実際には、すべての家計や企業が合理的だというミクロの合理性が成り立っているはずはなく、合理的期待は理論的な近似にすぎない。大事なことは「期待の自己言及性」を理論の中心に置くことであり、この点はいくら強調してもしすぎることはない。
物理学の進歩と対比しよう。古典力学の時空概念を革命的に変えたのがアインシュタインの相対性理論だったが、どちらも物理学者(観測者)が観察対象の外にいることが前提だった。これを覆し、観測者が物理システムの中にいる「自己言及性」を前提に構築されたのが量子力学である。古典力学・相対性理論と量子力学の間には、その世界観に「自己言及性の有無」という大きな断絶がある。
同じことがルーカス以前とルーカス以後の経済学についてもいえる。マクロ経済学者はこの点に自覚的で、大学院上級レベルの教科書として使われる米ニューヨーク大学のトーマス・サージェント教授らの本のタイトルは「再帰的マクロ経済理論」である。ここで使われている「再帰的(Recursive)」とは、自己言及的と同義である。
量子力学と違うのは、自己言及性を現実的な設定の下で扱うための道具立てが経済学にはまだない点である。そのため近似として採用された合理的期待仮説という非現実的な仮定が使われ続けている。合理的期待仮説に立脚するモデルは現実の政策の基礎として力不足の感を否めない。そこで現実的なマクロ経済理論を作るため、様々な理論上の改善が提案されている。
1つは経済物理と呼ばれる分野だ。統計物理学を応用して株価変動に法則性を見いだす研究などがあり、例えばスイス連邦工科大学のディディエ・ソルネット教授は2005年の論文で米国の住宅バブル崩壊を予言した。
ただ、経済物理学者は統計物理学の手法を使おうとするあまり、「家計や企業が経済法則を知って行動し、その行動が経済法則を生成する」という自己言及性を放棄している。自己言及性を捨てることは量子力学から古典力学に戻るようなものなので、そこは改める必要がある。
◆◆◆
過去10年、世界の中央銀行のエコノミストが経済分析の標準装備として使っている動学的確率的一般均衡(DSGE)モデルはどうだろう。DSGEは08年のリーマン・ショックを予想できなかったと批判されたものの、主導的地位は不変のままである。
DSGEは「すべての家計や企業が合理的」という仮定を置く。現実の景気変動はゆっくりと好不況のピークを迎え徐々に減衰する、という粘着性と増幅性があるが、単純なモデルではこうした特徴は再現できない。そこで標準的な理論では、家計の効用や企業の設備投資の調整費用について、特殊な関数を仮定することによって粘着性と増幅性を再現する。例えば米ノースウェスタン大学のローレンス・クリスティアーノの教授らの05年の論文が代表的である。
これで経済データは説明できるが、理論上は、景気循環は家計や企業の最適行動の結果ということになる。企業や家計の反応も、景気循環と相似形になる。標準モデルが正しければ、不況は家計や企業にとって「最適状態」なので対策を行う必要はない、という結論になってしまう。この欠点は標準的なDSGEモデルの共通点である。DSGEにおける経済政策は、景気の安定ではなく、価格の硬直性による非効率を正すことが目的なのである。
これを克服する動きとしては、米プリンストン大学の清滝信宏教授と英ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスのジョン・ムーア教授の12年の論文のように、合理的期待の仮定を維持したまま、異質な経済主体の相互作用を分析する理論モデルがある。この種のモデルでは、個々人の最適反応の総計は全体として最適にはならない。そのため景気循環を安定させることは正しい政策だといえる。
期待形成についても、行動経済学や限定合理性など、仮定を現実的ものに変える様々な試みがある。今年ノーベル経済学賞を受賞するシカゴ大のラース・ハンセン教授らも、1999年の論文で、政府や国民が「経済の真の構造が分からない」という条件下で経済法則を推測する、という新理論を提案した。ただ、どれも「企業や家計は完全に合理的」というミクロの合理性への批判であって、「マクロの期待は期待形成ループの不動点になっている」という合理的期待仮説の本質を覆すものではない。経済システムが持つ「自己言及性」という性質をいかにして手なずけて現実を分析するか。マクロ経済学に決定打はまだない。
2013年10月21日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


