バブル崩壊後の長期不況の中で、経済政策について様々な論争があった。結局、議論の対立は「景気浮揚が先か、改革が先か」という点に集約されると言えるだろう。最近の例でいえば「日銀の金融緩和をさらに大胆に進めることによって、デフレを脱却するのが先だ」という議論と「不良債権処理による金融システムの改革と企業の再編整理を進めなければデフレは終わらない」というデフレ論争がその典型だ。
この論争は、しばしば感情的な誹謗中傷のようなレベルにまで発展したが、なぜそうなるのか、ということが筆者にはずっと不思議だった。単に議論が白熱して感情的になった、というのとは違う印象なのである。この対立は、実は、何か根源的な価値観あるいは哲学の対立に根差しているのではないか、と筆者は考えるようになった。
この価値対立は、「自由主義」対「設計主義」という枠組みで捉えると分かりやすい。これは、1974年にノーベル経済学賞を受賞したF・A・ハイエクが提示した枠組みである(『自由の条件』、『法と立法と自由』)。
本稿では、まず、ハイエクにしたがって自由主義と設計主義の枠組みで最近の経済論争(特にデフレ論争)の背後にある価値観の対立を整理する。
また、なぜそのような価値観の対立が、金融政策を巡って顕在化するのかを考察し、今後の政策哲学に対する教訓を考える。
1.自生的な市場ルールを理性で設計することはできない
自由主義と設計主義
自由主義とは、現代社会の秩序を形成する最大の力は自由な個人による競争だと考える。そして、自由競争の確保に最大の価値があるとする。この考え方から出てくる重要な帰結は、競争におけるルールと規律の遵守が必要だ、ということである。ルールなしの自由競争は、不正がまかりとおる弱肉強食の世界になり、まったくの無秩序になってしまうからだ。経済の競争におけるルールは、競争に失敗した企業や銀行が退出する(あるいは必要な構造調整を経て再生される)、ということを含む。不良債権処理などの構造改革を重視する論者が求めているのは、究極的には、このルールを遵守することである。そういう意味で、構造改革派は、自由主義者だということができる。
こうした自由主義に対して、設計主義は、現代社会の秩序は人間の理性によって人為的に設計できるはずだ、と考える。高い理性を持った中立的な立場の社会計画者が社会全体の資源配分を人為的に行うことによって、望ましい社会秩序を達成できる、という考え方である。いわば、科学者が自然物を制御できるのと同じように、設計者(政府)が社会を制御できるはずだ、と考えるわけである。最近のデフレ脱却論は、「適切な政策をとれば、日銀は国民のインフレ期待をコントロールできるはずだ。したがって、金融政策でデフレから脱却できるはずだ」というものだが、これは、後述するように、ともすると設計主義と非常に高い親和性を持つ。
デフレ論争については次節以降に譲り、本節では、自由主義の根底にある考え方 ― 自生的な市場ルール ― を考察し、設計主義との本質的な違いを検討する。自由主義の擁護者であるハイエクは、設計主義の考えそのものを「言葉の厳密な意味において迷信である」と断じている。つまり、設計主義は、実際に知る以上のことを知っていると信じることだ、というのである。その論拠を追ってみたい。
自由主義と設計主義の対立は、古代ギリシャで既にその萌芽がみられたという。近代文明社会でも、思想、政策上の論争点として繰り返し現れてきた。ハイエクによれば、設計主義を推し進めた結果、不可避的に到達するのが全体主義(ファシズムまたは共産主義)であり、第二次大戦や東西冷戦は、自由主義と設計主義の最大の対決だったということができる。経済学の分野では、新古典派では自由主義的な傾向が強く、一方でケインズ経済学は、やや設計主義的なおもむきを持つと言えるかもしれない。自由主義と設計主義の違いは、社会の秩序を、「市場の秩序(市場競争の中でできた自生的な構造)」と見るか、「組織の秩序(人為的な設計によってできた組織構造)」と見るかという違いにある。
市場の秩序は、誰かが設計したのではなく、誰にも予想のつかない競争の結果として生成されてきた。個々の市場参加者(個人、企業、銀行、…)は、市場全体の情報など持ち合わせるはずもなく、自分自身の周辺にある情報のみを頼りに、自分の目的に向かって行動する。市場参加者のばらばらの行動が、全体として一定の秩序を形成するのは、「すべての市場参加者が市場のルールに従っている」ということが(かなりの程度)確実に保証されているからだ。市場のルールとは、たとえば、「私有財産の扱いは所有者の自由であり、他人は勝手にできない」とか、「他人の財産を侵害した者(借金が返せなくなった者)は、これこれの罰を受ける」というようなものである。
個々の市場参加者は、「ルールが守られている」という信頼を持つことで、将来の不確実性を払拭でき、自分の行動の結果を相当確実に予測できるようになる。市場のルールの役割は、個々の市場参加者の将来に対する「期待」に確実性を持たせ、ベストを尽くせる環境をつくることにある。そして、個々の参加者がベストを尽くした結果として、自生的な市場の秩序が生成される。
市場のルールはどこからくるか
では、市場のルールそのものは、誰が作ったのだろうか。市場を創設した「誰か」(政府、ワルラスの競り人、など)を想定したくなるが、ハイエクの答えは「誰でもない」というものだ。市場の競争の中で、ルールそのものも淘汰され、もっとも広く受容されたルールが生き残る。これは生物の進化の過程と相似のメカニズムである。市場の秩序構造(企業や産業の分布など)だけでなく、市場のルールそのものが、競争過程の結果として生成されるわけである。競争はルールに従って行われるが、市場参加者は自己の状況に合わせてその時々、偶然にルールの一部を改変する。そして、競争の結果、成功した市場参加者が採用した改変が広く受容され、市場のルールが進化するというメカニズムである。
しかし、市場のルールが誰かの強制ではなく自生的なものだとすると、個々の市場参加者は、そもそも、なぜルールに従うのだろうか。ハイエクは、「ルールが合理的だから、ではない」という点を強調している。ここで合理的というのは、慣習や伝統を排して、人間の理性から演繹的に設計できるということを意味している。たとえば、日本型経済システムと米国型経済システムが併存するように、自生的な市場ルールには、唯一絶対の型はない。なぜこのルール(の束)でなければならないか、という理由を、個々の市場参加者の理性だけで演繹することはできず、強いていえば、他のみんなもそのルールを守っているから自分も守った方が得だ、というだけだ。つまり、人間の理性からルールが演繹されるのではなく、他の人々がルールを遵守していることを前提にして、個々人が合理的に考えれば、そのルールを守ることになる、ということである。1
言い換えれば、市場のルールは、経済活動における伝統や慣習そのものなのである。ハイエク流に言えば、理性から演繹できない伝統や慣習(一見不合理にみえるかもしれないもの)に個々の市場参加者が敬意を払い、それを遵守することが市場の自由競争を成り立たせる。個々の市場参加者は、伝統や慣習の中にあって理性をはたらかせるのであって、そうした既存の価値体系を超越して理性が機能することはない。
「[設計主義的]合理主義が…偶然あるいは人間の気まぐれに基づく無意識かつ無意味な構成物と見なす…もの[すなわち伝統や慣習としての市場ルール]は、多くの場合、われわれの理性的思考能力が依拠する基礎である」(『法と立法と自由』、四角括弧内は引用者)
さらに重要な点は、「いま人々が従っている市場ルールを、完全な形で言語で記述することはできない」ということだ。いまのルールは暫定的なもので、新しい状況に合わせて進化していくからだ。これはたとえば民法や刑法が、判例によって新しい解釈が加えられたり、新しい事件に対応するために条文を改正されたりするのと同じである。あるいは、市場ルールの進化は、物理学などの自然科学の進歩と似ている。いま存在する物理学の理論は暫定的なものであり、新しい実験事実が発見されれば、それを説明するために理論は改善されたり、別の理論に取って代わられたりする。物理学の「究極の真理」は誰も知らないが、それでも我々は暫定的な物理学を使って生活をしている。同じことが市場のルールについても言える、というのがハイエクの議論である。
自生的で、暫定的で、偶然に変化していく市場のルールと、そのルールによって形成される市場秩序を、人為的に制御することは極めて困難なことである。こうした市場秩序観をもとに、設計主義を見るとどうなるだろうか。設計主義の大きな問題点は、「自生的な市場秩序を理性によって人為的に設計された組織秩序で置き換えることができる」という信念である。
人間の本能が市場競争に反発する
組織の秩序の原型は、原始的な狩猟民族の部族社会(あるいは農耕民族の村落共同体)にあるとハイエクはいう。小規模な共同体では、すべてのメンバーがお互いを知っており、首長が資源や仕事を各メンバーに配分する。この組織秩序は、軍隊、政府官庁、企業の組織原理として現代にも脈々として受け継がれている。企業などの組織が理性によって合理的に設計されるべきだ、というのは何の問題もない。しかし、市場の秩序もそうだ、というときには大きな飛躍がある。
市場のルールが理性から演繹されるのでなく自生的に発展する場合、また、市場ルールの究極の姿を誰も知らず、暫定的な真理として人々がそれを受容している場合、その市場ルールを人為的に設計することは原理的に不可能である。したがって、市場の秩序を人為的な設計物で修正しようとすると、(市場ルールを人為的に設計することはできないから、)結局は、資源配分を設計者の個別具体的な命令によって行うことになる。実際にはその設計者も限られた知識しか持ち得ないから、彼の資源配分は、市場秩序に想定外の影響を与え、多くの人々が「恣意的で不当だ」と感じるような配分結果をもたらす。経済効率も、市場秩序に比べてむしろ悪化することになる。
これが、設計主義(人為的に社会秩序を設計することによって、市場経済よりも良い社会を達成できるという考え)に対するハイエクの批判である。
最後に、なぜ自由主義と設計主義の対立がいつの時代も続くのか、という問題について、ハイエクは興味深い診断をしている。強制されたわけでもない自生的な市場ルールを遵守し、自由競争に身を投じることは、人間の原始的な本能に反するのである。自由競争による分業の拡張が近代産業社会の発展をもたらしたことは間違いないが、市場競争の中で、個人は疎外感を強め、自己責任を強いられて大きなストレスを感じる。個人の活動は、市場取引を通じて無数の人々とつながっている(それが文明社会の発展の原動力である)が、あくまでそれは顔の見えないビジネス上の関係であり、当人は暖かい人間的な絆を感じることができない。そうした中で、原始共同体的な一体感や権威に服従する安心感を求める心情が高まり、それが市場秩序への反発と、設計主義的な組織秩序への強い支持を生みだすのである。
このことは、経済情勢が悪くなるたびに、何度でも繰り返される現象である。経済政策を論じる際に常に心に留めておかなければならない重要な問題点であろう。
2.不良債権処理と自由主義
日本経済がこの10年で学んだこと
以上のような市場経済観から、これまでの不良債権処理の問題はどのように整理されるのだろうか。
1990年代前半に不良債権問題が深刻化しはじめたとき、当局が採用したのはまさに設計主義的な手法であったといえる。金融当局の指揮のもと、不良債権は時間をかけて、段階的・計画的に処理していく方針がとられた。商法の原則的なルールによれば、不良債権が発生したら即時に償却し、処理しなければならないことになっていたのだから、この方針は、不良債権問題に商法のルール(市場ルール)を適用するのを一時停止し、政府の監督下で、ケースバイケースの方法で損失処理(資源配分)を進める、ということに等しい。
ルールに基づく即時的な処理を行わず、政府の設計した計画によって時間をかけて不良債権処理をしようとしたことは、銀行や経済への影響を考えれば、合理的な判断だったように思われる。特に、不況の長期化が予想されなかった90年代前半の判断としては、なおさら正しかったように思える。
しかし、前述の市場秩序観からみると、この政策判断は、ルールの大きな例外を作ることについて、自生的な市場秩序への影響を過度に軽視していた、あるいは、政府の計画能力を過大評価していた、というべきであろう。
良債権処理の遅れがその後の不況長期化をもたらしたかどうか、という経済学的な因果関係を度外視しても、ルールに則った処理が迅速に行われなかったことは、日本経済全体の市場ルールの信頼性を大きく毀損したと思われる。つまり、「借金が返せなくなった場合は、こうなる」というルールが守られなかった結果、「借金を返せなくなっても、政府や銀行の恣意的な判断で、生き残れるかもしれないし、倒産させられるかもしれない」という極端な不確実性が発生してしまったわけである。
ハイエクがいうように、市場ルールの役割が、個々の市場参加者が直面する将来の不確実性を除去し、期待の確実性を高めることにあるのだとすれば、不良債権処理を巡って市場ルールに大きな例外ができたことは、あらゆる経済活動の不確実性を増やし、経済取引を萎縮させたはずである。たとえば、企業が何らかの事業を行おうとするときに、「失敗した取引相手が銀行に守られ、自分が損を被るかもしれない」など、市場ルールへの信頼が存在していたときにはあり得なかったような、様々な疑心にかられることになる。
ルールへの信頼が破壊されることによって市場秩序が被る影響の甚大さは、理性による事前の計算では、計り知ることができない。これこそまさに、設計主義に対するハイエクの警告の核心であり、日本経済は、10年もの時間をかけて、身をもってこの警告を学ばされた、と言えるのではないだろうか。
不良債権処理を迅速に進めなければならないことについては、現在、それほど強い異論はないだろう。しかし、その理由は、不良債権処理の遅れがデフレ不況を長引かせるから、という経済学的な理由だけではない。2
市場のルールに対する信頼を回復すること、そのために、(一見、合理的に考えれば打ち捨てても構わないように見える)市場のルールを尊重し遵守するという態度を我々が回復すること。むしろこのことが不良債権処理を進める意義だと考えなければならない。
こうした観点からは、不良債権処理は「事業に失敗した企業や銀行はどのような扱いを受けるか」というルールを明確にする形で進めるべきであり、つまり、責任論に答えを出すことが中心的な作業となるべきであろう。借り手の企業、貸し手の銀行、金融行政、それぞれの責任が、どのように処理されるべきなのか。3 それを明確に示すことが、ゆがめられ混乱した市場ルールへの信頼を回復するための第一歩になるはずである。景気の回復傾向が強まり、金融危機の懸念が遠のいた現在こそ、これまでの不良債権処理の経緯を見直し、冷静に総括する好機ではないかと思われる。
銀行への資本注入をめぐる思想の混乱
市場ルールの信頼性を回復するために不良債権処理が必要だという議論には、次の2つの反論が予想される。
1つは、「不良債権が発生したら即座に処理すべし」というのは欧米の市場ルールではないか、日本には別のやり方があるはずだ、という反論である。しかし、これは正しい見方ではない。不良債権処理の先送りによって壊された市場ルール、すなわち、「借金を返せなくなった場合には、こうなる」という共通理解は、明治以来、いや江戸時代、あるいはそれ以前から、日本で自生的に発展してきた商倫理である。銀行制度や会計制度が西洋由来のものであるために、この商倫理まで欧米のルールだという誤ったイメージが流布しているだけである。不良債権処理を遅らせたために破られたルールは、日本古来の商倫理そのものであり、我々が回復しなければならないのは、この商倫理なのである。不良債権処理の必要性は、日本経済に欧米流のルールを導入するかどうか、ということとまったく関係のない話である。
また、2つ目の反論として、「不良債権処理を迅速に進めることによって銀行が資本不足に陥れば、公的資金による資本注入が必要になる。これは、国家介入で、設計主義的な政策ではないか」という議論があり得る。しかし、資本注入は、銀行が預金者の財産を失ったときに、預金者に損失を負担させないという政策判断からくる当然の帰結であり、設計主義や国家介入とは無関係である。不良債権の発生によって、銀行が預金者の財産に損害を与えた場合、預金者が直接その損害を被る形で処理を行うことも理論的には可能だ。しかし、決済システムを守るために政府が預金者を保護することも、現代ではある程度、受け入れられたルールと言える。その結果、預金者が被るべき損失を納税者が代わりに引き受けるのが公的資金による資本注入であり、これは、銀行が預金者の財産に損害を与えたときに責任をとるというルールと整合的である。預金者の損失分を公的資金で穴埋めした後に、その銀行を破綻処理によって清算するか、業務を続けさせて再生させるか、というのは別途の政策判断である。
現状の資本注入政策が分かりにくいのは、「健全な銀行」に資本注入を行うという、あいまいな考え方に立っているからである。「健全な銀行」というと、あたかも預金者への支払不能に陥っていないかのような印象だが、もし支払不能でないならば、資本注入を行う必要性もない。「現在は支払不能だが、将来的には高収益体質を回復すると見込まれる銀行」に資本注入を行う、という形に政策思想を明確化するべきであろう。
資本注入を巡る政策思想があいまいで混乱しているために、注入に対する国民の支持が得られず、結果的に必要な資本注入が遅れて、金融再生のスピードが遅くなった、というのがこれまでの経緯ではないだろうか。将来、再び金融危機が起きることに備えて、資本注入の政策思想を整理しておくことが必要だと思われる。
3.インフレ期待の制御 ― 設計主義の罠
物価水準を決める2つの要素
不良債権処理については、自由主義的な立場に立って市場ルールの再生を目指すべきだということができたが、デフレに対処するための日銀の金融政策は難しい問題を抱えている。
日銀の金融政策について、筆者の基本的見解をまず述べておきたい。景気の下支えとして量的緩和の継続は必要だが、それだけで景気を完全に制御できるものではないと考える。量的緩和を続けているうちに、不良債権処理などを迅速に完了させることが、景気の持続的回復には必要、というのが基本線である。
本節では、デフレ脱却(景気回復)には、日銀が大胆に金融緩和を進めることが必要十分な政策だ、という最近のデフレ脱却論について考えたい。
いまの日本経済のように、名目短期金利がゼロの状態で、しかもデフレが何年も続くというのは、これまで経済学が想定したことのない異常事態である。こうした状態で中央銀行の金融政策がどのような役割を果たせるのか、ということは学問的に重要な研究テーマだ。世界中で多くの経済学者が、ゼロ金利あるいはデフレ下での金融政策のあり方を研究しはじめたのは当然の成り行きであり、その真摯な研究努力は尊敬に値する。
しかし、専門的な金融政策の研究者以外の論者が、「日銀が大胆な金融緩和を行えばデフレから脱却できるはずだ」という議論を熱心に唱道したり、こうした議論に非専門家の論壇で幅広い支持が集まったりする状況は、なぜ生じたのだろうか。多くの非専門家をとらえているのは、設計主義的な情熱なのではないか、ということが疑われるのである。
日銀の大胆な金融緩和によってデフレから脱却できるはず、という議論をもう少し詳細に見ていきたい。デフレの問題が難しい理由は、物価水準を決めるのが、人為的な設計の産物であるベースマネー(日銀が制御できる)と、市場秩序によって定まる貨幣流通速度という2つの要素が複合した結果であるためだ。
物価、ベースマネー、貨幣流通速度の関係を示す貨幣数量式は次のように書くことができる。
PY=MV
ここで、Pは物価水準、Yは実質国内総生産(モノの量)、Mは日銀が供給するベースマネー、Vはベースマネーの貨幣流通速度をあらわしている。
ベースマネーの量は、日銀が自分の意思でほぼ決めることができる。しかし、日本経済に供給されたベースマネーがどの程度の速さで経済全体を流通するか、ということは、日銀が決めることはできない。流通速度を決めるのは、銀行、企業、消費者の間で行われる取引活動の総体であり、まさに市場秩序が流通速度を決める、といって良い。経済学の理論モデルでは、議論を単純化するため、流通速度Vは一定不変であると仮定するのが通常である。つまり、日銀が制御するベースマネーMの効果を考える際に、市場秩序によって決定される流通速度Vが変化しないことが理論上の前提になっている。
日銀が国民の「インフレ期待」を制御できるか
ところが、現実の日本経済では、Vはバブル崩壊後の不況期を通じて年々低下しており、特に日銀がベースマネーの供給量を著しく増やした90年代末以降には、あたかも金融緩和政策の効果をうち消そうとするかのように、Vは急激に低下しているのである。
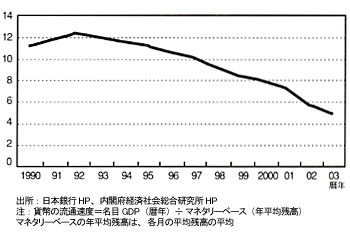
図 90年代以降の貨幣流通速度の推移
よく言われるデフレ脱却論は、(生産Yと流通速度Vが一定のときに)ベースマネーMを増やせば物価Pが上昇するはずだから、日銀が金融緩和でMを増やせば、国民はインフレ期待を持つようになるはずだ、というものだ。インフレ期待が生まれれば(名目短期金利ゼロという特殊な条件下では)その期待が現実のインフレになる。
ところが、もし「デフレが続く」という悲観的な期待を国民が持つ結果として流通速度Vが低下したらどうなるだろうか。その場合、日銀がベースマネーMを増やしても、物価Pは上昇しない可能性がでてくるから、国民のデフレ期待をうち消せない。つまり、市場秩序で決まる流通速度Vが変動するなら、日銀の政策は、必ずしも国民の「インフレ期待」を制御することはできない。4
以上の議論から分かるとおり、デフレ脱却論の問題は、日銀が政策を実施する際に、流通速度Vの低下は起きない、あるいは、起きたとしても無視できる程度でしかない、と考えていることである。つまり、市場秩序の変化を過小評価しているということだ。
「流通速度Vは一定」という仮定は、理論研究者が、あくまで理論を定式化する際に便宜的においた仮定である。現実には成り立っていないことは上で見たとおりだ。その便宜上の仮定が、現実の政策提言の議論においても、暗黙裡に仮定され続けていることは何を意味するのだろうか。
これは、設計主義の犯した論理の飛躍とまったく同型のものだと思われる。設計主義は「企業などの組織は、理性的設計によってコントロールできるし、そうするべきだ。だから、市場秩序を含む経済全体の秩序も、設計された計画によってコントロールできるはずだ」と考える。デフレ脱却論も「ベースマネーMは日銀が理性的設計によって完全にコントロールできる。だから、物価水準Pも、日銀の設計どおりにコントロールできるはずだ」と考える。ところが、物価Pは、市場秩序によって決まる流通速度Vの影響を受ける。上のようなデフレ脱却論の主張は、V(つまり市場秩序)がどのように動くかを解明した上で議論しない限り、論理の飛躍といわれても仕方がないものであろう。
市場ルールの信頼の揺らぎ
経済学の研究では、現在の日本経済において、なぜ流通速度Vが低下し続けているのか、十分な説明はついていない。もしかしたら、日銀の金融緩和が無効になるような、何らかの法則性をもって、流通速度が低下しているのかもしれないのである。こうしたことを考慮すると、現段階で、「大胆な金融緩和だけでデフレ脱却ができる」とは、専門的研究者の立場からは、必ずしも言い切れないはずである。
問題は、こうした論理の飛躍が見過ごされたまま、「金融政策のみによるデフレ脱却」という議論が、非専門家の論壇で強い支持を集めていることだ。それも、保守系の論者も革新系の論者もこぞって支持している点が興味深い。これは、経済の閉塞感の中で、市場ルールから逃れたい、原初的で整然とした組織秩序に身を置きたい、という設計主義の幻想が広く日本の論壇に広がっていることを示しているのではないか。
また、専門家以外のデフレ脱却論者が、不良債権問題などについて、市場ルールに則った処理を行うことに概して懐疑的、批判的であるという点にも注目しなければならない。設計主義の特徴は、自生的な市場ルールを軽視し、理性的な設計者による制御ですべてを置き換えることができる、という信念にある。設計主義的な立場から見れば、単なる慣習的な市場ルールに従うこと(ルールに則った不良債権処理など)には、合理的な理由も見あたらず、ばかばかしく思えるのももっともなことだ。そこから、「愚直にルールを守らなくても、もっと賢くやれるのに」という冷笑的な議論が出てくる。
しかし、その議論は、流通速度(市場秩序)を政府や日銀が制御できない、という事実に目を閉ざし、飛躍した論理の上に立っている ― まさに設計主義の熱情に囚われているというべきではないだろうか。
むしろ、市場ルールへの信頼を回復することこそ、デフレ脱却への近道である可能性すらあるのだ。不良債権処理の遅れなどのために市場ルールの信頼性が壊れ、その結果として、経済活動が萎縮し、流通速度Vが低下しているとしてみよう。もしそうなら、不良債権処理をルールに則って進め、ルールの信頼を回復することが、流通速度Vを高めることにつながるだろう。その場合は、Vの上昇にともなって、物価Pも上昇する。ベースマネーMを極端に増やさなくても、Vの上昇によってデフレ脱却ができるかもしれないのである。
4.将来への教訓
以上の議論では、デフレと改革(特に不良債権処理)とを巡る最近の論争を、古代からの思想的対立 ― 自由主義対設計主義 ― という観点から整理した。経済の発展をもたらす市場ルールが人間の本能にとって居心地の悪いものであり、一方、「設計された組織秩序」という観念が人間にとって魅力的なものであり続ける以上、この思想対立はこれからも続くだろう。注意すべきことは、設計主義的な熱情に囚われ、飛躍した論理を見過ごしたままで、重大な政策判断をしないことである。
近い将来に予想されるのは、財政破綻の危機(国債暴落の危機)がいよいよ切迫するときに、同じような論争が繰り返されるだろう、ということだ。財政赤字と国債発行残高がますます拡大する現状では、とり得る選択肢は二つしかない。ひとつは、歳出カットと増税による財政再建、もうひとつは、日銀が国債を無制限に買い入れるインフレ政策である。
財政再建は、政府自身がひとりの市場参加者としてルールをまっとうするという意味で、ルールを尊重する自由主義的な政策といえるだろう。一方、財政問題を日銀の国債引受とその結果として発生する高インフレで解消しようとすることは、マクロ変数の制御だけで問題を乗り切ろうとする設計主義的な路線といえる。
ちなみにインフレ政策で財政問題を乗り切ろうとした例として、1970年代、1980年代のラテンアメリカ諸国が有名だ。それらの例では、いったんインフレが発生した後は、自律的にインフレが高進し、最終的には、財政問題だけでは説明がつかないほど高率で長期間の自生的インフレに苦しめられることになった。結果的に、当初の政策設計者には予想もつかなかった市場秩序の変化(自律的な高インフレの定着)が出現したわけである。
財政再建とインフレのどちらを選ぶのか、という政策論争は、おそらく現在のデフレ論争と同じような様相を呈するかもしれない。
そのときに必要なことは、設計された政策の限界をわきまえることであり、また、市場秩序を政策で好きなように変えることはできない、という事実を謙虚に受け止めた上で、慎重に政策決定を行うことだろう。
2004年6月 ダイヤモンド社『日本経済の論点』より転載に掲載


