安倍晋三政権は賃金上昇を目指し経済界へ積極的に働きかけている。生産性の動向から見て賃金上昇は可能なのだろうか。可能とすれば何が必要なのだろうか。
一国全体の労働生産性は、労働時間当たりどれだけ実質国内総生産(GDP)が生産されるかで計測される。労働時間当たり実質GDP(例えば1時間5000円)のうち、時間当たり実質労働コスト分(例えば1時間3000円)が労働に分配される。したがって単純化して言えば、実質賃金の上昇率が労働生産性の上昇率を上回ると、労働分配率(上の例では60%)が上昇していくことになる。
労働分配率の上昇が続けば、資本収益率が下落し設備投資が減退するから、そのような賃金上昇は持続できない。これが賃金上昇を考えるにあたって労働生産性の動向に注目する主な理由である。
◆◆◆
表の上段には、1970~2011年をおおよそ10年ごとに区切って、日本経済全体の時間当たり労働コスト(企業が労働者に直接支払う賃金に社会保険料の事業主負担分などを加えた値)を消費者物価で割った値(以下ではこれを実質賃金率と呼ぶ)と、労働生産性(実質GDPを総労働時間で割った値)の推移が示してある。
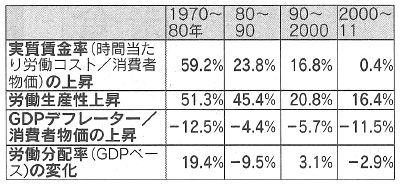
主なデータは、経済産業研究所・一橋大学の「JIPデータベース2012」と「消費者物価統計」である。労働コストと労働時間にはそれぞれ自営業主の労働報酬分と、自営業主・家族従業者の労働時間を含めている。
日本の労働生産性は、70~90年には10年間に約5割ずつ上昇したが、失われた20年と呼ばれる90年以降は10年間に約2割ずつしか上昇しなくなった。一方、労働生産性上昇が実質賃金率の引き上げにどれだけ結実したかを見ると、時期によって大きく異なる。
70年代や90年代には、労働生産性上昇にほぼ見合うだけの実質賃金率引き上げが達成されたのに対し、80年代や2000年以降は労働生産性上昇に比べて実質賃金率の引き上げが格段に小さい。特に2000年以降、労働生産性は16%向上したのに、実質賃金率はほとんど上がらないという特異な現象が起きている。
◆◆◆
2000年以降の実質賃金大停滞を理解するために、労働生産性、実質賃金率および労働分配率の関係をさらに厳密に考えてみよう。
労働分配率を、要素費用で表示した名目GDP(「雇用者報酬」「営業余剰・混合所得」「固定資本減耗」の合計)に占める総労働コスト(自営業主の労働所得分を含む)と定義すると、近似的には以下のような形に分解できる。
総労働コスト/要素費用表示の名目GDP=(時間当たり労働コスト/消費者物価)×(消費者物価/GDPデフレーター)÷(実質GDP/総労働時間)
ここでGDPデフレーターは名目GDPを実質GDPで割った値であり、日本で生産された財・サービスの価格変化を表すとおおむね考えることができる。この式の両辺にGDPデフレーター/消費者物価と労働生産性を掛けると、実質賃金率の上昇は、労働生産性の上昇、GDPデフレーター/消費者物価の上昇、および労働分配率の上昇の和にほぼ等しいことが分かる。つまり、表の最上段の実質賃金率の上昇は、その下段の3つの項の和にほぼ等しい。
表によれば2000年以降、実質賃金が停滞した主因はGDPデフレーター/消費者物価の下落であり、労働分配率の低下も一部影響したことが分かる。GDPデフレーターが輸出分を含む国内生産された財・サービス全体の価格を反映するのに対し、消費者物価は国内消費の対象のみをカバーし、輸入財・サービスの価格上昇も反映する。
今後さらに詳しい分析が必要だが、13年版の労働経済白書も指摘する通り、GDPデフレーター/消費者物価の下落は、日本の交易条件(輸出する財・サービスと輸入する財・サービスの相対価格)の悪化をかなりの程度反映している。
2度のオイルショックを経験した70年代と同様に、2000年以降、輸入価格と比べて輸出価格が相対的に下落したために、日本全体として所得が海外に流出した。これが16%の労働生産性上昇の大部分を帳消しにして、実質賃金率を停滞させたのである。
なお、実質賃金率を停滞させたもう1つの要因である労働分配率の下落は、主に、分母の名目GDPのうち「固定資本減耗(減価償却費)」の増加に起因していることに注意する必要がある。「固定資本減耗」は非製造業を中心に設備投資で資本ストックが蓄積されたこと、情報通信機器など減耗の速い資本の割合が増えたことなどで拡大した。
資本への分配を「固定資本減耗」を含まないネットの「営業余剰」のみで捉え、労働分配率を総労働コスト/(「雇用者報酬」+「営業余剰・混合所得」)で測ると、労働分配率は2000~11年に0.5%しか下落していない。
一部の大企業では膨大な利潤や内部留保が生じており、賃上げによって労働分配率を上昇させる余地はあるかもしれない。だが日本企業全体で見ると資本収益率は低迷しており、労働分配率を今後大幅に上昇させられるほどの余裕は無いように思われる。
◆◆◆
以上見てきたように、実質賃金を引き上げるためには労働生産性の上昇だけでなく、交易条件の悪化を減速させる必要がある。日本のように1次産品を輸入し、技術進歩の速い高度な機械や素材を輸出する工業国では、技術進歩に伴って輸出品の相対価格が下落し交易条件が悪化するのはある程度やむを得ない面もある。例えばドイツも2000~10年にGDPデフレーター/消費者物価が6.8%下落した。しかし、2000年以降の日本の11.5%の下落は大きすぎるように思われる。
交易条件を長期的に左右するのは、日本が輸出する財・サービスと、輸入する財・サービスの相対的な需給である。交易条件の悪化を止めるには、原燃料の海外調達における交渉力を増すと同時に、生産の海外移転の抑制が重要であろう。そのためには、環太平洋経済連携協定(TPP)の締結により、日本で生産された財・サービスの輸出を容易にすることや、法人税減税によって国内立地の優位性を高めることが欠かせない。生産の海外移転は、海外で国産品と同等の工業製品が膨大に生産されることを通じて、日本の交易条件を悪化させる。
筆者の研究を含め企業レベルの実証分析によれば、生産の海外移転は当該企業の収益を増やし、国内雇用も必ずしも減らさない。しかし、国内調達減少による取引先の雇用減少や技術流出の要因まで含めれば、国内の労働全体や他企業にとってはマイナスの効果が大きいはずである。
生産の海外移転とは、企業が持つ技術知識などの生産要素の国際移動と考えることができる。標準的な国際経済学によれば、生産要素の海外への移動は、当該生産要素(経営資源)の所有者(主に株主、大企業の場合には多くの外国投資家を含む)を潤す一方、移動が困難な生産要素(労働や土地)の所有者は損をする。
経済産業省は14年度の重点政策として、中小企業を支援し、新たに1万社の海外展開を目指すとしている。このような政策は、生産の海外移転を促進する危険がある。
グローバル化が進んだ今日、アジアの中で日本が置かれた状況は、日本国内の大阪府や愛知県に似ている。大阪府庁や愛知県庁が府県外への企業の生産移転を促進したとしたら、正気の政策と言えるだろうか。米国やフランスも製造業の国内回帰政策を進めている現在、日本政府が製造業の産業集積を国内に残すことの重要性を理解していないとすれば不思議である。
2013年11月1日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


