日中韓3カ国の全上場企業に関し、生産性比較を試みた。日本企業に対する韓国企業のキャッチアップが進み、格差は大きく縮小している。一方、中国企業との格差は5割以上あるが、一部業種で中国企業の上昇も著しい。日本の企業間では横並びの傾向が強く、産業の新陳代謝機能が課題である。
日中韓など東アジア諸国間では、直接投資拡大や中国の経済発展を背景に、製品貿易が急速に拡大しつつある。サムスン電子、現代自動車をはじめとする高い国際競争力を持った韓国企業の出現や、外資系企業を中心とする在中国企業の発展により、日本の製造業企業は厳しい国際競争にさらされるようになった。
一方、日韓の経済連携協定(EPA)交渉や中国の世界貿易機関(WTO)加盟で、中国や韓国でも、今後の一段の貿易自由化の下で、どのような企業が生き残れるかに関心が集まっている。中韓の企業が、生産性の面で日本企業にどの程度キャッチアップしてきたかは、興味深い問題だが、これまでほとんど研究されてこなかった。
多くの産業で日本最も高く
日本経済研究センターの日本・中国・韓国企業の生産性データベースの作成研究会は、一橋大経済制度研究センター、日大中国・アジア研究センター(プロジェクト代表は乾友彦教授)およびソウル大企業競争力研究センター(代表はリ・クゥン教授)と共同で、東アジア上場企業データベース(EALC2007、http://www.jcer.or.jpでデータを公開)を作成した(主査は筆者)。
同データベースは日中韓の原則として全上場企業(金融業を除く)を対象とし、企業レベルでの全要素生産性測定に必要な各年の実質総生産・中間投入、労働・実質資本サービス投入、全要素生産性水準の国際比較に必要な購買力平価などのデータと、経済全体を33産業に区分し、各産業内で日中韓企業の全要素生産性水準を比較した結果を収録している。カバーした期間は、日本企業(東証二部、JASDAQなどを含む)は1985年から2004年まで、韓国企業(KOSDAQを含む)は85年から05年まで、中国企業(上海・深セン)は99年から04年までである。
推計には、上場企業の財務データに加え、経済産業研究所と一橋大経済研究所が共同作成したJIPデータベースや経済産業研究所「環太平洋諸国の生産性比較研究プロジェクト」で推計された産業別生産・中間投入価格の日中韓比も使った。
EALC2007によれば、多くの産業で日本の生産性水準が最も高いが、この20年間、日本の生産性上昇は非常に低い。これに対し、韓国企業は多くの産業で生産性を著しく上昇させた。この結果、日韓企業間の生産性格差は縮小した。
図1と図2は、電機・自動車産業における日中韓代表的企業の全要素生産性の比較である。生産性の国際比較には、労働投入1時間当たりの実質付加価値など労働生産性が使われることが多い。しかし、同じ数の労働者に、コストをかけて多くの資本を装備すれば、労働生産性が高まるのは当然であり、労働生産性が高いからといって、企業の収益性や一国の生産効率が高いとはいえない。
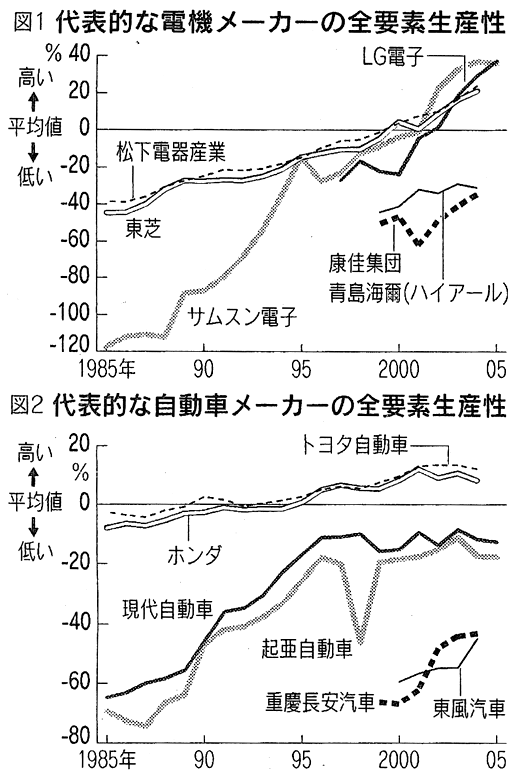
そこで、全ての生産要素(労働、資本、投入原材料)の組み合わせ一単位当たりの生産量を比較する全要素生産性を用いた。同じ国の中では、全要素生産性の高い企業は低い企業を比べ、労働・資本・原材料コストが少ない割に生産高が多いため、収益率が高くなる傾向がある。図の縦軸は、99年に当該産業に属した日本企業の全要素生産性の平均値と比べ、各企業の全要素生産性の水準がどれほど高いかを示している。
日本を抜いた韓国電機企業
図によれば、電機産業ではサムスン電子やLG電子が松下電器産業や東芝を抜いたのに対し、中国企業のキャッチアップは比較的遅い。韓国企業に比べ中国企業のキャッチアップが緩慢な傾向は、化学、一次金属など、他の多くの産業でも見られる。一方、自動車産業では、生産性格差は日韓間で2割以上、日中間で5割以上残っており、中国企業の生産性上昇が著しいのに対し、韓国企業の生産性上昇は通貨危機以降、停滞気味である。
分析結果の解釈では、2つの点に注意が必要である。第1に本分析は上場企業のみを対象としている。中国の株式市場に上場する企業の選定は2000年まで政府の管理下に置かれたため、上場企業は旧国営企業が多く、また生産性の高い輸出志向型の外資系企業の多くは上場していない。さらに韓国や中国では大企業ほど生産性が高い傾向が日本より強いため、大企業のみを見ると、産業全体の生産性を過大評価する危険がある。
第2に企業の国際競争力を決めるのは、生産性だけでなく立地条件も重要である。中国企業は生産性がまだ低いが、中国では労働や多くの原材料が格段に安く、高い競争力を持っている。また韓国ウォン高がさらに進めば、韓国企業の生産性上昇は相殺されよう。
我々のデータベースから分かるもう1つの事実は、日本と中韓間で、企業の生産性の分布や企業の生産性順位の変動が著しく異なることである。
長期のデータが得られる日本と韓国では、ともに同一産業内の企業間生産性格差が次第に拡大する傾向があるが、同じ時代で比較すると、日本では企業間の生産性のバラツキが小さいのに対し、中韓ではバラツキが大きい。例えば、04年で生産性が高い順に企業を並べると、トップ4分位の企業(例えば100社あれば25番目の企業)とボトム4分位の企業(75番目の企業)の間の生産性格差は、電機産業では、日本の8%に対し、韓国16%、中国14%、自動車・同付属品製造業では、それぞれ5%、8%、15%であった。
日本の上昇は「内部効果」で
産業全体の生産性は、企業内での生産性上昇(内部効果)だけでなく、生産性の高い企業の成長や生産性の低い企業の縮小(再配分効果)、生産性の高い企業の参入によっても上昇する。日本では、もともと企業間の生産性格差が小さく、新規参入が少ないこともあり、上場企業全体の生産性上昇はほとんど内部効果で生じている。一方、韓国や中国では、特に90年代末以降、再配分効果や参入効果が拡大する傾向が見られる。
日本のもう1つの特徴は順位変動が小さい点である。例えば、99年にトップ10%に属していた企業のうち04年もトップ10%にとどまった企業の割合は、電機産業では日本の54%に対し、韓国は16%、中国17%、化学産業ではそれぞれ28%、23%、14%であった。
日本国内で企業間の生産性格差が小さいのは、公正な競争や技術の伝播などをおそらく反映しており、それ自体悪いこととはいえない。しかし、中韓と比較して日本で順位変動や再配分効果が極めて少ない事実は、企業が果敢に独自の挑戦を行い勝者が規模を拡大するという、産業の新陳代謝機能が、日本では劣っていることを示唆している。欧米でのミクロデータを使った最近の生産性分析では、米国と比較して欧州大陸先進国では、創造的破壊が少ないと指摘されることが多い。日本も欧州諸国と同じく、新陳代謝機能の加速が課題といえよう。
2007年4月27日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


