服部暢達(一橋大学客員教授)共著
敵対買収といえども成立するのは売り手である既存株主の支持を得た場合であり、外国企業による敵対買収の脅威は誇張されている。ポイズンピル(毒薬)など安易な防衛策の導入は既存株主の利益を損なう危険があり、慎重に検討する必要がある。
日本の株式交換 国内会社が対象
最近、敵対買収とその防衛策の議論が盛んだ。政府は来年の商法改正(新会社法)で合併対価を多様化し、親会社株式を買収資金代わりに使う三角合併を認める方向で検討している。これにより外国企業による日本企業の買収が容易になり、敵対買収もさらに増えるとの懸念が出ている。
今回の三角合併解禁の検討は、1999年の商法改正で導入された日本型の株式交換・株式移転制度に端を発している。株式交換を導入する以前は、日本ではいったん公開会社となった会社を閉鎖会社に戻す手段がほとんどなかった。
欧米ではこのような取引はおおむね可能である。米国では三角合併制度があり、合併のために特別に新設した子会社と対象会社を合併させ、合併対価を親会社株式で支払うことで、対象会社を完全子会社にできる。また、多くの欧州諸国では親会社株式を対価とした公開買い付け(TOB)が行われ、95%など大半の株式を買い集めた場合に残りの株式を強制的に買収できる。
このため日本の産業界も、子会社を完全子会社化する手段(及び自己を完全子会社とする親会社を設立する手段)を強く要望し、これに対応して日本型の株式交換制度が作られた。しかし日本の株式交換は、合併に類似した取引として、完全子会社となる会社の株主に親会社となる会社の株式が割り当てられることになった。したがって、この制度は、海外の会社が日本の会社と合併できないのと同様、日本の商法上設立された会社同士でしか実施できない。
一方、米国型の三角合併や欧州型のTOBは、国境を越えた国際株式交換の場合でも使える。そこで海外から、外国企業も株式を使って日本企業を買収できるような制度の要望が相次いだ。これに対応して導入される予定なのが現在検討中の三角合併である。
株式による買収は、買い手にとって現金を調達する必要がなくなる分、ハードルが低くなる。欧米のトップ企業は多くの場合、日本の同業トップに比べて時価総額が数段大きい。例えば米国のP&Gは時価総額15兆円だが、日本の花王はその10分の1程度だ。そこで三角合併が認められると、外国企業による日本の優良企業に対する敵対買収が頻発するのではないかとの議論がある。
課税繰り延べ 必要不可欠に
確かに時価総額10兆円を超える企業といえども1兆円以上の買収資金を(買収が成功するか不透明な段階で)現金で調達するのは容易ではない。欧米でも大型の買収案件ほど株式でその対価を支払うことが多い。
では、三角合併の解禁により、欧米企業にとって日本は買収天国となるのだろうか。ところが、新会社法で三角合併が認められても、それだけでは使えない制度にとどまる。対価が現金ではなく株式で支払われる場合、売り手の株主の株式投資は継続しているが、日本では親会社株式を受領した時点でキャピタルゲインに課税されてしまうからだ。課税繰り延べ制度がないと、売り手株主の同意が得られないため、せっかくの三角合併もほとんど使われないだろう。万一、売り手株主の同意が得られたとしても、買い手も困る。売り手は現金で税金を納めるために受領株式を短期間に売却しようとし、買い手の株価が暴落するからだ。
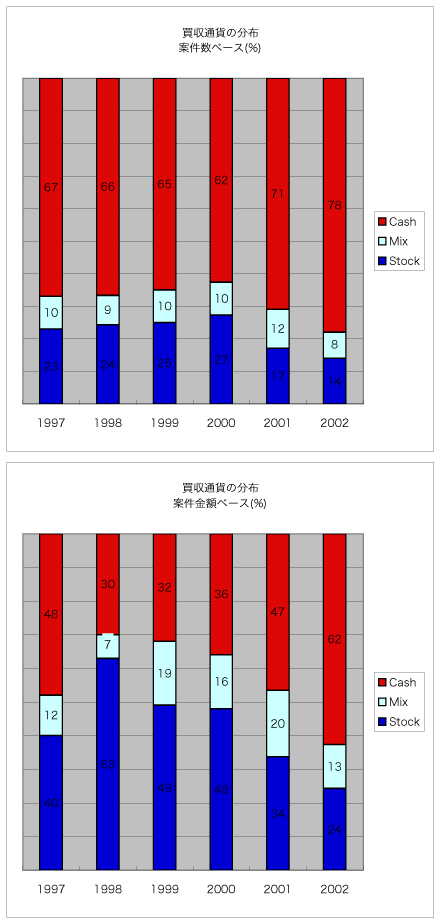
図に示したように世界のM&A(合併・買収)において、対価の一部または全部が株式で支払われる案件は金額ベースで40-70%を占める。よく知られているように先進諸国に対する直接投資の大部分はM&Aである。日本政府が対日直接投資倍増を政策目標に掲げている以上、財務省が検討中との報道もある課税繰り延べ制度を是非認める必要がある。
仮に繰り延べ制度が導入されて三角合併が使える制度となり、日本企業が外国企業に買収されるケースが出てきたとしても、悪いこととはいえない。企業買収は買い手が売り手に支払う買収プレミアムを上回る価値創造が可能と判断する場合にのみ成立する。価値が創造されるのは、経営者が怠慢で株主の利益を最大化する経営をしてこなかったか、または買収者が自らの持つ経営資源と買収先の資源を組み合わせることでより大きな価値を生み出せる場合だ。どちらの場合も敵対的M&Aは望ましい。既存の経営者が反対する買収が、株主にとって、また日本全体にとって損になるとは限らない。
実証分析によれば、対日M&Aの多くは買収先企業の生産性を高めている。経営危機の企業が買収された場合には雇用のリストラが伴う場合もあるが、仮に買収されなかった場合に存続できたとは限らない。日本の技術を安く手に入れるための買収という議論も根拠に乏しい。
過去最大の敵対買収は英ボーダフォンによる独マンネスマン買収だ。マンネスマンは従来の重厚長大産業の感覚で変化の激しい携帯電話事業を経営していたため、新興勢力のボーダフォンがマンネスマン株主の支持を取り付けて買収が成立した。敵対買収といえども最終的に買収が成立するのは株主の支持を取り付けた場合であり、その時点では株主にとって友好的な買収になる。
一方で、財務的買い手が敵対的に買収した企業を買収後に解体・ばら売りする例もある。こういった行為が企業の社会的資産としての側面を損なうとの議論もあるが、多くの戦略的敵対買収は、売り手の株主の支持を得て成立し、買収後も価値創造に努力している。また長期的には敵対的TOBの脅威そのものが経営規律を高めるともいえる。
ところで今年初めに日本を騒がせたユシロ化学工業などに対する敵対的TOBは、ここで述べた敵対買収とは別の物だ。この事例では買い手はユシロなどの株価収益率が同業他社とほぼ同等で、貸借対照表上の現預金を反映した会社総価値に対する営業利益などの比率が著しく低いことに着目した。つまり市場がこれらの会社の現預金を全く株価に反映させていないので、現預金を特別配当で流出させても株価が下がらないと考えたわけだ。結果はそのとおりになった。つまり彼らは、短期の利ざやだけが目的のグリーンメイラー類似であり、最初から経営権を取得する意思などなかったのだ。
ポイズンピルは 株主利益損害も
なお、投資ファンドは株式交換で対価として使用する株式を発行しておらず、通常は現金で買収する。したがって、三角合併による買収は、同業の大企業によって活用される可能性が高い。また、その場合、買い手の株式は流動性の観点から東京証券取引所外国部などに上場されている必要があり、東証外国部の活性化にもつながる。
とはいえ、ユシロのケースで、もし増配の決定がなければ買い手はいったんTOBで経営権を取得し、一回で現預金のすべてを吐き出すような増配を宣言した後に全株を売り抜けようとしたかもしれない。このような一般株主の利益に著しく反する恐れのあるTOBに対しては、経営者にある程度の抵抗手段を与える必要がある。
しかし、米国型のポイズンピルはその使い方を誤れば、まさしく毒薬となって既存株主の利益さえ損なう危険がある。そのため、その運用は、買収提案が株主の利益に資する案になるまで、取締役が条件闘争の手段としてのみ使用することが許されている。決してすべての買収提案を門前払いするために使用することは許されていない。日本の敵対買収対抗手段の議論では、取締役の保身によって株主利益が損なわれることのないように、この点に関して明確な整理が不可欠である。
2004年10月26日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


