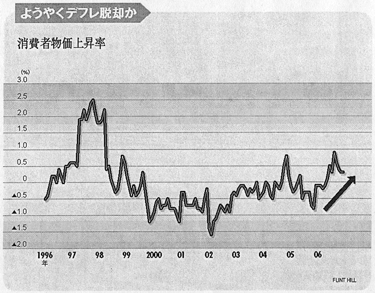安倍政権の成長路線は、経済成長で経済全体を底上げし、低所得層の生活レベルも上げていこうというものだ。一方、民主党などは、積極的な再配分政策によって、格差是正を行うべきだと主張する。安倍政権の成長路線は、適度なインフレを目標としているようだが、実はインフレは所得再配分効果を持っている。
米国のデータを使って、インフレによる所得再配分の効果を実証的に調べた研究が発表された(Matthias Doepke and Martin Schneider "Inflation and the Redistribution of Nominal Wealth". Journal of Political Economy 114(6): 1069-97.)。
インフレが起きると、資産を多く保有する高齢者世帯から、住宅ローンを抱える中流の若年世帯に所得が移転することがわかった。インフレは、若年の中堅層と高齢の高所得層の格差を緩和する効果がある。逆に、デフレ傾向が続いた過去10年は、20~40代の若年・中堅層が犠牲になり、高齢世代の資産家や高所得層が恩恵を受けたことになる。
格差問題に対する関心が非常に高まったのは、長いデフレと無関係ではないだろう。したがって、成長路線の政策によって適度なインフレが定着するならば、格差は解消の方向に進む可能性がある。
しかし、成長路線によってインフレが起きれば格差も解消する、という結論に単純に飛びつくわけにはいかない。いくつか留保条件があることに注意が必要だ。
インフレは家計から政府・企業部門への所得移転であり、家計全体にとっては増税効果を持つ。低所得の高齢者も、高所得の高齢者と同等にインフレで損をする。生活保護などの貧困対策は、成長路線が進めば、もっと重要になる。
また、インフレの再配分効果といっているのは、一般物価のインフレの場合であり、地価や株価のような資産価格のインフレについてではない、ということも重要だ。資産インフレで住宅価格が上昇すれば、住宅を買おうとする中堅層の生活はますます苦しくなる。
インフレで格差を緩和しようとするならば、資産インフレを防止し、生活保護などのセーフティネットを充実させたうえで、一般物価に適度なインフレを定着させる、というバランスが重要だ。
「週刊ダイヤモンド」2007年3月10日号に掲載