日本経済の中長期の課題を論じて欲しいとのことだ。そこで次の2つの問題を全く新しい視角から取り上げる。
1つは、景気循環とデフレとの関係だ。次の不況期に生じるかもしれないデフレ問題と言い換えてもよい。現在のわずか0.5%未満の低いインフレ率のまま次の不況期に突入したら、日本経済はまたまたデフレに陥るだろう。それを避けるためにはどういう政策をとるべきか。
2つ目は、働き手としての労働力人口(20~64歳)の減少が、必然的に高齢者層(65歳以上)に相対的貧困を生み出すことだ。多くの財界人や一般の評論家も、人口が少しぐらい減っても問題は小さいと考えている。ヨーロッパの先進国(ドイツ、フランス、イギリスなど)では、日本の人口の半分近い6000万~7000万人の規模で結構やってゆけるではないかというわけだ。労働生産性を上げていけば、1人当たり所得と生活水準が上昇するので、豊かな国民生活は維持できるはずだと考えているのであろう。それがとんでもない間違いであることを明らかにする。そこから、労働力人口の減少を防ぐ少子化対策が、なぜいま必要なのか、その緊急性も明らかになる。
長期不況克服の要因
1990年代の日本経済の長期不況を克服した要因は基本的に2つあった。
1つは、資産バブルの崩壊による「資産」デフレの克服だ。資産デフレの規模は、地価と株価の両者の暴落の合計で、国内総生産(GDP)の3.5倍にも達した。財政政策も出動せず、銀行のシステム危機を防ぐ公的資金も投入されなかったとしたら、日本経済は30年代初頭の米国の大恐慌並み(3年間で実質生産25%減、加えて物価下落つまりデフレ率25%)の大混乱に陥っていたかもしれない。したがって、銀行システムの立て直しと、地価や株価の下落が底をつくことが、日本の長期不況からの回復に欠かせない条件だった。
2つめは、企業の利潤率の回復だ。私が本誌でも何度か強調してきたように、日本の「物価」デフレ問題の本質は、多くの学者が論じたような、物価デフレ→ゼロ金利の下で実質金利の上昇→不況の一層の深刻化→物価デフレの下方スパイラル、というメカニズムにあったわけではなかった。消費者物価のデフレといっても、最大でせいぜい1%、だから実質金利も最高でせいぜい短期で1%、長期で2.5%だった。むしろ、企業の利潤率が低すぎたことのほうが真の問題だったのである。
低い利潤率の基本的な原因は、資本の過剰ストックと高い労働分配率だった。企業のリストラは97年秋の銀行危機を契機に本格化していった。設備投資の削減はもちろん、賃金デフレを実行し、名目賃金の下方硬直性を打破した。賃金デフレは、正規雇用者の賃金抑制に加えて、低賃金の非正規労働者の数を相対的に増やしていく形で実現された。こうして企業は固定費を削減し、損益分岐点を低下させた。
こうした企業の利潤率の回復があればこそ、設備投資は回復し、損益分岐点の低下により輸出の増大が利潤の上昇に結びついた。だから2002年春から始まる今回の景気回復とその後に続く好況期は、利潤主導・設備投資主導型である。大型ジャンボ機が前輪から離陸するのは当たり前だ。その前輪に相当するのが企業利潤と設備投資だが、後輪の賃金・消費の浮揚力が弱いのは、前述の企業リストラの性格に深く根ざしている。
加えて、いわゆるグローバリゼーションの影響が強い。企業は世界市場で競争している。自国内で賃金が高すぎたり、技術開発力が弱すぎたり、実効法人税率が高すぎたりすれば、事業を海外展開させ、国内活動が縮小することになる。日本の企業だけではなく、外国の企業も同じようにグローバリゼーション化の競争にさらされているので、国際競争の激化は避けられない。
しかも、情報技術(IT)革命は、新技術を体化した新生産物を速いスピードで一般商品化し(デジタル家電をみよ)、生産物のライフサイクルを短期化する。生産のモジュール(分割された各構成要素)化が進み、知識がマニュアル化され、途上国で容易にモジュールを組み立てられるようになる。先進国の低~中位の労働者の職は奪われていく。
それもモノの世界だけに限られない。サービスも、インターネットを使って、途上国のホワイトカラーに外注できる。コールセンターはもちろん、会計処理、データ管理、コンピュータ・プログラムの作成などの外国への発注がどんどん増えている。
これが世界資本主義の新しい流れなのだ。しかも、それが冷戦終結後、すなわち社会主義消滅後に生じている。換言すると、資本主義の下でみられる「資本」と「労働」の基本的な分配上の対立のなかで、同時に資本の力に対する労働側を中心とした拮抗力が失われたなかで、グローバリゼーションが進んでいるわけだ。
変容する景気循環と不況知らずの英国
以上のように、日本経済の今日の景気拡大期の特徴を整理してくると、今後、景気循環の性格が変容していく可能性がみえてくる。
第2次世界大戦後の景気循環のパターンは次のようだった。景気が好況期に入ると、労働市場の需給が引き締まり、実質賃金の上昇が労働生産性のそれを上回るため、賃金コスト(単位生産物当たり)が上昇し、利潤が圧迫される。その利潤の圧迫を金融政策の緩和による景気刺激で和らげようとすると、物価インフレが加速する。そこでインフレの加速を抑えるため金融政策が引き締められ、金利が上昇し、不況に陥る。つまり、労働需給の逼迫と物価インフレの加速が、不況の種だ。
ところが、前述した利潤・設備投資主導と深化するグローバリゼーションの下で生じている今回の好況では、物価インフレは加速しにくい。労働市場の逼迫の度合いが弱く、労働コストが上昇しにくいからだ。IT革命の技術革新により労働生産性の上昇が強まれば、実質賃金は上昇しても、それは生産性の上昇の範囲内に抑えられ、労働コストは上昇しにくい。この2~3年間も、石油価格の急騰で大騒ぎしながら、インフレは大きな問題にはならなかった。となると、インフレを抑えるための金融引き締めもあまり必要ではなくなる。
では、不況は来ないのか。必ずしもそうではない。企業の設備投資がいきすぎて過剰ストックが発生すると、設備投資が急減し、それが不況をつくる。第2次大戦以前の景気循環は主にこうしたパターンをとった。戦前の資本主義は基本的には金本位制の下にあったから、物価インフレは加速しにくく、いわゆる10年サイクルの設備投資循環が支配的だった。インフレ問題は、30年代に金本位制を離脱してから始まった。
だから、今日の日本経済の大問題の1つはこうだ。物価インフレが非常に低いままでの景気拡大は、そのこと自体としては、インフレの番人である日銀にとっても国民の生活にとっても望ましいことだ。しかし、設備投資のいきすぎで不況が発生したら、日本経済は再び物価デフレに陥るだろう。好況期の低いインフレは同じく低い名目金利を意味する。だから、その状態で次の設備投資循環の不況に陥ると、ゼロ金利の下での物価デフレという、嫌な問題に日本経済は再び落ち込むだろう。
では、どうするか。どのようにして景気循環を消滅させることができるのか。
1つの参考例として、92年以降今日まで15年間、不況知らずの英国経済が参考になるのかもしれない。では、英国経済は、92年以前と以降で何が変わったのか。
第1はサッチャー政権(79~90年)による労働市場の改革だ。強すぎた労働組合を弱くした。また、その他の規制改革などとあいまって、労働市場の弾力性はかなり高まった。加えて、サービス産業を中心に、英国経済全体の労働生産性の上昇率が高まった。
その結果、92年以降の実質GDPの年平均成長率は2.5%あり、実質賃金の上昇率は景気変動と同じ方向で動くようになった。これがなぜ重要かというと、景気循環上の不況は、不況になっても実質賃金が下がりにくく、これが利潤を圧迫し続けたために深刻化した。その不況期にみられた実質金利の上昇=利潤圧迫という「重し」が非常に軽くなったことを意味するからである。
第2は、92年以降、英国の金融政策は、インフレの抑制(約2%)に見事に成功している。70年代初頭に国際通貨が変動相場制に移行してから92年まで、年平均10%近い高いインフレに悩み続けた英国経済とは様変わりである。インフレの振幅の安定化とともに、設備投資やGDPの振幅の度合いも安定した。こうして景気循環の振動が安定化したのである(表1)。なお、英国の政府支出の振幅は、92年以前と以降ではそう変わっていない。財政政策の適切な発動が景気循環をスムーズにしているのかもしれない。
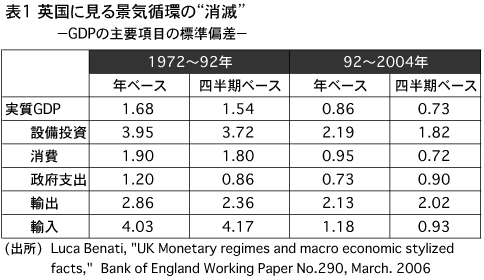
ただし英国の場合、高いインフレを抑えるためにインフレ目標値を導入したのであり、すでにインフレが安定している今日の日本の金融政策の主目標は、設備投資のいきすぎから生じる景気振幅を抑えるところにある。これには、潜在成長率の見合った設備投資の伸びと資本ストックの増大との関係の解明が大前提になり、そのうえで金融政策が設備投資に与える影響の大きさの解明が必要になる。
労働力減少と社会保障
2つめの長期的問題に進もう。高齢者の絶対数が急増し、人口扶養率(高齢者人口の労働力人口に対する比率)が高まっていることはよく知られている。その結果、高齢者の年金、医療、介護など社会保障の給付のための費用が高まり続ける。社会保障費がGDPに占める比率は、04年度の17.2%から25年度には21.1%へ上昇する。放っておくと、もちろん2025年度以降も上昇し続ける(表2)。
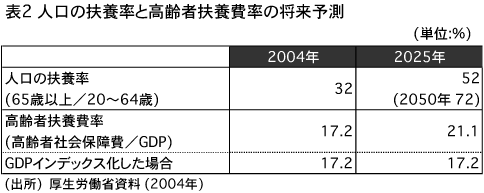
問題は次の3点にある。
第1に、高齢者の社会保障費は、GDPという日本経済の全体のパイの範囲内でしか賄うことはできない。つまり、社会保障費の比率の上昇にストップをかけないと、日本経済が破綻する。ところが、第2に、そのGDPを実際に生み出すのは働き手の労働力人口である。だが、その労働力人口は今後、年率0.5%程度で減っていく。だからGDPという日本経済が伸びにくくなる。その結果、GDPの範囲内に社会保障費の伸びを抑えることがますます難しくなる。
そのとき忘れてならない第3の点として、実質GDPの成長率は1人当たり実質賃金の上昇率より必ず低くなることだ。というのは、GDP成長率は「労働力人口増加率+労働生産性上昇率」で決まるが、他方で1人当たり実質賃金上昇率は労働生産性上昇率で決まるからだ。この2つの等式を比較すればすぐわかるように、GDP成長率は、労働力人口が減少する分だけ、必然的に1人当たり実質賃金の上昇率を下回る。
以上の3点は、以下のような日本の社会保障の根源的問題を浮き彫りにする。
まず、高齢者の社会保障費は経済全体のパイ、つまりGDPの範囲でしか面倒をみきれないのだから、日本経済が破綻しないようにするためには、社会保障費の伸びをGDPの成長率にリンクさせるしかない。これを社会保障のGDPインデックス化と呼ぼう。前述した人口の扶養率とGDPインデックス化を結びつけると、扶養費用の対GDP比率という概念が生まれる。GDPインデックス化とは、一方で人口上の扶養比率は上昇していくが、他方で経済政策上は扶養費の比率を抑えることを意味する(表2)。
04年度の日本の公的年金制度の改革の支柱は「マクロ経済スライド」と呼ばれるが、それは簡略化すると、このGDPインデックス化のことである。つまり、04年度の年金改革のマクロ経済スライドでは、新規受給者の年金給付額の増加はGDPの成長のみにリンクして決められ、労働力人口1人当たり平均賃金上昇率にリンクするわけではない。加えて、高齢者の平均余命が伸びれば、その「長寿化」分だけ、年金受給額は減らされる。この長寿化分だけ、マクロ経済スライドはGDPインデックス化より厳しい。
以上の結果、年金受給額の伸びがGDPの成長率の範囲内に収まり、日本経済の破綻は免れる。だが他方で、受給年金の伸びは現役の働き手の1人当たり実質賃金の上昇率よりも毎年毎年、遅れることになる。これが今後、10年、20年、30年と続くと、高齢者が受け取る年金給付額は現役の勤労者の賃金と比較してどんどん下がっていく。年金給付の賃金に対する比率は「所得代替率」と呼ばれており、この代替率が50%を割らないことが、今では日本の政治的合意になっている。
しかし、年金の所得代替率が低下していく基本的な原因は、繰り返すけれども、一方で日本経済の破綻を防ぐには高齢者の社会保障費をGDPインデックス化するしかなく、他方でGDPの成長率が現役の賃金上昇率を下回る限り、社会保障給付の伸びは賃金の伸びに遅れることにあった。それは年金の所得代替率の低下に表れているように、高齢者の生活水準が現役世代のそれに比較してどんどん低下していくこと(つまり相対的貧困化)を意味する。
根本的な解決策は人口増と女性の労働・子育て両立化
高齢者の相対的貧困化をどう防ぐか。既述のように、その根因は労働力人口の減少にある。そこで労働力人口をどう増やすかが緊急の課題となる。1つは、高齢者、女性、フリーターなどの労働力参加率を高めることだ。ここでその政策について詳論する余裕はない。しかし、多くの試算の結果をみても、労働力人口の減少率をある程度小さくすることはできても、減少そのものに歯止めをかけることはできないようだ。
となると、根本的解決は、有効な少子化対策をとって労働力人口の減少を止めることだ(移民政策は別)。いますぐ出生率が上がっても、それが労働力人口の増加に影響してくるのは20~30年後である。しかし、今すぐそれを始めないと、日本の高齢者の相対的貧困化は延々と続き、生活保護に頼らざるをえない高齢者が着実に増えていくことになる。
21世紀の終わりには日本の人口は現在の半分の6000万人台になる、という数字だけをみると、日本が現在の世界第2の経済大国からヨーロッパ並みの経済規模に縮小するだけのように聞こえる。だが、この数字の背後には、日本経済の長期的な社会保障問題、つまり高齢者の相対的貧困化という深刻な社会政治問題が隠されているのである。
少子化対策では、女性の労働力参加率の上昇との両立が政策の要となる。これは、日本の労働市場の特徴である正規職員の年功賃金制との関係でも重要だ。年功賃金を日本の古い制度だとして切り捨てるのは簡単だが、それでは実のある政策論争にならない。年功賃金制が企業内で熟練した多能工や暗黙知にたけたホワイトカラーを生みだし、日本の労働生産性を上げてきた面も十分あるからだ。だが他方でそれは、正規雇用を中心に、その企業に必要な人的資本を形成する手段であった。
その仕組みが、出産・子育てでキャリアを中断した女性が仕事へ復帰するのを妨げていることもまた事実である。出産・子育てと両立する新しい職能と給与体系のあり方が、改めて問われている。日本の高齢者の相対的貧困問題は、女性の労働力参加率の上昇と出生率の上昇を両立させる日本の労働制度の改革をも、迫っているのである。
2006年12月26日号『週刊エコノミスト』(毎日新聞社)に掲載


