05年日本経済に生じた3つの謎
2005年の日本経済は奇妙な謎につつまれた。
第1に、デフレのまま好況期を迎えたことだ。これは、デフレ(物価下落)を克服しないと、景気回復は訪れない、と主張していた多くの経済学者にとっては奇妙な謎のはずだ。
第2に、石油価格の急騰は景気を悪化させるどころか好況は持続し、設備投資や個人消費が堅調だ。石油ショック=スタグフレーション(インフレと不況の同時発生)という言葉が古ぼけて聞こえる。
第3に、石油価格が急騰したのにデフレが続いたのも謎だ。日銀が使うインフレ指標は、生鮮食品を除く消費者物価指数(CPI)で、実は石油価格は除かれていない。それなのに、石油価格を含むCPIインフレは、2005年暮れになってようやくゼロ%となった。
このように05年の日本経済は、デフレのままなのに好況期に入り、石油価格が急騰したのに好況が持続し、しかもその間デフレは続いたという、デフレ、原油高、好況の三者の共存という謎に包まれた。
素直に考えると、好況期を迎えてもなおデフレ気味という組み合わせは、中央銀行にとっては最も望ましい経済環境である。というのは好況期にはインフレの加速をいかに抑えて好況を長持ちさせるか、これが中央銀行の課題だからだ。グリーンスパンFRB(米連邦準備制度理事会)議長が04年6月から短期政策金利を何回にもわたって上げてきたのは、インフレの加速を抑制することで好況を持続させるためだ。ところが日本では、好況期(後述)に入って2年もたったのに心配しているのはインフレではなくデフレであり、インフレがなかなか到来しないことなのである。一体、日本経済が当面する問題は、デフレなのか、インフレなのか。
この問題こそが、06年の金融政策と財政政策に、加えて両者のポリシー・ミックスに挑戦的課題を投げかけている。量的緩和をいつ、どう解除するか。量的緩和をやめてもゼロ金利は続けるのか。ゼロ金利はいつやめるのか。財政政策はプライマリーバランスの改善を目指して、定率減税の廃止、公共投資の引き続いての削減、近い将来の消費税増税の可能性など、明らかに引き締め型である。では好況持続のために、金融財政政策のポリシー・ミックスはどうあるべきなのだろうか。小稿の目的はこうした問題をかいつまんで分析することにある。
デフレなのになぜ好況が到来したのか
デフレの下では、借金をしている企業にとって、実質金利が高まるのと同じ効果をもつ。例えば、ある企業がゼロ金利で100億円借りて同じく100億円の生産をしているものとしよう。この企業の生産物の価格が5%低下すると、生産の数量は変わらなくとも、95億円の売上額しか得られない。これは5億円つまり5%も金利が上昇したのと同じである。
換言すると、名目的にはゼロ金利の下でも、デフレ(物価下落)の分だけ実質金利は5%へ上昇しているのと同じである。こうしてデフレの下で生産するとデフレによる実質金利の分だけ企業利潤が減るので、生産や設備投資を落とすだろう。
こうしてデフレが続く限り実質金利の重みが景気悪化を招く。だから景気回復のためには、まずデフレを止めなければならない。日銀による量的緩和は01年4月からこのような考えで始められた。量的緩和とは市中銀行が日銀の当座勘定に積み上げておいていつでも引き出し可能な流動性準備(したがって法的必要準備は除く)、いわゆる過剰準備を増大させることである。過剰準備は04年初めまでに約26兆円の水準にまで膨張した。日銀が市中銀行の保有する国債(長期を含む)や手形を購入すると、市中銀行はその売却によって得た現金を日銀の当座勘定に預け入れ、いつでも必要なときに引き出す。
ではこの量的緩和はデフレを食い止めるのに役立ったのだろうか。答えはノーである。というのは、もし量的緩和が市中銀行の融資を増やしマネーサプライ(M2+CD)も増やすことに成功していれば、景気を刺激するのに役立つといえるだろう。しかし銀行融資は減少し続け、マネーサプライも年率1.5%前後の増大にとどまったままだったからだ。
では、量的緩和は何に役立ったのか。銀行システムの安定化へ役立ったといえるだろう。市中銀行が30兆円もの過剰準備を日銀の当座勘定に持った理由は、不良債権の重圧の下、銀行システムが不安定で預金取り付けやインターバンク市場で短資が調達できなくなった際、必要な現金をいつでも調達できるよう準備していたからである。だから不良債権の処理が進み04年に入って銀行システムの不安が遠のいてくると、市中銀行はこの過剰準備をあまり必要としなくなった。
したがって日銀が国債や手形を市中銀行から購入しようとしても、市中銀行はそうした入札にはあまり応じなくなり、いわゆる「札割れ」が生じた。だから過剰準備残高も04年初め~05年末にかけて2年近くも横這いのままで増えなかった(図1)。
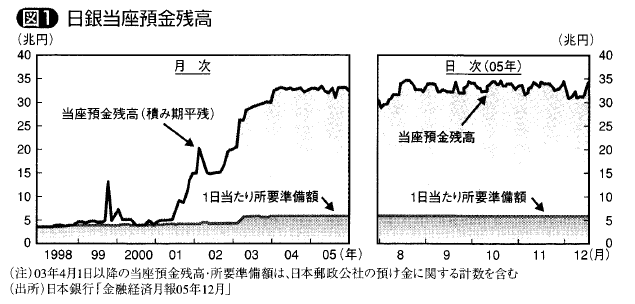
それなのに景気は回復し、デフレのまま好況期を迎えた。景気循環には4つの局面がある。不況→回復→好況→後退(そのあと次の不況)の4局面だ。
この景気循環は日銀短観の業況判断(DI)の動きをみるとよく分かる。この業況判断は、現在の自分の企業の業況を「良い」と見る企業数から「悪い」とする企業数を差し引いたパーセントポイントでみる。「良い」とする企業数と「悪い」とする企業数が一致すると(図2のゼロ線)、景気はちょうど中庸にある。これ以下だと、「悪い」とする企業数が多いわけだから、経済は景気循環上「不況期」にある。ここからゼロ線まで上がっていく過程が「回復」期だ。このゼロ線以上になると、「良い」とする企業数が「悪い」企業数を上回るので好況期だ。その後ピークを迎えると、景気はゼロ線の上にありながらも後退期に入る。
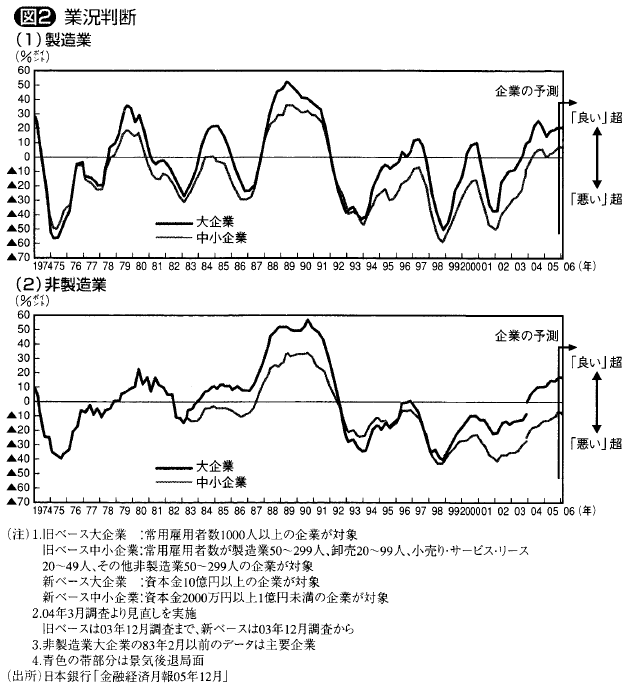
もちろん大企業、中小企業、製造業、非製造業によってこうした業況判断は違っている。日本経済全体をみるにはこれらの平均をみるとよい。
図をみれば分かるように景気循環上、日本経済はおおむね04年から好況期に入っている。04年のCPI(除く生鮮食品)はマイナス0.4%、05年平均はマイナス0.3%。つまりデフレのまま好況を迎えたのである。デフレが続く限り、回復は望めないという前述した「高い」実質金利説は正しくなかった。どこが間違っていたのだろうか。
回復と好況到来のメカニズム
間違っていたのは、実質金利があまり高くなかった点だ。デフレの最悪期でマイナス1%の物価下落率だから、ゼロ金利の下での実質金利は最大で1%。押しなべて0.5%程度だ。長期(10年)の国債金利は名目で1~1.5%だから実質金利は1.5~2%である。この程度なら、企業の利潤率が回復すれば十分克服できる。そうして実際、今日の回復期にみられた企業の利潤率(経常利益/売上高の比率)の回復は目覚ましく、そのレベルも既に04年には早くも1980年代後半のバブル期に並ぶほどに高まった。
企業の利潤率回復の原因は賃金デフレと企業のバランスシートの改善だ。名目賃金は99~03年に絶対的水準が下落した。これにより上昇し続けていた国民所得の中に占める労働所得の分配率が下がり、企業利潤の分配率は高まり、80年代の前半並みへ正常化した。
他方でバブル期の過剰債務の返済が進み、債務/株式の比率が下落しこれも正常化した。しかもこうした企業のリストラが、公共投資は減少し続け、景気刺激のない前述の量的緩和の中で、進んだのである。つまり伝統的なケインジアン的マクロ経済政策による刺激がない中で、かつデフレのまま、利潤率を回復して実質金利の壁を乗り越えた。これはまさに自律回復であり自律でつかんだ好況期だといってよい。
原油高騰のインフレ効果は小さい
今回の原油価格の高騰が日本経済にあまり影響しない第1の理由は、石油輸入金額/GDPの比率が86~00年の間、1%強から、05年の1.5%へとわずか0.5%しか上昇していないことだ、これに対し第1次や第2次石油ショック時には、この比率が70年の1.2%から74年には一気に4.3%へ、80年には5.2%に達した。GDPの何と4%もが産油国に所得移転されたことになり、今回の所得移転はその8分の1にすぎないことが分かる。
このように今回は、産油国への比較的わずかな所得移転で済んでいる理由は3つある。第1に日本経済のエネルギー効率の上昇、第2に1次エネルギーに占める石油のウエートの低下、第3に日本円の為替レートの上昇だ(74年=292円/ドル→05年=115円/ドル)。
一般消費者の生活への影響にしても、例えば、ガソリン(レギュラー)の小売価格は、73~80年の2度の石油ショックで、1リットル当たり60円から147円と2.5倍にもなった。これに対し今回は、2000~05年で106円から123円へ16%上昇しているにすぎない。
世界経済が原油高で悪影響を受け、日本の輸出が低下して日本経済が低迷するのではないかという危惧がある。だがこれもまた次の3点が石油ショック期とは根本的に異なる。
第1に今回の原油価格高騰はあくまでも「需要ショック」であって、70年代のような供給(途絶)ショックではない点だ。世界経済、とりわけ中国と米国の石油需要が強すぎる結果として価格上昇している。つまり、需要曲線が右へ大きくシフトして価格が上昇しても、その価格上昇が原因となって不況を生むわけではない。これに対し70年代の供給ショックはOPEC(石油輸出国機構)のカルテルによって供給曲線が左へシフトしたわけだから、石油価格が上昇すると同時に、経済活動は低下し、スタグフレーションが生まれる。
第2の世界経済上の相違点はOECD(経済協力開発機構)が全体としてGDP当たりの石油消費量を71~02年の間に事実上半減(48%)していることだ。
第3に石油価格の水準自体をみても、石油危機から今日までの一般物価の上昇率で調整した実質価格は、第2次石油危機後の80年が1バレル当たり80~90ドルと推計され、今日の60ドルと比べるとまだかなり低い。
以上のような理由から、今日の原油価格高騰がもったインフレ効果は小さく、同じく不況効果も産油国への所得移転とその後の還流(産油国の輸入増大など)で測ってみるとかなり小さいものだ、といえる。原油高、デフレ、好況の一見奇妙な共存はこうして説明できる。
ゼロ金利を維持して財政再建
では、日本経済が企業の自律回復力で好況期を迎え、それがデフレを終焉させつつあるとき、何が最も重要な政策課題なのだろうか。2つある。1つはこの好況をなるべく長期間持続させること。2つは次の不況期にデフレに陥らないよう、インフレの許容上限を高めに設定することだ。
まず量的緩和とゼロ金利政策にはどのようにして終止符を打っていくべきか。第1に量的緩和とゼロ金利を政策上峻別すべきだ。第2に「過剰準備」を1年位かけてゆっくり減らしていく。その間、ゼロ金利を維持したままでよい。この政策が長期金利の上昇を抑えてくれるはずだ。長期金利(国債10年物)が名目経済成長率を下回る環境をなるべく長く続けるべきなのである。第3に「過剰準備」が相当なくなるか全部なくなった時点で、ゼロ金利を解除する。その際、インフレ率が0.5%まで半年以上続くのを許す。その後で日銀による短期金利を0.25%にする(マイナスの実質金利維持)。
このように、量的緩和とゼロ金利から政策を峻別し、順序立ってそれぞれの政策から決別していくとき最も重要なことは、次の不況期に再びデフレに陥らないようにすることである。とりわけ次の日本の不況が米国経済の不況と重なると、間違いなく急激なドル安・円高となる。米国の金利や株価が下がり、GDP比6%以上もの今日の膨大な米国の経済収支赤字を埋めてくれるだけの民間資本の米国への流入はもはや期待できなくなるからだ。円高と重なった国内のデフレは非常に克服しにくい。
そこで金融政策の目標は、コアの消費者物価インフレを少なくとも3%近くまでもっていくまで低金利政策を採り続け、好況期をなるべく長引かせることだ。インフレターゲットを明示する必要はない。グリーンスパンFRB議長は、明示的なインフレ目標を掲げることはなかったが、極めて着実にインフレを2%前後に抑えた。日本の場合、それより高めがよい。円高の可能性があり、デフレへの下振れリスクが大きいからである。
資産バブルを心配する人も多い。しかし問題は90年代のバブルを大量の銀行融資が賄ったことにあった。こういうことが起きないようなプルーデンシャル規制を行えば資産バブルを心配することはないのである。
加えて今後の財政政策ははっきりと引き締め基調に入る。財政支出の削減であれ、増税であれ、この好況期を除いては財政再建はあり得ないからだ。
図2が示すように、この停滞の10年間は企業業況判断が「良い」と「悪い」の企業数の比較でゼロを上回ることはなかった。一部の製造業の大企業ではほんの一時的にそうなることもあったが、日本経済全体には広がらなかった。
だが現在は非製造業の中小企業を除くと、すべてがゼロを上回っている。まさに好況期である。俗称「失われた10年」とは「好況期が失われた」10年だったことが分かる。だから財政再建は難しかった。それがようやく可能となる好況期に財政引き締めが行われるのは当然だ。
だが、財政再建のもつ景気抑制効果を緩和基調の金融政策で相殺し、好況期を長期化することが重要である。財政引き締めと金融緩和というマクロ経済政策の協調は、次の不況とドル安を射程距離に収めたとき、インフレを3%まで許容したほうが望ましい金融緩和政策とも極めて整合的なのである。
2006年2月13日号『週刊エコノミスト』に掲載


