米国の赤字の持続性をめぐる大論争
米国の経常収支赤字は約8000億ドル、GDP比で7%近くに達してしまった(2005年)。20年ほど前の1985年のプラザ合意の頃は、この半分の約3.5%程度だ(図1)。
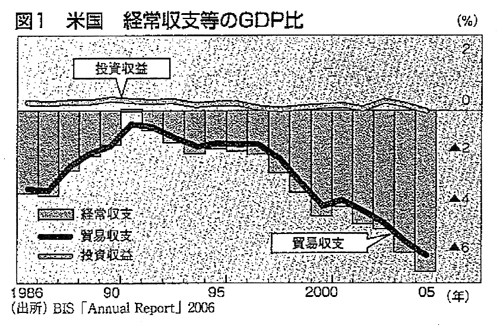
何故、今日これほど膨大になっている米国の経常収支赤字が、ドルの暴落を招くことなく「持続」しているのか。どのようなメカニズムでそうなっているのか。去る6月にボストン連銀が主催したシンポジウムでは、そうそうたる国際金融学者の間でおもしろい対決が見られた。
米国の対外「純」債務残高(対外総債務残高から対外総資産残高を差し引いた値)が、既にGDP比で21%に達している。それにもかかわらず、対外「純」投資収益はまだマイナスになっていない(図2)。つまり米国はGDPの2割にも相当する2.5兆ドルもの純借金を抱えながら、いまだに純利払いはゼロという「不可思議」をどう理論的、実証的に考えるか。借金していても純利払いがゼロであれば、米国の対外赤字は「持続」の可能性が高まる。
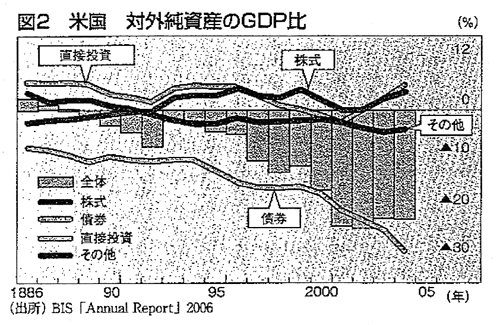
この現象は、米国が外国へ投資している総資産残高から上がる利益率が、米国が海外から借りている債務の利子率に比べ、かなり高いことからきている。R・クーパー(ハーバード大)は、米国による対外資産の運用利回りが高いのは、米国が金融上の技術革新を通してハイリスク・ハイリターンの資産へ運用する金融仲介機能を高度化しているためだと分析する。諸外国はそういう高度な金融市場をもつ米国に資産の運用を任せているのだ、というわけだ。経常収支黒字の大きい日本、ドイツ、中国、中東産油国などは、金融市場が依然として銀行中心で、証券化、デリバティブなど高度な金融技術では米国に後れをとっている、と説く。
これに対する反論も強い。米国がもつ対外資産の利益率の相対的優位性は、統計的に検証してみると、次第に低下してきている、というわけだ。前述のシンポジウムの最終スピーチを行った元米財務長官、ローレンス・サマーズ(ハーバード大学前学長)に至っては、米国の膨大な借金が持続可能だという諸々の説は、バブル期の真ん中にあってバブル的現象を合理化する、これまでもよく見られた理論、実証の動きの1つだ、と厳しい。88年という日本のバブル最盛期に、ジェフリー・サックス(コロンビア大)は、日本の高水準の地価は正当化できるという論文を発表したと、サマーズは被告者不在のまま判決を下した。
こうした議論はプラザ合意期の論調とは全く違っている。この論争内容の相違が、今日の世界の経常収支不均衡問題を解く政策論争上の違いとなっても現れている。私は今日必要とされる合意を「パン・パシフィック合意」と呼びたい。つまり先進国で決めた20年前の合意と違い、いまは日本、中国など東アジア主要国と米国を中核とした合意である。本稿では今日の不均衡問題がプラザ合意期のそれと質的にも量的にもどう異なるのかを明らかにし、従って合意の内容もどう異なるのかを考えたい。
プラザ合意期と異なる5点
ではまず、どこが大きく異なるか、それを整理しておこう。
(1)前述のように、今日は米国とその他世界の資産・負債の収益構造といったポートフォリオ上のバランスシートという「ストック」が問題の中心だ。これに対し20年前はもっぱら「フロー」が問題だった。80年代の半ば、米国の対外純資産はまだプラスだった(図2)。問題は経常収支の赤字、黒字というフローに集中した。
(2)そのフローの不均衡を生んだ犯人が為替レートのミスアラインメント(不整合)だった。80年代前半にドルが米国産業の国際競争力に比べて異常に強くなっていった。ドルが強くなりすぎた原因の1つに、レーガン大統領の供給力重視による法人税・個人所得税の大幅減税があった。その結果生じた財政赤字の膨張が、米国の長期金利を上昇させ、それが米国への資本流入を呼んで、ドルが過大評価されるようになった。この問題解明には、為替レートを内生化したマンデル・フレミングの理論構造が当てはまりやすく、その大国版をモデル化した世界経済モデル(日本の経済企画庁、米連邦準備制度理事会、OECDの3つが当時有名)を使って、シミュレーション分析を盛んに行ったものだ。
ところが今日の米国の大きな対外赤字や不均衡問題で、ドルが米国産業の国際競争力以上に強くなりすぎているというドルのミスアラインメント説は全くない。一言で言うと、米国の経常収支赤字は、もっぱら米国自身の貯蓄・投資のバランス上、貯蓄不足に原因があり、米国は国内の貯蓄不足を海外からの資本流入で補っていることになる。
(3)赤字を出しているいくつかの国もあるが(オーストラリア、スペインなど)、米国の経常収支赤字だけで世界の赤字総額の7割近くを占める。その反対側にある黒字国には、中国に加えその他の東南アジア(韓国、台湾、シンガポール、その他のASEAN4カ国、以下同)といった新興工業国の黒字合計が米国の赤字の3分の1の規模だ(表)。日本を入れると半分強の規模になる。これは20年前には見られなかった対極構図である。80年代は米国の赤字の対極にある黒字国は基本的に日本と西ドイツ(当時)だった。当時、日本の経常収支黒字は貿易黒字が主でありGDP比で当時4.5%もあった(今日は3~3.5%でしかも貿易収支黒字はその半分でしかない)。
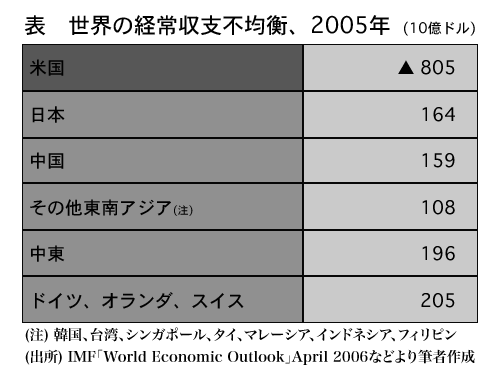
(4)20年前と現在とでは黒字国側の為替レジームが大きく違う。20年前は、日本を含め変動相場制を採用する先進国同士の間の不均衡問題だった。変動相場制の下で異常なマクロ経済政策に原因をもつ為替レートのミスアラインメントを抱えた世界経済だった。ところが今日、中国・その他東南アジアの為替レジームは多様である。中国やマレーシアのようにドルに事実上ペッグしている国もあれば(中国がバスケット制を採用した05年7月20日以降も基本的に変わっていない)、韓国のようにフロート性(04年秋以降)に近い国もある。その他の国は、これら2つの中間にある為替レジームだ。
(5)最後に、当時と現在では世界の貿易構造は、中国・その他東南アジアが勃興し生産ネットワークがアジアに確立した点で基本的に違っている。
20年前の世界の貿易構造は、一方で先進国と途上国の間は典型的な南北間の「垂直的な産業間」の分業であり、他方で先進国同士の間は「水平的な産業内」の分業だった。前者の南北間貿易の中心的構造は、先進国が資本集約的な財(機械、鉄鋼など)を輸出し、途上国は労働集約的な財(衣料、家具など)を輸出するという姿だ。これに対して後者の水平分業は、同じ産業でありながら、消費者の多様な嗜好に合わせた、例えば自動車産業でいえば馬力、スタイル、乗り心地が違う互いに差別化した製品を輸出入し合うという姿だ。これに加え半導体産業では(当時はDRAM中心)、生産規模が大きいほど、技術習得の学習効果が急速に高まり、国際競争力が高まるという製品も現れた。だから80年代の米国の赤字、日本の黒字というマクロ経済政策に根差した問題が、貿易摩擦としては自動車、半導体という先進国のリーディング産業で、しかも当時の世界の最先端の技術フロンティアで発生していた。
ところが20年たった今日はどうか。貿易摩擦は、南北間で、つまり中国と米国の間で生じている。何故そんなことになるのだろうか。中国が世界の技術の最先端で米国と競っているわけでも何でもない。問題の背景は、21世紀に入って確立した東アジアの生産ネットワークを土台にした新しい世界的三角貿易構造の出現にある。しかもそれは単に貿易だけではなく、多国籍企業の直接投資が深くからんで生み出された構造だ。
その特徴はこうだ。中国の輸出比率(対GDP)は35%に達し、既に日本の輸出金額を上回っている。ところがその6割近くは今日的な「加工貿易」だ。中国は日本、韓国、台湾などから技術集約度の高い部品、コンポーネント、産業素材などの中間財を輸入し、それを中国の低い賃金で加工した最終製品を、米国だけではなく世界のあらゆる市場へ向けて輸出している。この加工貿易の何と8割は外国企業の手による。
この20年間に世界貿易のなかで最も成長している財は、技術集約的中間財である。もはや20年前の最終資本財とか消費財ではない。しかも中間財貿易の推進役は多国籍企業だ。それが東アジアで展開されている。ではそれが世界の経常収支不均衡にどのようにかかわっているか。
この世界的三角貿易では、一方で中国は中間財の輸入をもっぱら他のアジア諸国から行い、米国やEUからはあまり輸入していない。理由は米国やEUがもはやそうした高度な中間財の輸出にはそれほど特化していないからである。ところが他方で中国は、加工した最終製品(パソコンなどIT製品)を世界のあらゆる市場に向けて輸出している。中国の揚子江デルタ地域では世界のノートパソコンの何と8割以上が組み立てられている。だから、米国から見ると、中国へ向けては中間財をあまり輸出していないのに、中国からは最終製品がどんどん輸出されてくる。この貿易構造が、米国と中国の間の二国間貿易で米国に2000億ドルもの赤字を生んでいる。だから米国は、米国の対世界赤字の4分の1は中国の黒字だといって騒ぎ、貿易摩擦を生む。しかし、米国の産業が中国からの輸入品と直接競合しているわけではないし、ましてや世界の技術フロンティアで両国が競っているわけでも何でもない。
しかも中国側から見れば、この三角貿易構造の下で、米国などその他の国との間で黒字となっているが、日本をはじめ他のアジア諸国との貿易収支は赤字なのである(1400億ドル、05年)。だから中国の「対世界」貿易収支黒字は、00~04年の平均ではGDP比でせいぜい3%前後だった。さらに05年には、中国の景気引き締めや、米国、EUの繊維輸入割当の撤廃(WTO上の約束)で、黒字が膨らんだわけだ。
30%のドル暴落にも耐えるパン・パシフィック合意
以上のような、20年前と今日の世界の経常収支不均衡の内容についての根本的な違いが、新しいプラザ合意(当時はG5の蔵相・中央銀行総裁の会合)というよりもパン・パシフィック合意を必要としている。そのためには次の2点をしかと押さえておきたい。
第1に、プラザ合意の目的は、ミスアラインメントの異常なドル高を、政策当局が意図的に市場に働きかけて是正することだった。その結果、85年初めには1ドル=250円が2年後には140円と大変な円高・ドル安となる。ポリシー・ミックスとしては、為替レートが大きく動くとき、赤字国(米国)は財政赤字の削減を、黒字国(日本)では内需拡大を、となる。
だが、今回の世界の不均衡では、ドルのミスアラインメントは見られない。となると、もっぱら米国による国内貯蓄の増大、具体的には、米国自身の財政赤字の削減と、住宅価格の上昇を担保に借金して消費を増やしている米国の消費需要を金利上昇で抑制することが、経常赤字削減の根本となる。
第2に、では為替レート政策はどうするか。今回は米国も黒字国も急激なドル安を望んでいない。市場もまた、IMF(国際通貨基金)やBIS(国際決済銀行)など国際機関による警告にもかかわらず、現在の不均衡の「持続性」に大きな不安を抱いてはいないようだ。フロート制をとるEUや日本は、ドル安に合わせて自国の通貨が強くなるのを認めるが、中国やその他の東アジア新興国は、自国通貨の急激な切り上げを好まず、ドル買い介入により外貨の蓄積(主に米財務省証券の購入)に走って、金融上は結局、米国の対外赤字の面倒を見てやることになりやすい。
以上のことから、パン・パシフィック合意は次のような内容を盛るべきだ。
(1)米国に貯蓄増強策として財政赤字削減と住宅価格に支えられた過大な消費・マイナスの家計貯蓄を是正する具体的政策を迫る。
(2)こうした米国の貯蓄・投資バランスの是正は、財政支出、個人消費、住宅投資などを低下させ、非貿易財(サービスや住宅など)の需要とインフレを、貿易財のそれらに対し相対的に抑えることになる。この貿易財の相対価格の下落を反映して、恐らく米ドルのゆっくりした下落を誘うだろう。そこでドルの急落も防ぐことができる。
(3)こうしたドル安に対し、中国とその他東南アジア諸国は協調し歩調を合わせて対ドル為替レートを切り上げる。今日の世界の不均衡を持続可能にするには仮に30%のドル安が必要だとしよう。ここで、前述の生産ネットワークと世界的三角貿易構造を反映して、東アジア諸国相互間の域内貿易比率は55%もあることを思い出してもらいたい。日本、中国、その他東アジア諸国の為替レートが一斉に30%切り上がった場合、対ドル切り上げの55%は相殺され、「実効」為替レートは13.5%の切り上げで済む(30%×45%)。この程度の切り上げが例えば2年の時間をかけて進めば、東アジア経済の成長は十分持続可能だろう。
こうした為替レートの上昇に見合って、東アジア諸国は内需の増大策、構造改革を進め、貿易拡大志向の経済政策を国内市場志向型へ転換する好機とすることもできるのである。
2006年8月14日号『週刊エコノミスト』に掲載


