1999年10月下旬、東南アジア諸国連合(ASEAN)プラス日中韓の識者26名がソウルで「東アジア・ビジョン・グループ」(EAVG)を結成し、第1回ミーティングを開いた。金大中大統領(当時)が各国に呼びかけ、司会は韓昇洲高麗大学教授(当時、元韓国外相・前駐米大使)が務めるという、韓国主導のハイレベルな会合であった。
デフレと景気回復共存の謎
日本の実質経済成長率は、03年度には1.9%だった(04年12月改訂値)。その後、04年度の4~6月期、7~9月期には成長率が鈍ってきたが、それでも前年同期比では、3%近くある。
ところがこの間、いわゆるデフレは依然として続いている。消費者物価の上昇率は、02年にはマイナス0.6%、最近の04年7~9月期にもマイナス0.2%だったからだ。
デフレのどこが悪いのか
デフレと景気回復の共存を解く鍵は、「デフレのどこが悪いの?」という問にきちんと答えることにある。ちなみに、デフレは景気や不況とは切り離されて、「物価水準の低下」と定義されている。
デフレが悪いのは、物価の下落が景気を悪くさせるからだという。なぜだろうか?
経済学ではこう答える。企業の借金残高がデフレのため実質的に膨らんでいくからであると。例えば100億円の売上高を持つ企業が、100億円の借金残高を持っていたとしよう。物価が10%下がれば、生産量は変わらなくとも、売上高は90億円に減る。ところが借金残高は100億円のままで変わらない。つまり、デフレのため、売上高に比べると、借金残高が自動的に実質10%膨らんだのと同じである。
これは10%のデフレが自動的に実質金利を10%高めることを意味し、これが設備投資を落とし景気を悪化させる。景気が悪くなると、需給関係が崩れて、さらに物価が下がるという、デフレ・スパイラルが生じる。これがデフレの悪いところだ。とすると、一方でデフレが景気を悪くさせているはずなのになぜ、日本の景気は回復しているのだろうか? 2つの理由が考えられる。1つは景気対策の効果、2つはデフレの悪さの度合い、つまりデフレの大きさ(実質金利の高さ)の実害がたいしたことではなかったかもしれない、という2つだ。
量的緩和の効果をどうみるか
景気対策といえば、財政拡大と金融緩和である。だが、日本の財政拡大の柱だった公共投資(実質)は、00年度を含め、毎年平均7%も減り続け、03年度には9.2%も減った。減税政策も、最も近年行われたのは、1999年の定率減税で、最近の景気回復の要因としてはいささか古い。個人消費(実質)は00年度から毎年0.7%の伸びにとどまっている。
金融政策も、99年からはゼロ金利政策が採られている。金利をゼロ以下に下げることはできないので、もはや金利低下によって景気を刺激することはできない。
そこで日銀はいわゆる、量的緩和政策を採っている。日銀が、公開市場操作を通して、日銀券と引き替えに市中の金融機関が保有する国債を買い上げる。その結果、金融機関には現金がたまる。その現金(ベースマネー)が銀行貸し出しに回れば、借り入れた企業はそれを何らかの投資に使うだろう。ところがその肝心の銀行貸し出しが増えていないのである。
どうして銀行貸し出しが増えないのか。それには、銀行貸し出しについての需要と供給の両面に、それぞれの原因がある。企業は、バブル期(80年代)に借りた膨大な借金を返済するのに忙しいので、銀行から新たな貸し出しを受けようとするわけがない。そこで銀行貸し出しに対する需要は落ちる。他方で、銀行自身も、バブルの崩壊(90年代)で生じた膨大な不良債権の処理に追われた。膨大な不良債権を処理すると銀行の自己資本が毀損されてくる。そうなると、銀行は新たな貸し出しを控えざるを得なくなる。自己資本比率(自己資本/貸し出し残高)を改善するため、分母の貸し出しを減らさざるを得なくなるからだ。
こうして、金利もゼロ以下には下がらず、日銀がベースマネーを増やしても、銀行貸し出しが増えないので、日銀がベースマネーを増やしても、銀行貸し出しが増えないので、日銀の量的緩和は景気を積極的に刺激できないままで今日まできている。
この間、日本はもちろん世界の学者も巻き込んで、ゼロ金利の下で、どうやれば量的緩和策が景気を刺激できるのか、盛んに議論された。日銀が思い切って株や土地を買ったらどうか、という議論もあった。しかし、株や土地の価値を決めているのは、将来の企業の収益であり、土地の上に建つオフィス等のレンタルというファンダメンタルである。だから日銀が株や土地を買っても、企業の収益やレンタルが上昇してこない限り、一時的にそうした資産価格を上げる日銀版PKO(Price Keeping Operation)にすぎない。
こうして日銀の量的緩和は、今日でも続いているが、それは流動性(現金)の増大を通して銀行システムの安定には寄与したものの、積極的に景気を刺激し上向かせることはできないままできている。
以上のように、財政、金融の両面からみた景気刺激策が、デフレ下の景気を回復させた要因ではないとすると、景気回復の原因はいわゆる自立回復力に求めるしかない。
大恐慌の場合はどうだったか
しかしデフレが、前述のように、高い実質金利を生んでいれば、企業が設備投資などするわけがなく、景気は回復してこないはずだ。
だがこうした考えが見逃している重要な点は、同じデフレやそれが生む高い実質金利といっても、そのデフレの大きさ、つまり実質金利の高さが問題なのである。
1929~33年の米国の大恐慌期には、デフレ(物価水準の下落)が、年平均8%に及んだ。これだと、名目金利が仮にゼロだとしても、実質金利は8%にもなる。こんなに高い実質金利では、企業は借り入れもしなければ、設備投資もしない。加えて金利はゼロどころか、企業の発行する社債の金利は、当時の信用リスクの高まりを反映して、4~5%もあった。だから、実質金利は12~13%にもなっていたことになる。このため設備投資は激減した。実質GDPも毎年8%以上で下落した。通算すると29~33年の間に、デフレ(物価水準の下落)は25%、実質GDPも25%減、両者を合計した名目GDPは何と50%減(半減!)したのである。こうした深刻なデフレと実物経済の大不況との共存は、グレート・ディプレッション(great depression)と呼ばれた。
デフレというと多くの人々が(エコノミストを含め)こうした米国の大恐慌を想起する。しかし今日の日本のデフレは、既述したように、02年で、年平均マイナス0.6%だ。単月でみても最も大きなデフレは、マイナス1%だった(前年同月比)。
高すぎるとはいえない日本の実質金利
より正しく実質金利を測るには、経済学的には将来に向けてのデフレ予想を使う方が、実際に生じているデフレを使うよりは正しい。先にちょっと触れたが、デフレの悪い点として、デフレがさらに深いデフレと呼ぶ、デフレ・スパイラルが考えられる。物価が下がれば、近い将来にはもっと物価が下がると考えて、買い控えをする。そうなると需要がもっと落ちるので、さらに物価は下がるという考えだ。
では、実際にこうしたデフレ・スパイラルが生じているという証拠はあるのだろうか。意に反してそうした証拠はないどころか、その反証がある。実際のデフレが1%のとき、デフレ予想はせいぜいその半分の0.5%だった。最近のように0.2%のデフレのとき、既にプラスのインフレを予想している(内閣府調査・国民生活アンケート調査04年)。
とすると、経済学的により正確な実質金利は、名目金利(短期は0%、長期は1~1.5%)マイナス予想デフレ率だから、日本の実質金利は、長期金利でみても、最高1.5~2%だったことになる。
この程度の実質金利をもって、高すぎるといえるのだろうか。真の問題はむしろ逆ではないか。つまり、この程度の実質金利をクリアできないほど、企業の利潤率が低すぎることに、問題の核心があったのではないか。
換言すると、政府・日銀の景気刺激策を借りないで、自立回復力がデフレ下にあって景気を回復させている原因は、企業の利潤率が高い水準まで回復していることにある。
企業の利潤率上昇とその原因
そうして実際、今回の景気回復の最大の特徴は、企業の利潤率のレベルが非常に高くなっているところにある。日銀短観(04年12月)によると(図)、売上高経常利益率は、とりわけ大企業・製造業の場合、03年度には4.9%あり、04年度(計画)には5.8%になる。この利益率のレベルは、80年代後半の4.8~5.8%に匹敵する高さなのである。大企業・非製造業となると03~04年度とも(3.4~3.7%)、バブル期をかなり抜いている。中堅企業・製造業の利益率(3.8~4.0%)もバブル期の平均(4.3%)に迫っている。中小企業・製造業とてバブル期の平均と変わらない。問題は、非製造業の中小企業の利益率がまだ低いことだ。
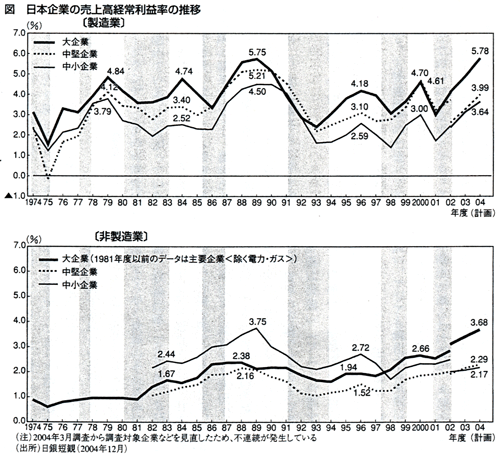
こうして日本経済全体をみると、売上高経常利益率のレベルが既にバブル期の平均にまで達している。これが実質金利1.5~2%をクリアさせている根本要因だ。では何が、企業の売上高経常利益率をそこまで回復させたのだろうか。97年11月の大金融ショック(大型金融機関の倒産)の後から数年続いたリストラである。リストラによって損益分岐点が低下した。それに加えて、デジタル家電に代表される技術革新があった。さらには、東アジアの経済統合を反映した輸出需要が伸び、国内の設備投資も伸びたのである。
リストラの内容は大きく2つに分かれる。1つは賃金デフレ、もう1つは企業のバランスシートの立て直しだ。
物価水準が下がっているとき、賃金が下がらない限り、企業利潤は回復できない。つまり物価デフレの下で利潤率が回復するためには、賃金デフレも生じる必要がある。これは容易なことではない。賃金の上昇になれているとき、500万円の給料が450万円に下がるという賃金の絶対的下落には労働組合をはじめ強い抵抗があるからだ。ところが日本の平均賃金は、この4年間(99~03年)で累計7%も低下した。ボーナスの大幅カットや、非正規雇用の増大が、これを可能にしたのである。04年度になっても、平均賃金は横ばいに近かった。
企業のバランスシートの改善は、97~98年に生じた日本の銀行危機(山一証券、北海道拓殖銀行、日本長期信用銀行、日本債券信用銀行といった大手金融機関の倒産)以降、急速に進んだ。銀行の不良債権処理の進展と裏腹の関係にあったといってよい。企業は過去の債務を返済し、負債/資本の比率は03年には93年のピークからほぼ半減し、バブル前の80年代はじめごろの水準にまで下がった。これが企業の利払い後の収益率を改善した。バブル期の過剰債務が残っている限り、前向きの設備投資などできない。そうしたバランスシートの調整が進んだのである。
技術革新もまた企業の利潤率を上げる。液晶フラットテレビ、デジタルカメラ、DVD(旧来のVTRに代わる)の新三種の神器の急成長は、今回の景気回復期にみられた技術革新の中で最も目に入りやすいものだ。アナログ家電からデジタル家電への転換によって、家電製品の中により多くの情報ソフトが含まれるようになっている。例えば、デジタル薄型テレビに使用されているソフトウエアプログラムの規模は、アナログテレビに比べ格段大きくなり、パソコンOS(基本ソフト)にかなり近づいている。また、DVDプレーヤーやテレビゲームに搭載されている半導体の比率は高く、その中でMPUマイクロプロセッサなどの割合は、デスクトップのPCやPCサーバーと変わらないか、それを抜いている。日本が強い家電やゲーム機や携帯電話が、日本が弱いパソコンやサーバー並みに急速に情報技術化(IT化)してきているのである(阿部忠彦「デジタル家電の成長戦略」04年富士通総研)。
以上のような理由による高い企業利潤率の出現が、デフレのハンディを乗り越え、景気対策の助けを借りない自立回復を可能にした。利潤率が高ければ、設備投資が増える。実際それは、03年度の8.2%も増加した。04年度の上期(4~9月)には鈍化したが、それでも前年同期比では7%ある。
東アジア全体が世界の製造センター化
企業の損益分岐点が上記のリストラで低下しているところへ、外需が増えた。しかし、この外需は、今回の景気回復期には、新しい特徴をもっている。それは東アジア全体が、日本、新興工業国(韓国、台湾など)、ASEAN諸国を含め、世界の製造センターになっていることだ。その中で、日本の企業が重要な役割を果たし、かつ日本の景気を支える外需をも生んでいる。
よく、中国が世界の工場であるかのようにいわれるが、そうした見方は「木を見て森を見ていない」。というのは、中国の工場は自分の足だけで自立できていないからである。中国は、日本、韓国、台湾、ASEANなど、アジアの多くの隣国から、技術的に高度な中間財や部品を輸入して初めて、それらを加工し、最終製品に仕上げて輸出しているからである。
中国のこうした加工貿易は、中国の総貿易の55%を占める(02年)。しかもその加工貿易自体、その8割は、アジアなどから中国に進出した多国籍企業の生産による。いまや東アジア全体が、生産・流通のネットワーク化した壮大な経済システムとして動いている。
電気機器や情報機器の生産は、エレクトロニクスにみられるように、高度な生産工程から始まって単純な労働によるアセンブリ(組み立て)工程で終わる長い生産工程だが、その長い工程が細かく分断されて、それらが比較的優位に沿って立地され、アジアの多くの国々に同一の産業内での精密な垂直分業が形成されているのである。自動車産業もそれに近い特徴をもつ。鉄鋼業もそうだ。
高度な技術を必要とする部品や中間財、多額の資本を必要とする資本財(半導体製造装置など)などは、日本が生産し、韓国、台湾などはそれに次ぐ高い技術集約的な部品・コンポーネントを生産、ASEAN諸国に所在する日本をはじめとする多国籍企業もまた高度な部品を生産し、それらを中国へ輸出しているのである。中国は、これらを比較的安い労働力で加工する。そうして出来上がった最終製品は、主に先進国へ輸出されていくのである。東アジア全体が世界の工場になっているわけだ。
その中にしっかりと組み込まれているからこそ、日本の輸出はしっかりと伸びるのである。
「踊り場」から脱出するメカニズム
04年からの半年間、実質GDPの伸びは横ばいだった(季調値、前期比)。原因は大きく分けて3つあった。(1)中国の景気調整、(2)原油価格の急騰、(3)デジタル家電などの在庫調整。
中国の年率9%台の成長は、マクロ経済一般のオーバーヒーティング(過熱)というよりは、電力、セメントなどでのいわゆるボトルネック・インフレーションを生んだ。それに加えて、主要都市での土地バブルも発生した。消費者物価も、02年のデフレ(マイナス0.8%)から、04年央には5%台のインフレになった。
しかし、食品価格の上昇を除くと、コアのインフレは2%強にとどまっている。食品価格の上昇は、経済過熱の結果ではなく、農政からくる作付面積の低下による穀物生産の供給不足が原因で、これも最近は低下し始めている。したがっていわゆるハードランディングの可能性は高くなく、一時的な景気調整とみて良いだろう。
原油価格の急騰は、先物価格でこそ1バレル当たり50ドル台をつけたが、スポット価格の実勢は40ドルだった。加えて、国際機関(IEAやIMF)の調査では、同じ10ドルの上昇でも、日本のGDP成長に及ぼすマイナスの影響は0.4%で、他の先進国の半分に過ぎない。日本では原油輸入金額の対GDP比は1.5%に過ぎず(第2次石油ショック時は7%)、先進国の半分だからだ。もちろん、日本以外の国々の成長が、原油価格上昇により鈍化すると日本の輸出が減るわけだが、米国の成長率は04年7~9月期も年率4%と高い。アジアも鈍化する気配はない。
デジタル家電の在庫調整も踊り場をつくったが、デジタル家電に使われる半導体や液晶部品の設備投資計画は根強い(ソニーや富士通など)。世界の市場ではまだデジタル家電の普及過程にある。
前述した高い企業利潤率は、一方で設備投資を維持する誘因である、他方で好調な株式市場を生み、消費に対する資産効果を持つ。日本の株価/収益比率(PER)も15~20倍とようやく世界のそれ並みに正常化してきた。企業収益が伸びれば株価が上昇する地合いが整った。
こうして企業の高い利潤率が、日本経済をデフレからも踊り場からも脱却させる力として働いている。
2005年2月14日号 『週刊エコノミスト』に掲載


