国民経済計算(SNA)と家計調査の貯蓄率の乖離の原因を論じる前に、今回は、まず比較する統計を明確にし、現状を把握しよう。
SNAとは、国内総生産(GDP)をはじめとして、経済活動全体を包括的にとらえた統計であり、マクロ経済分析には欠かせない。その中の制度部門別所得支出勘定では、家計・企業・政府などに分けて貯蓄・投資バランスが把握されている。家計部門の貯蓄を可処分所得で割った「家計貯蓄率」が家計調査と比較する項目である。
一方家計調査は、家計簿を集計して作成されるミクロ統計である。年齢や所得水準などの世帯属性別の消費・貯蓄行動を把握し、家計の意思決定をミクロ経済学に基づいて分析するための統計である。貯蓄率に対応するのは、可処分所得から消費支出を引いた「黒字」を可処分所得で割った「黒字率」であり、伝統的に「2人以上の世帯のうちの勤労者世帯(サラリーマン世帯)」の結果が用いられてきた。
貯蓄率の1970年以降の推移を見ると(図)、80年くらいまで乖離は小さかったが、その後は大きく開いた。しかも2000年ごろまでは水準だけでなく変化の方向も違っており、直近でも25%ポイントもの大きな差がある。
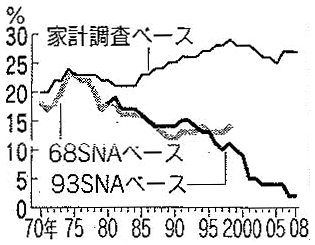
この乖離の原因の解明が、貯蓄率低下の原因を分析する出発点である。この2つは補完的な統計であり、SNAによってマクロ的な貯蓄率の変動を把握し、それを家計調査によって属性別の貯蓄率の変化に分解することで、貯蓄の決定メカニズムが分析できる。しかし、乖離があれば、ミクロとマクロで一貫した分析は不可能である。
この乖離の一部は対象世帯や貯蓄の定義など制度的な要因によっても発生する。しかし先行研究で指摘されたように、それらを調整しても乖離は残る。その残された乖離こそ本当の「謎」であり、ここで「統計のクセ」によって説明しようとする部分である。
先行研究は、制度的な違いに注目する一方で、統計のクセは放置してきた。それは、クセの存在自体が、客観的に示すことが困難だからだ。そこで、まずは先行研究にしたがい制度的な違いを調整し、統計のクセの大きさを明らかにしよう。
2010年8月25日 日本経済新聞「やさしい経済学―『真』の貯蓄率と統計のクセ」に掲載


