安倍晋三首相は「女性の活躍」を成長戦略の中核とした。その具体的対応の第1が「待機児童解消加速プラン」と名付けた保育所の整備だ。本稿では、筆者の経済産業研究所での研究に基づきこのプランの是非を論じたい。
結果を先に述べれば、保育所の整備を成長戦略と位置づけたことは高く評価できる。保育所の整備には、女性の結婚・出産と就業の「両立可能性」を高める効果があるからだ。ただし、待機児童解消を目標とすると政策がゆがむ可能性がある。政策の具体化や事後評価には、より適切な目標を設定する必要がある。
◆◆◆
女性の結婚・出産と就業の両立可能性は、少子高齢化の進む日本において最も重要な指標の1つだ。労働力の確保には女性の活用が不可欠であり、少子化の解消には女性の結婚・出産を促進する必要がある。2つの目的を同時に達成するには両立可能性を高めることが必須である。
しかし、これまで両立可能性は微妙に政策課題の中心から外れていた。女性労働問題の中心は男女の雇用機会や賃金の格差是正であり、少子化対策の中心は不妊や男女の出会いの欠如であったため、どちらの文脈でも両立可能性は主役になりきれなかった。成長戦略の文脈に位置づけて両立可能性に焦点を合わせた今回のプランは、まさに正鵠を射る政策だ。
政策の中心課題になれなかった理由はもう1つある。両立可能性が正確に計測されてこなかったという技術的な問題だ。現状が把握できていなかったため、政策の必要性も認識できなかったのだ。両立可能性の計測には、結婚・出産前後の女性の就業状態を知る必要があり、同一の個人の状況を追跡して調査する「パネルデータ」が必要だ。しかし、日本ではパネルデータの整備が遅れている。
この問題に対し、筆者は国勢調査の生年コーホートを用いた分析によって対応した。生年コーホートとは生まれ年が同じ個人の集団であり「世代」のことである。各世代の婚姻状態や労働力状態は各時点の年齢階級別データで把握できる。世代を構成する個人は各時点で同一なので、生年コーホートのデータは擬似的なパネルデータとみなせる。
たとえば、1980年に生まれた女性は2005年時点に25歳、10年には30歳になる。各時点での未婚率はそれぞれ74%、41%だった。その差を取ることで、この世代の女性のうち33%が05~10年に結婚したことが分かる。同様に、労働力率は77%から67%に低下しており、10%が労働市場から退出したとみなせる。
結婚した女性の割合と労働市場から退出した女性の割合が分かれば、その比率で「結婚した女性のうち労働市場から退出した割合」を推定できる。日本では結婚した女性の85%は5年以内に子供を産んでおり、逆に結婚せずに子供を産む女性は少数であることから、統計的には「結婚」を「結婚して出産する」割合として利用できる。すなわち、計測しているのは結婚・出産と仕事の両立可能性だ。
先述の例では、結婚によって非労働力化した者の割合は30%になる。逆に70%の女性は就業を継続した(すなわち「両立」した)ことになる。こうした各世代の就業継続率を集計したものを、各時点で両立可能性と解釈した。
◆◆◆
国勢調査を用いた生年コーホート分析によって1980~2010年の間の両立可能性の推移を観察すると、意外な事実が分かる。05年まで両立可能性はほとんど不変であり、最近までは全く改善していなかった。この期間に女性の労働力率は大幅に上昇しているが、それは両立可能性の改善によるものではなく、単に未婚化の裏返しの現象だったのだ。
ところが、直近の05~10年の5年間に両立可能性は急速に高まっている(図参照)。この変化も一般には認知されていないが、就業継続率は過去25年の変動幅からは考えられないほど急激に上昇している。この傾向は2000年以降に利用可能になった個人ベースのパネルデータである厚生労働省「21世紀出生児縦断調査」でも確認できる。出産前後で仕事をやめた母親の割合が01年出生児では67.4%であったが、10年出生児では54.1%まで低下している。
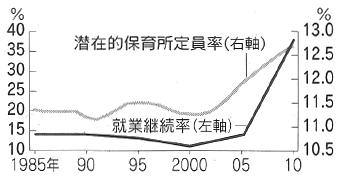
また、都道府県別・年齢階級別データにも生年コーホートの手法は適用できる。地域別に就業継続率を計算すると、その水準に大きな差があった。東京や大阪などの大都市部では両立可能性が低く、山形・富山・石川・福井などの日本海側各県では高いのだ。一方で、どの都道府県でも05年までほぼ不変で10年に改善する傾向は共通していた。
両立可能性が把握できればその決定要因を考察することもできる。カギとなるのは時系列的な推移や地域別の差といった統計的な性質だ。両立可能性を決定する要因があるなら、その要因も同じ統計的な性質を持つはずだからだ。
統計的性質から逆算的に特定すると、保育所の整備状況が最大にしてほぼ唯一の両立可能性の決定要因であることが分かる。筆者が「潜在的保育所定員率」と呼んだ20~44歳女性人口と保育所定員の比率で測った整備状況は05年まで不変で、その後に急上昇している。日本海側で高く、大都市部ほど低いという地域差もある。すなわち、両立可能性と同じ統計的性質をもっている。
一方、これまで両立可能性に影響を与えると信じられてきた他の要因のほとんどは、その重要性が否定される。たとえば、育児休業制度は92年に導入され急速に普及してきたし、3世代同居率は一貫して低下傾向である。これらが決定的な要因であるなら、両立可能性も時系列的に変化してきたはずであり、データ観察の結果と矛盾する。より一般的に、80年から05年までに実施された政策や社会の変化は、同じ時期の両立可能性が不変であったという事実から、重要な決定要因ではないと判断できるのだ。
◆◆◆
05年まで保育所整備が進まなかったという事実認識に違和感があるかもしれない。通常、保育所の整備状況は保育所定員率(0~6歳人口と保育所定員の比率)で測るが、その指標は過去30年間一貫して上昇しているからだ。しかし、実は保育所定員率の上昇は保育所整備ではなく、分母の0~6歳人口の減少によってもたらされている。つまり、少子化対策の成果ではなく、少子化の結果なのだ。
同じ問題は、待機児童数にもある。保育所が不足して入所できる可能性が極めて低くても、入所を断念するケースが多ければ待機児童はそれほど増えない。逆に、多くの自治体が実感しているように、保育所を整備すればするほど希望者が増加し待機児童が増える可能性もある。待機児童ゼロといっても、誰もが希望すれば入所できる「良いゼロ」と、誰も希望することすらできない「悪いゼロ」があり、保育所が不足しているかどうかとは関係ない。その意味で、待機児童ゼロを政策目標とすることは、適正な資源配分をゆがめる可能性がある。
この問題を避けるために、筆者は分母に20~44歳の女性人口を用いた潜在的保育所定員率で保育所整備を測った。潜在的に母親になる可能性のある人口1人あたりとすることで、保育所不足が原因で入所を断念したり結婚を断念したりする人の影響を回避したのだ。待機児童のように政策のゴールが見えやすくはないが、客観的に状況を把握できる適切な指標である。
先日、横浜市が待機児童をゼロにしたと報じられた。横浜市の取り組みは成長戦略にも積極的に取り入れてもらいたい。しかし、評価すべきは保育所の整備を真摯に進める姿勢だ。待機児童をゼロにすることが自己目的化しないよう、適切な指標を用意して政策を実行してもらいたい。
2013年6月11日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


