4月の消費税率引き上げから1カ月以上経過した。各種調査を見る限りは、価格への転嫁も順調に進み、心配された需要の反動減は予想より小さいようである。しかしこれまでの議論が、価格に100%転嫁できるかどうかや、引き上げ後の反動減・デフレ効果にのみ議論が集中しすぎているのは否めない。本稿では消費税引き上げの際の企業の価格戦略に着目し、政策的含意を考えてみたい。
◆◆◆
今回の消費税率引き上げで着目すべき点は、価格表示のあり方が特例措置で変わったことである。2004年度から商品の本体価格に消費税分を含めた総額表示が義務付けられてきたが、17年3月末までの期限付きで税抜き表示も誤認防止措置を前提に認められることになった。
これは来年10月に予定される10%への引き上げも視野に入れ、値札の張り替えなどの事業者負担を軽減するためである。ただし総額表示に慣れた消費者にとっては税抜き表示になることで値札に書かれた価格そのものは低下するため、むしろ割安と感じてしまう可能性はありそうだ。
もちろん消費者が合理的であれば、価格表示にかかわらず正確に自分の負担を把握し、消費行動が影響を受けることはないはずだ。しかし最近の研究では、税表示によって消費行動が変わることが明らかにされている。
米ハーバード大学のラジ・チェッティ教授らは09年の論文で、店頭での価格表示が税込み価格か税抜き価格かで消費行動が異なるか米国で調べた結果を示した。欧州では付加価値税込みで表示されるのに対し、米国では州レベルで小売税が導入されており、通常は税抜き表示となっている。スーパーでの実験で一部の商品に通常の税抜き価格と併せて税込み価格を付け加えた表示をすると、その商品の売上高は平均して8%減少することがわかった。
一方、ビールの場合は州レベルで小売税以外に酒税を課している。酒税は店頭で表示されている小売税抜きの価格に含まれている。チェッティ教授らは州ごとの小売税、酒税の水準や変化が異なることを利用し、酒税の上昇の方が小売税の上昇よりビール消費を減少させることを示した。これは税が値札の価格に直接反映されていなければ負担を軽く感じる「錯覚」があることを示唆している。
米コーネル大学のタティアナ・ホモノフ助教らは13年の論文で、たばこについて同様の分析をしている。たばこもビールなどと同様、店頭では小売税を除いた税抜き価格が表示されているが、たばこ税自体はこの税抜き価格に含まれている。彼らは高所得者と低所得者の違いにも着目し、双方ともたばこ税の変化には反応したが、小売税の変化に反応したのは低所得者のみであったことを示した。低所得者の場合、税の表示方式には関係なく総額の価格変化に敏感であることがわかる。
このように税抜き価格表示は誤認防止措置を講じていたとしても価格に応じた最適な消費行動を阻害する可能性がある。日本でも従来の総額表示の方が望ましいことを再確認すべきである。
◆◆◆
今回の消費税率引き上げに関するもう1つのポイントは、価格転嫁の仕方が商品によって分かれたことだ。
現実的な市場環境(不完全競争)を考えると、価格転嫁は需要が価格によってどう変わるか、さらには市場構造などによって異なる。理論、実証分析の両方で、最適な価格上昇率が税率変化幅を上回る場合と、下回る場合があることが知られている。
例えば100円で200個売れている商品A、B(原価ゼロ)があり、1円の値上げでAは2個、Bは0.5個ずつ販売数が減るとする。10%の消費税が課せられた時、全て上乗せすると、販売数はAが180個、Bは195個に減る。一方、税込み価格を100円に据え置けば販売数は変わらない。このとき利益は、Bが1300円減る一方、Aは200円増える(図)。
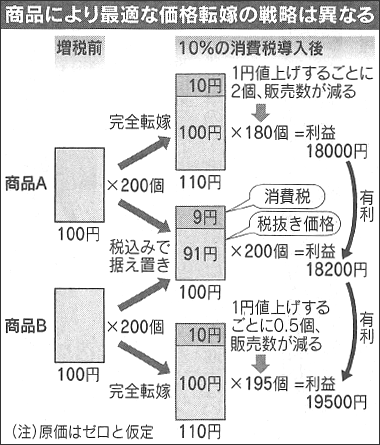
このように売上数量、コストも考慮した全体の収益を最大化しようとする事業者にとって商品によって転嫁率を変えるのは不思議ではない。従って「100%転嫁できないのは事業者の不利益」「税率上昇以上に価格を上げるのは便乗値上げ」といった見方は短絡的だ。欧米でも政府関係者は「全ての商品で転嫁率は同じ」「転嫁は完全であるべき(消費者が全て負担)」と仮定しがちだといわれ、正確な理解は案外難しいようだ。
興味深いのは、4月から税込み価格自体を下げた商品があることだ。例えば日本マクドナルドはハンバーガーを20円下げて税込み100円にするなど一部商品を値下げ。牛丼の「すき家」も牛丼並盛を10円下げ270円にした。こうした品目は同一企業が提供している商品の中でも価格帯が最も低く、価格を下げたときの需要の伸び率(弾力性)が高いと考えられる。その場合、価格転嫁をなるべく抑え、需要全体が消費税増税で落ち込んでいるとすればさらに価格を下げることは合理的な価格差別戦略といえる。
◆◆◆
こうした値下げ商品がある一方で、価格上昇率が消費税による上昇分を上回る商品もある。これは先に述べた商品独自の特性による影響も考えられるが、4月18日付「経済教室」で東京大学の渡辺努教授が指摘したように、消費税率の引き上げが価格の硬直性を弱め、デフレ脱却の契機を与えているという解釈も可能かもしれない。
価格硬直性とは、コストが変化しても価格がすぐに変化せず、価格改定の頻度などが制限されることを意味する。その原因として値札の変更など物理的な負担(メニューコスト)が挙げられることが多いが、実際にはライバル企業が価格を上げないと自分からは価格を上げにくいという「協調の失敗」の影響が大きいと考えられる。
この点については米ニューヨーク大学のルイス・カブラル教授らが12年の論文で、消費者が価格情報を入手するのにかかる費用(サーチコスト)に基づいて分析している。最も安い商品を調べるのにもコストがかかることを考えると、消費者は売り手の価格が変化しない限り価格調査はしない。ところがある売り手が価格を引き上げれば、消費者はコストが変化したと考え価格調査を始め、結局ライバルを利することになる。カブラル教授らは価格が引き上げにくい背景に、こうした構図があると強調した。
そう考えると消費増税は、コストを転嫁したくてもできなかった事業者にその機会を与えると解釈できる。欧州中央銀行の研究でも、多くの欧州諸国で付加価値税率変更の前後で価格改定の頻度が高まり、価格硬直性を弱めることが明らかになっている。
高齢化が急速に進む中で、日本の社会保障・財政の持続性を確保するには、将来、欧州並みの20%近くまで消費税率を引き上げる覚悟をしなければならない。消費税を消費者と企業のどちらが負担すべきかを議論するより、国民一人一人の生産性向上を考える方が有益だ。そうすれば企業側は価格上昇を抑えられ、生活者も収入が増えて負担を吸収できる。財政健全化の成否も最後は一人一人の生産性をいかに向上させていくかにかかっているのである。
2014年5月19日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


