はじめに
いわゆる「アベノミクス」の効果により株高、円安が進み、日本経済は足元では「失われた20年」からの脱却への一歩を踏み出したかに見える。しかしながら、長期間にわたって続いた円高や企業を取り巻く環境の変化等もあり、地域経済の状況は依然として厳しく、地方のものづくり企業をはじめとする中小企業の業況が回復するまでには至っていないとの現場の声も多い。こうした厳しい環境下、これまで日本の技術力の象徴であったといっても過言ではないDRAM 専業メーカーのエルピーダメモリ、液晶事業のシャープといった先端企業の経営危機が表面化した。現状、前者は経営破たんの後、会社更生法の適用を申請、更生計画認可決定が確定し、米マイクロン・テクノロジーの完全子会社として再建中である。他方、後者についても、足元ではスマートフォンやタブレット向け液晶に明るい兆しが見られるが、経営再建はこれからが正念場という状況かと思われる。筆者は両社の主力事業所が立地する東広島市に赴任して約1年半になるが、日本のものづくり文化を象徴するような有力企業が今後いかにして経営再建を進め、国際競争の舞台に再度登場し、他国の有力企業に対して競争優位を確保できるようになるのか、注目している。
造船、自動車をはじめとする輸送用機械、鉄鋼、電気機械、一般機械、食料品、化学など、様々な分野の企業がバランスよく立地する広島県では、ものづくりにおいて取扱製品または保有技術が他社にないオンリーワン企業、ないしは国内外の生産、販売シェア等が第1位であるナンバーワン企業として県の認定を受けている企業が多数存在している。しかしながら、デフレ、円高等の厳しい外部環境の影響を受け、地域全体でみると、中小製造業を中心とするものづくり企業の疲弊はかなり深刻と言わざるを得ない。これは広島に限ったことではなく、ものづくり企業を中心として成り立っている全国津々浦々の地域経済が直面する共通の問題と考えてよいと思われる。これまで日本の成長に貢献してきたものづくり企業から成る地域経済が再生し、輝きを取り戻していくにはどうすればよいか、また何が必要であろうか、本稿ではこうしたことを考えていきたい。
産学官連携の重要性
ものづくり企業にとって最も重要と思われるのは、絶えずイノベーションを生み出していくための技術力である。その上で、ものづくり企業が有する基盤技術を効率的な製品開発、あるいはイノベーションに結び付けていくためには、異なった立場の技術者・研究者が技術知識等の情報交換を行う産学官連携を活用した研究開発の推進、中長期的にものづくりを担っていける人材の育成等が必要である(経済産業省他(2013))。後述するように、日本において産学官連携の機運が高まってきたのは2000年代になってからであるが、その重要性が認識、共有されるようになったためか、近年話題に上ることが少なくなってきているようである。ここで再度、その重要性を確認しておくことは有用であろう。
イノベーションのもとになるアイディアないし技術知識は、人々の情報交換を通じて生み出され、開発、設計、試作と1つの製品として実用化段階に近づくにつれて情報交換の密度は徐々に濃くなっていく。さらに、1社だけでは解決が困難な課題になればなるほど、企業、大学、政府(及び公的研究機関)という多様な主体間での情報交換を通じた「気付き」が多くなってくる。このような公共財的な技術知識は「スピルオーバー効果」を有し、様々なルートにより外部に拡散していき、他社による模倣の対象にもなってしまう。そこで、こうした外部経済効果を内部化する手段の1つとして、共通のテーマにつき関心を有する産学官の関係者が連携することにより、効率的な研究開発を推進する産学官連携が重要になるのである(冨田(2012))。
産学連携の効果については、いくつかの研究により実証的に確認されている。元橋(2003)では、RIETI 産学連携実態調査と企業活動基本調査(経済産業省)の接続データを用いた定量分析が行われている。その結果、産学連携は企業の研究開発や生産活動における生産性に対してポジティブな効果を有し、かつ企業年齢の若い企業ほどその効果が強く現れていることが確認されている。また、企業年齢が若く企業規模の小さい研究開発型中小企業についても、産学連携により研究開発活動で高い生産性が確保されていることが分かっている(元橋(2006))。このように、産学連携に代表される研究開発ネットワークは、従来型の自前主義では立ち行かなくなっている日本のイノベーション・システムをオープン型に変えていくものとして注目されている。
さらに、地域においてイノベーションを創出しやすい環境を整備し、日本全体としてイノベーションを活発化させるために、2000年代初頭からいわゆるクラスター政策(経済産業省、文部科学省等)が行われてきており、企業間連携や産学官連携のネットワーク形成によるイノベーションの促進、新産業・新事業の創出が期待された。経済産業省の産業クラスター計画の事例を取り上げ、アンケート調査から得られたデータをもとに分析した児玉(2006)においても、新たな技術シーズを導入する上で、産業クラスター形成における大学の役割が重要であることを確認している。他方、より市場に近い新製品開発等には企業間連携が有効であることも見出されている。
日本における産学官連携の状況
米国においては、1980年代以降、低下した国際競争力を回復すべく、産業競争力強化への取り組みがなされてきた。その1つがバイ・ドール法で、大学・企業等が政府資金を利用して行った研究開発の成果物(特許)を大学・企業が所有できるようにしたものである。アカデミズムにおいては、バイ・ドール法の効果を限定的とする実証結果が多い(岡田(2006))との指摘もあるが、一般には米国の産業競争力回復の契機になったと言われている。羽鳥(2011)によれば、現在、米国の大学の研究成果に関するライセンス収入は20億ドルを超える水準にもなるという。
他方日本においては、バブル崩壊後、経済が長期にわたって低迷した1990年代を経て、概ね2000年代より競争力強化の取り組みがなされてきた。米国に遅れること約20年でようやくスタート台に立ったということであるが、1999年には日本版バイ・ドール法、2000年には産業技術力強化法(大学教員の兼業緩和等)が制定されている。
ここで、文部科学省により行われているアンケート調査「大学等における産学連携等実施状況について」(2003年度~)により、日本における産業界と大学等の間の連携関係がどのようになってきているかを見よう。図1は民間企業との共同研究実施件数と大学等が民間企業から受け入れている研究費受入額(大学等が要する経費を民間企業等が負担しているもの)を示しているが、2009年度にリーマン・ショックを契機とする世界経済危機により件数、受入額ともに落ち込みを見せた以外は、順調に拡大してきている。他方、民間企業からの受託研究の実施件数及び研究費受入額を示す図2を見ると、共同研究とは対照的に概ね減少傾向にあることがわかる。すなわち、産学連携の活動の重点が受託研究方式から共同研究方式にシフトしてきている状況にある。これは、企業の競争戦略が研究成果である知的財産権を保有し、できるだけ有効に活用しようという方向に変化してきたためかも知れない。というのは、受託研究では研究成果としての知的財産権が原則として大学や大学の研究者に帰属するが、共同研究では共有ないし貢献度により持分設定されることになるからである。
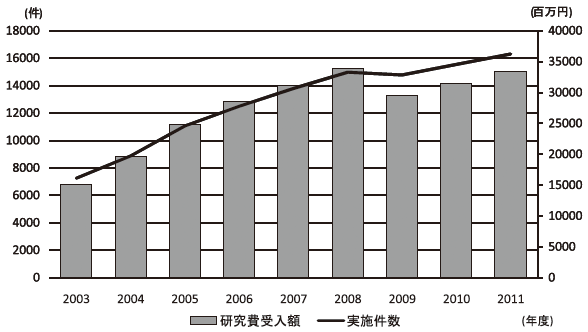
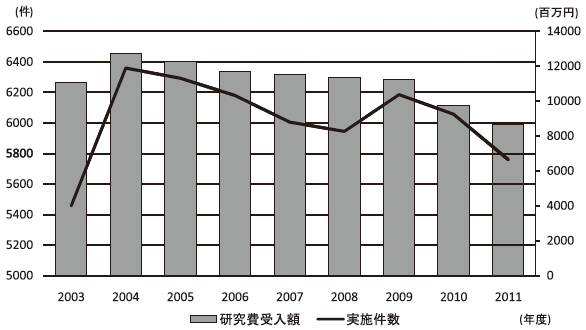
研究成果としての特許出願件数は2008年度以降伸び悩んでいるものの、足元の2~3年で特許権保有件数が急増しており、2004年度の国立大学法人化以降に出願された特許が権利化されたものと考えられる(図3、4)。また、外国出願比率、特許保有の外国比率ともに25~30%程度を確保している。さらに、図5を見ると、特許権実施等件数は大幅な伸びを示しており、収入額も増加傾向にある(文部科学省によれば、2010年度の収入が急増しているのは、一部大学で特許権の譲渡収入、イニシャルロイヤリティ収入が一時的に多かったことが影響しているようである)。
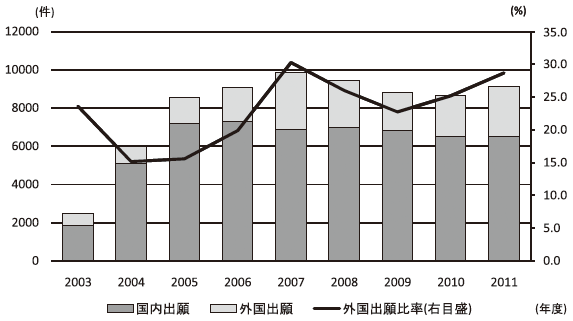
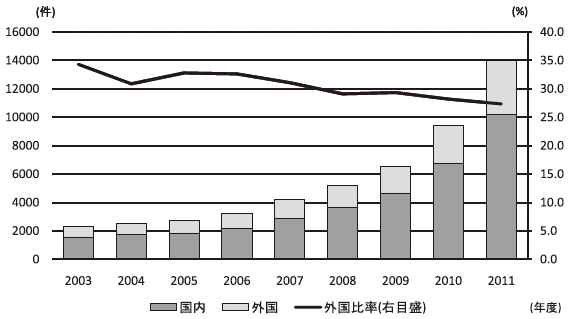
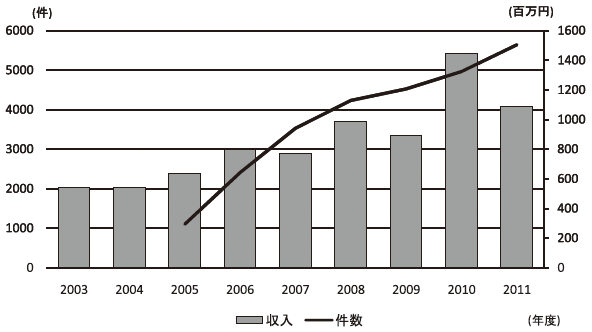
競争力強化を目指す産学連携に関する日本の取り組みが始まって僅か10数年、米国の実績等と比較するとまだまだこれからという感もあるが、量的拡大というよりは、そろそろ内容面での質的な充実に軸足を移してよい時期ではないかと思われる。すなわち、1件当たりの金額が200万円程度と少ない共同研究を充実させるべく、産業界の戦略的取り組みを促し、大学でも相応の研究費が充当される基盤を創っていくことが必要である(日本知財学会(2010))。また、外国企業との共同研究、成果である特許の外国出願等、国際的な産学連携を進め、自前主義ではないオープン・イノベーションを構築していくことも求められよう。
理工系技術者の人材育成
産学官連携を活用した研究開発の推進と並んで、ものづくり企業にとって重要なのは人材育成である。ここでは、産学官連携の枠組みの中で、大学等において行われている理工系技術者の人材育成に絞って議論を進めることとする。
まず、ものづくりを担う理工系技術者を養成することが、ものづくり企業の中長期的な基盤を支えていくことになるため、最も重要であることは言うまでもないことであろう。理工系技術者を養成する制度として参考になるのは、理工系の学部生、大学院生を産学官が連携して育てていくイギリスの制度である(後藤・ウルガー(2006))。プログラムとしては学部、大学院それぞれに様々なものがあるが、企業と政府がプログラムに採用された学生を資金面で支援し、学生は大学と企業双方の研究指導を受けるのが基本となる。学生にとっては資金、求職活動の両面でメリットがある一方で、産業界としても最先端の技術知識を有し、かつ業界のニーズを理解する研究を行う学生を採用できる。こうした方式は、学生を採用した後にOJT によりコストをかけて訓練していく従来のやり方とは異なる人材育成方法であり、国を挙げてこのような制度を採用してものづくり技術者を養成していくことは、中長期的なものづくり企業の人材育成のあり方に大きなインパクトをもたらすと考えられる。
日本においては、大学等の高等教育機関でこれまで必ずしも産業界のニーズに合った実践的教育がなされてこなかったとの指摘もある。そうした反省も踏まえて、国全体での大掛かりな人材育成プログラムとはいかないまでも、産業界と連携した実践的な工学教育の事例が見られるようになっている。例えば、大学教員と企業の熟練技術者が密接に連携し、バーチャルトレーニングと実習を融合した教育方法により、ものづくり技術者の育成を推進する事例(埼玉大学工学部)等がある(経済産業省他(2013))。
さらに、経済産業省及び文部科学省では、ものづくり企業をはじめとする日本企業がアジア等海外事業展開を加速していることに伴い、日本とアジア等の架け橋となる高度な海外人材を育成することを目指して、2007年以降「アジア人財資金構想」という取り組みを行っている。具体的には、日本企業への就職意識が強く、意欲のある留学生を対象に、実習を組み込んだ大学院教育プログラム、技術経営(MOT)、日本語コミュニケーション能力等を高める教育を各地域の協力大学が提供する。各都道府県及び都道府県内企業は、留学生に対する資金負担(奨学金支給等)、講師派遣、インターンシップ受け入れを行い、各地域の中堅・中小企業への留学生の就職にもつながっている模様である。留学生側のメリットとしては、(1)日本企業に就職するための企業との接点を創出できること、(2)企業で働くための実践的教育を受けられること、(3)奨学金の受給が可能であること等がある。企業としても、将来の採用に向けた優秀な人材との接点の創出というメリットがある。各プロジェクトは4~6年間の事業期間を経て一旦終了した状況にあるが、各コンソーシアム毎に大学、自治体、企業等の協力により自立化した体制を作り、従前通りの取り組みが続けられている模様である。
産学官連携コーディネータの養成
人材育成でもう1つ重要なのは、大学・公的研究機関の研究者のインセンティブ(オープン・サイエンス志向、プライオリティ重視)、民間企業の技術者のインセンティブ(技術の専有化志向、ミッション重視)の両者を理解し、調整していく役割を有する産学官連携コーディネータを育成していくことである。研究者と技術者それぞれのインセンティブ構造の違いを調和、融合させていくことが、産学官連携によるイノベーションを成功させる上でのポイントになると考えられるからである。
文部科学省では2001年度以来、産学官連携支援事業により全国の大学にコーディネータを配置している。2008年以降においては、地域の知の拠点担当、目利き・制度間のつなぎ担当など役割の特化を進める等、コーディネータには従来以上に高度な役割が期待されている状況である。
今後、大学でより高度な人材育成を狙ったコーディネータ養成プログラムを充実させるとともに、絶対数としても増やしていく必要があろう。産学官連携コーディネータとして一定の基準を満たしたものに国として資格を与え、ある種の名誉職として登録し、随時派遣するという制度も考えられよう。コーディネータという人材については、関連分野で必要性が声高に叫ばれている割には、巷間での認知度が低いことも問題である。国として、産学官連携コーディネータの必要性を改めて広くPR するとともに、大学における人材育成プログラム作成のためのバックアップ等、一層の支援を行っていく必要があろう。
おわりに
本稿において、ものづくり企業を中心に形成されてきた地域経済を立て直していくために、これまでも産業クラスター政策として推進されてきた産学官連携に再度焦点を当てて考えてきた。ものづくり企業が他社にない優れた技術力を有していることはもちろんであるが、様々な外部環境の変化の下でも揺るがない地位を地域経済の中で築いていくためには、企業の競争力を形成する中長期的な基盤が重要である。そのために、産学官連携を活用したより広範な視野での研究開発の推進、ものづくりを担う理工系技術者の人材育成、さらに大学・公的研究機関の研究者と民間企業の技術者をつなぐ調整役としての産学官連携コーディネータの育成・配置を産学官一丸となって推進していくことが急務である。それにより、研究開発・技術知識のネットワークが外部に広がり、イノベーション・システムがよりオープンな形に変わることにより、地域経済が再生し、輝きを取り戻していけばと願っている。
『統計』2013年10月号「論考」に掲載


