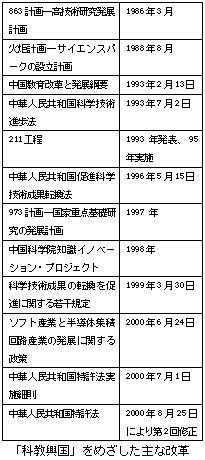 中国はITやバイオといった先端技術分野での研究開発を重点的に押し進めている。これまでの計画経済下における制度の改革を断行し、研究機関の整理や海外から呼び戻した研究者を中心に、研究成果の産業化も視野に入れた研究重点化を図っている。研究予算など限られた資源のなかで、中国の全般的な科学技術が先進国と肩を並べるにはまだ時間はかかるが、ソフトウェアや稲ゲノムなど、海外との知識ネットワークを生かしたいくつかの突出した分野で急速なキャッチアップが行われている。
中国はITやバイオといった先端技術分野での研究開発を重点的に押し進めている。これまでの計画経済下における制度の改革を断行し、研究機関の整理や海外から呼び戻した研究者を中心に、研究成果の産業化も視野に入れた研究重点化を図っている。研究予算など限られた資源のなかで、中国の全般的な科学技術が先進国と肩を並べるにはまだ時間はかかるが、ソフトウェアや稲ゲノムなど、海外との知識ネットワークを生かしたいくつかの突出した分野で急速なキャッチアップが行われている。
そうしたなかで、変化する中国を絶好の機会としてとらえている欧米諸国は、大規模で長期的な研究交流プロジェクトを展開し、存在感を高めている。世界的な「知識経済」の台頭は、研究開発分野のグローバル化を意味する。日本にとっても、生命科学や環境問題など主要な科学技術分野での中国との連携は、2国間の問題だけではなく、アジア地域を越えた世界的な重要性を持っている。このような観点からも、日中間での科学技術交流の重要性を再認識し、日本留学・研究経験者へのフォローアップなど、長期的な視野に基づいた国際的な知識ネットワークの確立を目指した交流が今求められている。
「科学技術是第一生産力」
「科学技術は、第一の生産力である」をスローガンに掲げ、トウ小平が改革・開放を行ってから早くも20年が経った。これまで中国は、低賃金による生産コスト面での比較優位の下に、「世界の工場」として飛躍的な成長を続けてきた。またその一方では、研究開発をベースにした新しい技術分野で、これまでにない企業形態である民営科技企業を積極的に育成してきた。そして、今後も中国が引き続き経済成長を維持していくためには新しい技術の産業化を進めることが不可欠であると認識し、研究開発能力をいち早く向上させるためのさまざまな優遇政策や、制度改革が行われている。
先進国を中心に知識型経済への転換が急がれている一方で、中国も技術革新を牽引力として一気にキャッチアップを狙っている。また、中国と競合関係にあるとされるASEAN諸国のなかでも、シンガポールが、ハイテク産業、とくにバイオ分野の研究開発拠点として生き残りを模索しており、「科教興国」中国のこの分野での台頭、とりわけ中国の研究開発活動の実態と、それを支える制度改革に世界の関心が集まっている。
1970年代終わりまでの中国の科学技術政策は、海外から先進技術を輸入し普及させることを主要な柱として成り立っていた。この間の中心的R&D組織は、(1)基礎研究のための中国科学院、(2)教および研究のための大学、(3)技術的な問題の解決および技術移転のための産業別研究機関であった。
このような研究開発制度の基本的な特徴は、国内自給の達成と、明確な政策的ミッションに基づいた研究(60年代後期の原子爆弾と水素爆弾、70年代の衛星)のための、集権化した完全な国有制度であった。そうした制度は、結果的に、(1)技術革新をもたらす創造や改善努力をするインセンティブは欠如させ、(2)技術の産業化に不可欠な学際的ネットワークの構築を難しくしてしまった。このように、改革開放以前の中国では、科学研究の成果を産業の発展に十分に生かしきれず、多くの成果は実験室に残ったままで、商業化にはなかなか結びついてこなかった。
85年の「科学技術体制の改革に関わる中共中央の決定」は、中国の改革開放政策の流れに沿って、大学や主要な研究機関の研究能力を最大限引き出すための制度改革の出発点になった。その後のさまざまな研究開発制度の改革をまとめると次の3点になる。
(1)国家自然科学研究基金の設立(86年)による競争的研究資金の導入、(2)研究開発機関に対する全般的な規制緩和や、大学内に技術移転組織を設立する一方で、技術市場の整備を進め、機関間の共同研究や技術移転を活発化させる、(3)大学や公的研究機関に所属する研究所に対して、兼業をはじめ柔軟な人事制度を導入することにより、国内外を問わず有能な人材を積極的に投入する。
なかでも、国立研究所の改革は著しい。99年5月、国務院は国家経済貿易委員会が管理する10の部局に所属している242の研究機関に対して、特定の企業集団に譲渡するなどの体制改革を行った。具体的には、131機関が企業集団に、40機関が個別の科技企業に、18機関が仲介的な組織にそれぞれ移転され、また24機関が大学へ、29機関が大型国有科技企業に譲渡された。さらに、98年にスタートした中国科学院の「中国科学院知識イノベーション・プロジェクト」が現在注目されている。
中国科学院は、49年に設立された100以上の研究所と5万人にも上る研究者を抱える、中国を代表する科学研究機関である。今後、2010年まで3段階に分けて、科学技術研究の効率性を上げるために、それぞれの研究所の目的などを明確にさせたうえで、組織改革を断行している。研究開発支出がさまざまな施策で近年増額されていくなかで、研究機関間での競争を促し、研究者の若返りを積極的に進め、国際的な水準へ向けての努力を続けている。
中国版産学「合作」と創業支援
中国の技術革新を巡る制度改革は、研究機関や大学による「民営科技企業」や「校弁企業」の設立によって、「産」不在の技術市場への参入をもたらした。
民営科技企業は、次第に研究機関や大学の新たな市場への足がかりとなり、伝統的な国有企業分野では見られなかった技術的企業家精神という文化を生み出し、中国のハイテク開発における重要な資産となってきた。ファウンダー、レジェンドのような中国のリーダー的なハイテク企業は、すでに国内外に広く知られている代表的な企業である。
民営科技企業は、それまでの企業に比べ、市場ニーズを的確につかんだイノベーションを追求し、それを支えるために独立した意思決定を行い、市場に根付いた経営と徹底した能力主義で人事管理をするという特色をもっているが、一方で、現在、金融制度の未整備からくる資金不足と企業経営に関する知識と経験の欠如という問題に直面している。
民営科技企業の創出と発展のために、政府は88年に火炬プログラムをスタートし、ハイテク産業の開発に有利な環境整備を目指した。最近の科学技術部の発表では、53の国家級ハイテクパークは、過去10年間成長を続け、2000年末までのハイテクパーク内の企業数は2万社以上で、従業員は251万人に上る。また、技術分野での総売上は9209億元(過去10年間で105倍)、税引き前利益で1057億元(同88.8倍)、そして輸出高185億8000万ドル(同103.2倍)とされている。
このように火炬計画のもとに建設された国家級ハイテクパークは、中国全土に広がっており、チベット、青海、寧夏の3自治区以外すべての省、自治区、直轄市で管理運営されている。
また、具体的な創業者支援としては、各ハイテクパークと並んで設置されているインキュベータがある。2001年末までに中国全土で設立された各種インキュベータは465ヵ所に上り、総面積768万平方メートルに達しているというデータがある。さらに、こうしたインキュベータと平行して各種仲介サービス機関も全体で788社までに増加している。その結果、設立された企業は1万5449社で従業員29万2000人(うち、海外帰国者は4100人)、インキュベータから既に卒業した企業は3887社、そのうち32社が上場までに至ったとされる。
中国では、政府が積極的に産学「合作」を作り出す環境を実現するために、大学法人化などの大学改革も行ってきた。結果として、北京大学や清華大学などが直接ベンチャー企業(校弁企業)を設立するような例が急速に増えてきた。現在、こうした校弁企業は、中国の民営科技企業の代表的企業に成長している。
またこのように、研究型大学が自ら企業を設立し、直接子会社として経営するのは世界的に見てもまれであり、まさに中国版産学合作といえる。これまで、民間による研究開発が弱かったことから、先進国に見られるTLOなど間接的な学から産への技術移転は現実的ではなく、大学自らがベンチャー企業を設立するという直接的な技術移転が奨励された。
現在、中国全土における校弁企業の数は5000社を超え、全体で480億元を上回る収入を得ているが、そのほとんどが北京に集中しており、また校弁企業による総収入も北京大学と清華大学の経営する企業集団が3割以上を占めている。
中国のハイテク産業の発展は、北京、上海など沿海部の大都市を舞台に、産学合作のダイナミズムにより支えられてきたといっても過言ではない。なかでも、北京市北西部に広がる中関村(ちゅうかんそん)は、「中国のシリコンバレー」としてここ数年その名を広めている。この地域には、中国を代表する清華大学や北京大学をはじめ、中国科学院など30以上の大学と200を超える研究機関が集まっており、また、大学や研究機関からスピンオフした企業も数多く存在している。
一方で、大学が直接企業を設立し経営するという校弁企業をめぐる課題も山積している。なかでも、大学が教育と研究という、従来の社会的役割と企業経営責任とを同時に果たし得る、バランスの取れた管理体制の構築が求められている。近年、清華大学など一部の大学では、配下の校弁企業をホールディングカンパニーに管理させ、今後は直接企業に資金提供するのではなく、大学インキュベーションなど間接的に技術面・人材面で支えるという方向に向かっている。こうした動きは、政府が清華大学などの取り組みを校弁企業改革のモデルケースに認定するといった後押しもあり、ほかの大学にも今後広がっていくことが期待される。
このように、校弁企業の台頭にみられるようなこれまでの機能別に独立したR&D機関が、横断的なネットワーク化で結ばれるような改革を推進しているのが、現在の中国である。
先進国とつながる中国の頭脳
近年、研究開発は、ますますグローバル化している。その背景には、アメリカ、ヨーロッパ、そして日本の多国籍企業による柔軟な市場対応を目指した研究開発の現地化や、海外での研究開発拠点をつなぐR&Dネットワーク化がある。こうした最近の流れの中で、研究開発拠点として中国がクローズアップされている。
最近の外資による中国でのR&Dは、優秀な研究開発人材が豊富であり、かつ相対的なコストが低いこと、中国市場のニーズに迅速に対応できること、それに付加価値の高い技術開発部門の現地化により、中国に対する企業イメージが高まることといった理由で、拡大している傾向にある。
また、政府は「科教興国」実現のために、マイクロソフトやインテルのような世界の代表的ハイテク企業のR&D拠点を中国に誘致することで、海外からの優秀で経験豊富なR&D人材と、現地の将来性豊かな若手のR&D人材育成を促進することのメリットを十分認識している。そのうえ、外資系R&Dセンターの設立は、中国のイノベーション・システムの中心的役割の1つとして期待されている民間企業のR&D強化につながると受け止められている。特に、今年発表されたマイクロソフト研究所による中国政府へのソフト開発人材育成支援は、外資系R&Dセンターが中国の研究開発能力を高める影響を示した典型的な事例だといえる。
欧米は、中国における次世代の科学技術者を発掘し、養成するといった長期的な視点も持っている。中国にある欧米の外資系研究機関では、中国国内の大学と連携するための専属のスタッフを置いているところも少なくない。また、公的機関としては、ドイツのマックスプランク研究所などは非常に積極的に対中研究交流を展開している。最近、マックスプランク研究所やフォルックスワーゲン財団が中国科学院に設立した上海高等研究所は、新たな中独間の研究交流の場所として注目されている。
求められる「頭脳循環型」知識ネットワーク
中国の技術革新の能力は、過去20年間、実に目覚ましい変化を遂げてきている。しかし同時に、中国の科学技術は20世紀の長年にわたって、計画経済の下で「鉄の試験管」のなかに閉じ込められてきたのも事実である。中国もやっと、世界的に目まぐるしい勢いで進む科学技術の変化に対応し始めたばかりである。したがって、世界の先端科学技術のフロンティアに追いつこうとする中国の挑戦は、これからも続くことになる。
そうしたなかで、中国が新たな技術革新の波に着実に乗れるかどうか、今後も引き続き見守らなければならない。今日、中国は科学技術を巡る根本的な制度設計という大きな課題を背負いながらも改革を着実に進めているが、「知識経済」を支える全体的な科学技術レベルが先進国と肩を並べるまでには、まだ時間が必要であろう。
そこで中国は、特に海外にいる中国人研究者や留学生を呼び戻すことで、科学技術の相対的な遅れを一気に取り戻そうとしている。研究費や帰国にかかる経費など資金面や居住環境で、さまざまな優遇政策を打ち出している。昨年の海外留学生の帰国者は、中国全体で7000人を超え、たとえば、北京中関村地区でもこうした留学帰国者が1000人に達し、そのうち350人がベンチャーを立ち上げているという。
こうした、「頭脳流出」から「頭脳循環」への転換に向けた努力を続けることにより、技術革新を支える研究者・技術者の柔軟な国際的ネットワークを構築し始めている。このような帰国組によってゲノム研究やコンピューターサイエンスなど、一部の分野で突出しているところもあるものの、現時点での科学技術は、先進国に比べてまだまだキャッチアップが遅れていることころも多い。
しかし、現在の中国の科学技術を先進国と比較してもあまり意味がない。過去20年間にわたる中国の変化は非常に目覚しいものであり、この変化を科学技術の分野で中国と連携する機会としてとらえることが、むしろ重要ではないだろうか。ほかの欧米の先進国は、こうした変化をチャンスととらえ、着実に、中国の科学技術の進歩と歩調をともにしている。
R&Dのグローバル化が進展するなかで、科学技術分野でのソフト面でのネットワーク化が「知識経済」の重要なカギとなっている。特に、欧米との研究機関間で組織的な研究交流が続いていることは、中国と欧米の間に構築された知識ネットワークの層をますます厚くしている。
日中間でも、これまで以上に、短期的利益のみをベースにした単発的な技術交流ではなく、21世紀型の知識ネットワークを構築するような、長期的視野に立った交流が求められている。日本も、まずは日本での留学や研究経験を持ち、現在、中国の科学技術を担っている優秀な研究者へのプロジェクト支援を行い、こういったフォローアップをもとにした知識ネットワーク構築支援策から始めることが第一歩になると考える。
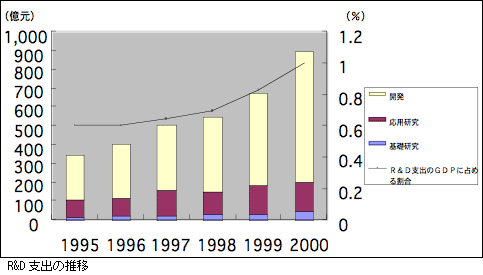
2003年1月号 『国際開発ジャーナル』創刊35周年記念特集に掲載


