ローレンス・サマーズ元米財務長官(米ハーバード大学教授)が昨年11月の国際通貨基金IMF)の会議で論じて以来、米国経済の「長期停滞(secular stagnation)」が米国の経済学者や実務家を中心に話題となっている。
同氏は2008年の金融危機以降、米国経済の回復が遅い理由として均衡実質金利(完全雇用の状態に見合う実質金利の水準)が長期的にマイナスになっているとの仮説を提起し、一因に労働力人口と生産性の伸び鈍化による投資需要の減少を挙げた。
米国の長期停滞論は1938年にさかのぼる。当時のハーバード大教授、アルビン・ハンセンが大恐慌からの回復が弱く失業が解消しない状況を長期停滞と捉え、基本的な原因を人口成長率の低下による投資需要の減少に求めた。長期停滞の捉え方、投資需要の減少や人口学的要因を重視する点で、サマーズ氏の議論はハンセンの古典的な長期停滞論を継承している。
批判的な意見もある。米スタンフォード大学のジョン・テイラー教授は回復の遅れは00年代以降の経済政策の失敗が原因と論じる。05年以前の過度の金融緩和と厳格さを欠いた金融規制がバブルとその崩壊をもたらし、その後の煩雑な規制、政府債務の累積、恣意的な金融政策が回復を遅らせているとの主張である。
◆◆◆
一連の議論は長期の歴史的視点からみた場合、どのように評価できるだろうか。図の上段は、長期停滞論で投資や実質金利の動向が重視されていることを踏まえ、米国の投資率(国内総生産=GDP=に占める総固定資本形成の割合)と、実質金利(長期国債の利回りマイナスGDPデフレーターの上昇率)を19世紀から直近まで示した。
全期間を通じて連続したデータは利用できないため「アメリカ歴史統計」や米大統領経済諮問委員会(CEA)の報告書など、複数の資料から得たデータを接続している。
まずサマーズ氏が注目する近年の動きをみると、08年の金融危機後に低下した投資率は、10年を底に回復しつつあるとはいえ、危機以前よりも低い水準にとどまっている。一方で、実質金利は金融危機以前より格段に低い1%未満まで下がっている。
実質金利が低下するなかで投資率が低下していることは、設備投資がどれだけの収益を生むかについての見通しである投資の期待収益率の低下を含意している。サマーズ氏の長期停滞論は、この現象に基礎を置いている。
時間的な視野を広げてハンセンが長期停滞論を提起した30年代後半についてみると、実質金利は0%前後、投資率は10%前後であった。これと比較すると、今日の経済状況は相対的に良好といえる。
さらに50~70年代のデータは近年の状態が米国経済の歴史において必ずしも特異ではないことを示している。50~70年代も実質金利が0~1%台に低下することはまれではなく、しかもそうした時期の投資率は今日とほぼ同じ15~17%であった。これらの観察から今日の米国経済を長期停滞と特徴づけることは、少なくとも早計であるといえる。
◆◆◆
日本の状況はどうだろうか。図の下段は、米国に対応する投資率と実質金利の長期データを日本について示した。日本のそれらの動きは、米国と大きく相違している。
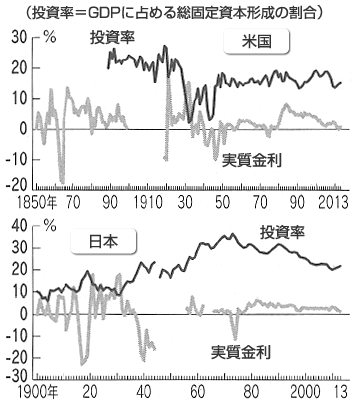
まず明らかなのは、30年代から70年代前半にわたる長期の投資率の上昇局面と、70年代後半から今日までの長期の下降局面の存在である。
前者の上昇局面は高橋是清蔵相による高橋財政や、戦時下の生産力拡充政策、戦後の経済復興、そして高度経済成長という日本経済史上の大きなエピソードを含んでいる。注目すべき点は、この局面では実質金利がほぼ一貫して低い水準にとどまっていたことである。戦時期の実質金利は大幅なマイナスとなっていたし、戦後の高度成長期も1~3%の年が多かった。
この動きには各時期の経済政策が強く反映されている。30年代前半には金解禁や緊縮財政で生じたデフレ圧力の解消を目指した高橋財政のもとで、低金利と緩やかなインフレが追求された。戦時期には民間金融機関の資金配分に対する政府の直接介入や、軍事費を調達するための多額の日銀引き受けによる国債発行から、インフレが加速した。
さらに戦後は、復興期のハイパーインフレの終息後から高度成長期にかけて預金金利を中心に政府が金利を規制する、いわゆる人為的低金利政策が実施された。すなわち、総じて30年代以降の投資率の上昇局面では手段の相違はあれ、政府介入によって実質金利が抑制され、政策的に投資が刺激された。
一方、70年代半ばに起きた投資率の低下局面への移行は実質金利の上昇と軌を一にしている。この実質金利の上昇は、75年以降の国債大量発行に伴う国債流通市場の形成と金利自由化を反映している。言い換えれば、投資率の低下局面への移行は、30年代以来、形を変えて続いてきた政策的な低金利レジームの終了によって引き起こされた。
ただし、投資率の低下傾向が継続するなかで、80年代以降、実質金利は緩やかな低下傾向に転じたことにも注意する必要がある。
金融政策に関する論議の文脈では、デフレによって日本の実質金利が高止まりして「失われた20年」の原因となったと論じられることがある。しかし実際には、実質金利は80年代後半の平均4.1%から、2000年代後半には2.7%まで低下している。すなわち日本では80年代以降、30年以上にわたって実質金利の低下傾向と投資率の低下傾向が併存してきた。
これは、日本で投資の期待収益率が長期的に低下傾向をたどってきたことを含意している。長期停滞という見方は米国経済よりむしろ日本経済に妥当するといえよう。
◆◆◆
長期停滞への対策として、インフレ率の引き上げなどによってすでに低い水準になっている実質金利をさらに引き下げることは、サマーズ氏が米国について指摘しているように、バブルを引き起こすリスクがある。さらに極端に低い実質金利によって投資を促進することは、経済の効率性を損なうおそれがある。
これを避けるとすると、日本が「長期停滞」から抜け出す方途として、2つが考えられる。第1に、投資の期待収益率を引き上げることであり、先月発表された政府の成長戦略は、この方向に沿った施策と見ることができる。
第2に、これと必ずしも矛盾しない方途として消費の経済成長への寄与拡大がある。投資不足は換言すれば貯蓄過剰であり、サマーズ氏は長期停滞の原因として投資不足のほか所得分配の不平等化による消費の減退も挙げている。
日本でも80年代以降、所得分配の不平等度が上昇しているが、他面で人口構成の高齢化という長期的かつ大きな動きがある。人々のライフサイクルにおける所得と消費の関係の推移を反映して、高齢化はマクロの貯蓄率を低下させる。そしてこの動きはすでに顕在化している。こうしたなかで投資を過度に促進することは、経常収支の赤字を拡大することになる。
増大する高齢世代の需要に対応した消費財やサービスの開発、それらを供給する産業への資源配分のシフトなど、高齢化社会に適合した消費をエンジンとして組み込んだ経済構造への移行も、日本経済の進むべき方向であろう。
2014年7月16日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


