急速な少子高齢化で社会保障費が急増する一方で、税収が歳出の半分を下回る異常事態に陥り、日本財政は危機的状態にある。その結果、政府債務の国内総生産(GDP)比率は、第2次世界大戦の敗戦直後に急激なインフレを招いた戦前のピークに近づきつつある(図参照)。
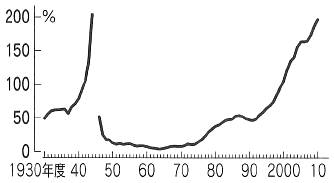
政府債務をストックでみる場合「海外投資家の国債保有割合は7%程度であり、9割以上は国内で消化されているので問題はない」との楽観論も多い。しかしフローでみる場合、最近では短期債を含む政府債務増加分の3~5割は海外投資家が吸収しており、国債市場における海外投資家の存在感は高まっている。
◆◆◆
先の通常国会では、消費増税を含む社会保障・税一体改革関連法案が成立し、消費税率が2014年4月に8%、15年10月に10%に引き上げられることが決まった。しかし5%の増税は「止血剤」にすぎず、本質的に日本財政が危機を脱出したわけではない。
今回の5%増税で調達できる財源は約12兆円(消費税率1%分を約2.5兆円で換算)だ。これに対し、毎年1兆円超のスピードで膨張する社会保障費を抑制しないと、今後10年間で社会保障費は約10兆円以上増える。さらに債務残高の急拡大により、現在約9兆円の利払い費は、金利水準が変わらなくても今後10年間で約8兆円増の約17兆円に膨らむ見込みだ。この結果、今回の増収分を考慮しても、財政赤字は現在の約44兆円から今後10年間で50兆円以上に拡大する計算となる。
内閣府は8月下旬の「経済財政の中長期試算」で、今回の5%増税を実施しても、20年度の国と地方の基礎的財政収支(GDP比)は約3%の赤字になるとの試算を公表した。先般、主要7力国(G7)会合で国際公約した「基礎的財政収支の黒字化」の達成には、さらに6%の消費増税が必要ということになる。
しかしこうした中途半端な試算は、国民が急増する社会保障コストに対する正しい認識を持つのを妨げ、「危機の先送り」を招く可能性が高い。社会保障費を抑制しない場合、内外の研究が示すように、財政安定に必要となる最終的な消費税率は30%超に達するとの試算も多いからだ。
この観点では米アトランタ連銀のR・アントン・ブラウン氏らの研究が重要だ。社会保障費が急増する中で、財政安定のため17年に一気に消費増税をする場合、最終税率は33%になると推計する。さらに増税を5年遅らせて22年とする場合、最終税率は37.5%に上昇すると推計する。その差は約5%だから、1年の改革先送りで財政安定に必要な税率は1%上昇することになる。これは「改革の先送りコスト」で、引き上げ時期を遅らせるほど最終税率は上昇し、若い世代や将来世代の負担を高めることを意味する。
なお、米カリフォルニア大学ロサンゼルス校のゲイリー・ハンセン教授らは最終税率について35%と推計。一橋大学の小林慶一郎教授と筆者の共著では、50年ごろの消費税率は約31%と推計(機械試算)する。これらの研究の共通コンセンサス(合意)は、社会保障費を抑制しない場合、消費税率は20%でも不十分であり、それ以上の税率に引き上げないと財政は持続可能でないことを示唆している。
ところが今回の改革では、政治的制約が存在するとはいえ、「5%増税」の議論が先行してしまった。そもそも、最終的に何%までの増税を目指すのかについての議論は皆無で、国家が目指すゴールが全く見えてこなかった。これは「木を見て森を見ず」の姿勢、すなわち日本という船が向かうべき港を検討せずに航海に出るようなものだ。5%増税でも相当な政治的パワーを要することから、20%以上への増税を政治的に議論するのは不可能との意見もあろうが、それはブラウン氏らの研究が明らかにする「改革の先送りコスト」を高めるだけだ。
◆◆◆
この関係で、政治が国民に提示すべき主な選択肢は「高福祉・高負担」「低福祉・低負担」「中福祉・中負担」の3つだ。しかし社会保障改革が現実味を帯びないのは、政治がこの全体の枠組み(給付と負担)の選択を常に避ける傾向が強く、メディアなどの関心がすぐに「細部」の議論に向かってしまうからだ。
戦略ミスは戦術では挽回できない。細部に関する議論が精緻でも全体の枠組みに関する議論が不十分で、現在のように社会保障の給付水準が負担を上回る状況のままでは、最終的に改革が破綻するのは避けられないであろう。
むしろ改革議論で重要なのは「議論の順番」である。すなわち、年金の制度設計などの細部の議論よりも、「給付水準と同レベルの負担」を前提に、まずは給付水準と負担をセットで全体の枠組みを議論する必要がある。若干粗い議論であっても、最初に全体の枠組み、続いて細部という順番で議論を進め、社会保障の給付水準(=負担)をどのレベルに設定するのかを最初に決定するのが望ましい。
全体の枠組み議論の出発点となるのは、社会保障費を抑制しない「高福祉・高負担」のケースである。政府・与党は近々設置される「社会保障制度改革国民会議」の場で、財政安定に必要となる最終的な負担の姿について、最終税率が約30%になる可能性も含め、公式に試算して国民に明らかにする義務がある。
そのうえで、今回の5%以上の増税を望まない「低福祉・低負担」のケースを選択肢として検討するのであれば、財政安定に必要となる最終的な歳出削減の幅の試算についても公表する必要がある。若干粗い試算では最終的に、消費税率約20%分に相当する50兆円程度の歳出削減をする必要があると考えられる。毎年1兆円超のスピードで膨張する社会保障費との関係から、大部分は社会保障費の削減で達成しなければならない。
現在、年金・医療・介護などの社会保障給付(100兆円)については、うち約60兆円を保険料収入で賄い、不足分の約40兆円を公費で賄っている。この公費の相当割合を削減するといった極めて厳しい給付削減となるであろう。
このため「高福祉・高負担」「低福祉・低負担」のどちらも望ましくないと判断されれば、残る選択肢は中間の「中福祉・中負担」しかない。
その場合でも消費税率は20%超となる可能性が高い。欧州の付加価値税の平均は20%で、スウェーデンは25%、英国、フランス、ドイツは約20%だ。仮に、本来最終税率は30%とすべきなのに、実現可能な消費税率の上限を25%とすると、今回の増税に加え、15年以降も消費税換算で15%分の追加増税を実施するとともに、消費税率5%分に相当する約12兆円の歳出削減を同時に進める必要がある。
年金支給開始年齢については、欧米の計画(イタリアの69歳、英国の68歳、米国・ドイツの67歳)をみても、引き上げを検討すべきであろう。年金課税の強化、医療・介護保険の自己負担引き上げなど抜本的な社会保障改革を推進し、今後20年の自然増(20兆円超)を約半分に抑制することも検討せざるを得ない。
◆◆◆
いずれにせよ、現状は「給付水準>負担」であり、本当の政治主導とは全体の枠組みを議論し、その選択をすることにある。細部の議論も重要だが、それは最初の議論ではない。全体の枠組みの選択とその強い実行こそが、部分最適かつ縦割りの省庁では担うことができない最も重要な政治の役割であり、日本政治に最も求められている決断だ。
なお、選択には「将来世代の負担の限界も直視し、できるだけ世代内で困った人を困っていない人が助ける」といった「改革の哲学」が重要であることはいうまでもない。今こそ、政治は「何が受け入れられやすいかではなく、何が正しいかを考えなければならない」(ドラッカー著「経営者の条件」)といえる。
2012年10月18日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


