我が国は2002年から2007年にかけて、外需主導で景気回復を実現してきた。しかし、2008年9月に世界経済危機が発生した後、我が国の景気回復を支えてきた外需は「蒸発」と形容されるように劇的に減少した。「蒸発」した外需を取り戻すか、あるいは「内需」で埋める目処が立たない限り、我が国経済が再び成長の道を進むことはできない。
本稿では、我が国経済の回復の観点から、外需・内需双方の動向を見通した上で、今後取り組むべき対外経済政策上の課題について考察する。
Ⅰ 外需主導の景気回復の終焉
考察の準備として21世紀以降の我が国経済の動向を振り返る。
既に忘れ去られているかもしれないが、我が国経済は2002年1月から2007年10月にかけて戦後最長の景気回復を経験した。この景気回復の特徴を一言で言えば、「外需主導」である。経済産業省(2009a)では、実質GDPの需要項目の動向について、今回と80年代後半以降の景気回復期の比較を行っている(図1)。これを見ると、2002年以降の景気回復期には、輸出が最も速いペースで増加していることが分かる。この時期、我が国の輸出は、低金利による円安を背景に、2004年から毎年過去最高値を更新し、輸出依存度も2007年には17.1%と過去最高を記録した。一方、内需をみると、設備投資も一定の拡大を示したが、これは輸出拡大によってかなり牽引されたものである(*1)。需要項目の中で最大のウエイトを占める民間最終消費は低い伸びに終始した。
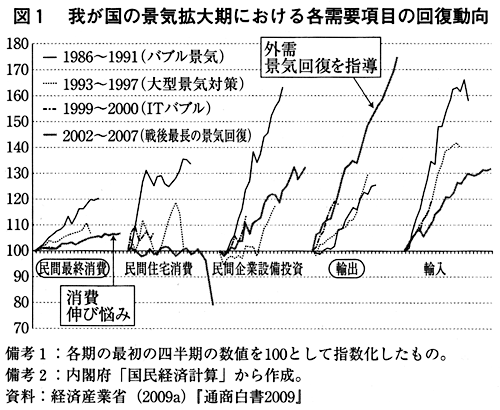
こうした外需主導の景気回復を支えたのが、好況が続いた欧米経済であり、また、欧米向けの輸出等で高成長を実現した中国をはじめとするアジアの新興国経済であった。財務省「貿易統計」により、我が国の輸出が最高値を記録した2007年の我が国の輸出の国・地域別構成を見ると、米国、EU、アジア向け輸出の構成比はそれぞれ20.1%、14.1%、48.1%であり、これらの地域で輸出全体の8割以上を占めている。近年は、特にアジア向けの部品等の中間財輸出が大幅に増加し、アジアに輸出された中間財が最終財に加工されてさらに欧米等に輸出される、いわゆる「三角貿易」が拡大した(図2)(*2) (*3)。
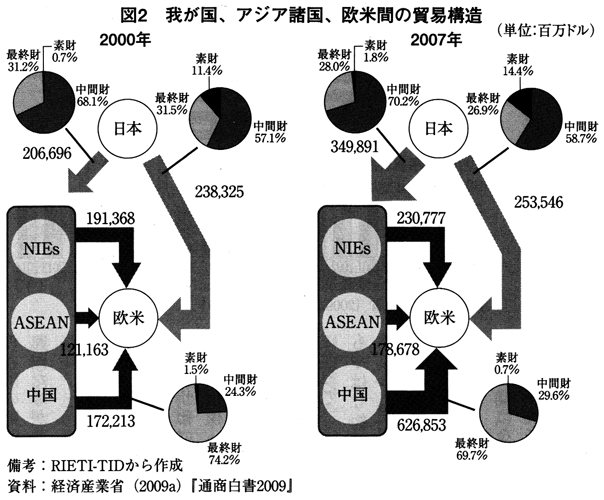
しかし、外需主導の景気回復も、サブプライムローン問題が顕在した2007年夏以降、陰りが生じ始める。2007年9月には、米国向け輸出が減少に転じ、2007年11月から我が国の景気は後退し始めた。その後も欧州やアジア向け輸出は増勢を続けたが増加率は徐々に低下する中で、2008年9月15日を迎えたのである。
世界経済危機が発生した後、全ての地域向けの輸出が急速かつ大幅に減少した。2008年12月には前年同月比で35.0%減少し、その後8カ月連続では減少率が35%を超えている。
外需に依存していた我が国の実質GDP成長率も、2008年第4四半期、2009年第1四半期に、前年比年率でそれぞれマイナス12.8%、12.4%と、1980年以降最も低く、主要先進国の中でも最低の成長率を記録した。
今年上半期の我が国の輸出は、約24.0兆円、前年同期の約41.9兆円から42.7%減少した。減少幅の17.9兆円は、2008年の名目GDP508兆円の3.5%にも相当する。単純に考えれば、これだけの規模の需要が回復されなければ、危機発生前の経済水準に回復することは困難、ということになる。
果たして、このような大規模な需要の回復は可能なのであろうか。
Ⅱ 「蒸発」した外需復活の見込み
最初に「蒸発」してしまった外需が回復する可能性について検討してみよう。
①米国経済
米国は世界最大の経済大国であり、単一国家としては我が国最大の輸出先でもある(*4)。我が国経済の先行きも、米国経済の回復に依存する部分は大きいであろう。
しかし、残念ながら、米国経済の先行きはあまり芳しくない。
まず、米国経済の需要の7割を占める消費回復の目処がついていない。米国の消費の特徴は資産効果の大きさにあるが、現在は住宅価格の大幅な下落で逆資産効果が生じている。雇用動向の悪化も消費を下押ししている。次に、家計の雇用環境の悪化等によりローンの延滞率が上昇しており、不良債権の拡大から金融機関の経営破綻が増加しつつある(*5)。不良債権処理スキームは今年3月に発表されたが、小林(2009)のように、この制度の効果を疑問視する意見も多い。実際、我が国や、我が国と同様1990年代初頭に不動産バブルが崩壊したスウェーデンでも、結局不良債権処理に目処がついたと言われるのは金融機関が所有する不良債権の償却に公的資金が投入された段階である(図3)。米国の不良債権処理はまだ紆余曲折が予想される。
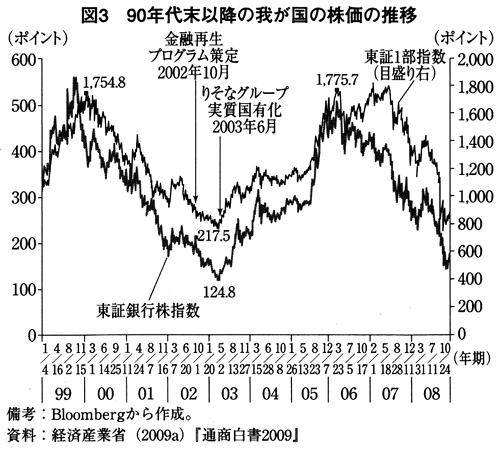
さらに、仮に不良債権処理に目処が付いたとしても、そこから回復するには一定の長い期間が必要である。不良債権の処理に成功したと評価されるスウェーデンのケースでも、不動産価格がバブル前のピークである1991年の水準まで回復するには7年を要した(*6)。これまでの処理対応を見る限り、米国ではより長い時間を覚悟する必要がある。もちろん、米国には世界的に見ても優れた企業が数多く、科学技術面でも世界の最先端である等、経済の基礎的な体力は強く、世界経済におけるプレゼンスは依然大きいものの、過剰ともいえるような消費を通じて世界経済を牽引することは、当面はないと思われる。
②欧州経済
欧州経済の市場規模は、北米(米国、カナダ)に匹敵する。2007年のEU27カ国の名目GDPは16.9兆ドルと、北米の15.2兆ドルを上回る。このうち、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインの5カ国で7割以上を占めており、欧州経済の動向はこれらの国が鍵を握る。
しかし、この5カ国のうち、EU域内で最大の規模を誇るドイツ経済(名目GDPシェア19.6%)は輸出依存度が46.7%(2007年)と高く、我が国と同様輸出が急速に減少し、成長率も昨年第4四半期にマイナス9.4%、今年第1四半期にマイナス13.4%と大幅なマイナスを記録した。また、英国とスペインでは、米国と同様、不動産価格の急落により深刻な影響を受けている。イタリア、フランスも景気後退に直面しており、欧州経済の回復には、やはりまとまった時間を要すると見るべきである。
③新興国経済
先進国と対照的に高い成長を維持したのが、中国、インド等のアジアの新興国である。
中国は、2008年の実質GDP成長率が9.0%と6年ぶりに10%成長を割り込んだが、今年は1~3月期対前年同期比で6.1%、4~6月期に同7.9%と、他の国・地域と比較してきわめて高い成長を維持し、かつ回復傾向を示している。
中国経済も輸出依存度が高いものの、1人当たりの所得水準が低く潜在的な消費需要が旺盛である。このため、消費や設備投資といった内需が世界経済危機発生後も堅実に拡大し、輸出減少の影響を軽減している。
中国の他にも、インドやインドネシア経済は比較的堅調に推移している。インドは昨年10~12月期、今年1~3月期と連続して前年同期比5.8%と比較的高い成長率を実現している。インドネシアも危機発生後今年4~6月期まで、4%台の成長率を維持している。両国とも、人口大国であること、1人当たりの所得水準が低く潜在的な消費需要が旺盛であること、外需への依存度が低いこと等が、危機の影響を軽微なものにしている。
このように、世界経済危機発生後の各国の動向を見ると、当面は、新興国だけが着実に成長する可能性が高い。
ただし、経済規模で見れば、新興国と先進国の間には大きな隔たりが残るのも事実である。今年4月のロンドンサミットに参加した19カ国の経済規模(名目GDPの合計)を先進国(G7+豪州)と新興国に分けて比較すると、2008年では2倍以上の格差があり、IMFの予測に従って2014年時点で比較してもやはり約2倍の格差が残る(図4)。
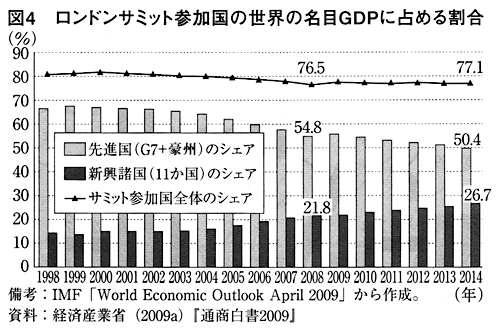
また、1人当たりの所得水準を比較すると、格差はより大きくなる。中国が名目GDPで日本を抜いて世界第2位になるのは時間の問題であるが、1人当たりGDPでは2007年時点で約13倍もの開きがある(*7)。これだけの格差がある国々の市場に先進国企業が参入するのは容易ではない。「蒸発」した我が国の外需を、新興国経済が単純に肩代わりすることは非現実的と考えるべきである。
以上のように考えると、「蒸発」した外需が復活する可能性は、長期的な将来はともかく、当面の間は極めて低いように思われる。
Ⅲ 内需拡大の見込み
そこで、内需によって外需の減少の埋め合わせを期待したいところであるが、戦後最長の景気回復過程でも内需が活発化しなかったことを考えると、内需拡大にも大きな期待はできない。
図1で見たように、直近の景気回復期において、民間消費は停滞していた。
民間消費の停滞は直接には所得水準の低下が大きく影響している。通常、景気回復期には所得水準は向上するが、今回の景気回復期には所得はむしろ低下していた。厚生労働省「賃金構造基本統計調査」によれば、一般労働者(男女計)の月額賃金は2001年の30万5800円から毎年低下し、2007年には30万1100円に落ち込んだ。これは80年代後半のバブル期や、90年代の景気回復期にも見られなかった現象である。
他方、企業の売上高、経常利益は着実に増加していた。財務省「法人企業統計」によれば、金融保険業を除く全業種の法人の売上高、経常利益とも2002年度から2007年度にかけてそれぞれ19.1%、72.5%上昇している。
以上の点を考えると、企業における利益配分方法が従来から大きく変化したと考えられるが、この変化には、経済のグローバル化が少なからず影響している。すなわち、新興国経済の世界経済への統合により世界的に競争が激化しており、我が国の企業・産業は国際競争をより強く意識せざるを得ず、競争力強化のための投資、株主への還元を積極的に行う一方、人件費等は抑制せざるをえず、その結果利益の配分方法を変更せざるを得なくなったと考えられる(*8)。
このように、内需低迷は直接的には所得減少の影響であるが、その背景には、グローバル化の企業・産業に対する影響が指摘できよう。従って、我が国の産業がグローバル化を踏まえた対応を行わない限り、内需回復もまた期待薄である。
Ⅳ 経済成長に向けた対外経済政策上の課題
これまで見てきたように、我が国の外需、内需とも、危機発生の前の水準に回復する兆しは見えてこない。このような状況では、需要の機会を求めて自ら動くことが不可欠である。その際、時代の潮流を見据えることが重要である。世界経済危機発生後、一部の国では保護貿易的な措置が見られるが、経済のグローバル化の流れが止まることはない。むしろ、新興国経済の成長により、グローバル化は今後一層進展する。我が国は、この潮流を踏まえ、経済のグローバル化をより一層活用することを意識すべきである。
この観点から、対外経済政策の分野では、以下のような取組みが重要となる。
(1)新興国市場の開拓支援
「蒸発」した外需の穴埋めには不十分であるものの、当面世界で最も成長力があるのは新興国経済である。特に、近年は新興国において中間層(「ボリューム・ゾーン」)人口が加速度的に増加しており(*9)、その市場に企業が参入することは、経済的に自然な行為である。
我が国の企業が新興国市場に参入しようとする場合、現地企業の買収、現地企業との提携など、現地への進出を伴うことが予想される。市場における需要の特性を把握する上で現地に入り込むことが有益であることに加え、新興国の消費者の所得水準を考慮すると、先進国で生産された輸出品は、新興国で生産された製品と比較して価格競争力で水を開けられるからである。
また、現地への進出も、今後は製造業に限らず様々な分野で盛んになると思われる。新興国では、経済成長に伴い、社会資本やエネルギー不足、環境汚染等の課題が顕在化している。我が国の電力・鉄道・水道等のインフラ関連産業はこうした課題に長年取り組んできた過程で優れた技術を擁する一方、国内では経済の成熟化により需要が飽和しつつあり、国際展開の必要性が高まっている状況にある。
こうした動向を踏まえれば、企業が新興国のボリューム・ゾーンを獲得するために必要な低コスト化、マーケティング等に資するような政策を推進することが一層重要となる。具体的には、新興国との間で経済連携協定、二国間投資協定、租税協定などを締結することによる投資環境の整備、新興国における知的財産権の保護、新興国に進出した我が国企業の活動に資する外国人人材の育成等は、今後より重要となる政策課題である。
(2)海外の成長活力の国内経済への導入・活用
ただし、近年の国際貿易の研究で明らかにされつつあるように、新興国市場に直接進出できる企業は、政策面で支援しても、生産性の高い規模の大きい一部の企業にとどまると予想される(*10)。残りの大半の(比較的生産性の低い)企業・産業は、引き続き国内だけで活動せざるを得ない。
しかし、こうした国内で活動する企業も、新興国の経済成長の恩恵を受けることは可能である。
観光の分野を例に挙げれば、近年は新興国の経済成長が世界の海外旅行者数の増加を牽引している(*11)。2008年の中国の観光旅行者数は4584万人(*12)と、日本の1599万人の約3倍近くに到達している。こうした観光客を日本に呼び込むことで、国内の企業には大きなビジネスチャンスがもたらされる。
また新興国からの企業の誘致についても同様の効果が期待できる。新興国経済の成長とともに、今後新興国から海外に進出しようとする企業も増加する。こうした外国企業を我が国に誘致すれば、生産性の向上等を通じて国内経済を押し上げる効果が期待できる(*13)。
国際観光の振興や対内直接投資の拡大については、既に様々な政策が講じられ、その効果も現れている。ただし、諸外国と比較すれば、一層の効果が見込まれる(*14)。新興国経済の成長という機会を逃さず活かすには、従来から指摘されている懸案事項にも踏み込む用意が必要である(図5)。
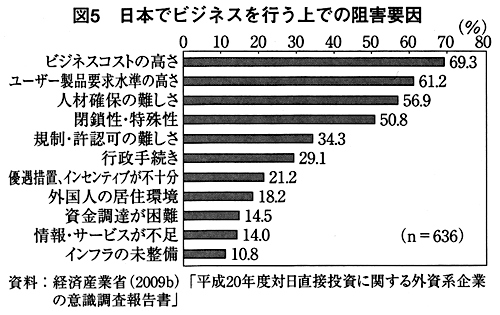
(3)国際競争に対応した産業構造への転換
(この課題は「対外経済政策」からやや外れるが、グローバル化への対応という広い意味で、対外経済政策である)
Ⅲ節で見たように、我が国の企業・産業が国際競争に十分対応できず、内需拡大上の障害になっていることは指摘できそうである。従って、国際競争に対応した産業構造に転換することが急務である。
しかも、企業・産業間の国際競争は、新興国産業のキャッチアップ等により、今後一層激化することが予想される。新興国は、労働集約的な産業だけでなく資本集約的な産業でも徐々に競争力をつけつつある。日中貿易を例に挙げれば、中国の主要輸出品は最初のうちは繊維等の軽工業品であったが、徐々に一般機械、電気機械にシフトしつつある。
激化する国際競争に対して、我が国の企業としては、研究開発等を通じて生産性を向上し、キャッチアップされないようにすることができれば理想的である(*15)。しかし、現実にキャッチアップが進展している以上、労働集約的で新興国に浸食されつつある産業から、より資本集約的な産業、あるいは高い成長が期待できる産業への転換も真剣に検討する時期が到来したと考えるべきである。
我が国のような成熟市場にはそれなりに高い成長性が見込まれる産業が存在する。米国では医療・福祉分野の雇用が急速に拡大しており、今後の雇用創出効果も期待されている(*16)。米国以上のペースで高齢化が進展しつつある我が国でも急速な成長が期待できる分野である。また、気候変動問題への対応が迫られる環境関連分野も高い成長性が見込まれる。
本来、成長性の低い産業から高い産業への転換は企業が自発的に取り組むべき課題であるが、我が国で今後成長が期待される上記のような産業は、政府が制度設計に深く関与している。この場合、政府の制度設計が企業の業種転換行動に大きな影響を与える。
政府に求められるのは、制度設計を通じて、こうした産業が発展する将来像を明示することである。なお、ここでいう「産業の発展」においては、当該産業で働く労働者の所得が上昇することが不可欠である(そうでなければ内需拡大、日本経済の成長につながらないからである)。
さらに、こうした将来像を海外に発信することができれば、少なからぬ人が「日本経済が大きく変化し、大きく成長する」と考え、人の移動や対内直接投資の拡大にも貢献する。
Ⅴ まとめ~ピンチをチャンスに
以上の取組みはいずれも実現には相当の困難を伴うものである。しかし、危機的な状況は、従来の取組み・仕組みを根本的に見直し、改める絶好の機会でもある。事実、ピンチをチャンスに転じることに成功した例は歴史を振り返れば枚挙に暇がない。戦後の日本経済を見ても、敗戦後の復興、2度の石油ショックへの対応等、危機的と思われる事態に直面したが、業や政府が従来の方針を大幅に変更することで、克服してきた。反対に、90年代初頭から、我が国経済は「失われた10年」と呼ばれる長期的な停滞を経験することとなったが、停滞が緩慢に進行したため、1990年代末に危機的な状況に陥るまで本格的な対応がなされなかった。その後は危機への対応に振り回され、我が国経済全体が力強い成長を実現するには至っていない。
今回の世界経済危機によって我が国は大きな需要を喪失したが、これを機に我が国経済のあり方を根本的に問い直すことができれば、停滞から決別するまたとないチャンスになるかもしれない。否、是非チャンスにすべきである。
『世界経済評論』11・12月号(社団法人世界経済研究協会)に掲載


