中国は、大幅な対外収支黒字に直面しながら、人民元レートの対ドル安定を維持するために、年率2000億ドルに上る大規模なドル買い介入を行い続けている。これを反映して、2006年6月の外貨準備が9411億ドルに達し、年内には1兆ドルを超えることが確実になっている。介入に伴う過剰流動性が投資の過熱と資産バブルの膨張を助長しており、金融政策の舵取りが難しくなっている。
人民元の切り上げを抑えるためのドル買い介入は、中央銀行がベースマネー(注1)を放出してドルと交換することに他ならない。年間2000億ドルに上る介入は、直接1.6兆元(1ドル=8元に基づいて換算)に上るベースマネーの増加(伸び率にして約30%)をもたらしている。「信用乗数」(注2)が一定であれば、広義の貨幣供給(M2)も、それに比例して増えることになる。
過剰流動性の発生を防ぎ、介入に伴う貨幣供給の上昇を相殺するためには、当局は、「不胎化」政策を採らなければならない。最も広く使われる方法(狭い意味での不胎化)は、中銀が、公開市場操作(所有する国債、または自ら発行する中銀手形の売却)を通じて、積極的にベースマネーを回収することである(注3)。なお、介入と不胎化(公開市場操作)を同時に進めることは「不胎化介入」、不胎化(公開市場操作)を伴わない介入は「非不胎化介入」と言う。
介入、不胎化、そして不胎化介入の三者の関係は、中央銀行のバランスシートの変化に沿って確認できる(表1)。「介入」によってドル資産(外貨準備)とベースマネーという債務が増えるが、「不胎化」(公開市場操作)によりベースマネーが減る代わりに中銀手形が増える(注4)。一方、介入と公開市場操作を組み合わせた「不胎化介入」により、ドル資産とともに中銀手形という債務が増える。このように、(非不胎化)介入と不胎化介入の違いは、ドル資産を吸い上げるために、前者は流動性の高いベースマネーを放出し、後者は流動性の低い中銀手形を発行するのである。
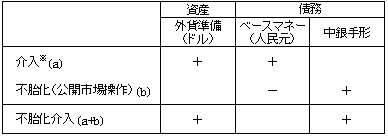
現段階では、不胎化が成功しているかどうかについては、判断の基準によって評価が分かれている。前年比で見て、直近のベースマネーの上昇率は10.0%(6月)、CPIも1.0%(7月)という比較的低水準にとどまっており、不胎化がうまくいっているように見える。しかし一方で、現金預金比率と(超過)預金準備比率の低下で「信用乗数」が高まったことを反映して、M2の伸びが2004年の14.6%から、2006年7月には18.4%へと加速している。これを受けて、投資の過熱が一向に収まらず、不動産価格と株価がバブルの様相を呈しているという意味で、不胎化は成功しているとは言いがたい。
その上、介入の規模があまりにも大きく、しかも中長期的に持続されているだけに、それに対応するための不胎化がますます困難になってきている。
まず、2003年4月から、中央銀行は、公開市場操作を実施する際、保有する国債の玉不足を補うために、自ら中銀手形を発行するようになり、その発行量が膨らんでいる。2006年6月現在の残高は前年同期と比べて、1.20兆元増え、2.86兆元(ベースマネーの45.4%相当)に達している(図1)。
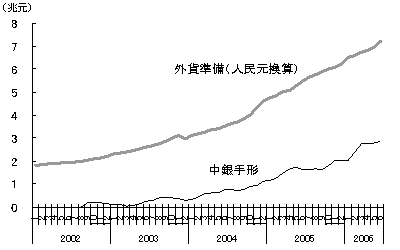
また、当初、発行された中銀手形の満期期限は3ヵ月が中心であったが、だんだん長期化しており、現在、1年物が中心になっている。長期金利が短期金利を上回っているため中央銀行にとって、資金調達のコストがその分だけ高まっている。
さらに、中銀手形の発行利回りも高まりつつある。2006年8月15日現在、1年物の中銀手形の発行利回りは2.7961%に達し、年初と比べて0.9%ポイントほど高くなっている。金利の上昇は、更なる資本流入、ひいては介入と不胎化の規模の拡大という悪循環を招きかねない。
最後に、中央銀行は、今年の5月以来数回にわたり、入札と併用で割り当てによる中銀手形の発行を実施している。この手形割り当ては、利回りを市場実勢以下の水準に抑え、強制的に銀行に割り当てるものである。例えば、6月14日に実勢より0.4%ポイントほど低い2.1138%という利回りで1000億元の1年物の割当発行を実施したが、その内、建設銀行が420億元、農業銀行が300億元,工商銀行が120億元,交通銀行が100億元、その他が60億元を引き受けることになっている。貸出の伸びが高い銀行ほど、割当のターゲットとされるが、低金利で中銀手形を引き受けさせることは、これらの銀行に対する一種のペナルティとなる。
巨大な対外収支黒字を前に、金融政策の運営に当たり、中国は、(1)不胎化介入、(2)非不胎化介入、(3)人民元の切り上げという三つの選択肢に直面している(図2)。為替政策の変更がなければ、外貨準備が今後も年率2000億ドルを超えるペースで増えると予想され、不胎化介入がますます難しくなろう。不胎化政策が限界に近づいている中、中国は、介入の規模を抑えて人民元の切り上げを加速させるか、さもなければ、介入をしながら不胎化をあきらめ、過剰流動性とそれに伴う物価と資産価格の上昇を容認するか(非不胎化介入)、という選択を迫られている。
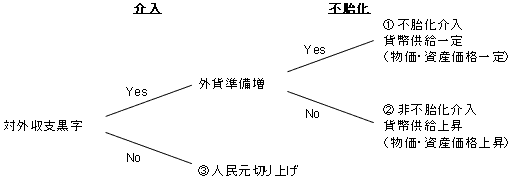
2006年8月23日掲載


