中国では、従来の不動産価格の上昇に加え、この一年間ほど株価も高騰しており、バブル経済の様相を呈している。その最大の原因は、高まる元高圧力に対して当局が外為市場に大規模な介入を続けており、それに伴って過剰流動性が発生していることにある。このような状況は、1980年代後半の日本にますます似てきている(表)。残念ながら、中国当局は、日本が経験した切り上げによるデフレ圧力(マッキノン説)を心配するあまり、円高を阻止するための金融緩和策が逆にバブルの膨張につながった事実(黒田説)を見逃してしまった。その結果、せっかく参考となるはずの日本の教訓が十分に活かされていない。
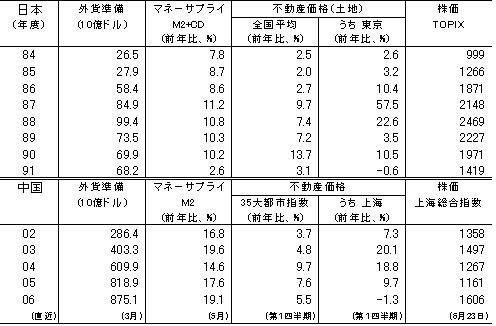
中国では、円高の経験を論じる際、長期にわたる円高の傾向が日本経済に強いデフレ圧力をもたらしているというスタンフォード大学のマッキノン教授の主張が主流となっている(『ドルと円』、日本経済新聞社、1998年)。すなわち、70年代以降、米国の圧力の下で、円が年率4%ほどドルに対して上昇傾向を辿り、円高期待が定着する中で、この4%はそのまま日米の金利差として反映されるようになった(金利裁定を反映して、日本の金利水準=米国の金利水準-円高期待)。米国の金利が高い間はよかったが、1990年代に入って米国の金利が低下するにつれ、日本の金利はゼロに向かわざるをえなくなった。かくして1990年代後半、日本は(金利がそれ以上に下げられない)「流動性の罠」に陥り、金融政策が有効に働かなくなったゆえに、不況が長引くことになったという。中国も日本のように米国の圧力に屈し、切り上げと変動為替レートを実施すれば、デフレが深刻化し、流動性の罠に陥りかねないとマッキノン教授は警告する(「中国は東アジアの安定要因かデフレ要因か」、『人民元切り上げ論争』、東洋経済新報社、2004年)。
一方、中国ではまだ少数派の見解にとどまっているが、元財務官で現在アジア開発銀行総裁を務めている黒田東彦氏は80年代後半の日本でバブル経済が発生した原因を、円高そのものではなく、円高に伴うデフレ圧力を和らげるための金融緩和に求めている(「円高の経験と中国にとっての教訓」、『人民元切り上げ論争』、東洋経済新報社、2004年)。プラザ合意前後に1ドル=240円前後だった円ドル相場は、1985年末には200円割れに、1年後には150円へと急激な円高が進行した。円高で競争力の落ちた輸出産業を助けるために、日銀が1986年1月から1987年2月まで合計で5回にわたって公定歩合を5.0%から2.5%に引き下げ、それまで最低となった金利水準は1989年5月まで続けられた(注)。一方、ドル高是正という目標が達成されたという認識の下で、1987年2月にG7参加国間でドルの安定を目指す「ルーブル合意」が交わされた。これをきっかけに、日銀は積極的にドル買い介入を行うようになった。急激な利下げと外為市場への介入によるマネーサプライの増加によって、カネ余り現象が起こり、資金が株式市場や不動産市場へと向かった結果、バブル経済が形成され、90年代に禍根を残したのである。
確かに、マッキノン説のように、円高(期待)は、バブル崩壊後の日本経済のデフレに拍車をかけた側面もあろうが、現在の中国経済の置かれている状況はむしろ黒田説が対象とする80年代後半の日本に近い。日本の二の舞にならないように、中国としては、一刻も早く、介入の規模を減らして、人民元の切り上げのペースを加速させることを通じて過剰流動性を抑えなければならない。
2006年6月28日掲載


