失敗にこそ教訓がある
主要国で最悪の水準にある日本の財政赤字。政府は財政再建の重要性を事あるごとに訴える。
だが、肝心の再建手法はというと、単なる帳尻合わせに堕していないか?
米国議会のスタッフとして、米国の90年代の財政再建を見つめた経験を報告する。
これから本格化する2003年度の予算編成作業で、政府は一般歳出の規模を前年度以下にする方針で臨むようだ。この不況時、歳出削減に対しては「財政の健全化をめざせば、景気がもっと悪くなる」との批判が根強い。だが、「財政健全化=景気悪化」という論理は単純すぎるのではないだろうか。
筆者は今年春まで10年近く、米国議会でスタッフとして働いたが、米国はこの間、経済の持続的成長と財政再建の両方を達成した。一方、日本の過去10年を振り返ると、景気刺激のために歳出を増やしても効果が薄かったことは明らかだ。米上院予算委員会での公聴会や上院本会議でも、財政政策が景気回復に無力だと主張する場面では、しつこいほど日本の例が引き合いに出されたものだ。
どの国であれ、あらゆる政策問題は財政に置き換えることができる。高齢化社会、年金、医療、環境、安全保障、海外援助、金融、福祉、教育、犯罪対策、地方分権など政策の諸問題は、予算が必要なものがほとんどであり、財政と直結する。言い換えれば、予算を配分するにせよ削減するにせよ、財政とは国家のあり方を描く作業なのだ。日本の財政赤字は先進国中で最悪の水準にある。こうした状況がいつまでも続くと、政府は手足を縛られ、本当に必要とする政策を実行できなくなる恐れがある。
米国だけでなく、財政バランスの健全化に成功した国は景気回復も実現させている。現実を見ても財政再建と景気回復は二律背反ではない。日本も両方を同時に解決することは不可能ではないはずだ。
図は、米国の国内総生産(GDP)成長率と財政バランスの1985年度から2001年度までの推移を示したものである(大統領予算教書のデータを基に作製。米国の会計年度は前年10月1日から9月30日まで)。米国の財政赤字のピークは1992年度で、赤字額は2900億ドル余、GDP比で4.7%に達した(ちなみに日本の財政赤字のGDP比は2001年度で7.7%)。それから6年後の98年度には、29年ぶりに財政均衡を達成した。実質的に将来の債務となる社会保障基金の黒字を除いたバランスでも、2000年度には財政黒字となった。
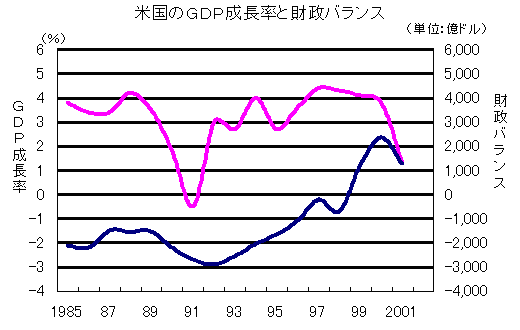
この時期の米国経済が繁栄を謳歌したことで、劇的な改善ぶりに対し「米国は景気がよくなったから簡単に財政均衡できた」と受け止めている日本人は多い。しかし、実際には米国の財政均衡への道のりは決して平坦ではない。70年代からさまざまな財政プロセスの改革が試みられ、失敗を繰り返してきた。むしろ失敗こそ貴重である。かつて巨額の財政赤字に苦しんだ米国がいかにして財政均衡を成し遂げたのか。そこから日本のとるべき道を探りたい。
行政府に対抗する議会予算局
米国の予算決定のプロセスはどうなっているのか。日本とはかなり異なるため、その説明から入ろう。米国の予算編成の基礎となっているのは、74年の議会予算法である。この法律に基づき、(1)議会の付属機関である議会予算局(CBO、Congressional Budget Office)、(2)議員たちの合議の場所である予算委員会(上院と下院にそれぞれ設置)、(3)予算委員会が中心になって本会議で採決する予算決議、という3つの大きな柱が整備された。
議会予算法が成立するまで、米国議会の中に財政の収支バランスを長期で見通すシステムは全く存在しなかった。具体的には、歳入委員会が税制法をつくって歳入を立法化し、歳出委員会が歳出法をつくって予算をつける枠組みだけが存在していた。財政の全体像においては、もっぱら行政府であるホワイトハウスに追従するのみだった。
大統領制の三権分立のもと、大統領に立法権限はない。しかし、行政府は予算全体を把握する組織と機能が充実しており、ホワイトハウス付属の行政管理予算局(OMB、Office of Management and Budget)は各省庁の予算を査定し、執行の調整もする。日本の財務省主計局に似た役割を果たしている。OMBは毎年2月、大統領が議会に提出する予算教書の策定も担っている。
議会予算法は、ベトナム戦争の反省から生まれた。予算編成に関する大統領の力が極めて大きかったことから、ベトナム戦争の戦費などで膨張する財政赤字を議会は十分にチェックできなかったためだ。
OMBの管理職は政治指名で、100パーセント大統領をサポートする組織であるのに対し、CBOは政治から距離を置き、立法作業に加わることもない専門家集団である。あくまでも議員、スタッフ、そして委員会の立法作業をサポートする役割に徹する。緻密な予算見積もりなどは、今日では日常の立法作業に欠かせないものとなっている。
専門家が議員を補佐
上院と下院にそれぞれ設置された予算委員会も多くのスタッフを抱え、政策立案能力は高い。
民主党と共和党の議席割合で、多数党が予算委員長を占める一方、少数党もランキングメンバーと呼ばれる野党側トップを出す。委員長だけでなく、ランキングメンバーにも予算が割り当てられ、委員会スタッフを雇うことができる。通常は委員長が3分の2の予算とオフィススペース、ランキングメンバーが3分の1の予算とオフィススペースである。
2つの党派に分かれたスタッフはライバル関係にあり、共同作業はほとんどしない。委員会スタッフは、委員長またはランキングメンバーの黒衣として、予算決議など委員会の管轄する立法作業を担う。また、委員会による公聴会開催も立法作業の重要な一部分である。委員会では公聴会から法案の叩き台づくりまで党派色が必ず反映されるため、政策スタッフにとって中立という立場はあり得ない。
こうした体制では委員会における責任の所在が明確で、国民は、どちらの党が何をしようとしているのかよくわかる。政党の側も選挙を意識して、ライバルとの政策の違いを明確にすることに励む。そのためには、PRも大事で、委員長もランキングメンバーも、それぞれの報道官と複数のプレス用スタッフを委員会に抱えている。
委員会の専門スタッフも議員と同様、選挙結果によって職を失ったり減給されたりする可能性がある。公務員ながら政策立案・立法作業に責任を持つ格好になる。公務員にとっては厳しいシステムだが、失業しても専門性ゆえ、予算畑で仕事を続ける人間が多い。党籍を変えることなく、選挙の結果、多数党になったり少数党になったりしながら、20年以上を委員会で過ごすベテランも存在する。ほかに、上下院の歳出委員会、OMB、CBO、大学教員、シンクタンクなど転職先は多々ある。
予算決議は議員の長期プラン
もう1つ重要なのが予算決議だ。細かい歳出内容を協議する前に、議員たち自身が国家運営の青写真を大枠で描き、それを本会議で投票にかけ議決する。これは議員たちの投票行動を拘束することを目的とする。
裁量的経費全体にキャップ(上限)をつけ、出費項目を20に分けて大枠の数字を決める。そのプロセスを有効に使えば、ダイナミックな項目別優先順位変更も可能となる。
米国予算の約3分の2は、年金や福祉予算などの義務的経費で、法改正をせねば自動的に支出されてしまうものである。大きな変更となると、法改正が必要だ。米国でも議員はとかく地元への利益誘導に走りがちだ。総論では予算の見直しに賛成したところで、地元に不利益になりそうな各論では反対の立場をとるかもしれない。予算決議の採決というプロセスを経ることで、議員に「総論賛成・各論反対」の矛盾を指摘できる。
このように議員たちが主体となる国家運営の長期プランだけに、予算委員会は、大枠づくりには4カ月ほどの時間を費やす。上院と下院のバージョンが食い違えば、両院協議会を開いて代表者が違いを折衝し、全く同一の決議をまた上院と下院の双方にかけて採決をする。
議院内閣制と大統領制、政権交代の可能性など国情の違いはあるが、こうした米国のシステムは日本でも参考になるはずだ。経済財政諮問会議が設置されたとはいえ、予算編成の知識やノウハウは財務省に集中したまま、族議員は姿を見られずに行政府に圧力をかけ無責任でいる。国会が予算編成に関する専門性を高めれば、行政府へのチェック機能は飛躍的に高まる。当然、国会や野党の責任も重くなる。
機械的歳出削減の失敗
もっとも、こうした制度をもってしても、80年代のレーガン政権の大型減税や議会の歳出圧力などもあり、財政赤字は膨らみ続けた。中でも財政赤字解消のため制定されながら失敗に終わったのが、85年と87年の財政収支均衡法(通称、グラム・ラドマン・ホリングス法、GRH法)である。法律名は発起人となった3人の上院議員の名前によるものだが、その1人のホリングス上院議員は後に「こんな悪法に自分の名前は冠したくない」と言いだし、一般にはグラム・ラドマン法という呼び名になってしまった後日談がある。
均衡予算の達成をめざしたGRH法は、目標の数値に達しなければ、支出の一律カット命令が待ち受ける厳しいものであった。しかし、予算編成のプロセスを変えないで、成果だけを性急に求めるやり方は稚拙だった。たとえ当初は達成可能と思われる目標数値を定めたところで、予算年度中に景気が下降し始めると税収見積もりが減収し、結果的に非現実的な目標となってしまう。また、国民の反発を恐れ、義務的経費などを一律カットの対象項目外に設定する抜け穴があった。
当初は91年に財政均衡させる目標だったのだが、87年には目標を2年先延ばしして93年とする有り様で、90年になると、議員の多くがGRH法の廃棄を考える状況になった。
この年、米国は厳しい状況にあった。S&L(貯蓄貸付組合)の破綻処理に加え、イラクのフセイン大統領のクウェート侵攻に対応する必要もあり、歳出は膨らむ一方だった。そのため、年頭に1000億ドルほどと見積もっていた年間の財政赤字は、3月には1610億ドル、年末には2030億ドルに跳ね上がると予想された。
GRH法のもとでは850億ドルの歳出一律カットになる。内訳は国防費で32%カット、国防費以外の裁量的経費で35%カットという、とてつもない水準である。もはやGRH法は完全に行き詰まってしまった。かといって、増税も難しい。当時のブッシュ(父)大統領が88年に掲げた選挙公約は「私を信じてほしい。増税はしない」(read my lips: no new taxes)であり、議会共和党も増税による財政均衡には大反対であった。局面打開のため、ブッシュ大統領は政府と議会からなる超党派の「予算サミット」を提案し、民主党主導の議会と折衝して方向転換の道を探ろうとした。
増税で再選阻まれた大統領
振り返ると、この「予算サミット」は米国の国家像の選択の場だったといえる。
後に下院議長となるニュート・ギングリッチ氏を中心とする共和党保守グループは、限りない減税による小さな政府を標榜していた。民主党のミッチェル上院院内総務を中心とするリベラル派は、民主党伝統の大きな政府論だった。中道・現実派のブッシュ大統領は、この間に挟まれて苦労する。
議会の実力者、ミッチェル上院院内総務は貧しい家庭から身を起こした筋金入りの弱者救済派で、ブッシュ大統領に対して一歩も引かない。名門に生まれ、「銀の食器で育った」と評されたブッシュ大統領とはもともと根本的に意見が違っていた。増税を避けたかった大統領も、最後には民主党との妥協を図るため、増税政策を余儀なくされた。
GRH法に代えて、90年11月、個人所得税等の増税を盛り込んだ財政均衡パッケージ(90年包括財政調整法、OBRA90)が成立する。選挙公約を破ったことで、大統領は共和党内の保守主義グループの猛反発を受けた。それが92年の再選失敗につながる。しかし、長期的な歳出抑制のメカニズムが生み出されたのはこの時であった。
増税容認ばかりが攻撃されたOBRA90だが、増税でまかなうのは3分の1程度、残りの3分の2は歳出カットで財政均衡を達成しようという計画だった。OBRA90と抱き合わせで、90年の予算執行法(BEA、Budget Enforcement Act)も制定された。緩やかな歳出キャップは災害や不景気などの緊急財政出動の額を除くとし、最初からコントロールの利く裁量的経費だけに割り当てるなど、GRH法と違って実行可能な長期計画となった。また義務的経費については、新規歳出には財源探しを要求するpay-as-you-go(PAYGO)ルールを適用することとした。
当時は不況の最中で、S&Lの不良債権処理もあり、92年まで財政赤字が増え続けた。しかし、新ルールがなければ財政赤字はさらに膨れ上がっただろうといわれる。93年度からは財政赤字が減り始め、新ルールは歳出圧力を抑える防波堤として、じわじわと効果を見せ始めたのである。
BEAは93年と97年の2回、議会の圧倒的支持を得て延長された(2003年度以降の延長はまだ可決されていない)。
ペロー旋風が財政赤字への関心惹起
米国の財政赤字を国民レベルの問題にしたのは、92年の大統領選挙で注目されたテキサス州の富豪ロス・ペロー氏であるとよく言われる。ギャラップ社の調査結果によると、彼が巨額のキャンペーン資金を投じて毎晩テレビ出演して財政均衡を唱えるまで、赤字問題が重要だと感じていたアメリカ人はせいぜい10人に1人だったとされる。
ペロー氏の功績は偉大だが、当時のペロー氏自身は、実は具体的にはどのようにすれば財政均衡を達成できるか何も知らなかった。具体策を聞かれたペロー氏は、1000億ドルの歳出削減は裕福な老人に年金を拒否することでまかない、別の1000億ドルはヨーロッパやアジアの同盟国が軍事費としてアメリカに支払うことで得て、さらに1000億ドルは徴税当局のコンピューターを近代化して人件費を浮かせて節約する、と気楽に発言していた。
ペロー候補に刺激されて、大統領選では民主党のクリントン候補も財政規律を唱えるようになった。ただ、達成方法についてはペロー候補と同じと言わないまでも、かなり無知であった。クリントン政権発足後、ホワイトハウスの補佐官たちが大統領の選挙公約内容を詳しく予算見積もりしたところ、どんなに少なめに見ても2200億ドルの出費増になるという結論が出たほどである。
クリントン政権の背中を押したのは、財政規律を重く見ていた連邦準備制度理事会のグリーンスパン議長だった。議長は93年の年明けの上院予算委員会で、大統領が97年までに1450億ドルの赤字削減をしたいと伝えてきたと証言した。実のところ、大統領は内心では具体的金額の公表に躊躇していたとされる。議長の発言を聞いたマスコミ各社の記者たちは部屋から猛スピードで飛び出した。ニュースはあっという間に既成事実となった。
クリントン大統領自身が当初、どこまで財政規律を重視していたか、疑問は残る。大統領は議会に対して財政による景気刺激策をリクエストしたり、ヒラリー夫人が中心になって作成した国民皆保険制度案を民主党議員を通して提案したりしたからだ。ともに廃案になったが、実現すれば間違いなく歳出を膨らませる政策だった。
ただ、クリントン政権を支えた政府高官は、元下院予算委員長のパネタOMB長官やリブリンOMB副長官(元CBO局長)ら、財政均衡を重視する立場の人が控えていた。もちろんグリーンスパン議長もそうだ。財政の専門家にとっては赤字削減を進めるしかないという強い思いがあり、それがクリントン政権を動かしていく。大統領は財政赤字削減を最重要課題の1つに掲げ、高額所得者への課税強化、医療給付の削減などを盛り込んだ93年包括財政調整法(OBRA93)を成立させる。
増税反対派の巻き返し
増税を盛り込んだクリントン政権の財政再建プランに対して、ギングリッチ下院議員を中心とする共和党内の保守派は猛反発した。
94年の中間選挙で共和党は40年ぶりに下院での多数を握り、上下両院を支配するに至り、「共和党革命」と呼ばれた。選挙でギングリッチ議長のグループは「アメリカとの契約」という公約を掲げ、最優先事項に財政均衡を挙げた。目指す財政均衡の姿は、当然ながらクリントン政権とは違い、徹底した歳出削減で達成すべきものとした。
上下両院の共和党議会は、95年の年明けから猛スピードで独自の予算案を練り始める。年末までに5000ページを超える新しい法案ができあがったものの、大統領は拒否権を発動し、成立することはなかった。だが、その後も議会と大統領府は対立を続け、95年から96年にかけての冬には、2度にわたり政府の窓口閉鎖など機能が一部停止した。
そのため、95年10月から発動するはずの96年度歳出法は、最後の13本目が通過したのが96年4月下旬で、それまでは暫定予算で繋いで政府機能を維持する状況だった。もっとも、暫定予算は前年レベルの歳出規模であるため、裁量的経費が節約でき、結果的には支出削減になるという皮肉なおまけがついた。
2度の政府機能停止によって、ギングリッチ議長は「悪役」のイメージが広がり、96年の下院選挙で共和党は多数派を維持したものの、議席を減らした。急激に小さな政府をめざそうとしても生活に影響が出ると国民も感じ始めた。
97年には議会と大統領の妥協がなり、歳出削減と一定の減税を図る、財政収支均衡法と納税者負担軽減法がともに成立した。これで財政バランスの改善は予想以上のスピードで進んだ。
テロ事件以降ゆるむ財政規律
以上述べてきたように90年代を通して、財政規律はワシントンで最大の政治課題だった。しかし、2001年の9・11テロや、景気後退を防ぐことを口実に最近は財政規律が崩れ始めている。財政が政治そのものである以上、無理からぬ帰結とはいえ、財政規律の維持は、それほど容易ならざるものである。 戦時予算となった2002年度は財政赤字に転落、赤字額も1600億ドルを超えるという予測も出ている。さらに今年は議会内の対立から、予算決議も本会議で成立していない。財政均衡が達成されてからというものの、予算決議の大枠をはみ出した歳出が行われ始めた。
米国では「過去何十年と、ただひたすら赤字削減のためだけに予算編成プロセスを改革してきた。だから黒字という環境下での有効なプロセスが見つからない」という嘆きの声もあったが、これも束の間のことだった。
実のところ、筆者は再び米国が泥沼のような財政赤字に苦しみ続ける可能性は少ないと見ている。財政赤字の増大は、既に構築された赤字削減のメカニズムが再び動き出すことを意味するからだ。数値目標でなく、プロセスの改革を経験した強みである。
日本での財政再建論議を見ていて危惧するのは、プロセス改革の議論が少ないことだ。「新規国債発行を30兆円以内に」とか「公共投資を1割削減」とか数値目標がまずありきでは、国のあり方を決める予算編成の進歩にはつながらない。
まず、日本が取り組むべきなのは現行の予算決定システムそのものを徹底して見直すことではないか。国民に見えにくい予算編成作業をどうオープンなものにするか、族議員の介入と政治主導をどうバランスさせるか、歳出の中身を誰がどう見直すか――。単年度予算のままでいいのか、という根本的な問題まで含め、問い直すことになる。それは日本の政治そのものを見直す作業である。米国では揺れ動きながらも政治家たちは徹底的な論争の中から、改革の妥協点を見いだした。日本も同じ覚悟が必要なのだ。
2002年9月号 『論座』 (朝日新聞社)に掲載


