尖閣諸島の帰属を巡って日中間の議論の応酬が続いている。日韓の竹島問題も8月と比べるとやや落ち着いてきたが、依然収拾からは程遠い。
最近、米倉弘昌経団連会長が尖閣諸島について「領土紛争」があることを認めるべきだと主張したほか、橋下徹大阪市長が法にのっとって国際司法裁判所(ICJ)で解決すべきだと発言した。尖閣諸島や竹島の日本領有の正当性の議論から一歩進んで、日中、日韓が角を突き合わせている現状にどう対処すればよいかという議論が登場するようになった。ただ、領土紛争の存在を認めることが何を意味するか、ICJによる国際法にのっとった解決とはどういうものかについて、十分に理解しているのかはやや疑問だ。
◆◆◆
竹島について韓国は領土紛争の存在を否定し、尖閣諸島については逆に日本が領土紛争の存在を否定している。領土紛争の有無は、相手方の領土主張に対して一定の正当性を認めるかどうかに関わる。
土地の所有権に例えると分かりやすい。ある日Aの家の前を通りかかった人(B)が突然家に来て、この家は自分の家だと申し出た場合(ケース1)と、Xが所有する土地をまずYに売り、それを隠してZにも売った(二重売買)ときに、土地の所有権がYにあるかZにあるかが問題になった場合(ケース2)を考えよう。ともに特定の土地の所有権が問題になっているが、状況は全く違う。ケース1のBの主張は完全な言いがかりだが、ケース2のY、Zにはそれぞれ一理ある。紛争があるというのはケース2で、主張の対立があっても紛争がないというのがケース1だ。
尖閣諸島については、日本はケース1、中国はケース2に当たるという立場だ。逆に竹島については、韓国はケース1、日本はケース2と考えている。日本が竹島について領土紛争があると考え、尖閣諸島についてはそう考えないことは、全く矛盾していない。
領土紛争の存在を認めることは、相手方の領土の主張に一定の正当性を認めることである。領土紛争の存在を認めると、両国はその領土紛争の解決のために話し合いを始めることが求められる。この点を如実に示すのは、北方領土に関する日本とソ連(現ロシア)の経緯だ。北方領土については1956年の日ソ共同宣言で継続協議とされたが、その後ロシアは領土問題は解決済みと主張し始めた。ソ連の主張は日本側の粘り強い交渉で覆され、91年の日ソ共同声明でソ連は領土問題の存在を認め、日ソ間で北方領土の帰属を巡る交渉が始まった。
ソ連が領土紛争を認めたというのは、領土の帰属が全部または一部が日本のものでありうることを認めることにほかならない。尖閣諸島について、そうした立場にわが国は立つべきなのか。尖閣諸島の帰属について、中国が日本領とは認めないという主張をして日中間で見解が対立することと、領土紛争があるということは全く違うことだ。
また「紛争」を「国際紛争」と呼ぶ場合もあるため、国際紛争(conflict)と紛争(dispute)が混同されることがある。国際紛争とは武力衝突のある状態を意味し、それに至らない状態を対立とよぶ。紛争が元で対立や武力衝突が生まれることはよくあるが、紛争の有無にかかわらず対立や武力衝突は起こりうる。日米安保条約が関係するのは武力衝突であって紛争ではない。尖閣諸島を巡って武力衝突が起きれば米軍は動くことになろうが、尖閣諸島の帰属を巡って米国が日本の味方をしてくれると考えるのは早計だ。
米国政府も尖閣諸島の領有権については中立の立場をとることを再三述べている。国際紛争や国家間対立は国際社会の平和に関わる国際的関心事項だが、領土帰属の問題は国内の土地係争と同様に基本的には関係2国間の問題だ。
◆◆◆
紛争の司法的解決を考える際には、国際裁判と国内裁判の違いを頭に入れる必要がある。国内の紛争については、当事者の一方が裁判所に付託すれば他方の意向にかかわらず、裁判所が最終的な決着をつけられる。他方、国際裁判にかけるには、両当事者の合意が必要だ。国際社会では、紛争の平和的解決が義務づけられているが、国際法にのっとってICJなどの国際裁判所で解決することまでは要求されていない。
国内ならばケース1でもケース2でも、所有権を主張する側は裁判所に訴えて決着をつけられるが、国際社会はそうではない。紛争を平和的に解決するための1つの選択肢として、国際裁判所による司法的解決があるにすぎない。
竹島について日本政府は韓国に対してICJへの付託を提案した。それは日本が国際法にのっとった解決を志向することを通告し、韓国の一連の行動への「対抗策」を打っただけであり、韓国はそれに応ずる法的義務も道義的義務もない。一時マスコミは応訴しない場合は韓国側に説明責任が生じると報じていたが、それは誤りだ。国際裁判は、紛争解決のための有力ではあるが1つの解決方法でしかない。
最近ICJでは領土問題の扱いが増えている(表参照)。とはいえ、国際裁判の領土問題への関与についての評価が変わったわけではない。国際裁判所で領土問題の解決が可能なのはどういう場合だろうか。第1の条件は、領土問題を残しておくよりも、たとえ全部ないし一部が相手方に移っても領土問題の解決の方が重要だという意識が生まれることだ。例えば、領土がどちらに帰属しても大した話ではなく、領土問題が残ることで両国間の関係が悪化するのは良くないという雰囲気が広く存在するような場合だ。
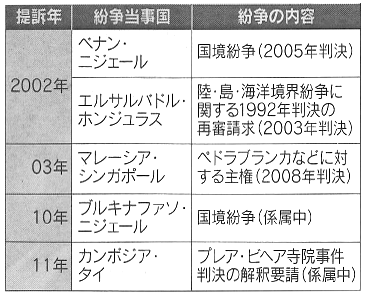
領土に関連して海洋資源や鉱物資源が取り沙汰されるが、竹島問題があっても、日韓間では漁業協定や大陸棚開発に関する協定も既に締結されている。同様に、尖閣諸島問題があっても、東シナ海漁業について日中漁業協定が成立している。これらの例は、領土問題を解決しなくても周辺の天然資源問題を処理できることを示している。
どのような形であれ、平和的に領土問題を解決した方がよいという判断が成り立てば、次にそれをどう実現するかが問題になる。最後まで交渉により解決を図るという考え方もあるが、裁判官という第三者により国際法にのっとって結論を出してもらった方が短時間で済み、かつ国民などの関係者の納得も得られやすい、すなわち処理コストが低いと考えられる場合もある。この意識が成り立てば、当事国は国際裁判による司法的処理を選ぶことになる。ただし、一方の勝訴の可能性があまりに高い場合には、他方の裁判付託の誘因は弱まる。
尖閣諸島や竹島についてICJで解決を得るには、島の帰属問題よりも両国間の関係の安定化の方が重要であり、かつ帰属問題を解決する最善の方法は司法的解決だという意識が日中韓3国の間になければならない。しかし、島の帰属を巡る対立が反日感情と結びつき、尖閣諸島の領有が中国の核心的利益と位置づけられている現状では、国際裁判により問題を処理する条件は全く整っていない。
◆◆◆
領土帰属がナショナリズムと結びついた大きな政治問題である限り、力ずくの解決を求めないとすれば、関係国・国民が冷静になり両国関係が安定するまでは、領土帰属を巡る対立を完全に解消できないと考えるほかない。両国の主張の是非について最終的な決着をつけることは求めず、当面凍結して、対立の解消に向けた雰囲気が醸成されるまで問題処理を気長に待つ以外に方法はない。国際問題の平和的解決を国是にすることは、一刀両断の解決を求めないことといえる。
2012年10月9日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


