60年ぶりに全面改定された新統計法が4月1日から全面的に施行された。「行政のための統計から国民の財産である社会の情報基盤としての統計へ」を標榜する新統計法にはいろいろ特筆できる点があるが、特に重要なのは、匿名データを活用できる体制を促進することがうたわれたことであろう。
◆◆◆
ただ、統計情報の活用体制が整備されただけで、政策立案や政策効果の予想、検証といった政策分析に関する議論が格段に進むわけではない。
まず、現在収集されているデータ自体は、必ずしも個々の経済主体の行動を理解したうえで政策を立案したり、効果を予測・検証したりすることを念頭に集められているものではない。また、そのため現在あるデータでは基本情報が不足しているものが多い。特に教育、社会保障、生産性改善といった重要な政策課題を議論するために必要となる経済主体の行動を分析するのに十分ではない。例えば商業の生産性の測定をしようとしても、労働者が管理職かどうかの区別すらない。
この背景には、経済統計の多くが、国内総生産(GDP)など経済全体の状況をとらえるために考案された、国民経済計算(SNA)体系と呼ばれる二次統計を作成するために収集されているという事情がある。SNAは一国全体の経済状況について、生産、分配、支出または投資といったある一定期間のフローと、資産や負債といった現状までのストックの両面から、数値を体系的にとらえ、経済の実態を世界共通の尺度で明らかにするものだ。
もともとは1950年代にR・ストーン英ケンブリッジ大教授を中心に開発されたが、今日の経済実態は、設計当時とは様変わりしており、これをどう体系に反映させるかという点でSNAは難しい問題を抱えている。さらにより根本的には、当時から飛躍的に進んだコンピューターの能力を前提にすれば、修正が加えられてきたとしても今のSNA体系だけでは現在ある一時統計データから十分な情報が引き出せているとはいえない。
◆◆◆
SNAを中心とする統計整備が進んできたのは、個別の家計や企業の匿名データ(個票データ)を直接実証分析の対象とする研究が難しかったからだ。しかしコンピューター性能が飛躍的に高まり、膨大な情報を処理が可能になったうえ、世界的に学問的な知見が蓄積され、個票データ分析は格段に進歩した。
この先駆けとしては、D・マクファーデン米カリフォルニア大バークレー校教授らによる公共交通システムの設計が挙げられよう。サンフランシスコの地下鉄(BART)建設に際し、教授らは通勤手段に関する個票データの分析を活用した。個票自体には個人の属性と実際用いた交通手段の結果しかない。だが個人がなぜそれを選んだのかは、料金、通勤時間などのほか、置かされた環境や好みの強さなどによる。そこでそれぞれの選択肢を選ぶ確立は相対的料金、通勤時間で表されるという「定性的選択モデル」を考案、料金変更は通勤手段の選択確率を変えると考えることでその効果が測定できるようにした。
個票分析の重要性に対する認識が一段と高まったのは、70年代半ばのいわゆる「ルーカス批判」からだ。すなわち、R・ルーカス米シカゴ大教授は、政策変更によって集計されたデータを用いた経済モデルの係数が大きく変わる可能性があることをいくつか例示し、国民経済計算から得られたデータによる従来の経済分析を批判した。その後、K・ウォルピン米ペンシルバニア大教授、R・ミラー米カーネギーメロン大教授、J・ラスト米メリーランド大教授らが、個票データを使って、政策変更によっても変わらない人々の経済行動の構造を解明する「構造推定アプローチ」をベースに経済行動を把握しようとする研究を進めた。
構造推定の研究が進んだ背景には、同一の対象を継続的に観察して記録する「パネルデータ」が充実してきたことも寄与している。米国ではこういったパネルデータは、政府ではなく、ミシガン大学やオハイオ州立大学などの研究者によって、60年代から整備が進められたという点は特筆すべきだろう。
こうした経済の構造事態を把握しようとする構造推定と並行して、90年代以降は、いわゆる「自然実験アプローチ」とよばれる個票分析の研究も進み、むしろこちらが主流になっている。これは根本的に緩やかな仮定の下で、データから確実にいえることは何かという点を強調するものだ。
実験から政策効果を分析するものには、70年代に米ランド研究所が実施した、健康保険の自己負担率が医療需要に及ぼす効果を測定するための社会実験や、80年代に行われた社会実験による職業訓練効果の測定などが有名だ。自然実験のアプローチは、社会実験のように実際に実験を行うのではなく、現実社会の中で実験に相当するようなものを見いだして分析する。
例えばブレア英政権下での雇用政策「ニューディール」では18-24歳の若者が6カ月失業した場合にはゲートウエート呼ばれる再就職を目指すプログラムを受けることが義務付けられた。R・ブランデル英ユニバーシティー・カレッジ教授らは、24歳とこのプログラムに入らない25歳になったばかりの同様の失業者のその後の就業行動を比較し、この政策に効果があることを確認した。
もちろん、自然実験アプローチで政策効果が認められたとしても、そこにはどんなメカニズムが働いたのかは必ずしもわかるわけではない。それだけに、構造推定と自然実験は相互に補完するアプローチとして認識され、双方の研究が進化している。
◆◆◆
以上概観したように個票データを用いた研究分野は、政策をどう立案し、効果をどのように予想し、検証するかという非常に具体的、切実な要請に応えるべく進展してきている。日本では、政府の統計データを用いた個票分析は、「目的外」として原則データの使用ができず、分析することすら難しかった。新統計法では匿名データの提供が制度化され、学術研究などの要請に対応できるようになった。
もちろん、政府が収集している個票データは、政策分析を主体とした研究を念頭に設計されているわけではなく、その面で、政府統計に携わる担当者と実証分析に携わる研究者のコミュニケーションを密にすることは急務である。
とはいえ、具体的な政策効果の分析に関し、当局者でなくても政府と同じ土俵で検討できることは、妥当な社会経済政策を模索する上で基本的な要件である。その点で、新統計法で個票データ分析が進む環境が整備されたことは、大きな前進といえよう。
もちろん、それだけで個票データ分析が「本格的研究」として研究者の動機づけを高めるのに十分なわけではなく、新しい科学的知見を得るために、研究者自身が主体になって、大規模データを構築していくことも必要だ。例えば高齢化という先進国共通の課題については、米ミシガン大学の「健康と退職に至る行動に関する研究(Health and Retirement Study)」をはじめ、各国で「世界基準」のパネルデータ整備が進んでいる。日本でも吉冨勝・前経済産業研究所所長が主導した「くらしと健康の調査(JSTAR)」があり、先進国社会が抱える高齢化問題の解決に大きく貢献することが期待される。
問題なのは、わが国で、現在の標準的な手法に精通し、社会の難題解決に向けて貢献しうる人材が不足していることだ。例えば、経済学の有力雑誌に過去掲載された日本の大学に所属する日本人研究者の論文のシェアを見ると、70年代半ば以降ほぼ一直線に低下している(図)。動機づけに関する彼我の差は見過ごせない点といえよう。
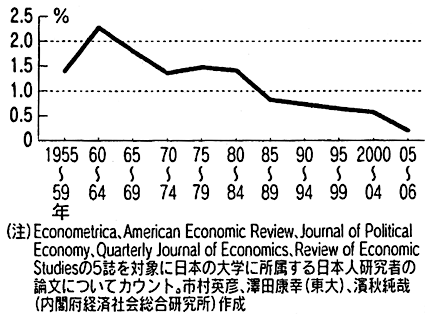
新統計法の下、現在あるデータの活用体制が整備され、政策分析の精緻化の道が開けることは大きな前進だが、同時に「人材不足」の点も、解決に向けた問題意識を共有すべきだろう。
2009年5月1日 日本経済新聞「経済教室」に掲載


