円の対ドル・レートは昨年夏頃から80円割れの水準が常態化し、対ユーロも100円前後の水準が続いてきた。円高は、高い法人税率、電力不足等とともに日本企業の事業環境を厳しくしている「六重苦」の1つとされており、過度の円高に伴う製造業の海外移転の加速、国内の空洞化が懸念されている。こうした中、デフレ克服とともに円高を是正するため、一層の金融緩和を求める意見も少なくない。
分かれている円高への見方
現在の円レートおよびその国内経済への影響については、産業界や政策実務の見方と経済学者の評価の間にギャップがあるように見える。たとえば、経団連は「円は歴史的な高値圏で推移している」とした上で、「現在の円高水準への対応は、国際的に高い競争力とシェアを誇る産業群ですら、極めて困難な状況である」と述べている(経団連「成長戦略2011」)。経済産業省は、産業構造審議会の報告書(2012年6月)の中で、「現状の円高水準が継続すると、素材型製造業も含め、サプライチェーン全体が急激に海外に移転する『根こそぎ空洞化』」を招くと警鐘を鳴らしている。
これに対して、物価上昇率の格差および貿易相手国のウエイトを考慮した実質実効為替レートから見て、現在の円相場は過度な円高とはいえないと評価する経済学者は少なくない。たしかに日本銀行が公表している円の実質実効レートを見ると、「超円高」といわれた1995年4月は30%以上、2000年代初めを見ても20%程度、現在に比べて円高だった。過去20年間の平均値と比較しても、現在は同程度ないしわずかに円安水準である(注1)。
産業・企業の国際競争力を評価する上では、名目為替レートよりも実質為替レートを見るべきであり、また、二国間レートではなく多数の貿易相手国通貨との加重平均である実効レートを見るのが適当である。しかし、為替レートが「円高」かどうかは、過去の水準との比較だけでなく「均衡為替レート」との関係で評価する必要がある(注2)。RIETIの研究成果の中では、Sato et al. (2010)が、生産性上昇率に着目して均衡円ドル・レートを推計したYoshikawa (1990)の方法を拡張して中国人民元の対ドル均衡レートを試算し、現実の人民元が均衡レートよりも6割以上過小評価であるとの推計結果を示している。この研究は人民元と円の関係を直接に評価したものではないが、中国が日本の輸出入の約2割を占める最大の貿易相手国であることに鑑みると、円の均衡レートが円安化している(現実のレートが過度な円高となっている)可能性を示唆している。
交易条件と為替レート
ところで、実質為替レートは交易条件(輸出価格/輸入価格)と密接な関係がある。貿易財のみを考慮した最も単純な二財モデルでは、実質為替レートは交易条件と定義上等しい(小宮・森川, 1995)。つまり、交易条件は、実質為替レートの国際競争力から見た均衡水準との乖離を判断する1つの目安ともいえる(注3)。そこで、日本銀行の輸出物価指数、輸入物価指数から計算した交易条件を実質実効レートと並べてプロットしたのが下図である。縦軸の上ほど円高、下ほど円安である。
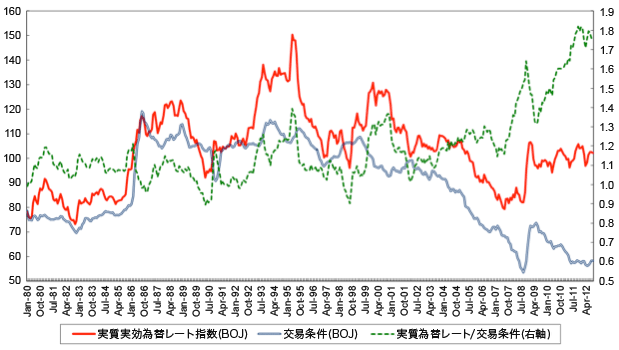
これを見ると、近年の交易条件の悪化傾向が明瞭に観察でき、均衡為替レートが円安化を続けている可能性を示している。交易条件、実質実効為替レートはいずれも基準年との関係で見た指数なので、両者の絶対水準を単純に比較することはできないが、図で実質実効レートが交易条件よりも上にあるほど現実の為替レートが均衡水準に比べて円高方向にあることを意味する。1995年も為替レートが交易条件と大きく乖離した円高だったが、それ以上にリーマン・ショック以降の乖離幅が大きくなっている。参考までに実質実効レートを交易条件で割った数字を破線で表示している。これを見ると、交易条件との比較で見た最近の円高度合いは過去に例がない大きさである(注4)。この事実は、近年、日本の産業の国際競争力が傾向的に低下しており、貿易財産業の実力との比較で大幅な円高が進んでいること、最近の円高に対する産業界や政策実務の見方が的外れではないことを示唆している(注5)。
どう対応すべきか?
このような実質実効レートと交易条件の大幅な乖離の要因は、論理的に3つに分けることができる。(1)世界的な金融不安等の影響で現実の為替レートが均衡水準よりも円高になっている、(2)一次産品価格の上昇もあって輸入物価が円高の割には低下していない、(3)輸出物価が円高にも関わらず大幅な低下傾向にある、又はこれらの組み合わせである。
それではこうした状況にどう対処すべきだろうか。(1)円高を修正して競争力を反映した水準に近付ける、(2)交易条件を改善して現実の為替レートとの乖離を小さくする、のいずれかということになる(注6)。
しかし、為替水準の大幅な修正を目的とした介入は国際的な批判を覚悟しなければならないし、為替市場への介入によって為替レートの水準を中長期的に大きく変えることは難しい。金融緩和政策は名目での通貨安を導く傾向を持つが、実質為替レートを減価させる効果を持つかどうかは物価と為替レートへの効果の大小関係次第である。ただし、円レートの大幅な不均衡が現に存在するとすれば、政策とは関係なく円レートの急激な減価がいずれかの時点で生じる可能性も否定できない。
一方、交易条件を改善するためには、円高のメリットを活かして輸入財価格を引き下げ、あるいは省エネ・省資源によって価格が上昇しているエネルギーや原材料の輸入ウエイトを低下させる(あるいは代替を図る)といった輸入側からのアプローチが1つである。もう1つは、世界的に需要の所得弾性値が高い財の輸出ウエイトを上げる努力等を通じて輸出財の相対価格を高めることである。いずれも経済のファンダメンタルズに関わる構造的な対応が必要となる。


