計画経済の時代の平等主義に伴う弊害を打破すべく、改革開放以来、中国は鄧小平が提唱した「先富論」を旗印に、平等よりも成長を優先させる発展戦略を推し進めた。30年余りが経ち、総じて国民生活は向上してきたが、その一方で所得格差が容認できないレベルまで拡大してしまい、そのままでは、社会が不安定化する恐れがある。幸い、近年、農村部における余剰労働力の枯渇(いわゆる「ルイス転換点」の到来)に伴う労働力不足をきっかけに、労働分配率が上昇しており、その結果、所得格差も縮小し始めている。所得分配の改善は、消費拡大につながると期待される。
相次いで縮小に転じた三つの格差
中国では、これまで「都市部」と「農村部」、「東部」と「中西部」、そして「高所得層」と「低所得層」の間を中心に所得格差が拡大してきたが、ここに来て、この三つの格差は、相次いで縮小傾向に転じている。
まず、都市部と農村部の間の格差については、2010年以降、農村部の一人当たり所得の伸びが都市部を上回るようになった。これを反映して、都市部の農村部に対する一人当たり所得の比率は2009年の3.33倍をピークに低下傾向に転じており、2013年は3.03倍となった(図1)。
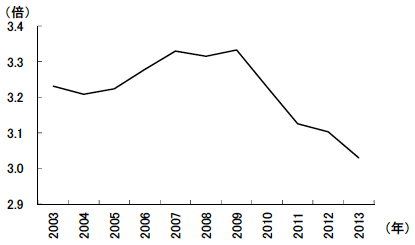
次に、東部と中西部の間の格差については、2007年以降、中西部の経済成長率(実質GDP成長率)が一貫して東部を上回っている(図2)。また、東部の中西部に対する一人当たりGDP(名目)の比率も、2003年の2.30倍をピークに、2013年には1.76倍に低下している(図3)(注)。
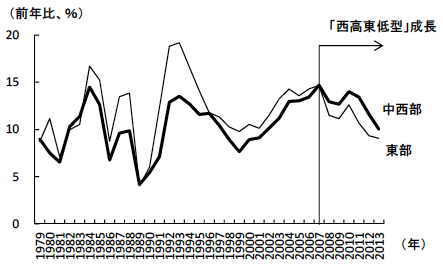
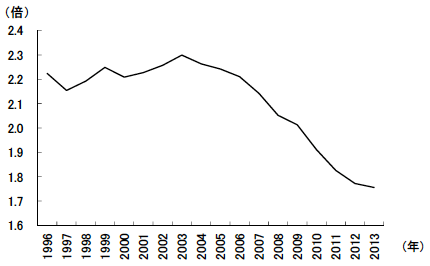
そして、「高所得層」と「低所得層」の間の格差については、都市部では、上位20%の世帯の下位20%の世帯に対する一人当たり所得の比率が、2003年の5.30倍から2008年の5.71倍に拡大した後、低下傾向に転じており、2013年には、4.93倍に戻っている(図4)。農村部においても、上位20%の世帯の下位20%の世帯に対する一人当たり所得の比率は2011年をピークに下がり始めている。
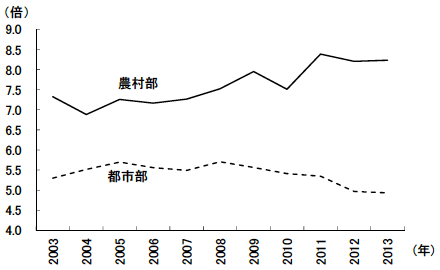
このような変化を反映して、(農村部と都市部を合わせた)国全体の所得格差を総合的に示すジニ係数も、2008年の0.491をピークに、2013年には0.473に低下している(図5)。しかし、中国のジニ係数は低下傾向に転じたとはいえ、他の国と比べてまだ高い。
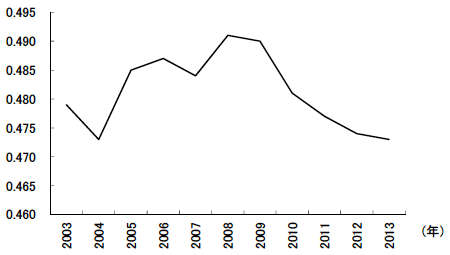
労働力不足を背景とするクズネッツ転換点の到来
経済発展と所得格差の関係については、1971年にノーベル経済学賞を受賞したサイモン・クズネッツが提唱する「逆U字仮説」が有名である(Kuznets, 1955)。それによると、所得格差は経済発展の初期段階において拡大するが、やがて改善に向かう。縦軸に所得格差を示す指標(たとえばジニ係数)、横軸に経済発展の段階を示す指標(たとえば一人当たりGDP)を取ると、両者の関係は「逆U字型曲線」を描くという(図6)。
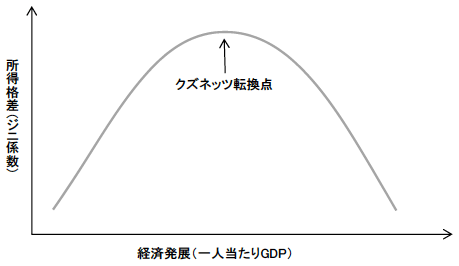
この仮説に沿って言えば、中国はちょうど「逆U字型曲線」の頂点(「クズネッツ転換点」)を通過し、所得格差が縮小の方向に向かい始めていることになる。そのきっかけは、農村部における余剰労働力の枯渇を意味するルイス転換点の到来である(Lewis, 1954)。ルイス転換点を通過する前の段階においては、農村部が余剰労働力を抱えているため、経済が成長しても、賃金がそれほど上がらず、労働分配率が低下する一方で資本分配率が上昇する。このことが所得分配において、主に賃金収入に頼っている低所得層よりも資本収入の多い高所得層に有利に働くため、経済成長に伴って格差は拡大してしまうのである。これに対して、ルイス転換点を過ぎてからは、労働力不足が顕在化し、賃金上昇も加速する。その結果、労働分配率が上昇し、所得格差は縮小に向かうのである。
中国では、2011年以降、経済成長率が大幅に低下してきているにもかかわらず、求人倍率が上昇し続けていることに象徴されるように、ルイス転換点はすでに到来したと見られる(図7)。それを受けて、労働分配率も2011年を底に上昇に転じており、所得格差も縮小に転じ始めている(図8)。このように、ルイス転換点とクズネッツ転換点の関係は、中国において観測されているのである。
―ルイス転換点の到来を示唆―
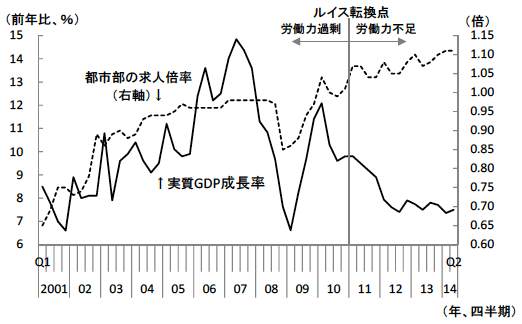
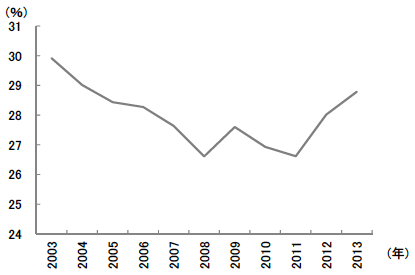
もっとも、ルイス転換点の到来に伴う労働力不足は、所得分配の改善をもたらした唯一の原因ではない。2002年に誕生した胡錦濤政権は、「先富論」を改めるべく、「調和の取れた社会」というスローガンの下で、「新農村建設」、「西部大開発」、「中部の勃興」の推進などを通じて、所得格差の是正を目指すようになった。政府の取り組みに加え、農村部から都市部へ、中西部から東部への大規模な労働力の移動も、出稼ぎ労働者による故郷への送金を通じて、格差の縮小に寄与していると見られる。
消費拡大のきっかけに
所得格差の縮小は、社会の安定だけでなく、経済成長を需要側から支える消費の拡大にも寄与すると期待される。
一般的に、所得に占める消費の割合を示す消費性向は、所得水準と反比例し、高所得層ほど低く、低所得層ほど高くなる。所得格差が拡大することは、所得が消費性向の低い高所得層に集中することを意味するため、全体の消費性向を低下させる要因となる。逆に所得格差の縮小は、消費性向の低い高所得層よりも、消費性向の高い低所得層の所得が増えることを意味し、全体の消費性向を高める要因となる。
消費性向が高所得層ほど低く、低所得層ほど高いという傾向は中国でも見られている。まず、農村部の家計所得が都市部より低いことを反映して、2012年には、農村部の消費性向は74.6%と、都市部の67.9%を上回っている。また、都市部と農村部のいずれにおいても、家計の一人当たり所得順に5階級に分類した場合、消費性向は、下位の世帯が最も高く、中下位、中位、中上位、上位の順で低下していく(図9)。たとえば、都市部の場合、下位の世帯の消費性向は81.7%と高く、上位の世帯の消費性向は61.4%と低くなっている。
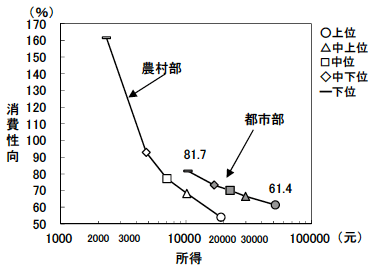
現に、これまで低下傾向を辿ってきたGDPに占める民間消費の割合は、2010年の34.9%を底にようやく上昇に転じており、2013年には36.2%に達している(図10)。所得格差の縮小が消費を拡大させる要因であることを考えれば、このような変化が見られるようになったことは決して偶然ではない。
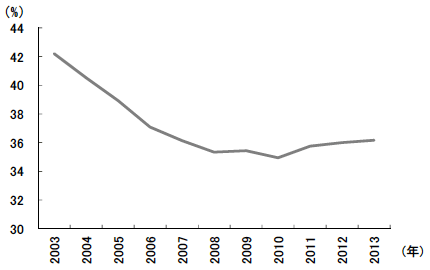
中国はまだクズネッツ転換点を過ぎたばかりの段階にあり、今後も所得格差の縮小傾向が続くと予想される。このことは、消費性向を高めることを通じて、消費の本格的拡大につながるだろう。
2014年8月27日掲載


