1972年に日中国交正常化してから40年余りの歳月が流れたが、前半の20年間における日本経済の躍進に対して、後半の20年間では中国経済が目覚ましく台頭した。これを背景に、日本にとっての中国は、援助の対象から対等のパートナーに変わってきており、また、工場としてだけでなく、市場としての重要性も増している。しかし、領土問題や歴史認識などを巡る政治面での対立に妨げられ、両国間の補完性は十分に発揮されていない。
日本を上回る経済大国となった中国
1980年から2013年にかけて、中国のGDP規模は日本の27.9%から1.87倍へと急拡大してきた(図1)。また、世界貿易に占める日本のシェアが急低下しているのに対して、中国のシェアは急上昇している(図2)。これを背景に、輸出と輸入の面において、中国の日本への依存度が大幅に低下していることとは対照的に、日本の中国への依存度は大幅に上昇している(図3)。
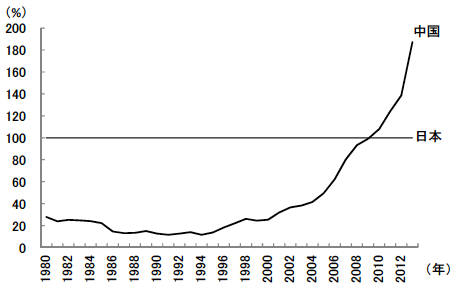
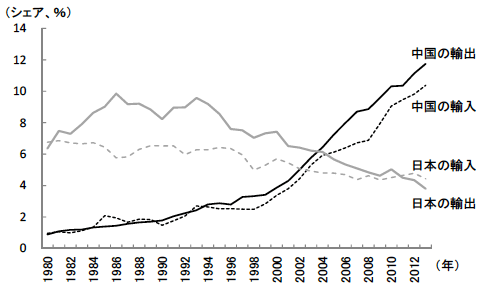
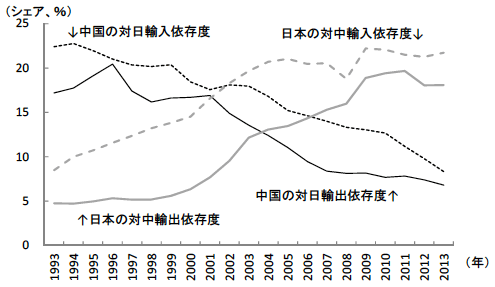
資金面では、中国は日本に次ぐ世界第二位の純債権国として浮上している。2013年末現在、中国の対外純資産は2.0兆ドルと、日本の3.1兆ドルには及ばないものの、外貨準備高は日本の約3倍に当たる3.8兆ドルに達している。また、政府による後押しもあり、中国の対外直接投資の規模も急増しており、フロー・ベースでは日本の水準に近づいてきている(図4)。今後、資本移動の自由化が進むにつれて、民間資本による海外へのポートフォリオ投資も増えると予想され、国際金融市場におけるチャイナ・マネーのプレゼンスは一層高まるだろう。
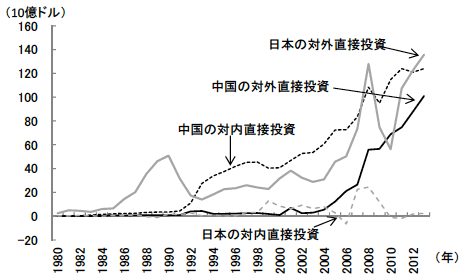
援助の対象から対等のパートナーへ
これを背景に、日本にとっての中国は、一次産品の供給国から輸出のための生産基地へ、そして市場へと変貌してきている。
1980年代には中国の輸出の主役は石油をはじめとする一次産品だった。しかし、1992年に「社会主義市場経済」が経済改革の目標として定められたことをきっかけに、中国は、輸出のための生産基地として世界中の企業から注目されるようになり、日本企業も、労働集約型製品を中心に、対中直接投資を増やした。その結果、中国の輸出に占める工業製品の割合が急速に高まり、この傾向は対日輸出においても顕著である。
さらに近年、中国は日本企業にとって、「工場」としてだけでなく、「市場」としての重要性も増している。経済産業省の「海外現地法人四半期調査」によると、2001年度から2013年度にかけて、中国(香港を含む)における日系企業の現地生産額は251億ドルから2,265億ドルに、そのうち、現地販売額は87億ドルから1,446億ドルに急増しており、現地販売比率も34.6%から63.8%に上昇している。これは現地市場を目指した自動車の生産拡大によるところが大きい。2013年の中国における自動車販売台数は2,198万台に達しており、世界一の規模となっている。乗用車に限ってみると、1,792万台に上り、そのうち、日系企業によるものは293万台に上っている(中国汽車工業協会データによる)。
その上、日中間の資金の流れは、「日本から中国へ」という一方通行から、「中国から日本へ」も加わった双方向に変わりつつある。
日本から中国への資金流入は、当初、政府開発援助(ODA)が中心だった。その大半を占めている円借款は、1979年に始まってから2007年に終了するまで、累計3兆3,164億円に達した(外務省データによる)。1990年代以降、中国における改革開放と経済発展が進むにつれて、民間企業による直接投資も増えるようになり、2013年末現在、対中直接投資の残高は10.3兆円に上っている(日本銀行、「直接投資・証券投資等残高地域別統計」)。
その一方で、近年、中国の対日投資も増えている。まず、レノボがNECのパソコン部門を傘下に収めたことや、ハイアールが三洋電機の白モノ家電部門を買収したことなど、中国企業による直接投資は、M&Aを中心に目立つようになった。中国企業にとって、直接投資は、技術やブランドなどを獲得するための有効な手段であり、日本企業にとっても、資金面の支援に加え、急成長する中国市場への足がかりを得られるというメリットが大きい。また、中国は外貨準備の運用の一環として、日本国債を大量に購入している。2013年末現在、中国による日本の債券の保有額は14.3兆円に上っている(日本銀行、「直接投資・証券投資等残高地域別統計」)。その大半は国債であり、中国は諸外国の中で日本国債の最大の保有国となっていると見られる。
日本企業にとっての商機
このように、中国はすでに日本を上回る経済力を持つようになった。しかし、中国は、GDP規模が日本を上回るようになったとは言え、人口が日本の10倍に上るため、2013年の一人当たりGDPが7,000ドル未満と、日本の約40,000ドルにはまだ遠く及ばない。また、平均寿命、乳児死亡率、第一次産業のGDP比、都市部のエンゲル係数、一人当たり電力消費量といった経済発展を示す指標を見ると、直近の中国の数字はおおむね1970年代前半の日本と同じ水準にあり、日中間の発展段階における格差は40年前後と見られる(表1)(注)。これは、両国が競合関係というよりも補完関係にあり、互いに協力する余地が十分に残っていることを意味する。
| 中国(直近) | 日本 | |
|---|---|---|
| 平均寿命(歳)注1 | 74.8 (2010年) | 74.8 (1976年) |
| 乳児死亡率(千分比) | 13.1 (2010年) | 13.1 (1970年) |
| 第一次産業のGDP比(%) | 10.0 (2013年) | 10.1 (1968年) |
| 都市部のエンゲル係数(%)注2 | 35.0 (2013年) | 35.1 (1966年) |
| 1人当たり電力消費量(kWh) | 3967 (2013年) | 4063 (1976年) |
| (注)1.平均寿命は男女平均 2.エンゲル係数は家計消費に占める食料費の割合 (出所)中国国家統計局『中国統計摘要』2014、中国衛生部『2013中国衛生統計年鑑』、『数字でみる日本の100年』国勢社(1986年)、厚生労働省『人口動態統計』、日本経営史研究所「日本電力業史データベース」より作成 | ||
ここで言う補完関係とは、「中国の強い分野において日本は弱いが、逆に中国の弱い分野において日本が強い」ことを指す。これは、「中国の強い分野において日本も強く、中国の弱い分野において日本も弱い」ことを意味する競合関係とは対照的である。実際、「製品間分業」の観点から見ると、日本と中国の得意分野は、それぞれハイテク製品とローテク製品に集中しており、サプライチェーンに沿った「工程間分業」においても、日本が付加価値の高い川上(研究開発やキーパーツの生産)と川下(マーケティング、アフターサービス)の工程において強く、中国の強みは組み立てなどの製造過程に限られている(図5)。競合関係は、一方が得すれば、もう一方が損するというゼロサムゲームになるが、補完関係は、双方が得するウィンウィンゲームになりうる。
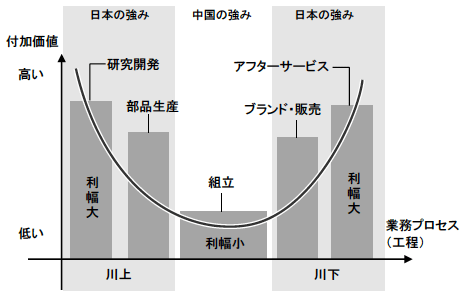
具体的に、日本企業にとって、中国の次のような分野において、多くのビジネス・チャンスが期待できる(日中経済協会、『日中経済産業白書2013・2014―速まる中国の構造変化と日中ビジネス再構築』、2014年)。
- ①都市建設とインフラ整備=スマートコミュニティ、エコシティ、分散型エネルギー、発電設備、都市交通(地下鉄、都市交通制御システム)、鉄鋼、汚水排水処理設備、ごみ処理設備、廃棄物回収・再利用、通信ネットワーク、住宅・事務所・商業施設建設、建設機械
- ②ビルファシリティ=エレベーター、空調システム、照明、BEMS(ビルエネルギー管理システム)
- ③交通=電気自動車(EV=乗用車、バス)、EV用電池・モーター
- ④一般消費財=住宅内(家具、家電製品など)、事務所内(パソコン、複写機などの事務機)
- ⑤サービス・流通
- ⑥ヘルスケア(予防、診断、治療、予後など)
- ⑦食の安全(植物工場、無農薬・有機栽培、物流システムなど)
- ⑧介護、養老(施設=ハードとソフト、高齢者ホーム運営管理、福祉介護サービスなど)
- ⑨環境保護(大気・水・土壌の汚染対策)、省エネ
- ⑩娯楽(アニメ、映画など)
- ⑪その他(飲食関係、人材教育・派遣業、学校、学習塾、病院、アパート・マンション管理、コンビニエンスストア、養殖・畜養、金融サービスなど)
ウィン・ウィンの前提条件となる政治関係の改善
残念なことに、ぎくしゃくしている日中間の政治関係に翻弄されて、このようなビジネス・チャンスは必ずしも十分に活かされていない。勢いを増す各種の中国脅威論も、対中ビジネスに水を差している(BOX)。その影響は、特に2012年9月に中国各地で発生した大規模な反日デモ以降、顕著になってきている。
2013年11月に国際協力銀行が発表した「わが国製造業企業の海外事業展開に関する調査報告-2013年度海外直接投資アンケート結果(第25回)」によると、中期的(今後3年程度)有望事業展開先国・地域として、中国は調査開始以来維持してきた第1位から、インドネシア、インド、タイに次ぐ第4位に後退し、得票率(複数回答可)も2012年の62.1%から37.5%に急落した。
実際、日中関係が悪化する中で、多くの日本企業は、リスクの分散化を図るために、中国への投資を行いつつもあえて集中させず、平行して他の国へも一定規模の投資を行う「チャイナ・プラス・ワン」という戦略を本格化させている。これを反映して、2013年に、日本の対中投資は、前年比17.6%減少している(円ベース、財務省、「国際収支状況」)。また、2009年に初めて対米を抜いた対中輸出は2013年に再び逆転されており、世界輸入に占める中国のシェアが増え続けているにもかかわらず、日本の輸出に占める中国のシェアは、2011年の19.7%をピークに、2013年には18.5%に低下している(財務省、「貿易統計」)。その一方で、中国の日本離れは、日本の中国離れ以上に進んでおり、中国において、日本の存在感は、欧米と比べてますます薄れている。
今後も、日中関係においては、経済面での緊密化と政治面での対立という二つの力が同時に働くだろう。確かに、マルクスが主張しているように、最終的には経済基礎が政治という上部構造を変化させ、経済関係が深まれば、政治関係も改善されるだろう。しかし、短期的には、政治関係の悪化がすでに経済関係に悪影響を与えている。両国は、こじれた関係の改善を模索しているが、今年の11月に北京で開催されるアジア太平洋経済協力(APEC)首脳会議に合わせて、2012年5月の野田首相(当時)訪中以降途絶えている日中首脳会談が実現できれば、それに向けた大きい一歩となろう。
BOX 中国脅威論の論点整理
中国の急速な台頭を背景に、日本では、各種の中国脅威論が浮上してきた。警戒の対象となる分野は、安全保障にとどまらず、経済、資源・環境にも及んでいる。また、中国の脆弱性に着目する「チャイナ・リスク論」も盛んである。以下、それぞれの論点を簡単にまとめる。
- 軍事脅威論
- 日本は、近年の中国における軍事拡張を強く憂慮している。2014年7月に明らかになった平成26年版の『防衛白書』の概要は、2013年11月に中国が東シナ海の広い範囲に防空識別圏を設定したことについて、「現状を一方的に変更し、事態をエスカレートさせ、不測の事態を招きかねない非常に危険なものだ」として強い懸念を示している。また、東シナ海や南シナ海で海洋進出を強める中国について、「国際法秩序とは相いれない独自の主張に基づき、力を背景とした現状変更の試みなど、高圧的とも言える対応を示している」と指摘したうえで、公表された国防費が過去26年間でおよそ40倍となっていることなどを挙げて強い警戒感を示している。(NHK、朝7時ニュース、2014年7月17日)。
- 経済脅威論
- 中国は安い労働力を武器に、安い製品を大量に生産し他国に輸出することで、日本の雇用を奪い、産業空洞化とデフレをもたらしている。また、中国は、人民元レートや労働者の福祉を人為的に抑えながら、知的財産権の侵害や環境破壊を放置することで、生産コストを抑え、日本を不公平な競争に晒した。中国発デフレは、日本経済の長期低迷の主因だと見る論調も一部で見られる。
- 資源・環境脅威論
- 中国経済の高成長は、資源の大量投入によって達成され、その大半は海外からの輸入に頼っている。その結果、世界的に資源価格が高騰してきており、長期的には石油などの一部の資源の枯渇に拍車をかけている。また、中国はすでに米国を抜いて世界一のエネルギー消費国と二酸化炭素(CO₂)排出国となっており、資源、中でもエネルギーの大量消費は、自国内にとどまらず、地球環境の悪化にもつながっている。日本では、以前から黄砂や酸性雨など、中国発の環境問題の悪影響が懸念されてきたが、近年、食品安全問題とPM2.5による深刻な大気汚染問題がクローズアップされたことは、日本企業の中国離れに一層拍車をかけている。
- チャイナ・リスク論
- 中国の台頭を前提とする上述の各種の中国脅威論とは対照的に、「チャイナ・リスク論」は、中国の脆弱性に注目している。まず、中長期的な問題として、労働力の供給に制約されて中国の潜在成長率が急速に低下していることが挙げられる。また、短期的には、不動産バブルの崩壊に伴って、中国も1990年代以降の日本と同じように、長期低迷に陥る恐れがある。さらに、少数民族の不満や、所得格差の拡大、官僚の腐敗といった社会問題も深刻化している。このようなマクロ面のリスクに加え、両国間の歴史認識や領土問題を巡る対立も、日本企業が対中ビジネスを展開する際の大きなリスクの一つと見なされている。
2014年8月5日掲載


