中国人民銀行(中央銀行)は6月19日に、為替相場メカニズムの改善の一環として、人民元相場の柔軟性を一段と高めると表明し、週明けに2008年7月以来続いた事実上のドルペッグ制を終了し、人民元の切り上げを再開した。近年、日本では、中国が低賃金を武器に輸出を増やしてきたことが国内のデフレの原因とされるだけに、人民元の切り上げがデフレの解消に寄与すると期待される。しかし、日中両国の経済構造は競合的というよりも補完的であることを考えれば、人民元の切り上げに伴う中国発インフレは、日本製品の競争力の向上よりも、生産コストの上昇につながる可能性が大きく、日本の景気への影響はむしろマイナスである。
中国発デフレから中国発インフレへの転換
振り返ってみると、中国発デフレから中国発インフレへの転換点は、人民元がドルペッグ制から「管理変動制」に移行した2005年7月頃に遡る。その頃から、人民元の実質実効為替レートは、それまでの低下傾向から上昇に転じ、2008年7月以降、ドルペッグに復帰してからも、上昇傾向が続いた(図1)。その背景には、中国が発展の過程における完全雇用の段階(いわゆる「ルイス転換点」)に差し掛かっていることがある(BOX)。
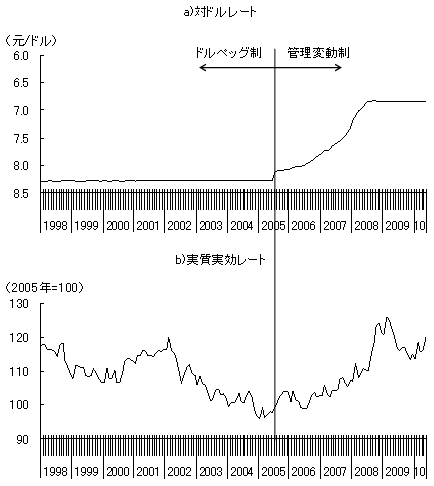
中国では、長い間、労働力が過剰であっため、生産性の上昇は賃金の上昇よりも、むしろ製品価格の低下につながった。その結果、廉価な中国製品が世界中に溢れ、世界経済に中国発デフレをもたらした。しかし、ここに来て、農村部における過剰労働力の枯渇を反映して、労働力が急速に過剰から不足に変わってきており、賃金上昇、ひいてはインフレが加速している。インフレを抑えるために、当局は人民元の切り上げを容認しなければならない。インフレと元高のいずれのケースにおいても、外貨建てで見た中国製品の価格が上昇し、中国発デフレが中国発インフレに変わることになる。
「良い中国発インフレ」Vs「悪い中国発インフレ」
日本にとって中国は最大の輸出先であると同時に最大の輸入先でもあり、元高は日本にインフレの圧力をもたらす。しかし、これは必ずしも生産規模の拡大につながるとは限らない。ここでは、生産規模の拡大をもたらす「良いインフレ」と生産規模の縮小を招く「悪いインフレ」を区別した上、人民元の切り上げの日本経済への影響について考える。
日本が期待しているのは、言うまでもなく「良いインフレ」のケースである。すなわち、中国の輸出価格が高くなれば、日本国内だけでなく、第三国の市場においても需要が中国製品から日本製品にシフトする。これは日本の物価の上昇だけでなく、日本の生産の拡大をもたらす(図2a)。
一方、中国発インフレには、「悪いインフレ」いう側面も考えられる。すなわち、中国から様々な部品や中間財を輸入している日本企業にとって、人民元の切り上げによる中国からの輸入価格の上昇は、生産コストの上昇を意味する。その場合、日本の物価は上昇する反面、生産は低下する(図2b)。
-日本(先進国)にとっての影響-
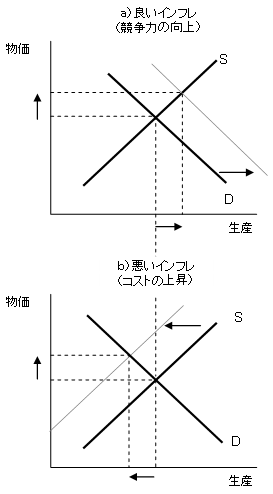
日本に「悪いインフレ」をもたらす「元高」
日本にとって、元高による「良いインフレ」と「悪いインフレ」の効果のうち、どちらが大きいのかを考える際、日中の経済関係が競合的と見るのか、補完的と見るのかによって結論が異なってくる。日中が競合的と見た場合は、需要側の効果が大きくなり、生産に与えるプラスの影響が大きいことになるが、日中が補完的であると見た場合、供給側の効果が大きいため、生産に与えるマイナスの影響の方が大きくなる。
実際、日本と中国の輸出構造は、前者が付加価値の高いハイテク製品、後者が付加価値の低いローテク製品が中心になっているように、互いに競合している部分は低く、両国経済が補完関係にあることは明らかである。そのため、元高になっても、中国製品から日本製品への需要のシフトはそれほど起こらず、むしろ輸入コストの上昇は、日本における生産の縮小につながる可能性が大きい。
もっとも、人民元の切り上げは、「価格効果」だけでなく、「所得効果」を通じても、日本経済に影響を与える。確かに、中国では元高に伴い、消費者の実質所得が増え、日本製品への需要も増えるが、その一方で、輸出が減速することから、日本からの中間財の輸入が逆に減る。両者が相殺し合った結果、元高に伴う「所得効果」の日本経済への影響はほぼ中立であると見られる。
このように、「価格効果」と「所得効果」を合わせて見ると、人民元の切り上げは、必ずしも日本の景気回復に寄与するとは限らない。同じロジックは、日本と同様に中国と補完する米国をはじめとする先進国にも当てはまる。
「元高」は「円高」要因にならない
人民元の切り上げの影響は、主要国の物価と生産にとどまらずに、金利と為替レートにも及ぶ。元高は、中国発デフレが中国発インフレに変わるきっかけとなる以上、中国から大量に輸入している先進国にとって、金利上昇要因になる。特に、人民元の切り上げは、人民元レートが均衡水準に近づくことを意味し、切り上げが行われなかったときと比べて、ドル買い・人民元売りの介入の規模が小さくなる。その分だけ、中国の外貨準備の上昇、ひいては米国債の購入が抑えられることになる。その結果、米国金利は、日本など他の先進国よりも上昇幅が大きくなる。日米の金利差の拡大を反映して資金が円建て資産からドル建て資産に流れれば、「円が人民元につられてドルに対して上昇する」という市場の「常識」に反して、元高はむしろドル高・円安要因になると理解すべきである。
BOX 完全雇用の達成で顕著になるバラッサ・サミュエルソン効果
国際経済学の教科書にも登場しているバラッサ・サミュエルソンの仮説が主張しているように、一般的に、高成長をしている国ほど為替レートが強くなるという傾向が見られている。これは、成長性の低い国よりも、成長性の高い国において、製造業を中心とする貿易財部門とサービスを中心とする非貿易財部門における生産性上昇率の格差が大きいことを反映している。
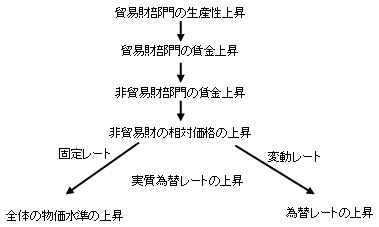
具体的に、高成長をしている国の場合、貿易財部門(たとえば、電子産業)では、生産性の上昇率が高く、それに見合った形で賃金が上昇する。しかし、統一した国内の労働市場を前提にすれば、賃金の裁定関係が働くため、非貿易財部門(たとえば、床屋)において、生産性がそれほど上がらなくても、賃金水準が貿易財部門並みの水準に上がってしまう。その結果、非貿易財の価格が貿易財に対して相対的に上がる。
非貿易財の貿易財に対する相対価格の上昇は、次のいずれかのルートを通じて、実質為替レートの上昇をもたらす。まず、固定相場制の場合は、貿易財において「購買力平価」(PPP)が成立し、海外での価格が所与のものとすれば、貿易財の価格は変わらないが、相対価格の変化は、サービス価格の上昇、ひいては全体の物価水準の上昇という形で現れる。もし政府はインフレを容認できないというのであれば、為替レートを切り上げるという形で対応しなければならない。その場合は、物価の代わりに為替レートが上昇する。いずれのケースにおいても、実質為替レートが上昇することになる。
バラッサ・サミュエルソンの仮説は、1970年代から90年代にわたって見られた円高の説明によく使われている。これに対して、これまで中国では、農村部で多くの労働力が余っていたことを反映して、貿易部門の生産性の上昇は必ずしも十分賃金上昇にはつながっていなかったため、経済の高成長にもかかわらず、人民元は、中長期にわたって、名目ベースでも、実質ベースでも、上昇傾向が見られなかった。しかし、中国は完全雇用を達成することを意味するルイス転換点を通過することにより、バラッサ・サミュエルソンの仮説通りに、高成長に合わせた形で人民元も強くなりつつある。
2010年6月29日掲載


