中国では、これまで目覚しく成長してきた沿海地域(東部)と比べて内陸部(中部と西部)の成長が遅れているため、地域間の格差が大きくなってきた(図1)。これに対して、2002年に誕生した胡錦涛政権は、「調和の取れた社会」の実現を目指すべく、「西部大開発」や「中部勃興」、「東北振興」など、地域格差を是正する方策に積極的に取り組むようになった。その一環として、沿海地域から内陸部への産業移転を進めてきた。戦後のアジア地域において多くの産業が先発国から後発国に段階的に移されてきたことは「雁行形態」と呼ばれているが、中国が目標としているのはその国内版に他ならない。2007年以降、その効果はようやく現れ始め、経済成長率が従来の東高西低型から西高東低型に転じている。今後、中西部が東部を追い上げる形で、地域格差が縮小に向かう可能性が出てきた。
(2008年1人当たりGDP)
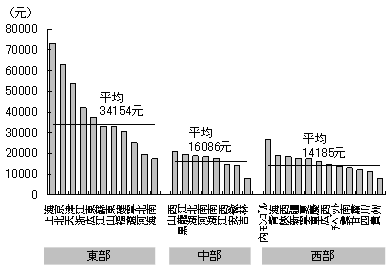
これまでの30年間、東部は、労働集約型製品の生産と輸出を梃子に高成長を遂げたが、近年、人民元レートの上昇や、賃金と土地の価格の上昇に見舞われ、労働集約型産業は競争力を失ってきている。より安い労働力と土地を求めて、外資系企業のみならず、中国企業も直接投資などを通じて、生産拠点を移転せざるを得なくなってきており、中西部が投資先として注目されている。
産業の移転を支援するために、商務部は2006年からの3年間で約1万社の海外企業と東部企業が中国の中部および西部へ投資するよう推進する「万商西進」というプロジェクトを進めている。その具体的措置として、中西部地域における経済開発区のインフラ整備、人材の育成、中部地域投資貿易博覧会の開催、西部横断高速物流ルートの構築などが実施されている。
続いて、商務部は、2007年11月と2008年4月の二回にわたって中西部地域において計31の加工業の重点移転先を認定し、それに合わせて関連プロジェクトに対し融資などの面において優遇措置をとることとした(図2)。これを通じて全国の加工貿易に占める中西部の割合を5ポイント上げることを目標としている。
さらに、今年の人民代表大会における温家宝総理の「政府活動報告」においても、「中西部地区における産業移転受け入れの具体策の検討、制定を急ぐ」ことや、「輸出指向型加工業の中西部への移転を奨励する」ことが2009年度の主要任務として取り上げられている。
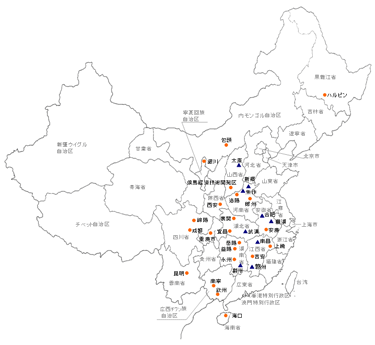
[ 図を拡大 ]
政府の呼びかけに応える東部企業は多く、履物や、アパレル、プラスチック製品といった労働集約型産業を中心に、中西部への産業移転が盛んになってきた。財政移転の拡大も加わり、2007年以降のGDP成長率、社会消費品小売売上、都市部の固定資産投資、輸出といった主要なマクロ経済指標の伸びをみると、東部よりも中部、中部よりも西部が高いという傾向が顕著になってきた(表1)。
2009年に入ってから、世界的金融危機の影響を受けて、中西部も東部と同じように、輸出の大幅な落ち込みを余儀なくされているが、東部(中でも上海、浙江省、広東省)と比べて中西部は輸出への依存度が低いため、世界経済の減速から受けた悪影響は比較的軽い。その上、昨年11月に発表された4兆元に上る景気対策の主役となる公共投資が中西部、中でも西部に傾斜していることを反映して、2009年第1四半期のGDP成長率は、西部が10.5%、中部が7.8%、東部が7.2%と、「西高東低」という構図が定着している(図3、図4)(注)。
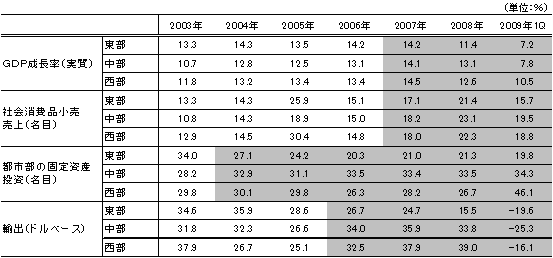
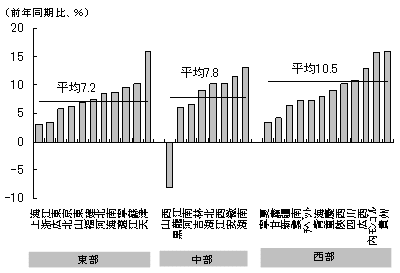
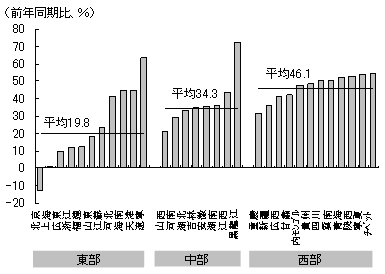
多くの国の経験から、地域間の格差は発展の初期段階において拡大し、ある程度の所得水準に達してから改善に向かうという傾向が観測される(「クズネッツ仮説」)。中国においても、30年間の高成長を経て、産業の移転の加速をきっかけに、これまで拡大してきた地域間の格差はようやく転機を迎えようとしている。
2009年6月5日掲載


