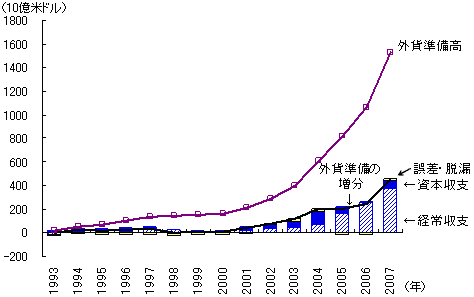近年、中国の国際収支黒字の拡大とそれに伴う外貨準備の急増に象徴されるように、人民元は上昇圧力にさらされているが、国内経済への悪影響の懸念から、中国政府は、人民元の切上げには慎重である。しかし、為替レートの安定を維持するために、当局は外為市場に介入し続けなければならないため、外貨準備が急増する一方で、国内市場での流動性も膨張している。その結果、株式や不動産といった資産バブルの膨張や、インフレの高騰など、それに伴う弊害がすでに顕在化している。また、金融政策は為替レートの安定という目標に割り当てられているため、マクロ経済を安定化させる手段として十分に活かされていない。対外不均衡を是正し、金融政策の独立性を回復させるためには、中国は、当局が原則として市場に介入せず、為替レートの需給を市場に委ねるという「完全変動相場制」に移行しなければならない。
中国における変動相場制への模索は、2005年7月に行われた「人民元改革」から始まった。これをきっかけに、中国は従来の「ドルペッグ」から「管理変動相場制」に移行した。しかし、その後も、為替政策の重点は「変動」よりも「管理」に置かれており、人民元の上昇を抑えるために、当局が日々大規模な市場介入を続けている。その結果、金融政策の独立性は大きく制約されたままである。
中国が置かれているこのような状況は、固定相場制から変動相場制への移行を迫られていた1970年代初めの日本と類似している。日本は、1971年のニクソン・ショックをきっかけに、紆余曲折を経て1973年2月に変動相場制に移行した。いずれの場合においても、マクロ経済環境だけでなく、為替政策を中心に交わされている政策論争についても、多くの共通点が見られている。ここでは、中国の現状を踏まえて、当時の日本の経験を振り返り、その中から中国が学ぶべき教訓を明らかにする。
1.未完の人民元改革
中国では2003年頃から、外貨準備が急増しており、2008年6月には1.8兆ドルに達している。外貨準備が急増している背景には、貿易を中心とする経常収支と直接投資を中心とする資本収支のいずれも大きな黒字(いわゆる「双子の黒字」)を計上していることがある(図1)。本来、完全変動相場制の下では、当局が一切外国為替市場に介入せず、外貨準備が増えないことになる。現在の日本のように、仮に経常収支が黒字になっても、資本収支の赤字によって自動的に相殺される。中国の外貨準備が増え続けることは、当局が為替レートの上昇を抑えるために、言い換えれば、為替レートを市場の均衡水準より割安の水準に維持しようとするために、介入し続けた結果に他ならない。介入が控えられるようになれば、外貨準備が上昇する代わりに、元高が進むはずである(図2)。
このような市場の圧力に並行して、米国をはじめ、中国の主要な貿易相手国から人民元切上げを求める声も漸次に高まった。当初、中国当局は、「元高」に伴う輸出の減速や、雇用の悪化、デフレ圧力などを懸念したため、切上げには消極的であったが、その後、市場と外国政府からの圧力がさらに高まったことを受けて、2005年7月21日に、ついに人民元の2.1%の切上げを実施すると同時に、これまで採ってきたドルペッグから離脱し、「人民元レート形成メカニズムを改善するための改革」(「人民元改革」)に踏み切った。
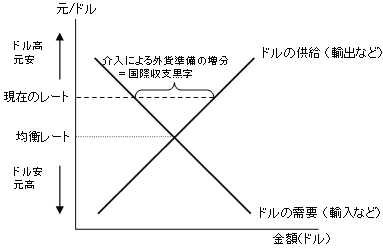
その際、中国人民銀行(中央銀行)のスポークスマンは、なぜ人民元レート形成メカニズムの改革を行う必要があるのかについて、次のように説明している(中央銀行スポークスマン、「なぜ中国は人民元レート形成メカニズムを改善するための改革を行うのか」、2005年7月21日、新華社電)。
「人民元レート形成メカニズムの改革推進は、対外貿易の不均衡の緩和や内需の拡大、企業の国際競争力の向上、対外開放水準の向上への必要によるものだ。ここ数年来、中国(の対外貿易収支)は経常項目、資本項目ともに黒字が拡大し、国際収支のアンバランスを激化させている。2005年6月末現在、中国の外貨準備高は7110億ドルに達した。今年(2005年)に入り貿易黒字は急速に伸び、貿易摩擦がさらに深刻化している。」
これを踏まえて、人民元レートの水準を適切に調整し、レート形成メカニズムを改革することには、次のようなメリットがあると指摘した。
(1)内需を中心とする持続可能な経済発展戦略の徹底や、資源配分の改善に役立つ
(2)金融政策の独立性の強化、金融調節の主体性と有効性の向上に役立つ
(3)輸出入の基本的バランスの維持、交易条件の改善に役立つ
(4)物価の安定維持、企業コストの縮減に役立つ
(5)企業の経営体制の転換促進、自主開発能力の強化、対外貿易の成長方式転換の加速、国際競争力とリスク対応力の向上に役立つ
(6)外資導入構造の改善、外資の利用効率の向上に役立つ
(7)国内・海外両方の資源と市場の十分な利用、中国の対外開放水準の向上に役立つ
これらの目標を達成するために、新しい制度においては、人民元レートをドルのみに連動させるのではなく、国内・海外の経済金融情勢に応じ、市場の需給を基礎に、通貨バスケットで計算した人民元の多国間実効為替相場を参考にして、人民元レートへの管理と調整を進め、人民元レートの合理的でバランスの取れた水準での基本的安定を維持するとしている。通貨バスケットを参考にすることは、外貨間のレート変動が人民元レートに影響することを意味するが、通貨バスケットへのペッグ制をとるのではなく、さらに市場の需給関係をもう一つの重要な根拠として、管理された変動相場が形成されるのである。
2.人民元改革への評価
2005年7月に採用された為替制度について、中国人民銀行貨幣(金融)政策委員会委員(当時)である余永定氏は、国際金融の教科書にも登場するBBC方式であり、変動幅(Band)、通貨バスケット(Basket)、そしてクローリング(Crawling、ある方向性を持って為替レートを微調整していくこと)に基づく「管理変動相場制」だと解説している(「人民元為替制度改革という歴史的決定」、『金融時報』、2005年7月23日)。しかし、新しい制度が導入されてからも、人民元の対ドル上昇は当局の市場介入によって抑えられ、為替政策の運営に当たっては「変動」よりも「管理」に重点が置かれている。それを反映して、当初、人民元の対ドル上昇は年率1%程度にとどまっていたが、2007年以降、インフレ対策の一環として、当局は切上げのペースを加速させている(図3)。
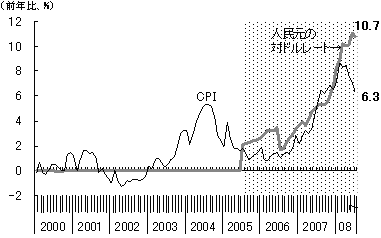
「人民元改革」が始まってから三年以上の歳月が経ったが、振り返ってみると、当局が目指した7つの目標の中の(1)、(3)、(5)、(7)番目に関しては、それなりの成果を挙げているが、(2)、(4)、(6)番目はまだ達成できていない。(周昆平、唐建偉、「為替レート形成メカニズム改革は依然として任重くして、道遠し」、『上海証券報』、2008年7月22日)。
概ね達成できた目標については、次のように評価されている。まず、(1)番目に関しては、輸出が減速している中で、消費が比較的堅調に推移している。また、(3)番目に関しては、貿易収支が、2008年に入ってからようやく低下傾向に転じている。さらに、(5)番目に関しては輸出に占める繊維などの労働集約型製品のシェアが低下し、その代わりに機械など資本、技術集約型製品のシェアが高まっている。最後に、(7)番目に関しては、中国の対外直接投資が急速に増えており、中国経済の対外開放はもっぱら外資企業に「来てもらう」段階から、中国企業も「出て行く」という段階に来ている。
一方、達成できていない目標に関しては、次のような改善すべき課題が残っている。まず、(2)番目に関しては、人民元切上げの期待が続く中で、大量の短期資金(ホット・マネー)が中国に流入している。それに伴う人民元の上昇を抑えるために、当局は大規模な外為市場への介入を続けざるを得ず、これは流動性の膨張を招き、金融政策の独立性を大幅に制約している。
また、(4)番目に関しては、市場介入に伴う流動性の膨張は、インフレの加速につながっている。原油など一次産品の国際相場の急騰や、円やユーロといった主要通貨のドルに対する上昇も加わり、人民元のこれまでの対ドルの緩やかな切上げでは、輸入インフレを抑えるのに不十分であった。
さらに、(6)番目に関しては、人民元の切上げを見込んだホット・マネーは資本流入の大半を占めるようになった。このような資金の流入は、金融政策の舵取りを困難にしているだけでなく、短期間で引き揚げられ、金融危機を誘発しかねないリスクも孕んでいるという。
このように、2005年7月に行われた為替制度の変更は、あくまでも人民元改革への第一歩にすぎず、これらの目標を達成するために、今後、完全変動相場制に向けて、当局はできるだけ介入を減らし、為替レートの決定を市場に委ねなければならない。
3.日本の変動相場制への移行過程
中国が直面しているこのような状況は、ニクソン・ショック前後の日本と似ている。ブレトンウッズ体制の下で日本は1ドル=360円の固定相場制を採用し、これを維持することは政策の最優先課題であった。しかし、1960年代になると、基軸通貨国である米国では、資本流出を反映した国際収支の慢性的な赤字が続き、ドルの信任が揺らぎ始めていた。その一方で、日本は高度成長期を経て、輸出の国際競争力が高まり、1968年頃から国際収支は赤字基調から黒字基調に転じた。黒字幅が拡大するにつれて、1967年まではわずか20億ドル前後で推移していた外貨準備は、1970年末には44億ドル、ニクソン・ショック直前の1971年7月末には79億ドルへ急激に拡大した(図4)。こうした中で、円の切上げ観測は日増しに高まっていった。
-変動相場制への移行期を中心に-
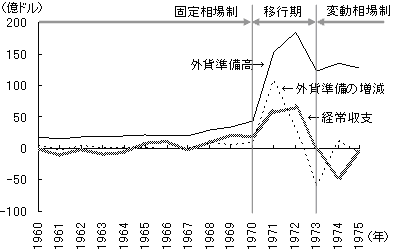
特に、1971年に入ると米国は貿易収支が戦後初めて赤字に転落したにもかかわらず、景気拡大を目指して3回の公定歩合の引き下げを実施し、ヨーロッパ諸国との金利差が拡大した。ドル切下げ観測も加わり、大量の投機的資金が米国からヨーロッパに向かった。こうした中で、5月に西ドイツは変動相場制に移行し、これを受けて、円が次の投機のターゲットとなり、円の切上げ圧力はいっそう高まった。
このような国際通貨不安が続く中で、ニクソン米大統領は1971年8月15日に、ドルと金の交換停止、10%の輸入課徴金の賦課などを内容とする「新経済政策」を発表した。これに対応するために、ヨーロッパ諸国は一時為替市場を閉鎖したが、翌週の月曜日23日から為替市場が再開された時に、変動レートを容認せざるを得なかった。これに対して、日本は為替市場を閉鎖せず、1ドル=360円を守るためにドル買い介入を続けたが、8月28日についにヨーロッパ諸国に追随し、変動相場制に移行した。その間の介入規模は40億ドル(当時の輸入のおよそ4ヶ月分相当)に上った。
当時、変動相場制はあくまでも一時的避難措置であると認識され、主要国の間では平価の調整を経て再び固定相場制に復帰するための模索が続いた。そして、1971年12月に主要10ヵ国蔵相・中央銀行総裁が出席したスミソニアン会議において、主要国通貨の対ドルレートの調整が合意され、円の対ドルレートは従来の360円から308円へと切上げられた。
スミソニアン体制が発足してからも、米国の貿易赤字の拡大を背景に、ドルに対する不信が深まり、円の上昇圧力は収まらなかった。日本では、円の再切上げを防ごうと、金融緩和が行われたが、当局による外為市場へのドル買い・円売り介入の影響も加わり、流動性が膨張し、物価と株価が急騰した(図5)。1973年に入ると、世界的な通貨危機が再燃したことを背景に、日本は2月14日に、主要各国も3月に相次いで変動相場制に移行し、スミソニアン体制はわずか一年あまりで崩壊することになった。
日本が変動相場制に移行してからも、円の上昇圧力が止むことはなく、円高傾向は対ドルレートが一時80円を突破した1995年4月まで続いた。また、資本移動に関する多くの規制が維持され、資本取引の本格的な自由化は、外国為替及び外国貿易法(外為法)の全面改正が実施された1980年12月まで、実需原則(先物為替取引を輸出入等の実需に基づく場合のみ認めること)の撤廃に至っては、1984年まで待たなければならなかった。さらに、ダーティ・フロートという言葉に象徴されるように、市場介入を止めることはなかった。しかし、変動相場制への移行により円レートの均衡水準からの乖離が解消されたことを背景に、介入の狙いは、円高を阻止することから、為替レートの乱高下を防ぐことに変わった。日銀が完全に介入しなくなったのは2004年3月17日以降である。
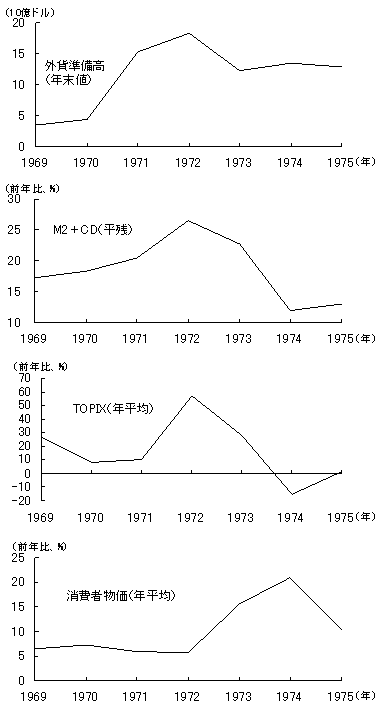
4.日本の変動相場制への移行に関する評価
ニクソン・ショック前後の日本では、強い円高脅威論ないし円高回避論が当局者の間では支配的であった。為替レートを変更しないということを前提に、国際収支における黒字を減らす政策として、
(1)輸出抑制・輸入増進による経常収支対策(金融および税制上の輸出優遇措置の撤廃、輸入奨励のための規制緩和措置、輸入自由化の徹底)
(2)対外投資・対外援助の促進などによる資本収支対策
(3)総需要拡大のための財政・金融政策(拡張的財政支出政策、金融緩和政策)
(4)調整的インフレ政策(国内物価水準上昇政策、貨幣賃金率の引き上げ政策)
を中心とする「円対策8項目」が実施された(「総合的対外経済対策の推進について」、1971年6月」)。
これに対して、1971年7月10日に36人の経済学者によって構成された「為替政策研究会」(代表幹事:天野明弘神戸大学教授、小宮隆太郎東京大学教授)は、当時の日本の国際収支が、大幅な受け取り超過を続け、明らかに「基礎的不均衡」に当たるという認識を示した上、ポリシー・ミックスという観点から、「国際収支の均衡という目標には為替レートの変更を最優先的に割り当て、その他の目標を達成するには他の手段を用いるのが適切な政策目標と手段の組合せである。」と反論した。これを踏まえて、できるだけ早い時期に次のように、「円の小刻み切り上げ」(クローリング・ペッグ)を実施することを提言した(切上げを支持する具体的な理由については、BOX参照)。
「1回の平価変更の幅は1%以内とし、3ヵ月ないし5ヵ月に一回ずつ、したがって1年間を通じて2.4ないし4%程度の速度で、その時々の情勢を考慮しながら、国際収支の黒字が解消し、累積した過大な外貨準備が減少するまで調整を続ける。この場合、日本銀行が市場レートの急変を避けるよう為替市場に介入することが望ましい。変更の頻度と幅については、固定的に考える必要はなく、毎月1回0.2ないし0.3%程度とする方式も考慮に値する。」(為替政策研究会、「円レートの小刻み調整についての提言」、『季刊現代経済』、第2号、1971年9月に掲載)。
「為替政策研究会」は、小刻み調整の利点として、次の4つを挙げている。まず、大幅な平価変更の場合と異なり、投機ないしヘッジングを目的とする短期資本の移動の誘因を生じない。第二に、調整が徐々になされるため、各産業における適応が容易である。第三に、最終的な切上げ幅をあらかじめ決める必要はなく、黒字が解消し過大な外貨準備が減少するまで調整を続ければよい。もし情勢が逆転すれば逆の調整(切下げ)を行うこともできる。最後に、特に日本の場合、この方式はIMF協定に抵触せず、日本政府の決断により実行できる。
一方、ニクソン・ショックを受けた当局の対応に関しては、小宮隆太郎氏と須田美矢子氏は、共著の中で「当時の日本経済のマクロ的状況からみれば、円のフロート移行は遅きに失したとの感を免れない。田中首相が円の『再切り上げを避けるためにあらゆる措置を取らなければならない』と述べ、スミソニアン・レートをあくまでも堅持する方針を示したため、為替当局の選択範囲が狭まってしまったのは、不幸なことであった。......日本政府は自らの主体的な選択によって、もっと速やかに、たとえば、1972年秋に、スミソニアン・セントラル・レートを調整するか(円の再切り上げ)、それともフロートに移行すべきであった。」と批判している。また、第一次石油危機が勃発した73年10月の前からインフレはすでに進行していたことに着目し、1972年秋当時、政府・日銀が円の再切り上げの回避を最優先の目標と考えて進めていた拡張的マクロ経済政策が、1973~74年の狂乱物価を招いたと断じている(『現代国際金融論-理論・歴史・政策(歴史・政策編)』、日本経済新聞社、1983年)。
5.日本の経験から学ぶべきもの
このように、現在の中国は、1970年代初めの日本と同じように、固定相場制から変動相場制への移行期にあるが、当時の日本の経験と教訓から何を学ぶべきだろうか。
まず、「為替政策研究会」の「提言」で取り上げられている切上げの是非を巡る議論は、現在の人民元問題を考える上でも、多くの示唆を与えている。中でも、国際収支黒字の増大とそれに伴う外貨準備の累積の弊害に関する指摘や、政策と手段の最適な組み合わせを目指したポリシー・ミックスという発想、「輸出増進や外貨獲得こそ国益だ」という重商主義への批判などは、現在の中国にもそのまま当てはまる。
第二に、当時の日本では、切上げや変動相場制への移行には抵抗が強く、このことは、当局の対応を遅らせる原因となった。しかし、無理して介入を通じて割安な為替レートを維持しようとした結果、流動性の膨張、ひいてはインフレの加速と資産バブルを招いてしまった。残念ながら、中国は、この教訓を活かすことができず、近年、同じような状況を許してしまった。
第三に、貿易財部門(製造業)において生産性の上昇の高い国では、実質為替レートが長期にわたって上昇圧力にさらされるため、物価の安定と為替レートの安定を同時に達成することは困難である。当局は、物価の上昇か為替レートの上昇というトレードオフ関係に沿って、政策目標を選択しなければならない。変動相場制に移ってからの日本は、物価の安定を優先し、円高を容認したが、もし為替レートの安定を維持したならば、インフレ率がもっと高かったはずである。
第四に、資本取引の自由化は変動相場制の前提条件とされているが、中国は資本取引の自由化が遅れており、それを推進していく条件も整っていないことを理由に、変動相場制への早期移行に反対する意見がある。しかし、1970年代における日本の経験は、資本規制を維持しながらも、変動相場制への移行が可能であることを示している。
第五に、2005年に実施された「人民元レート形成メカニズムを改善するための改革」と、1971年に行われた「為替政策研究会」による「円レートの小刻み調整」という提言は、ともにクローリング・ペッグと分類される一種の「管理変動相場制」である。ニクソン・ショックをはじめとする内外情勢の急激な変化を受けて、日本は、「円レートの小刻み調整」が実施されることがないまま、変動相場制に移行したが、中国においても現行の制度はあくまでも移行期の措置だと理解されるべきである。すでにその限界が明らかになっており、完全変動相場制に向けて、さらなる改革が求められている。
最後に、当時の日本は参考となる他の国の経験がなく、準備も不十分なまま、固定レートを維持するためにあらゆる手段を使い果たした段階で、変動相場制への移行を余儀なくされた。これに比べて、中国はもう少し余裕を持っている。実際、2005年に行われた改革は、外圧が高まりつつある中ではあるが、ニクソン・ショック当時の日本のような危機的状況で行われたわけではなかった。中国としては、日本をはじめとする諸外国の経験を参考にしながら、完全変動相場制への移行に向けてのロードマップを前もって用意しておくべきである。
最終移行のベスト・タイミングは、実際の人民元レートが市場の需給を反映した「均衡レート」にほぼ一致する時である。海外で取引されている人民元の先物(NDF)レート(一年物)の現物レートに対するプレミアムが、今年春の10%を越えた水準から、8月21日現在で3%程度にまで低下していることに象徴されるように、その日はすでに近づいてきている(図6)。
-現物Vs.先物-
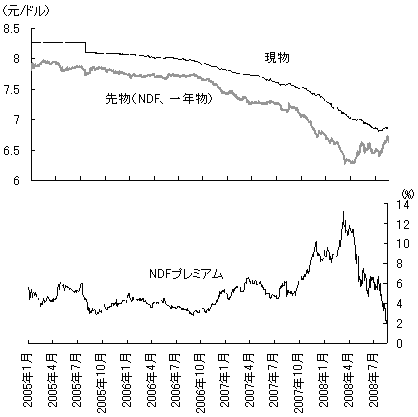
BOX なぜ円の切上げが必要であったか――「為替政策研究会」の見解
ニクソン・ショック前後の日本において、円の切上げ反対論が世論の大勢を占めていた。その主な論拠として、
(1)円の切上げは、「輸出増進」と「外貨獲得」という「国益」に反すること、
(2)円の切上げよりはドル切下げ、もしくはそれを可能にするための国際通貨制度の改革が必要であること、
(3)産業界への影響が大きいこと、
(4)いったん切上げを行えば、歯止めを失い、円平価の安定性が失われること、
(5)経済成長の誘因を喪失させること、
(6)物価安定の効果に乏しいこと、
(7)国内に弱い円を切上げる理由はないこと、
が挙げられている。
これらに対して、「為替政策研究会」は、円レートの小刻み切上げが実施されることを前提に、次のように反論している。
(1)国際収支の黒字の累積は、国益に即するどころか、経済活動の本来の目的である自国の消費・投資・政府支出が生産以下に抑えられる結果に他ならない。その上、赤字国からのインフレ輸入を招き、国際金融協力を困難にするなど、国民経済への弊害が大きい。
(2)ドル本位制の欠陥を克服するような国際通貨制度の改革は、日本だけで実施しえない問題である上に、その改革について多くの国々の同意を得るためには、恐らく長時間を必要とする。これに対して、黒字の累積によってもたらされた日本経済への悪影響を是正することは、日本にとって、自ら取り組まなければならない緊急課題である。
(3)円レートの切上げは、日本の輸出産業にとって、海外市場での競争が厳しくなるが、日本企業の競争力が年々高まっていることから考えると、小刻みの切上げ調整の場合、切上げることによる競争条件の不利化は、転換過程を通じて吸収される可能性が高い。また、円の切上げにより、国内の有効需要の落ち込みと国内資源の不完全雇用が引き起こされた場合、円の小刻み調整と同時に拡張的財政支出政策を組み合わせることによって、十分対応できるはずである。
(4)構造的に日本の黒字累積傾向が絶えず続くと予想される場合には、国際収支調整策として大幅な切上げで調整すれば、切上げのたびごとに大きな影響を国民経済にもたらすが、小刻み切上げ調整方式は、経済全体としての衝撃はそれほど大きなものとはならない。
(5)円レートの切上げは、企業の利潤と賃金上昇を抑えることを通じて生産性向上の意欲、ひいては経済成長を阻害すると懸念されるが、成長の意欲は賃金上昇と生産性上昇率との関係によってもたらされるのではなく、成長の基本要因は投資行動と技術進歩の諸要因にある。
(6)円の切上げの目的は国際収支の不均衡がもたらす日本経済への全般的損失を減少させることであり、物価対策は円の切上げの一つ側面にすぎない。物価安定効果からと言っても、他の代替案より、輸入自由化と組み合わされる円の切上げの効果は、国際収支調整策としても、物価抑制効果の面においても、より好ましい成果をもたらすと考えられる。
(7)円の切上げは外に対して円の購買力を高めることができ、内に対しても円を強くすることになる。
1970年代初めの日本における為替政策の在り方に関するこのような指摘は、現在の中国にも当てはまるように思われる。
2008年8月26日掲載