| 執筆者 | 森 知也 (ファカルティフェロー)/Tony E. SMITH (ペンシルバニア大学) |
|---|---|
| 研究プロジェクト | 経済集積の形成とその空間パターンにおける秩序の創発:理論・実証研究の枠組と地域経済政策への応用 |
| ダウンロード/関連リンク |
このノンテクニカルサマリーは、分析結果を踏まえつつ、政策的含意を中心に大胆に記述したもので、DP・PDPの一部分ではありません。分析内容の詳細はDP・PDP本文をお読みください。また、ここに述べられている見解は執筆者個人の責任で発表するものであり、所属する組織および(独)経済産業研究所としての見解を示すものではありません。
地域経済プログラム (第三期:2011~2015年度)
「経済集積の形成とその空間パターンにおける秩序の創発:理論・実証研究の枠組と地域経済政策への応用」プロジェクト
従来の典型的な産業集積の要因分析では、式(1)のように、個々の産業について集積度をスカラー値に集計して評価し、その値をさまざまな産業特性で回帰することにより、産業特性と集積度を関連付ける方法が用いられてきた。
ここで、Di, Xiは、それぞれ、産業iの集積度と産業特性ベクトル、εiは産業固有の誤差項である。説明・非説明変数共に空間的性質を集計によって抽象化するこの方法は、Rosenthal and Strange (2003)により初めて紹介されて以降、その単純さゆえに、産業集積の実証分析において標準となった。しかし、手軽さの反面、集積の規模と位置の関係が抽象化されており、具体的な政策に結びつきにくいことが欠点であった。日本の製造業小分類を例に取れば、産業内で集積(雇用)規模分布における最大・最小5%ポイントの差は、実に9~3000倍 (中央値で280倍)もあり、集積規模は、その形成地域によって著しく異なる。集積の形成位置に影響し得る産業特性の代表的なものに投入産出関係があるが、必要な労働者のタイプや取引先への近接性は地域により異なり、その違いは、各地域に形成される集積の規模に影響を及ぼす。どのような地域にどのような要因でどのような規模の集積が形成されるのかを具体的に説明するには、まず、集積の位置を地図上で明示的に特定する必要がある。
本論文では、まず、産業毎に個々の集積を地図上で統計的に検出し、検出された集積の雇用規模を、さまざまな地域特性により回帰するという二段階の手続きを用いて集積の要因分析を行うための基本的な枠組みを提案している。第1段階の集積検出では、産業が同一かつ単一事業所からなる企業のみにより構成される単純な状況を仮定することにより、産業固有の立地確率分布を任意の地域分割上の多項確率分布により近似することを可能にしている。この地域分割に対して凸形状を制約として課すことにより空間集積を表現し、統計的に最適な地域分割、つまり、集積群を検出している。第2段階では、得られた集積の雇用規模を非説明変数とし、集積形成地域の特性(人口近接性や産業固有の取引連関近接性などの内生的特性と、港湾近接性、道路網中心性、その他自然条件等の外生的特性)を説明変数として、式(2)を用いて回帰分析を行う。
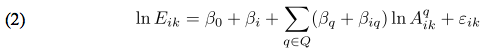
ただし、Eikは産業iに属する集積kの雇用規模、Qは地域特性のバラエティ、Aqikは集積kの形成地域における地域特性qの値、εikは誤差項である。β0とβqは、それぞれ、全産業共通の切片と地域特性qに関する係数、βiとβiqは、それぞれの係数に関する産業i固有の逸脱を表している。
本論文の方法は、式(1)を用いる従来の方法に対して3つの重要な優位性を持っている。第1の優位性は、式(1)ではサンプルが産業であるのに対して、式(2)では、それが個々の集積であることによる。従って、式(2)では、全産業の集積群をプールし、産業カテゴリーを導入することにより、産業間で地域特性の効果を定量的に比較することや、産業毎に集積規模と相関する地域特性を特定することが可能である。特に、集積度では区別がつかない産業でも、実は集積の空間パターンは大きく異なり、よって、集積の要因も大きく異なる場合なども、その要因を定量的に、かつ、地図により視覚的に理解することができる。たとえば、図1に示す楽器製造業と製鉄・圧延業は、Mori, Nishikimi and Smith (2005)による集積度(D指標)に関しては統計的な有意差がないと判定されるが、図に示すように集積形成地域は大きく異なる (暖色ほど雇用規模が大きい)。式(2)を用いて回帰分析を行えば、前者は平均的産業に対して取引連関近接性が、後者は人口近接性が有意となり、集積の要因がそれぞれ異なることが示される。
第2の優位性は、地域データを用いた回帰分析で問題になる、回帰残差の空間的自己相関に関するものである。この問題は、式(2)のような回帰分析において、変数を定義する地域単位が実際の集積より小さい場合(たとえば市区町村を用いた場合)に顕著になり、その場合はOLSを用いることが不適切となる。本論文では、地域単位に内生的に検出された集積を用いることにより、従来の恣意的な対処方法に頼ることなく、殆どの産業でこの問題を回避することができることが示される。都道府県のように、実際の集積よりも大きい地域単位を用いた場合でも、回帰残差の空間的自己相関自体は回避できるが、一方で、説明変数に用いる各種近接性の指標が適切でなくなり(たとえば、北海道における人口近接性は札幌などの限られた都市部では全国的にも大きい値を取るが、道レベルでは逆に相対的に小さい値となる)、回帰結果は地域単位に集積を用いた場合と大きく異なるものとなる。つまり、都道府県をもって産業集積を近似することは難しい。
第3の優位性は、個々の集積を明示的に扱うことにより、集積の要因分析に留まらず、個々の集積における事業所の生産性まで、一貫した枠組みの中で分析が可能となる点である。本論文では、集積の内部と外部で事業所の全要素生産性を統計的に比較しており、殆どの産業について、集積形成により事業所の全要素生産性が向上することのみ示している。原理的には、さらに、集積形成による生産性の向上効果を定量的に推定することも可能である。
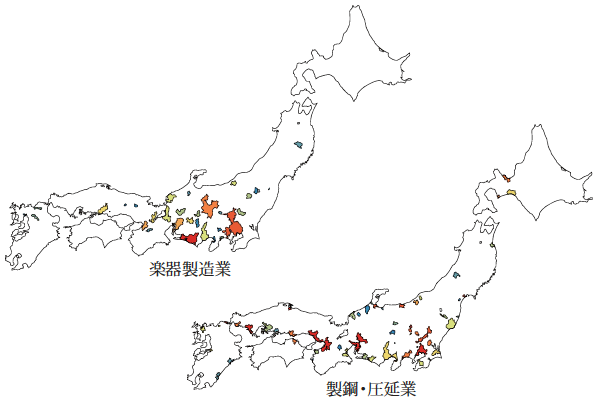
最後に、本論文では説明変数の内生性の解決について論じていないが、式(2)の厳密な推定を行うには、操作変数法を用いる必要がある。特に、鍵となる内生変数として、市場近接性や賃金と強い相関を持つ人口近接性、取引先との位置関係より導出される取引連関近接性、労働者学歴などがあるが、人口については歴史的人口データや地質・土壌などの自然条件が操作変数として機能することが知られている(Combes et al., 2010)。本論文において、新しく導入されている取引連関近接性に対しては、事業所開設時期から推定した集積年齢(たとえば、集積に含まれる最古の事業所の年齢)が有効に機能する。
引用文献
- Combes, P.-P., Duranton, G., Gobillon, L., Roux, S. 2010. "Estimating Agglomeration Economies with History, Geology, and Worker Effects." In E. Glaeser (ed.), Agglomeration Economics. Chicago, IL: The University of Chicago Press: 15-65.
- Mori, T., Nishikimi, K., Smith, T.E., 2005. "A Divergence Statistic for Industrial Localization," Review of Economics and Statistics, 87(4), 635-651.
- Rosenthal, S.S., Strange, W.C. 2001. "The determinants of agglomeration." Journal of Urban Economics 50(2): 191-229.

